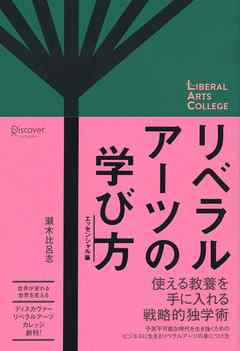感情タグBEST3
Posted by ブクログ
「知は力である」 ―フランシス・ベーコンー
上記の言葉から始まる。私は知というものはリベラルアーツという学問無くしては語れないものだと理解している。ただ、リベラルアーツとはどんなものなのか、どんなことを学べば良いのかが不明だった。
リベラルアーツの起源は、ギリシア・ローマ時代にまで遡る。当時は自由人が学ぶ必要のある自由七科である文法学、修辞学、倫理学、算術、幾何学、天文学、音楽を意味した。現在の大学でいう教養課程ということになる。
この本はそのリベラルアーツの基本的な学び方が記されている。リベラルアーツの中でも音楽、絵画等の芸術鑑賞から学ぶ方法が色濃く紹介されている。読み進めていくと著者の趣味を推し進めるものかと思うほど芸術分野への偏りを感じるが、その重要性も理解が出来てくるものになっていた。
私がリベラルアーツを学ぶには、芸術鑑賞するまでの基礎知識が大幅に欠如しているため、本書で紹介されている参考図書の中から数冊を精読することから始めてみる。
Posted by ブクログ
瀬木比呂志(1954年~)氏は、裁判官を経て、明治大学法科大学院教授。2014年出版の『絶望の裁判所』がベストセラーとなり、2015年の『ニッポンの裁判』により城山三郎賞受賞。
本書は、2015年に発表された作品のエッセンシャル版として2018年に出版されたもの。
著者によれば、「リベラルアーツ」の起源はギリシア・ローマ時代にまで遡り、当時は、自由人(奴隷ではない人)が学ぶ必要のある自由7科(文法学、修辞学、論理学、算術、幾何学、天文学、音楽)を意味し、現在の大学で言えば教養課程に属する科目であったが、近年注目されている意味での「リベラルアーツ」とは、大学における基本科目という趣旨よりも、そのもともとの意味、すなわち「人の精神を自由にする幅広い基礎的学問・教養」という趣旨で、とりわけ、その横断的な共通性、つながりを重視する含みを持って用いられる言葉である。そして、リベラルアーツとしての教養とは、飾りやファッションではなく、社会に起こっているさまざまな問題について、世界で交わされているさまざまな論争について、どのような世界観や人生観を選ぶべきかについて、あるいはビジネス上の課題にいかに取り組むかについて、考えてゆくときの基盤となるパースペクティブやヴィジョン、すなわち、各自の「思想」を築くための「思想的道具」なのである。
更に、本書で特徴的なのは、リベラルアーツを提示するのは書物だけではないとして、音楽や映画などの芸術についても積極的に触れ、推奨している点である。
第1部の「なぜ、リベラルアーツを学ぶ必要があるのか?」、第2部の「リベラルアーツを身につけるための基本的な方法と戦略」に続く、第3部の「実践リベラルアーツ~何からどのように学ぶのか?」では、様々な著作、芸術作品が紹介されている。(エッセンシャル版では、この部分の記載が簡略化されている)
類書に比較して、個人的な経験・思考が強く出た記述が多く、やや読み難さは感じるものの、基本的なスタンスは共感できるものであり、リベラルアーツを語った一冊として読む意味はあるものと思う。
(2020年3月了)
Posted by ブクログ
元裁判官という経歴をお持ちの方のリベラルアーツ論。それぞれいろんなことを学んで、それに共通することを取り出す、いろんなパースペクティブを手に入れることが世界を広げる学び、それを手に入れるにはこういう本を読んでこう感じてくださいと書いてある本です。
リベラルアーツが何なのか全く知らない人にはぴったりですが、ある程度知っている人はちょっと物足りないかも…
Posted by ブクログ
この本を読んで、この先読んでみたいと思う本のジャンル、映画、美術作品などが増えたし、どう付き合うかなどを考えさせられた気がした。
教養は単なる知識ではなく、柔軟な思考力や想像力、完成を身につけるためのもの。
教養は世代により変化するものではなく、他の世代、他のコミュニティなどのコミュニケーションを取ることができるようになる。しかし、現代の日本においてはタコツボ化、村社会、同世代とのコミュニケーションばかり。若い世代の常識は上の世代の常識ではないことや、その逆もしかり。教養とはそういつまたギャップを埋めることができる、人としての前提、根底のようなものといったところ。教養があるということは色々な世界で生きていくことができる力といったところか。