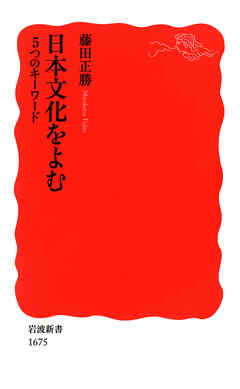感情タグBEST3
Posted by ブクログ
著者の藤田正勝氏(1949年~)は、ドイツ哲学、思想史、日本哲学史を専門とする哲学者、思想史研究者。
哲学を専門とする著者が日本文化を考察した本書を記した背景は、近年、世界全体において、それぞれの文化、民族、宗教の間の溝が一層深くなる方向に動き始めており、そうした状況の中で求められるのは、お互いの歴史や文化を認め合い、対話し、尊重することで、その前提として、我々は、日本の文化や思想、宗教が長い歴史の中で生み出し、作り上げて来たものを再認識する必要があると考えたことだという。
そして、西行の「心」、親鸞の「悪」、長明と兼好の「無常」、世阿弥の「花」、芭蕉の「風雅」の5つのキーワードを基に、彼らの詩歌や思索、信仰を辿り、日本の文化の中に通奏低音として響いているのは「無常」への深く強い思いであることを明らかにしている。
「風になびく富士のけぶりの空に消て 行方も知らぬ我思哉」(「西行法師家集」)
「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。淀みに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとゞまりたる例なし。・・・朝に死に、夕に生るゝならひ、たゞ水の泡にぞ似たりける。不知、生れ死ぬる人、何方より来たりて、何方へか去る」(「方丈記」鴨長明)
「あだし野の露きゆる時なく、鳥部山の烟立ちさらでのみ住みはつる習ひならば、いかに、もののあはれもなからん。世はさだめなきこそ、いみじけれ」(「徒然草・第七段」吉田兼好)
「つらつら世間の幻相を観ずるに、飛花落葉の風の前には有為の転変を悟り」(謡曲「柏崎」世阿弥)
「楽天は五臓の神をやぶり、老杜は痩たり。賢愚文質のひとしからざるも、いづれか幻の栖ならずやと、おもひ捨てふしぬ」(「幻住庵記」松尾芭蕉) 等々
いずれに流れているものも「無常」への思いである。
そして最後に、西田幾多郎の思想を引用して、西洋文化と東洋文化の違いは、前者は「有を実在の根底と考へる」文化であるのに対し、後者は「無を実在の根底と考へる」文化である、換言すれば、前者は、具体的な「形」をとったものを重視する文化であるのに対し、後者は、そのような「形」が生まれてくる以前のもの、つまり「形なきもの」を重視する文化であると述べている。
著者の語る通り、世界中でナショナリズムが声高に叫ばれる近時にこそ改めて認識するべき、日本の文化・思想のエッセンスがコンパクトにまとめられた良書である。
(2017年10月了)
Posted by ブクログ
西行の「心」、親鸞の「悪」、長明と兼好の「無常」、世阿弥の「花」、芭蕉の「風雅」の五つのキーワードをめぐって、日本文化の諸相を論じている本です。
著者はヘーゲルや日本哲学の専門家で、とくに世阿弥についての考察で、禅からの影響を重視しているところに、京都学派的な日本文化理解の特色が見られるように思います。
また最終章では、西田幾多郎の『日本文化の問題』がとりあげられ、日本文化の優越性を主張する偏狭な国粋主義が跋扈する時代にあって、西田が世界のなかで日本文化の個性を生かしていく方途をさぐっていたことがとりあげられ、現代を生きるわれわれが日本文化をどのように受け取り論じるべきなのかという問題にかんする著者自身の見解が示されています。