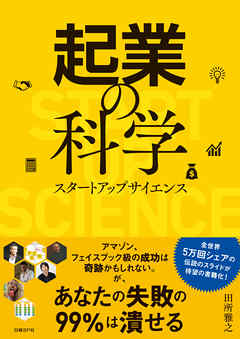感情タグBEST3
Posted by ブクログ
直感的に、今後の自分にとってのバイブルになる気がしている。これまで既に一定軌道に乗っているビジネスをどう伸ばすか、そのための仕組みや体制をどう作るかについて考えることがほとんどだったので、いざ新規事業を立ち上げる当事者になってみると暗中模索で何をすべきか全く分からずに不安を抱えていた。
「賢者は歴史に学ぶ」という言葉があるように、既に諸先輩方が試行錯誤してきた歴史がある中で、その知見や経験を活かさない手はない。
本書を通じて、新規事業を立ち上げるためにここ数ヶ月間自分が取り組んできたことは、過去の失敗例を踏みまくっていることが分かったので、早速軌道修正していきたい(笑)
Posted by ブクログ
課題の質を上げてから、ソリューションの質を上げる。その逆はない。
技術ありきではいけない
自分ごとの課題を解決せよ
スタートアップとスモールビジネスの違い
①指数関数的な成長
②市場環境が存在するかどうかわからないアイデアを今やること
③スケールへの姿勢
④ステークホルダー
⑤商圏が限られてない
急成長していなければスタートアップとは呼べない
スタートアップは「一見悪く見えて、本当に良いアイデア」を発見することである。
ペルソナを想像するためには、「場所」「時間」「イベント」といった文脈を絞り込む
Posted by ブクログ
僕の起業のバイブル。この本に惚れてスタートアップに惚れ込んで人生を左右された一冊。
あまりにも盲信しすぎて他のことを学ぶのを躊躇ってしまうほど熱狂的に良かった。
いまだに振り返って読む起業の辞書
Posted by ブクログ
たまに存在する「日本語でのみ読める素晴らしい文献」の一つに数えたい。これを読めるということが、日本語話者にとってのその分野での競争優位の源泉にもなりうる。
Posted by ブクログ
課題が一番大事。
ピボット前提で。
最初は作り込みすぎない、そもそも課題があるのか?顧客はいるのか?何が欲しいのか?を見極めるところに時間を使う。機能追加は二の次。
Posted by ブクログ
顧客を熱狂させるためには、課題を明確に設定して、何度もプロトタイプで実際に実験すること。そして、そこから得られる意見を正確に読み取り、インサイトしていく。じっくり、じっくり、泥臭くやっていくことがスタートアップの最も重要なこと。
起業していくなかで、ソリューションに目を向けがちだが、一番大切なのは、どんなところがむず痒いのか、そして、なぜ今、起業するのかが明確に答えられることが大切だ。
Posted by ブクログ
スタートアップに必要な考え方がわかりやすく書いてある。
豊富な例とともに、順を追って書かれているのでとても理解しやすい。
スタートアップでは、ユーザーのニーズをしっかりと分析し、今までなかった、誰もやろうとしなかったプロダクトを開発する必要がある。
プロトタイプの開発後は、ユーザーからのフィードバックを受け取り、先鋭された少数メンバーでピボットを繰り返し、プロダクトの磨き上げをする。
Posted by ブクログ
相当おもしろい。
起業における成功の再現性を担保すべく気をつけるべき点は何かをフェーズごとに追っていく構成。
Chapter1に割かれているページが一番多いことからも分かるように一番重要なのは人々が感じている痛みを解決するようなアイデア(課題ドリブン)→この痛みが破壊的イノベーションの元!
この技術があるから起業したいというように技術ドリブンだと失敗するのはかなり大きなトラップでは?
「既存の市場における課題」は何か普段から頭を回していたい。
起業家もその痛みを共有していることが望ましく、解決のためのビジョンを描くことで仲間を集めていく
→ユーグレナの出雲社長にお話を伺う機会が過去にあったが、本書にある通り自らが感じている痛みとそれを解決すべく思い描いているビジョンの解像度が圧倒的だった
望ましいスタートアップメンバー構成
3H+ボケツッコミ(p.175)
→自分や自分の周りの人がどれに当てはまるのかという視点を持っていると面白いかも
(テーマのせいかいつも書いてる文章とちょっと雰囲気が違う気がする。読んでて分かったら何が原因か教えて欲しい)
Posted by ブクログ
この本を読む前は
起業は自分の強みやできる事、から考える
と思っていました。
この本を読んで私は、
いいアイデアとは解決策ではなく、
客先の課題、痛みを真っ先に考える
課題の質を高めることが最優先事項
誰かに話したときに相手が戸惑うようなアイデアのほうが、スタートアップには向いている。
詳細なビジネスプランは無駄
客先に合わせて変わっていくものだから
フィードバックを得て
課題を解決できるかに注力
失敗する多くのスタートアップは、自分たちで解決できる範囲内に収めるため、そもそもの課題をでっちあげてしまっている。「自分たちが作りたいから作る」のではいけない。スタートアップの命となるのは、「本当にその課題が存在しているのか」
ペルソナ(顧客の具体的なイメージ)とジャーニー(顧客の心理、行動パターン)を考える
ということに気づきました。
今後、
本業でも客先の課題、ペルソナ、ジャーニー、
を意識したインタビュー
を実行します。
複業は解決策から始めるのではなく、
課題の検討を最優先に
を実行します
Posted by ブクログ
起業とは何か分からない人は必読
起業に関する知識が何もない中て読んだが、この本によって、起業する上で気をつけなければいけないポイントが明確になった。
ほとんどの項目を図解してくれていて、知識がなくても、大枠を学ぶことができる。
何度読み返しても、自分の段階ごとに学びがある本。
Posted by ブクログ
スタートアップ向けに書かれた本だが、
UXデザインにて新規事業を立ち上げる際のステップと
組織や財務の視点以外は変わらない。
アイデアから顧客課題を検証して、
プロトタイプを作成し、PMFを達成して、
ユニットエコノミクスを健全化するところまでの
一連の流れが分かりやすくまとまっている。
第1章 Idea Verification
アイデアの検証
1-1.アイデアに気付く
スタートアップにとっての「良いアイデア」とは
どういう課題を解決するか明確にする
1-2.スタートアップのメタ原則を知る
1-3.アイデアの検証
アイデアの蓋然性を検証する
スタートアップとしての潜在性を検証する
1-4.Plan A(最善の仮説)の作成
リーンキャンバスを用いてPlan Aを作る
-サイドプロジェクトで始める
サイドプロジェクトでアイデアを練る
第2章 Customer Problem Fit
課題の質を上げる
2-1.課題仮説の構築
カスタマーの抱えている課題が何かを言語化
2-2.前提条件を洗い出す
ジャベリンボードを使って課題の前提条件を洗い出す
2-3.課題〜前提の検証
カスタマーが本当に課題を持っているか明らかにする
-Founder Problem Fit
創業メンバーは課題が腹落ちしているか
創業メンバーと課題が合っているかを見極める
第3章 Problem Solution Fit
ソリューションの検証
3-1.UXブループリントを作成する
カスタマーがどのように解決したいかを明らかにする
3-2.Build Prototype
プロトタイプの構築
ブループリントをベースにプロトタイプを作る
3-3.Product インタビュー
プロトタイプを実際に使ってもらいインタビュー
-Forming team
共同創業はするチームを作る
核となるメンバーをFixしていく
第4章 Product Market Fit
人が欲しがるものを作る
4-1.ユーザー実験の準備をする
4-2.MVPを構築する
4-3.MVPをカスタマーに届ける
4-4.MVPの評価を計測する
PMFを達成できたか?
4-5.新たなスプリントを回す
4-6.継続的なUX改善
UXを磨き込む
4-7.ピボットを検討する
ピボットする
-柔軟性の高いチームを組成する
PMF達成へ柔軟性の高いチームを作る
第5章 Transition to Scale
スケールするための変革
(ユニットエコノミクス健全化)
5-1.ユニットエコノミクスを計測する
5-2.顧客1人当たりの売り上げ・利益を高める
顧客1人当たりのLTVを高める
顧客ロイヤルティーを高めてLTVを最大化する
5-3.顧客獲得コスト(CPA)を下げる
コンテンツマーケティングで広告を使わず顧客獲得
ユニットエコノミクスが健全化するまで回す
以上
Posted by ブクログ
いままで言語化できてなかったもやもやが全部まとまってた。議論の共通言語ができることが一番ありがたい。
#起業の科学 #スタートアップサイエンス #田所雅之 #課題図書 #読書記録2018 #読書記録 #再読候補
Posted by ブクログ
1.IDEA VERIFICATION
リーンキャンバスを使って、顧客の課題やソリューションを洗い出す。
サイドビジネスでOK。
2.CUSTOMER PROBLEM FIT
顧客と課題が見つかったら、課題を磨き込む。
検証可能な仮説を立てる。
顧客自身、課題を正確に捉えていないので、徹底的にヒアリングする。課題の磨き込みが甘いスタートアップが多い(ソリューション優先)
3.PROBLEM SOLUTION FIT
課題を磨きこんだら、ペーパープロトなどでソリューションが効果的か検証する。時間やコストをかけすぎないこと。ソリューションが効果的かどうかわからない中でプロダクト作りを先走らない。
4.PRODUCT MARKET FIT
プロダクト作り。リーンやアジャイルな開発でMVPを構築し、継続的なUXの改善を行う中で、仮説検証していく。
最初は人力であったり、商品分野を絞ったりして小さい市場を独占する。
5.TRANSITION TO SCALE
LTVの最大化
CPAの最小化
【印象に残った言葉】
・起業家がやることはマーケット分析ではなく、顧客の声を聞きに行くこと
・誰も欲しがらないプロダクトを作ってしまう
・工程が進むにつれ、創業メンバーも洗練されていく
・工程が進むにつれ、ピボット(方向転換)によるコストは増大する
Posted by ブクログ
データなど図も使って字だけの本よりは格段に見やすいし、個人的には例などをスキャンしてまた見返せるようにした。
内容は自分はまたまこれが完全に理解できるようなレベルじゃないと思ったが、著者がスタートアップに関する情熱は伝わってきた。
スタートアップする人の参考資料にはいいと思います。
パッて読むよりはこの本を理解できる人に内容を教えてもらい、コンサルしてもらうのが1番早いのではないかと思う。
Posted by ブクログ
スタートアップのリスクを体系的に減らすためノウハウが詰まった濃厚な一冊。
1. 課題仮設を発見する。
2. 課題仮設を検証し、顧客の存在を確かめる。
3. プロトタイプで解決策を検証する。
4. MVPを投入して、機能とUXを改善する。
5. 採算性を考慮して、スケールする。
全てをBuild-Mesure-Learnのループに基づいて行う。
Posted by ブクログ
これはスタートアップにとっては、ガイドラインでありマニュアルでありバイブルですね。暗中模索に陥りがちなスタートアップの光明として、見えない道を照らしてくれる本。
Posted by ブクログ
確かに『スタートアップ・サイエンス』の名にふさわしく、起業におけるプロセスが検証可能な形で整理されている。アイディエーションの肝はソリューションの質ではなく、解決すべき課題の質というのっけの部分から非常に腹落ち感満載。
Posted by ブクログ
「起業の科学」タイトル通り。
網羅的で、失敗の確率を下げるための良書の1つ。
答えるべき問いが多く含まれ、見えていなかったものが、
見えるようになるはず。事例も分かりやすく、イメージがつきやすい。
自分の偏見で、全体を大雑把にまとめると、、
失敗の確率を下げるには、
・順番を飛ばさず、重要なことから論理的に進めよ
・思い込みではなく、自ら、具体にアプローチせよ
・本質を見出し、管理し、ストックへ繋げよ
このように理解した。
以下はしっかりインストールしたい本質を抜粋
・道筋は1つしかない。課題の質を上げてから、ソリューションの質を上げる。
・今検討しているアイデアは、顧客にとって本当に痛みのある課題なのか?
・課題の質を高めるには、課題が自分ごとであるか(原体験があるか)どうか。
身近な人の課題でも、しっかり理解していれば良い。
・誰がその製品を心の底から欲しがっているのか?
・誰(カスタマー)の何(課題)をどのように解決するか」を一言で表せないアイデアは磨き込みが足りない。
・一部の人に熱狂的に好かれるプロダクトを作ることこそ、スタートアップの使命
・顧客の反応によって、常に覆されることを前提として作っていく必要がある
・差別化を目指すのではなく、いかに高いUXを提供できるかをベースに考えるべき
・最初から機能が多いと、コア機能が何かがぼやけてしまう。マストハブに絞る。
・起業家が会うべきは、顧客であり、参画してくれそうな仲間である
・PMFを達成できていない段階でユーザーを集めても穴の開いたバケツで水を汲むようなもの
・カスタマーと直接対話をして、フィードバックをどんどんもらい、プロダクトを磨き込むこと
・創業メンバーは事業に関する全てを常に学び続ける必要がある
・限定市場を独占してから、周辺市場に攻め込むことが王道。
・早く参入し過ぎてコストが高い、もしくは性能が低いと誰も相手にしてくれないし、市場が熟すまで待つと大手に勝てない
・ベストなタイミングを掴むため、プロダクトの進化が止まっている領域を探してみるのもよい方法。
・アイデアを検証する時にも「大企業ができそうもないことをやっているか?」という問いが大事になる
・スタートアップのフレームワーク
中間プロセスの排除
バンドルを解いて最適化
バラバラな情報の集約
休眠資産の活用
等々
・小さくてもいいので市場を独占せよ。
・サイドプロジェクトでアイデアを練る
・課題検証の究極の目標は、顧客すらも気づいてない奥に潜む潜在的な課題に光を当て、本当に良いアイディアを見つけ出すことにある。
・想定したカスタマーの課題は本当に存在するのか?
・「自分たちが作りたいから、そのプロダクトを作る」と言う呪縛から抜けることだ。
・起業家は確証バイアスがつよい人が多い。
・自分が想定する課題仮説やソリューション仮説は反証されることを前提に臨むべきだ
・価値検証を始める前に課題仮説を磨き込む
・課題仮説の磨き込みなしに、カスタマー候補と話をすることは無駄が多くなる
・カスタマーインタビューの相手は、ランダムではインサイトは得られない。初期ユーザーとなり得る「エバンジェリスト」や「アーリーアダプター」を選ぶこと。自ら情報収集を行い、判断する人。他の消費者への影響力が大きく、オピニオンリーダーとも呼ばれる人。不都合な状態に対して敏感で、積極的にソリューションを探しているような人が該当する。
・「この製品が出たらいくらまでお金を払ってもいいですか」よりも「現在この課題の解決にいくら払っていますか」と聞く。
・「それは過去1カ月に実際に何回起きましたか?」と具体的に聞くといい
・答えありき(自分たちの作りたいソリューションありき)の誘導尋問してはいけない。
・現地、現物でしか気付けないインサイトがある
・カスタマーが本当に欲しいものを見つけることは、スタートアップがすべき仕事。何が欲しいか尋ねない。
・現状と理想のギャップが何で、それを埋めるための阻害要因が何なのか?に注目して質問していくと、課題の当事者ですら気づいてなかったことを発見できることがある。
・最低でも20人近くのインタビューをする
⇨同じセグメントのユーザー5人と話すと問題の80%は発見できる。切り分けれていない場合、4象限で分けて整理すると考えるならば、20人は必要になる。
インタビュー相手がエバンジェリストカスタマーで貴重なインサイトを与えてくれる人だと分かったら、インセンティブをつけて協力を仰ぐ
・ジョブシャドーイング⇨ユーザーの特定の活動を観察してその行動と経験を記録していく
↓特に以下のような要素を観察↓
・時間をとられている特定作業はあるか
・繰り返す作業はあるか
・問題や面倒を避けるため、不合理な策をとっていないか
・フラストレーションがたまっていないか
・コンピューターが、代替できそうなものはあるか
・紙、エクセル、メモなどバラバラな道具を同時に使っていないか
・カスタマーに対する理解が深まるにつれて、プロダクトの質がどんどん上がっていく
・プロブレムソリューションフィットの段階では、プロダクトの検証に注力する。終わる前にプロダクトの最適化に走るのは危険。
・充分検証ができている課題に対して、どのような価値提案(何を)をするのか?そのためのソリューション(どうやって)を立てる。
・馬しか乗ったことがないカスタマーには、車を想像する事はできない。早い馬としか言えない。
・顧客価値を実現するソリューションを実際に考えるのはカスタマーの仕事ではない。
・ソリューションインタビューは、アーリーアダプターへ。
・フィーチャーは、必須、あったら良い、不要の3段階に分ける
・スタートアップはカスタマーから見てmust haveのフィーチャーのみを実装することを心掛ける
・nice to haveな機能の追加は、must haveな機能が確実に市場に受け入れられると分かった後
・エレベーターピッチの基本フォーマットは、
『我々は、〈対象カスタマー〉の抱えている〈ニーズ/課題〉を満たしたり、解決したい。〈プロダクト名〉というプロダクトは、〈重要な利点〉をカスタマーに提供できる。このプロダクトは〈代替手段の最右翼〉とは違い、〈差別化の決定的特徴〉が備わっている。アナロジー:〈我々は〇〇業界の〇〇である〉』
・アナロジーは、30秒ピッチをさらに要約した5秒ピッチにあたる
・プロダクトのプレスリリースを作成することから始める
・カスタマーにプロダクトの使い方を学ぶことを強制しない。説明を見なくてもすいすい使えるUXを目指したい
・市場で既に受け入れられているプロダクトのUXを調べる。自ら、使い倒して、エッセンスを抽出する。
・PMFとはバケツの穴がほとんど塞がり、最初に獲得したユーザーを熱狂させ続けて定着させ続けられる状態といえる
↓優れた計測指標が持つ特徴↓
・改善につなげやすい
・計測しやすい
・漏れなくダブりなく
・インパクトがある
・2014年のサッカー、ドイツ代表のKPIは「ボールを受け取ってからパスを出すまでの時間短縮」に設定し、短いほど勝率が高かった。スピードプレーでW杯優勝。
・インパクトあるKPIは多くの場合、先行指標になる。改善できれば、結果も大きく改善される。
・インパクト指標を見つけることが、PMF達成の鍵。
・最初の10人にすら売れないものは、100万人に売れるプロダクトには絶対になり得ない
・環境が整ってからユーザー拡大を考えれば良い
・エンゲージメントは、「使ってみたい」「もっと使いたい」「お金を払ってでも使いたい」と考えるユーザーの比率がどの程度あるかで測れる。
・新しいフィーチャーの追加を何も考えずに行ってはいけない。機能を2つ追加したら、使われていない機能を1つ削除するスタンス。
・「このプロダクトがなくなったらどう思うか?」と質問して、40%以上のユーザーが「非常に残念」と答えたのであれば、今後も継続的に顧客を獲得できると判断できる
↓カスタマーの負担を減らす↓
・行動を完了するまでの時間
・行動を起こすために必要な身体的な労力
・行動を起こすための脳への負荷
・使う時に社会的立場から逸脱しないように
・行動を起こすための財政的な負担
・日常からの逸脱
・安心、安全に使えるように
・オイシックスの事例では、初回限定セットで利益が出なかったとしても、美味しい野菜を一回食べて満足してもらえば、会員として定着してもらいやすくなる
↓顧客獲得コストを下げる↓
・自ら動いて、鶏と卵のジレンマを解消する
・供給が足りない特殊な状況を狙う
・自らサプライヤー(何でも屋)として振る舞う
・他のサービスやプラットフォームを間借りして発信
・コンバージョンページを核に据える
・想定顧客はどこにいるのかを見極めること。ターゲットに合う発信手段を選ぶ。
・将来的にカスタマーになりそうな潜在顧客と接点を持ち、「すぐ欲しいカスタマー」に育成する
・広く興味を引くコンテンツで集客⇨集まった顧客をコンテンツで育成⇨コンテンツに信頼を持った顧客に販促
Posted by ブクログ
・課題の質とソリューションの質
→ スタートアップの成功に必要
→GoogleグラスやApple Watchは課題ではなくソリューションやテクノロジーありきで進めた事が失敗要因。
・スタートアップの10フレームワーク
1. 中間プロセスの排除
・中間マージンを得ているプレイヤーを飛ばす。例)Uber
2.バンドル(一つに束ねる事)解いて最適化
・一度バラバラにしてUX改善
例)新聞→グーグルアドワーズ、スマニュー
3.バラバラな情報の集約
・断片情報や機能を集約することで価値提供 例)価格コム
4.休眠資産の活用
・使われていないリソースの活用
例)Airbnb 、Uber
5.戦略的自由度
・既存の枠からあえて外れるブルーオーシャン
例)スナップチャット→メッセージが時間がたつと消えるので自由にコミュニケーションできる。
6.新しいコンビネーション
・全く違う領域で活用されていたサービスを組み合わせて価値を提供する
例) エアークローゼット →スタイリスト+送料無料+クリーニング+フリークローゼット
7.タイムマシン
・別の市場で検証済みのモデルやプロダクトを他の市場に持ち込むアイデア
例)GO JEK →オンデマンド型バイクライドサービスをジャカルタで展開。Uberのビジネスモデルをそのまま輸入。
8.アービトラージ
・需要に対して供給が不足している市場に、供給過多になっている市場からリソースを持ってくるアイデア
例)フィリピン英語教師は供給過多→日本の生徒とマッチングさせる
9.ローエンド型破壊
・過剰な性能を削ぎ落として安価に提供
例)ティファール →早く沸かすだけ。
10.サブスクリプション化
・売り切るという発想からサブスクリプション化するアイデア
・リーンキャンパスを作成する
Posted by ブクログ
読みやすかった。
特に課題設定が全てというのはプロダクトアウト思考からマーケットイン思考に移行するために参考になる考え方であった。
自分の業務に生かせるかはまだわからないが、新規事業を行う際にはまた読みたい。
Posted by ブクログ
やや理論的にすぎる印象はあるものの、困った時に振り返るのにすごくいい本だと思います。別にスタートアップに限らず、ビジネスクリエイションに関心があればとても役に立つと思います。
Posted by ブクログ
起業の教科書とも呼べるような一冊。
アイデア出しから、CPF・PSF・PMFとどのようなプロセスをとって会社を作り、育てていくべきなのかについて、網羅的に整理されており、非常に参考となる。
<メモ>
・大成功するスタートアップを作ることはアート、ただし、基本的な型を身につけ失敗しないスタートアップはサイエンスにより実現可能というコンセプトで構成。
・構成は次の通り
アイデア検証→customer problem fit →problem solution fit →product market fit → translation to scale
・提供するもの
自分たちが正しい方向に進んでいるかのコンパス
時期尚早な拡大を防ぐためのガイドライン
各ステージの目標を具体的なアクションに落とし込むノウハウ、ツール
包括的な情報
・良いビジネスアイデアはソリューションでなく、課題にフォーカスしている。バリューのある仕事はイシュー度と解の質両方が高い必要がある。真っ先に注力すべきは解決を目指す課題の質を向上させること。顧客にとって本当に痛みのある課題なのか。
・クラウドファンディングに集まる人たちはなんとなく面白そうで支援することが多く、初回のプロダクトが出荷されてもスケールしないことも多い。
・課題の質を決める3要素
1 高い専門性
2 業界(現場)の知識
3 市場環境の変化(PEST)に対する理解度
さらに、自分ごとであるかどうかも重要。
・課題に対する強い共感が湧くことが非常に重要。課題を徹底的に磨き込むことに繋がり、ビジョン、ミッションに翻訳されていく。それが競争優位性につながる。また、人が集まる。
・一見すると悪いが、本当は良いアイデアである、クレイジーであることが重要。
・新規事業を考えるときには無消費をターゲットにせよ。代替サービスがないからこそ、前例も既存消費者もいないためPMFが達成できれば大きく成長見込める。
・スタートアップが避けるべき7つのアイデア
1誰が見ても最初からいいアイデアに見えるもの
2ニッチすぎる
3自分が欲しいものでなく作れるものを作る
4根拠のない想像上の課題
5分析から生まれたアイデア
6激しい競争に切り込むアイデア(競争は避けるべき)
7一言では表せないアイデア(核心をつき、アイデアを的確に表し仲間を集めることが必要)
・スタートアップとスモールビジネスの違い
1 スタートアップは Jカーブを描く
2 不確実な環境下での競争。タイミングが重要
3 初期は少数だが一気に市場を席巻する
4 VCなどがステークホルダー
5 対応可能市場はあらゆる場所。エリアなど限定されない。
アイデア出しや課題存在検証から始まるのがスタートアップ、ユニットエコノミクスの健全化から始まるのがスモールビジネス。
・一般企業との違い、よくある間違い
1詳細なビジネスプランを作る(検証・ピボットが重要)
2正確な資金計画を作る(作り得ない)
3精緻なレポートにこだわる(顧客意識深掘り、課題発見に時間を割くべき)
4まあまあ好かれるプロダクトを大勢に作る(優等生だが、緩やかな成功しかしない)
5詳細な仕様書を元に開発(アジャイルがより重要)
6最初のビジネスモデルに執着する
7競合を意識しすぎる(独自のインサイトがより重要)
8差別化を意識しすぎる(いかに高いUXを提供するか)
9Nicetohabeな機能を追加する(あったら嬉しいよりなくてはならないが重要)
・スタートアップの成功要因トップ5
タイミング、チーム実行力、アイデア突き抜け度、ビジネスモデル、資金
タイミングは早くても遅くてもうまくいかない。
プロダクト進化が止まっている領域はどこか。
市場を再定義できるか
・ガートナーのハイプサイクルでテクノロジーの流れを読み取る。
・スタートアップの10のフレームワーク
1 中間プロセスの排除
2 バンドルを解いて最適化する(UX改善etc)
3 バラバラな情報の集約(価格コム)
4 休眠資産の活用
5 戦略的自由度(snapchat)
6 新しいコンビネーション
7 Time Machine
8 アービトラージ(レアジョブ英会話)
9 ローエンド型破壊(過剰な部分の削ぎ落とし)
10 As a service化する(売り切りからサブスク型へ)
・TAM対応可能市場 100億以上が望ましい。
焦って大市場を狙わない。局地戦で勝つことが重要。
・「実は高いがまだ気づかれていない」×「市場規模存在しない」ところが狙い目!
<リーンキャンバス>
・12重要なのは課題と顧客。
顧客を特定する。(アーリーアダプターを捉えていることが重要。そこから周囲に広めてくれることを狙いたい。)
3独自の価値提案 4ソリューション
5チャネル 6収益の流れ
7コスト構造 8主要指標
9圧倒的な優位性
PMFを達成して初めて優位性の構築が重要に
・リーンスタートアップでできるだけ早くリリースしタイムアウト前にモデルを見つけることが重要。
複数バージョンのPlan Aを作る
もっとも不確実性の高い項目は何かを理解する。
(課題がそもそも存在するか、カスタマーがそこにいるか、ソリュー村は妥当か)
四段階で検証する
課題を理解する。解決策を定義する。定性的な検証をする。定量的な検証をする。
・サイドプロジェクトでアイデアを練ることも重要
未来志向で未来から逆算することできる。
失敗しても次を試せる。
業務上の制約を外せる。
・MVPを構築する前にもっともリスクの高い項目を検証する。ペルソナを想定して、CPFを進める。
カスタマージャーニーなどを活用する。
・CPFの終了条件
課題が存在する前提条件を検証し、課題の存在を確認できた。
課題を持っている顧客イメージを明確にできた
・良いファウンダーの条件
「自分ごと」の課題を解決したいと思っている(課題に強い共感がある)
パラノイア的な要素を持っている
構築したい理想のUXのイメージがある
想定カスタマーとの強い結びつきがある
プロダクトマネジメントの経験がある
発想に柔軟性がある
・PSF プロダクト最適化にフォーカスすると失敗につながる。プロダクト検証に集中すべき。
Content is king UX is queen
内容はソリューションの良し悪しを決める最重要要素であるが、ユーザーに適切なUXを提供することはそれと同じくらい重要な存在である。
・エレベータピッチ
我々は<対象顧客>の抱えている
<ニーズ・課題>を満たしたい。
<プロダクト>は
<重要な利点>をカスタマーに提供する
これは<代替手段の最有力>と違い
<差別化の決定的な特徴>が備わっている。
アナロジー:我々は・・業界の・・・である。
・UXブループリント カスタマー目線でフィーチャーを構造化する。表示コンテンツを明確化する。
画面遷移に落とし込む。
利用前、利用後、利用時間全体のUXを想定する。
・PSFの終了条件
顧客がそのソリューションを利用する理由を明確に言語化できる
仮説磨き込みを通じて課題の理解が深まった
課題を解決できる必要最小限の機能を持つソリューションの洗い出しができている
一時的UX、予期的UX、などカスタマーが期待すること全体を言語化できている。
・スタートアップの創業メンバーに必要な役割
ハッカー 開発者。洗練されたものを創造できる人
ハスラー 敏腕な仕事人。人間関係構築力が高い人
ヒップスター デザイン性の高いUX UIを設計実装できる人
ストラテジスト ビジョナリーの目標達成に向けたロードマップとマイルストーンを設計できる人
ビジョナリー クレイジーなアイデアとビジネスプロダクト全体のあるべき姿を描ける人
・避けるべき人
失敗を恐れる
ハックしたことがない人
アイデアを出すが実行できない人
成功体験のない人
テクノロジーに弱い人
好奇心が弱い、課題意識低い、
柔軟性ない、専門知識ない、
・MVP スプリントキャンバス
実験したいこと、ユーザーストーリー、
コスト時間、とその結果を1枚にまとめたもの。
・良いユーザストーリー
顧客が価値を感じる
UXがシンプル
ストーリーがユーザー視点
現場の臨場感がある
想定する範囲が大きすぎず小さすぎない
テストができる
・AARRRの導入
Acquisition獲得
Activation使用開始
Retention継続利用
Referralカスタマーの紹介
Revenue売上、コンバージョン
水漏れがあるうちは集客に力を入れない。
穴の空いたバケツに水を入れるようなもの
・MVPの最重要KPIは定着率
・プロダクトは作り込みすぎない。機能増やし過ぎない。
・PMF達成基準
ユーザーの高いリテンションを保てているか
カスタマー獲得から売上獲得の流れは確立できているか
リーンキャンバスの項目全体を見て成立しているか
・ユーザーが熱中するUXを磨きこむ
機能<UX
・使うときのカスタマー負担を減らす
時間、体力、ブレインパワー、社会的承認、お金、日常生、安心安全
・人間の認知の癖を使い、モチベーションを高める
希少効果、フレーミング効果、アンカー効果、バンドワゴン効果(同じプロダクトを使う人が増えると使いたくなる)、エンダウドプログレス効果(目的に近づけば近づくほどモチベーションが向上)、コンコルド効果(リソースのサンクコストが増えるとやめにくくなる)
・カスタマーに投資させる
関連情報入力、選好の入力、レベルアップ、コンテンツ投稿、フォロワー、評価
・報酬の設定
ソーシャルの報酬(協力や競争による共感の喜び)
ハントの報酬(リソースを自主的に探させる)
達成感の報酬(アクションに対する成果に対し報酬)
自律性の報酬(カスタマーが主導権を持っている感覚)
熟達の報酬
予測不能な報酬
・ピボットの検討
プロダクトのスプリントを回してUXを改善しても、ユーザー定着率が伸びない
ユーザ定着率は伸びるが、今の成長ペースでは市場で支配的なポジションを取れない
投資の5〜10倍のリターンを生み出す見通しが立たない。
・ピボットパターン
顧客変更、課題変更、事業構造変更(toB、toC)
ズームイン(プロダクトの一部に集中)
ズームアウト(プロダクトのスコープを広げる)
プラットフォームピボット
チャネル変更
・バーンレート 現金がなくなる早さ
・ダメなピボット
エンジニア不足によるもの
カスタマーの声と無関係にピボット
検証結果によらない主観的なピボット
やりきっていないピボット
・ユニットエコノミクスにフォーカス
本業からの収入に集中する
LTV(顧客生涯価値)を計測する
UXをあげ一人上がりLTVを最大化
熱狂顧客を作り出す
定着率が低い理由を分析
Posted by ブクログ
ウェブコンテンツの焼き直しかと油断してたらスタートアップ成功の秘訣を体系立てて驚くほど科学していた。著者の研究と経験の知見がふんだんに盛り込まれている。海外には『リーン・スタートアップ』などスタートアップ科学の良著が数あれど洋書の独特の「ノリ」がある。対して本書は日本語ネイティブの日本人が書いた有難い本である。
MVPやAAARR、アジャイル開発については類書で良く語られることだが、書籍の3分の1程度割いて課題設定・検証を説いているのは好感が持てる。それほど重要な論点ということである。ほか各ステージで大切なことや犯しやすいミスが丁寧に解説されておすすめである。
1つ不満としては大判サイズで重くて扱いずらいので、単行本サイズにして手元で都度参照できるようして欲しかった。
Posted by ブクログ
今検討しているアイデアは顧客にとって本当に痛みのある課題なのか?
課題に対し、高い専門性・業界現場の知識・自分で痛みを感じているか
自分がそこまで共感や思い入れがない他人の課題は避ける
スタートアップは誰が聞いても良いアイデアを選ぶべきではない
スタートアップ Jカーブ、スモールビジネス 一次関数
スモールビジネスこそ地域で生き残る凡人経営者がとるべき道。ランチェスター戦略を採用する
リーンキャンバスをつくり、早くサイクルをまわす
スタートアップはサイドプロジェクト 本業があって余裕を持ちながらやる
Posted by ブクログ
* スライドを書籍化したものだからか誤字脱字は目立つ。が荒削りだけどとりあえず出す、というスタンスはlean startupを体現していていいんじゃないだろうか。
* かなり体系的にまとまっていて、起業をする前に一度騙されたと思って試していく、というのはすごく効果があると思う。特にPMFと製品観点の観点ではキーとなる概念をとてもわかりやすくまとめているので、チームの共通言語として使ったりするのには便利。
* とはいえこんな綺麗に一つ一つ沿って進めているスタートアップなんてほとんどいなく、後から振り返ってできてることだよなーとは、実際に足を踏み入れると思うのもたしか。スタートアップに関しては、ある程度バカであるから始められることは、実際悪くもあるが良くもある。歳をとったり、MBA出たり、やたらスタートアップに詳しくなったり…頭がよくなればなるほど、始めにくくなるというのはとても多い事例で、実際始めて死ぬスタートアップよりも、始められずに死ぬケースの方が実際は無数にあるのではないだろうか。
* 個人的には「Collision Installation」の話にはハッとさせられた。この本にも出てくるが、スタートアップは一つのことにフォーカスする為に圧倒的に無駄を排除しなければいけなく、ついつい外出とか過度なサポートというのはNoと言いがちなんだけど、大企業ではなく、小さなチームだからこそできる泥臭さというのは実際本当に大事なところだよなと。