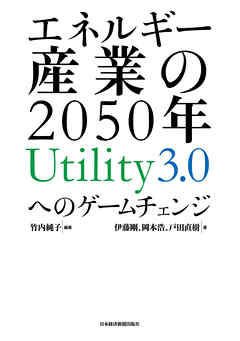感情タグBEST3
Posted by ブクログ
エネルギー業界初心者でも、kWh価値, kW価値, ΔkW価値が何を意味するのか、再エネ増加が電力システム全体にどのような影響をもたらすのか、今後の電力サービスはどうなるのか、を概観できる良い本でした。電気自動車のTeslaがVPP事業を手掛ける現在、全貌を理解するのは大事だと思いました。
Posted by ブクログ
内容としては少々物足りないものの、エネルギーにまつわる産業の現状及び将来図を描いた良書である。特に、kWh・kW・ΔkW価値(DER化に伴い、kWとΔkWh価値向上)や託送料金に関するデススパイラル問題、電気自動車の市場参入等は分かりやすくまとめられており、なるほどと感じた。需要家目線では普段気にすることはほとんどないが、日本における電力制度設計は複雑であり、これらの課題に対応すべく柔軟に変更していく必要があるのだろう。
ただし、太陽光や風力発電等の再生可能エネルギーや蓄電池の指数関数的価格破壊が起こりうる、そうなった場合には冒頭のストーリーのように電気代という概念がなくなる、といった記載があったが、現状からは到底想像もつかないため夢物語であると感じてしまった。そのような未来が到来する日がくるとよいが、、、
Posted by ブクログ
インフラ小売業の未来予測。総括原価だった1.0の時代、自由化の2.0の時代の先を占う。
電気インフラは特に影響が大きい、人口減少、同時同量、分散電源化、kwh価値の減少とΔkw価値の増大、電気as a serviceのような流れ、電気自動車の普及。
料金体系から見直すんだろうな。
Posted by ブクログ
電力ビジネスの今と未来について書いた本。素人にも分かりやすい言葉で書かれている上に、内容がコンパクトにまとまっているので時間をかけずに読むことができた。
原発事故でも感じたが、電気は私たちにとって当たり前にある一方で、電力ビジネスは想像以上に複雑である。電気を使うことイコール本書で言うところのKWh価値を買うと一般的には思われているが、KW価値、ΔKW価値というユニバーサルサービス的なものがあっての電力市場だということはほとんどの人は知らないのではないだろうか。そうでなければこんな無邪気にSDGsとか言っていられないだろう。
現状KW価値、ΔKW価値をKWhに対する料金で賄っているということだが、再エネ普及でKWh価値がほぼ0になった場合は、電気代というのはどうなるのだろうか。すぐに思いつくのはNHKのようにユニバーサルサービス料金を一律で徴収し、KWh価値からはほぼ徴収しないまたは接続機器の個数やら電力量で課金していくような形だろう。
KWh価値であれば、余剰電力をビットコインマイニングなどの電気をそのまま換金するようなビジネスでペイできるかもしれないが、KW価値やΔKW価値はやはり公共とする、または電池に活躍いただくくらいしか素人には思いつかない。まあ、このような悩みは再エネが順調に普及するシナリオでの悩みなので、そのレベルにまで再エネを普及させられるかの方がハードルが高いだろう(むしろその長い道のりのなかで、KW価値、ΔKW価値問題解決の糸口が見つかりそうだが)
Posted by ブクログ
すでに自由化に関しては進みつつあるのですけど、人口減少については過疎化でインフラの持続性の問題が起こること、そして脱炭素化は世界的な潮流となっているため、日本にとっては国をあげて対策が必要になるなと。
対策案として分散化の項目に該当する分散型電源の普及になります。日本の太陽光発電の現状も公平に書かれていてわかりやすかったです。
インフラは生活で必要不可欠なものですし、そういう意味では日本でも合併で規模が現状よりもでかい会社ができたり、サービス提供会社への転換する可能性を頭の片隅に置いておきたいですね。
Posted by ブクログ
本を読んだり聞いたりして地球温暖化はガチでやばいんだと理解したので、再エネ系の本ということで読んだは良いものの、内容が難しすぎて細かい所はわからなかった笑
未来に向けて電気のあり方を変えていく必要があるのは分かった、
このままいくとライフライン維持が難しくなったりもするし、改善した方が楽しい未来がありそう!
とにかく今の火力発電や原子力発電以外のものでの発電(太陽光、洋上風力など)を増やす
指数関数的に蓄電技術を伸ばす
EVの普及
など投資対象を探す、それに投資する明確な理由を見つける良い本だった
Posted by ブクログ
エネルギー関連の本を読むのが初めてだったが、分かりやすかった。
ただ初めて知ることが多すぎて理解しきれていない気がするから読み返す必要はありそう。
Posted by ブクログ
娘が生きているであろう2050年、2100年へと思いを馳せながら読んだ。約6,000万人まで人口減少すると予測されている2100年の日本。人口減少を見据えたコンパクトシティの実現、妥当性を確保した発電設備のスリム化のために、これまでよかれとされてきたユニバーサルサービスを見直す必要があるという提言が興味深かった。
Posted by ブクログ
【内容】
エネルギー業界が直面している、あるいは今後直面するであろう変化について「5つのD」というキーワードでまとめられており、それぞれのDに対する問題点やそれに対する筆者の考え(現状の分析や解決策等)が記載されている。
5つのD
1. Depopulation(人口減少)
2. Decarbonization(脱炭素化)
3. Decentralization(分散化)
4. Deregulation (自由化)
5. Digitalization (デジタル化)
【感想】
「5つのD」というキャッチーなフレーズでエネルギー問題が簡潔に述べられており、今後、日本はどのように変化していくのか、また何をどうすべきなのか、ということを考えさせられる内容だった。
特に日本が抱える大きな問題の1つである人口減少の影響により現状の電力インフラを維持することが困難になる(かもしれない)問題は、今後の更新工事を計画する際、設備の規模感を検討する重要なポイントになると感じた。
Posted by ブクログ
noteにも書いたけど、今後のトレンドを5つのDとしてわかりやすくカテゴリー分けされている点が良い。
またマネタイズ方法がモノから体験"サービス"に移ることをよく理解できる良書
Posted by ブクログ
エネルギー問題の専門家達が書いた、2050年時点でのエネルギー産業の未来予測とそこに至るベストシナリオ、ホラーシナリオ。最も印象に残ったのは、良い方のシナリオでいけば、2050年までにはエネルギー(特に電力)は、太陽光等の新エネにより、無尽蔵の供給を得るようになる、というところ。これはブロードバンド時代直前に「これからはジャブジャブ・インターネットになる!」と村井先生を中心として提唱していたあの頃のインターネット業界と重なるものを感じたこと。
ジャブジャブ電力が到来すれば、いまのあらゆる産業や社会は大変革を遂げると思う。機会が莫大に生じる。ベストシナリオだけを信じて今からいろいろ仕掛けたいなと前向きな気持ちになりました。
ちょっと時間がないので、またヒマな時に詳細を書き足します。
Posted by ブクログ
電力の2050年、特に原発が稼働せず人口も減少していく日本で、如何にインフラとしての電力供給を維持していくかを、東電在籍の著者等が若干電力業界寄りではありつつも極力フラットに書こうとしている良書。
分散電源や蓄電池の技術進歩が無いと手詰まり感がいっぱいと。
Posted by ブクログ
分散電源社会。
どちらかというと、CO2削減のためにはどんな社会にすべきかということを論考したもの。
電気自動車の存在が不可欠。
BERも重要。電流の周波数を安定化する役目だったり、提供価値は存在している
Posted by ブクログ
原子力についての考察はとってつけたような印象が拭えないが、縮んで高機能化する受給システムに、電力インフラをどのように接合するかについて深くて広い論点が挙げられており、内容は豊かだ。
Posted by ブクログ
私には所々難しかったけど今後のエネルギーや自身の生活を考えるには役に立った
風力発電などが優れているとも言い切れないこと、火力発電や原子力発電がそんなに悪くないこと
家ではガスコンロが絶対だったけど将来のことを考えるとオール電化にすべきかなとも思った
2050年豊かに暮らせていることを願って
Posted by ブクログ
2050年に向けて、電力にどのようなゲームチェンジが起きるのかまとめられた本。
マシーン同士が安い電気の話し合いをしてくれ、家庭の電気代が安くなるように働いてくれる未来は、なんだか想像すると微笑ましい感じがした。
Posted by ブクログ
エネルギー業界は外からだと全くわからない世界で、知らない言葉も多いので、そこそこ良い入門書だと思う。ただ読み物として面白くないので、なかなか進まなかった。(まあ横書きの本は大体そう)
Posted by ブクログ
評価
読みやすいと言えない。
しかし、今後の日本のインフラの在り方を考えさせられる。
数字を根拠にしっかりと考察されているため、わかりやすい。
米、英、中の実例をもとに、今後の方針を示しているため説得力がある。
感想
人口減少の中、インフラを保つことの難しさを痛感した。
電力業界をデジタルを駆使し、顧客体験をベースに改革することへの必要性、ワクワク性を感じたい。
原子力保有の考え方も、技術問題や環境問題の切り口から書いてあり整理できた。
電力小売としては、今後のニーズに応じて先手を打つことが大切。
Posted by ブクログ
30年後の2050年、エネルギー産業を取り巻く5つのD[Depopulation(人口減少)、Decarbonization(脱炭素化)、Decentralization(分散化)、Deregulation(自由化)、Digitalization(デジタル化)]について書かれておりとても参考になりました。日本や外国を取り巻くエネルギー環境を冷静に考えつつ、極端に脱原発・再エネ促進と向かわずに地球環境及び省エネについても考えていければ良いと思います。
Posted by ブクログ
エネルギー業界で働く身として非常に興味深い内容であった。
○電気の購入という概念ではなく、サービスの購入になる。(その中に電気代は含まれている)
○送配電事業者もPVや蓄電池の普及、人口減少によう需要減で全く安定的ではない。託送料金も簡単には上がれないだろう。
事実確認としては非常に役立ったが、一方でその対策としてはもう少し踏み込んだ具体的な内容が欲しかった。ビジネスモデルとかの具体的なイメージがあればより分かりやすかったと思う。
Posted by ブクログ
今後のエネルギー産業がどうなっていくかを分かりやすく説明した本。頭の固い私にはなかなかスッと入って来ない所も多く再読が必要だと感じた。電気は手段であり、今後家計費から電気代が消えるという考え方は面白く、実際にそうなっていくだろうと思う。昔は電力会社に就職すれば安泰だと思ってだけど、時代は変わって行くんだなと切に思う。