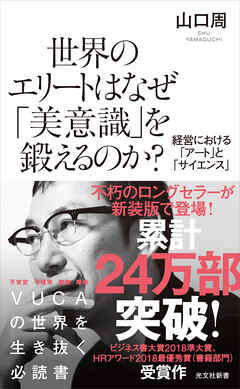感情タグBEST3
Posted by ブクログ
こんにちの世界において、論理的にシロクロつけられないときに頼れるのは美意識である。そんな内容。
顧客の美意識を優先するのか、自らの美意識を優先するのか、という点は、今までぼんやり感じてきたこと。
市場が求めていることをやるのか、自分のやりたいことをやるのかって話と同じなのかなと思った。
例えば売れるアーティストと売れないアーティストの違いって、自分がやりたいことがたまたま時代の雰囲気とか時代のニーズに合っていたかどうかが大きいよね?って思ってた。いや、狙うこともできるんだろうけど、「これは自分がやりたかったことじゃない!」みたいなことってあるよね。あるいは、時代が追いついてきた、とかもそう。
でもこれを書きながら思ったけど、本書のマツダの例は、それを超えて市場を引っ張るぜ、って話か。
てか、それを目指してきたアーティストや企業はたぶんこれまでもたくさんあるんだ。
こんにちの世界では、それがより強くなっているので、ビジネスマンレベルでもその美意識を鍛えることが必要ですよっていう話なのかな?
おりに触れて読み返したい。
Posted by ブクログ
時代がどのように変わっていこうとも、大切なことは今も昔も変わらないという、シンプルな結論が安心させてもくれ、勇気も与えてくれました。
頭でっかちになりがちな現代社会に生きる人たちにぜひ読んでほしい本です。
Posted by ブクログ
読む前
エリート層は資産に余裕があるから美意識を好むのかと思っていた
読んだ後
サイエンス重視の経営の限界
市場の変化
法整備がシステムに追いつけないこと
を挙げて内政や外交を担うリーダーのアートの要素が必要であることを説いている
PCDAサイクルのplanを担当するリーダーにとって哲学/美意識/倫理観を養うことの重要性が分かった
文章も要点を先行→後にその解説という構成で新書として読みやすい構成となっている
Posted by ブクログ
真・善・美を判断するための美意識を鍛える必要性がさまざまな面から語られていて、納得。狭い世間の掟を見抜き、人生を評価する自分なりのモノサシ、美意識を鍛えていきたい。より高品質の意思決定を行うために主観的な内部のモノサシを持つ。どうやって鍛えるか、の部分も納得!哲学をコンテンツから学ぶというよりもプロセスやモードから学ぶ、ということをもとに哲学の本も読んでいこう✊
Posted by ブクログ
「直感」と「感性」の時代⁈
論理的•理性的なスキルに、
更に美意識をプラスさせる!こと
【「美意識」を全面に出して成功したマツダの戦略】
がとてもわかりやすかったです。
論理的思考が苦手な私としては、
せめて、直感や感性を磨きたいですが、
それには、
自己認識=セルフアウェアネスも必要のようなので、毎朝のヨーガ(瞑想)を楽しんで続けながら、
「真•善•美」を意識していきたいです♪
Posted by ブクログ
現代はあまりに不確定要素が多いVUCAの時代であり、論理的、実証的に物事を判断し進めていくのが非常に困難になってきている。本著はそこで「美意識」が指し示す直感的に正しい方向へ経営を進めることこそが重要だと主張する。
これは5年前の著書だが、確かにビックモーター、ジャニーズ、自民党の不正献金問題、文春砲等の昨今取り沙汰されている問題を考えても、「正しくないこと」への現代の風当たりは非常に強くなってきている。利益至上主義、超合理主義ではどこかで危うく地雷を踏みかねない。
意思決定のモノサシに主観的な「アート」を用いるということは、身の破滅を防ぎ長期的に社会に利する企業への第一歩になりうると、大変共感できる内容であった。
Posted by ブクログ
比較的読みやすい内容でとっつきやすくすらすら読み終えた。現代の閉塞感からの解放として一助になる主張だと感じた。
アート的思考は、既存の枠組みやルールをに沿った上で、そのままでいいのかと疑いを持ち批判的に検証するための基盤。アートというと音楽や絵画が頭よぎっちゃうけど、ここでは広義に哲学や文学(詩)なんかを含め重要性を説いてる。
論理的理性的な判断は言語化可能=説明できるのに対して、直感的感性的な判断は言語化不可能、アカウンタビィヒティが低い=説明できない、でもそこに新しい価値を創造する力があるんだといった論旨だと理解。
会社のルールに縛られるなといった扇動的な主張ではなく、あくまで内部の人として席を置き、内部から改変するといった態度がこれからの「VUCA」な社会にはエリートに求められる。(堀元見の著作あとがきでVUCAいじってるの先に読んじゃって、ここでも使われてる!って変に気になってしまった)
ダマシオ「ソマティック•マーカー仮説」とアイヒマン絡みのアーレントはどの本にも触れられていて、利便性高いんだなーと感じるとともに、ではそれぞれのテーマに関する書籍(原著)に当たらねばと読書の連鎖は続いていくのです。
Posted by ブクログ
文字を通して「真実 善意 美」の意味と、なぜ経営者にアートが必要かが理解でした。内容ちょいと理解するには苦労するが、素晴らしい本である
私ごとのメモ
アートとは一瞬で美しい、良いな、と言う感性(理に適っている[論理])と判断力だ。
整理整頓も必要、不必要、の判断が必要で、ビジネスでもその様な「直感」が有る無しのスピードの差が結果に反映すると思う。
ネット印刷は「モノ」販売、印刷会社は「こと」を生業としている。同じ印刷物を製造としても、原点が全く異なる企業で有る。
Posted by ブクログ
偏差値が高いけど人の心がない。
この言葉がささった。自身を振り返ると哲学というものにこれまで触れてこなかったなと反省。より多くの思想や美的知識に触れ、自分の世界を広めていこうと思った。
Posted by ブクログ
素晴らしい本だった。近年読んだ新書の中ではベスト。
近年、企業の経営者たちは美意識を磨くことを重視しているそうだ。なぜなのか。その答えが明確に、論理的に示されていて、100%腹落ちした。世の中には頭がいい人がいるものだな~(著者のこと)。
戦略系経営コンサルタントとして様々な企業を見てきた著者は、成功している会社と行き詰まっている会社の経営方針の差に気が付いた。トップの経営者には、サイエンスとクラフト(経験)だけでなく、美意識が必要と思われる。アップルやマツダをはじめとする数々の実例が非常に興味深い。
消費者は何を求めているのか、そしてそこにあえてすり寄るのではなく、上から目線でアプローチする企業のもくろみは。
なるほど~と感心させられたのは、千利休が世界初のクリエイティブディレクターだったというくだりである。サイエンス的な戦略を担う織田信長や豊臣秀吉をアートの面から助言をし、見事に奏功した。将軍たちに美を理解するこころが無ければ、このコラボレーションは成立しなかった。つまり、リーダーには美意識が求められているのだ。
著者の主張は説得力があり、感心させられる。おすすめの1冊である。
Posted by ブクログ
何故かの答え
①論理的思考のコモディティ化
②世界中が「自己実現的消費」へ
③ルールの制定が追いつかない世の中
→自分はアートに弱いから、これからも、アートを学ぼう!
Posted by ブクログ
わかりやすい新書もあるものだなと思った。毎節軽くまとめがあり、最後には具体例を出さないとイメージしにくいですか?と聞いてくれさえする。なんて親切。
内容も面白い。経営は、アートとサイエンスとクラフト(美意識、統計、経験)の3つが混じっており、現代企業の多くはサイエンスとクラフトが重視されるが、それは最終的に「早くて安い」が評価指標となりいずれ限界が来る。その為、何が良いのかをマーケティングするサイエンスではなく、これがいいと提案するアートが必要になってくるが故、会社の中枢であるエリートにはアートが必要とのこと。統計的に有意なデータを取ろうとすると、エリート以外も混ざるのでどうしても「センスの悪い人たちの選好が混じる」というのはどきつい真実だなと思う。一部、短い引用一つを根拠に結論づけられていたのは気になったが、惹かれる言葉が選ばれていた。
一つ、アートが前に出過ぎると引き継ぐことが難しくなるのでは?と感じた。エリートの引き継ぎはそのあたりはあまり問題ないのだろうか。平民的な思考なのだろうか。
Posted by ブクログ
現代におけるアートの大切さがわかる
「THE VISION」と「VISION DRIVEN」と「武器になる哲学」がこの一冊で繋がった。
「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」という言葉に関して、
負けは論理的におかしいから負ける。勝ちは論理性がある上で、アートという視点があるから勝つ。
この視点はロジック偏重でもアート偏重でもダメで、そのバランスが大切という事を伝えてくれていた。
読み物としても非常に面白かった。
Posted by ブクログ
読む:10分
話す:5分
書く:5分
下記3つに親しむことの重要性が示唆されている。
◾️絵画
・VTSで見る力を鍛える
①何が描かれているか
②絵の中で何が起きていて、これから何が起きるか?
③どのような感情が、自分の中に生まれているか?
カラバッジオの「聖マタイの召命」は良い題材。キリコは良くない。
・パターン認識から自由になれる
ブラックスワン。トレーダーから科学者になった話。
◾️哲学
◾️文学
罪と罰。①知的レベルが高い青年が、②高利貸しの老婆を殺すことを正当化しようとするも、罪の意識に苛まれ、③家庭を支える売春婦の姿を見て、自首する話。全員が何かしら罪を帯びているけど、どれが一体罪なのか、考えさせられる話。
Posted by ブクログ
私たちの持つパターン認識能力が、いかにして美しいという感覚の換気を妨げているかについての小林秀雄の文章が心に残った。
例えば、諸君が野原を歩いていて一輪の美しい花の咲いているのを見たとする。見ると、それはスミレの花だとわかる。なんだ、スミレの花か、と思った瞬間に、諸君はもう花の形も色も見るのをやめるでしょう。諸君は心の中でおしゃべりをしたのです。スミレの花という言葉が、諸君の心のうちに這入って来れば、諸君はもう眼を閉じるのです。それほど、黙ってものを見るということは難しいことです。言葉の邪魔の入らぬ花の美しい感じをそのまま持ち続け、花を黙って見続けていれば、花は諸君に、かつて見たこともなかった様な美しさを、そへこそ限りなく明かすでしょう。
Posted by ブクログ
論理とデータが支配する時代に、「直感」と「感性」の重要性を訴える一冊。著者の山口周氏は、組織開発やリーダー育成の専門家として、不確実なビジネス環境で成功するための新しい方法を提案しています。
この本に手を伸ばしたのは、ビジネスにおける「美意識」がどう役立つのか知りたかったからです。山口氏の視点は、これまでの著作にも見られる新鮮さと独自性に満ちています。
読み進めると、「美意識」が現代ビジネスにおいていかに重要かが明らかになります。例えば、フェラーリのデザインプロセスの話は印象的です。デザイナーが追求する車の美しさが、単なる移動手段を超えた芸術作品を生み出しているのです。
また、「美意識」を鍛える方法も紹介されています。アートや文学に触れることで感性を磨き、日常で美を見つける習慣を持つことが、ビジネスだけでなく、個人の生活を豊かにするためにも役立ちます。
「美意識」は、芸術的な感覚以上のもので、ビジネスにおいても強力な武器になります。山口氏は、経営に「美意識」をどう組み込むかを具体的に示しており、リーダーシップにおいても直感や感性の重要性を強調しています。リーダーの美意識は、組織の方向性を直感的に捉え、成長や革新を促進する力であることを、私は本書を読んで痛感することになりました。
総評として、本書は、新たな視点を提供する画期的な本です。直感や感性が新たな武器としていかに重要かを教えてくれます。得られる洞察は、ビジネスパーソンに限らず、あらゆる分野で活躍する人々にとって有益です。自分の美意識を見つめ直し、それを日常や仕事に活かすきっかけになると思います。
Posted by ブクログ
・論理的思考は誰でも身につけられ、それにより正解のコモディティ化が生まれている
・つまりは、似たようなサービスが生まれ差別化が図れない
・そのような社会では、何を実現したいかというビジョンが大事
・ビジョンは人をワクワクさせ、ビジョンにはストーリーが必要で、ストーリーは誰にも真似できない
・つまり、それこそが唯一無二となる
・これを実現するためには、美意識を鍛える必要があり、それは小説・哲学・美術館賞・瞑想などにより高められる
・パターン化ではなく様々な視点で物事を見る特性を養い、自分なりの感性を磨いていくことが重要
Posted by ブクログ
同僚に勧められて読んだ。とてもいい読書だった。
・論理的、理性的な情報処理スキルの限界
・市場が自己実現消費へ向かっている
・システムの変化にルール、制度が追いつかない
内在的に真・善・美を判断するための美意識
→ビジョン、行動規範、経営戦略、表現
意思決定におけるアート、サイエンス、クラフトは、アカウンタビリティー偏重ではダメ
イノベーションは機能、デザイン、ストーリーで成り立ち、ストーリーはコピーされない。
美意識を鍛えるためには、絵画、哲学、文学、詩
Posted by ブクログ
思っていた内容とは違ったけど、面白かった。
サイエンスや経験重視の意思決定に染まってしまっている現代社会の停滞を打ち破るには人々が「美意識」を鍛え、それを活用していく他にないという主張を伝える1冊。
Posted by ブクログ
ビジネスパーソンこそステレオタイプになっている
システムの外にいる人にはシステムを変えることはできない
まさに今自分が直面している課題を克服する言葉に出会えた一冊
Posted by ブクログ
「美意識」とは「アート」の話かと思っていたら、「哲学、倫理」のほうが比重が大きかった気がする。
脳科学の話は面白かった。「美しいもの」を見ると脳の前頭前野の血液量が増し、そこは意思決定の中枢に関わるという話。瞑想によって鍛えられるという。
著者は美意識を高めるために重要なのは「見ること」だと述べているが、「見る力」をデッサンによって叩き込まれる美術大学からは、なぜエリートがあまり生まれないのだろうというのは気になる。
Posted by ブクログ
論理的、理性的に考えて経営を行うのには限界があり、それに加えてアートを取り入れるべきだ、という最近の世界のエリート界での傾向について、様々な角度から説明している。
スポーツも将棋もビジネスも、技術や能力に加え、美しさがあるのとないのとでは大きく違うという。
勉強になりました。
Posted by ブクログ
確かに昔より格段に世間の美意識は上がっていて、それに企業も応えられないと企業は生き抜いていけない世の中になっていることに納得。
日頃読むビジネス書には論理的思考などの昔ながらのスキルを磨くことが書いてあり、自分もそう思っていたけど、それ以外の感性も大事な要素なのだなと感じた。
Posted by ブクログ
パブリック・スピーカー(?)である山口周さんの本。
エリートでもグローバル企業の幹部でも会社の経営者でもない私には、本書の取っ掛りから自分にはこの本は向いていないかも、と思いました。
けれどまずは結論から述べられている読みやすさに加え、ウォークマンの製品化のエピソードやスティーブ・ジョブズ氏のiMacの5色のカラーでの販売の意思決定、そのような「論理」と「直感」のバランス、アートとサイエンスのバランスがいかに大切かということをとても分かりやすく解説してありました。
そして、リーダーシップにおける言葉の力の大切さについても述べられていて、その力はまさにアート、即ち文学や詩によって育まれることも非常に納得でき興味深かったです。
「真・善・美」の判断においては、経営だけにとどまらず、その美意識が生きていく上での豊かさ、正しさ、美しさに繋がるものだと感じました。
著者が最後に「物質主義・経済至上主義による疎外が続いた暗黒の19~20世紀が終わり、新たな人間性=ヒューマニズム回復の時代が来た」と述べられていますが、この本が2017年に書かれ、その後コロナ禍が訪れまさに世界がそのように変化していることを実感している今、この人の先を見すえる視点がなんて鋭いのだろうと感心せずには居られませんでした。
Posted by ブクログ
経営は、「サイエンス(分析・論理・データ)」「クラフト(経験則)」「アート(直感・美意識)」の3つのバランスが重要であり、昨今の日本はアートの部分が欠けていることを指摘している。時間をかけてアート的な思考を磨いていきたいと思った一方で、現時点での自分はサイエンスとクラフトも圧倒的に不足しており、本書に書かれていることを都合よく解釈せずに、自分自身をしっかりと分析し、サイエンス、クラフト、アートをバランスよく身につけていきたいと感じた。経営を抽象的な概念で捉えている本書は、実務的な部分からは離れ、俯瞰して思考を捉え直すのに役立つと思う。
Posted by ブクログ
サイエンス(合理性)だけを追求するのではなく、「美意識」によって差別化を図ることの重要性を説いた本。
確かにサイエンスの行き着く先は均質化(正解のコモディティ化)であり、それだけでは他社・他人との差別化を図ることができない。そこで、倫理・理性・信念とも言い換えることができる美意識を鍛えることにより、数値だけでは白黒をつけることができない事象に対しての判断力を養っていくことがこれからの時代により重要となる。
着眼点が素晴らしく、非常に学びとなる本。一方で、著者の山口周氏のウンチクを随所に盛り込んでくるところが何とも好きになれない。本書の本質は冒頭の2割くらいに詰まっており、残りの8割は著者のうんちくがダラダラと語られているだけの気がして、冗長な感じがした。