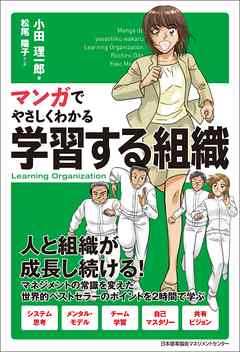感情タグBEST3
Posted by ブクログ
同時期に出た入門書の内容に絵をつけただけかと思い、それでも入りやすいかと購入。大胆にもう一段まとめられていて、判りやすかった。
実践しようと思う時に、具体的なアクションがシンプルにまとまっていて良い。
Posted by ブクログ
マンガ最高。
組織における「学習障害のものさし」。危機的なレベルの計り方がわかる。
また、「認識ギャップがあるな。」と表面的に気づいていたりする事柄が「なぜなのか?」の部分が体系的に理解できる。
感情的な部分で現場では見落としそうなところ
「悪いのはあちら。私はこれだけやっているのに。」と思ているのだが、実は構造上の問題であり、そういった気になってしまう事に気づく事が一番のキー。
オープニングの「ビールゲーム」のところで、マンガの読み手は気づく。
ゲームと実際の現場では違い、自分で気づくのは難しいという事。内省力が試される事。
よって、採用で掲げている「素直さ=柔軟性」「自分で考えて行動できる=好奇心・推進力」はとても合っていると思った。素直さがないと、内省できない。
「私はこれでやってきた」とい過去の囚われは無駄であり、やはりアンラーンは重要。
レベル1:儀礼的な会話
チームの初期段階。丁寧さが出ているが、この人はこうだろうと既にバイアスがかかっている事が多い。難しい課題にチャレンジし、何かを創造してくような仕事はできない。何年もたっていながらこのモードでしか話ができない数多くのチームがある。
レベル2:討論
誰かが提案したときに、賛成するときもあれば反対する意見もでる。一方で、反対意見がでてきたままでお互いの立場前提を変える事ができなれれば、創造的な解決ができなければならない。
レベル3:内省的な対話
意見の違う相手であっても、その人の立場になって、共感的な聞き方ができる事
自己内省な話方をすることができる。
レベル4:生成的な対話
自分も他人も相互につながっている全体の一部であるという前提ではなしができる。
共有ビジョンがもたらすもの
私たちは何を創るのか、私たちはどうありたいのか。
使命はは組織がなぜ存在するのか。
ビジョンは組織が何をつくりだすのか。
価値観は組織がどのような基本理念や規範を大切にするのか。
共有ビジョンの善し悪しは、それがどんなに美しい言葉であるかではなく、どれだけ社員の心を動かし、行動を引き出すかである。
Posted by ブクログ
学習する組織について、知人が数名学んでいるようだったので、夫の本を拝借しました。
自己マスタリー、信奉理論、使用理論に関心を持ちました。ちょっと活用したいものがあるので、部分的に再読しようと思います。
Posted by ブクログ
会社の研修の事前課題図書なので読んだ。
自ら学習する組織を作る方法を、分かりやすく分解し、説明してくれた本。
この内容を最大限分かりやすくした本だと思う。
自ら学習する組織を作るためには
自分の内面を直視し、
間違った認識に基づき行動していないか、
自分のビジョンは何かを見定めたり、
必ずしも関係が良好ではない相手とも
コミュニケーションもとるよう促す場面があったり
(目標はビジョンを1つにして共に学習する仲間に
なることだけど)
実践するには精神的にかなりしんどいな、
というのが率直な感想。
それができたら、乗り越えられたら素晴らしいけど
傷ついたり感情をマイナスに揺さぶられそうで
怖い。
最後に、タイトルは「マンガでやさしくわかる」
ですが、この本はマンガは一部分でしかなく、
文章がほとんど、と思って読んだ方がいいです。
マンガのおかげで分かりやすくなっているけど、
マンガとたかを括っていたら、内容のボリュームに泣きました。。
Posted by ブクログ
チームとしての経験学習サイクルが学べる本。
「漫画で優しくわかる〜」
と書いているけど、具体的な内容は文を見なくてはならず、またその文章も長い。
漫画は多く語りたい作者の熱を和らげるものとしての挿絵程度に思っておくと良い。
しかしながら文は実践的なものも多く、人事やコーニングに悩む人には良いかもしれない。
Posted by ブクログ
組織について考えるときに、自分の理想通りに周囲を動かかそうとしてはいけない。人間は駒ではない。みんなでビジョンを共有し、主体的に動いていったとき、理想を超えた世界が見えてくる。
Posted by ブクログ
メンバーに熱量を感じない、積極性を感じない、受け身な姿勢を感じているけど、チーム一丸となってもっともっと大きな成果をあげたい、と考えているリーダー向け。
システム思考、メンタルモデル、共有ビジョンといったテクニック・ツールに初めて触れる人には大変おすすめの書籍。
マンガは全体の3分の1程度だし、入門書としてはやや難解な部分もあるかもしれないという印象は、ある。
自分自身はこの本をとっかかりに「学習する組織」に挑戦するところ。
Posted by ブクログ
54
・自己マスタリーと共有ビジョンが育まれること。多くのマネジメントが不要になる。
・共創的な対話する力。相互の学び合いが起こる。
・複雑性を理解するシステム思考。個人の問題ではなくシステムのエラーに着目する。
Posted by ブクログ
マンガを通じてエピソードを学べるものの、主要な解説は文字ページによる。バラバラの状態から「学習する組織」に変わっていく対比が見事。キーパーソンと関係を作るのが大事か。
Posted by ブクログ
組織を成長させる方法を物語形式で解説するマンガ。
マンガのページは多い様に見えるが、実際は活字の部分も多くて入門書としては読み応えがあり、あまりスッと理解できない事も多いと感じた。
個人的に直ぐに取り入れたいと思ったのは2つあって、1つ目は複雑性を理解すること。
見えている課題に氷山の一角で、その下に本当の問題が隠れているという考え方。時系列パターン、構造、メンタルモデル(意識や考え方)まで掘り下げると根本的に解決する。
2つ目は意見が合わない時は推論の梯子を降りるという事。なぜその意見にたどり着いたのかを一段ずつ説明するとお互いの理解が深まる。
不満が多かったり成長しないチームや組織を何とかしたい人にオススメです。
Posted by ブクログ
センゲの『学習する組織』について、マンガだけならごくさらっと読める。
ポイントである、システム思考、メンタル・モデル、チーム学習、自己マスタリー、共有ビジョンの概念や実践のためのプロセスとツールは本文の方でしっかりと説明されている。
どちらかと言えば本文中心で、マンガは解説のためのエピソードといった位置づけなので、マンガだけで理論までやさしく学ぶことを期待すると手こずるのでは。
17-117
Posted by ブクログ
マンガのページ数は文章のページ数より少ないです。笑
「学習する組織」の概要がわかります。ただ学習する組織はコンポーネント(要素)が多いので、本著ではそれぞの要素の解説は比較的あっさりしています。しかし、要点は外していないので入門編に最適です。
Posted by ブクログ
マンガだが、やさしくは分からない
学習する組織の内容より主人公の行動力に圧巻
◆氷山モデル
メンタルモデル→構造→時系列パターン→出来事
◆信奉理論と使用理論
前者は自分の頭の中のメンタルモデル
後者は実際に行動する際のメンタルモデル
両者が異なってしまうことが多々ある
例:工場で手伝いたいと言いながら服はスーツ
Posted by ブクログ
会社の先輩に勧められて読む。やはり漫画が間に入っているので、理解を促進させてくれるのがいいですね。
個人的に一番ためになったなと思う部分は、メンタルモデルの部分です。仕事だけでなく普段の生活でも、どうしても先入観などが邪魔して必要なことを考えるのを排除させたり、実際とは違う考えを持ってしまうというのはよくあることです。そういったことを避けるためにも、お互いの推論のはしごがどの位置にあるかを把握するように心がけ、また、視座の転換によって相手の主張を理解しようと心がけることは必要なことだと思います。日本人同士でもお互いの主張がハイコンテクスト過ぎて伝わらないこともあるので、とくに背景の異なる外国人だとなおさらこういった部分を気にしないといけないですね。
Posted by ブクログ
マンガでエッセンス的なところはつかめますが、使えるようにするにはそれなりに理解を深めることが多く、ちゃんと読むことが求められます。基本的にはよい本だと思います。
Posted by ブクログ
マンガの部分はかなり分かりやすかった。
概念的な話なので、章の間の補足説明はすんなり分かるものと分からないものがありましたが、組織改革には各層がリーダーとなり一人一人のマインドを変えることが必要だと理解しました。論理的思考をしがちなので、システム思考についてもっと知りたいと思いました。
内容は面白かったのですが自分が概念的な理解が及ばず、補足説明部分でアッサリだった分マイナスにしました。
重要だと感じた点をメモベースで。
・階層のある組織で他責や無力感を感じるのは受け身の姿勢だから。自分事で捉えることが創造的な組織につながる。
・論理的思考はシンプルな問題への解決法、システム思考は複雑な問題や答えが複数ある場合の解決法。
・視点のレベルには4つある。出来事ベースで見ると反応的な対処しかできない。傾向パターンに注目すると計画的な対応かできる。構造で見るとより戦略的になる。メンタル・モデルで対話を行うと創造的な対応がてきる。
・自分の知らないことを素直に受け入れ探求すること、自分が知っていることから仮説をたて主張することを繰り返すのが大事。探求を高めるには相手に真摯に問いかけること。