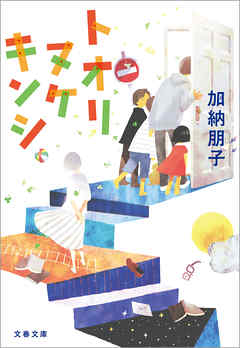感情タグBEST3
Posted by ブクログ
短編集なので、感想文を書くのが難しいのですが...
一冊通しての印象は、やはり「心ほっこり系」かな(^ ^
全編通して、割と淡々とした文体で、
さらりと読めるが内容は意外と重い。
巻末の解説を読んで初めて気づいたが、
通底する共通項は「珍しい病気・障害・体質」。
ネガティブなだけではないので、病気とは限定できず。
物語の主役たちは、ちょっと変わった症状を抱えていて、
そのおかげで「社会」とちょっと普通じゃない
関わり方をしている。
そのおかげで、ちょっと普通じゃない事件とか
「現象」とかに遭遇することになる。
本作で重要なのは、主人公の「周辺人物」の存在。
それぞれに活躍したり、別の障害を抱えていたり、
おせっかいを焼いたりと、主役との関わり方はまちまち。
だが全編通して、周辺人物のおかげで話は進み、
物事は解決に向かっていく。
全てがハッピーエンド、とはならないが、
それでも「前向きな終わり方」が描かれて
読後感はとてもさわやか(^ ^
難病からの政官経験を持つ作者だからこそ
生み出せた愛おしい作品たちであろう(^ ^
Posted by ブクログ
素晴らしかったです。
短編集で、連作ではないけれど、最後の話でのみそれぞれのその後が垣間見える構成になっています。
場面緘黙症や、共感覚、相貌失認など、最近少しずつ知名度の上がってきたものを取り入れながら、大仰にし過ぎず、かといって軽んじることなく、この作者らしい優しく温かな文章で物語を綴られています。
どのお話も好きですが、『フー・アー・ユー?』が一番可愛らしくて好きかな。
『空蝉』や『座敷童と兎と亀』とも好きです。
Posted by ブクログ
○ ぼくは人の顔が識別できない
あなたはそんな事を言われたらどう思うでしょうか?
○ コンタクトレンズを入れたら、また、〈声〉が聞こえるようになった
あなたはそんな事を言われたら聞き間違いだとは思わないでしょうか?
では、小さなお子さんにこんな風に話しかけられたらどうでしょうか?
○ やさしかったおかあさんは、おそろしいバケモノにたべられてしまった。ほんもののおかあさんはたべられてしまって、いまうちにいるのは、おかあさんのふりをしたバケモノなんだよ
この作品は、これらのえっ?という文章に続く物語がまとめられた短編集です。それにしても『人の顔が識別できない』とはどういうことなのでしょうか?『コンタクトレンズ』を入れたら、どうして〈声〉が聞こえるようになるのでしょうか?あなたはこれらに続く物語の内容を予想できるでしょうか?では、三つ目の小さなお子さんの訴えはどうでしょう。『ほんもののおかあさん』という言葉をヒントにして、多分そういうことなのだろうと思ったあなた、残念ながらこれはそんな単純な話ではありません。
そう、単純そうで単純じゃないこの作品は、そんな意味不明な事ごとの裏に隠された真実をそこに見る物語。読者の想像の遥か上を行くその真実の中に主人公たちの未来を垣間見る物語です。
さて、この作品の作者である加納朋子さんは2010年に急性白血病と告知されて緊急入院、弟さんからの骨髄移植を受けられ、回復されて現在に至ります。『病気をしたことで、人の身体の面白さと不思議さ、何か一歩調子を崩した時の怖さを実感したんです。それで、こういうテーマになっていったという気がします』と語る加納さんが描くこの作品。『他の人とは少しだけ違う病気や能力、後遺症』に光を当てる六つの短編から構成されています。一部弱い繋がりを持つものもありますが、基本的にはそれぞれが独立した物語。どの作品もその世界に読者を一気に引き摺り込む強烈なインパクトをもっています。
そんな六つの物語の中からまずご紹介したいのは一編目の表題作〈トオリヌケ キンシ〉です。『トオリヌケ キンシ』、『その札を見るたびに』、『そうか、ここからどこかに通りぬけられるんだ』と思っていた主人公の田村陽(たむら よう)。『古いマンションの外壁と、つぶれた銭湯の板塀との隙間、五十センチくらいの幅しかない』というその空間。『こんなとこ通るの、野良猫くらいだよ』と思っていたものの、ある日『じゃあ通りぬけてやろうじゃん』と思った陽。きっかけは『学校で少しだけ嫌なことがあ』ったから。それは、理科の時間のことでした。『かげはたいようの( )にできる』など『先生が黒板に書いた問題に、答えることができなかった』という陽。『じゃあこれは宿題』、となり、他の男子から『田村のせいだー』と言われてふてくされる陽は『アウトローな気分』になって『まるで秘密のトンネルみたいに見えた』というその空間を進みます。そして『生け垣の向こうに古ぼけた木造の家』を目にし『…ボロいうち』と呟く陽。『ボロくて悪かったですね』と真後ろからの声にぎょっとして振り向くと『今来たばかりの道に、女の子が立っていた』という光景。『なんで入ってきたの?トオリヌケキンシって書いてあったでしょ?字、読めないの?バカじゃない?』と『にくったらしい口調で』話す女の子は同じクラスの川本あずさでした。『おめーだって入ってんじゃん』と返す陽を横目に『ただいま』とその家に入ったあずさ。『あら、お友だち?』と出てきた女性に招き入れられ、おやつをご馳走になる陽。『あのさあ…ホラ、今日、最後に出た宿題さ、あれ、わかった?』と訊く陽に『とうぜん。簡単』と答えるあずさ。思わず『じゃあさ、教えてくんない?』と頼む陽に、あずさは『まず最初の問題ね…』と答えを教えてくれました。そして後日、『この間の宿題、ちゃんとやってきた?』と先生に当てられた陽。『かげはたいようの(おもいどおり)にできる』…と教えてもらった通りに答えた陽。『たいへんユニークな答えをありがとうございました』と先生から突き放され、『みんながゲラゲラと笑った』という展開。一方で『いちばん前にすわる川本あずさのノートが目に入』ると、そこには『かげはたいようの(はんたいがわ)にできる』と、正しい答えが書かれていました。『だまされた、バーカ』と『にやりと笑』うあずさ。『なんだよ、めちゃくちゃタチ悪いぞ、あいつ』と憤る陽は再び『トオリヌケキンシ』を無視してあずさの家へと向かいました。そんな陽とあずさの不思議な関係。そして、そんな小学校時代もやがて過ぎ去り、中学生になった陽。そんな陽は『おれは学校に行けなくなった』と『部屋に鍵を掛けてひたすら閉じこも』る日々を送ります。そんな中、あずさと再開した陽は、『私は子供の頃、出口のない道を歩いていたの』という、あずさのまさかの真実、あの時のあずさの態度の裏に隠されていた真実を知ることになります。そして…というこの短編。『トオリヌケキンシ』というとても気になる表題の裏に隠された物語。『どん詰まりに見えても、その先に道はある。トオリヌケキンシもきっと未来へつながっている』という加納さんの温かい思いがとても感じられる好編でした。
『他の人とは少しだけ違う病気や能力、後遺症』に光が当たるこの作品では『場面緘黙症』、『相貌失認』、そして『醜形恐怖症』と恐らく大半の読者にとって初耳の病名、症状を表す言葉がそれぞれの短編に唐突に登場します。いずれも架空のものではなく実際にそのことで悩み、苦しんでいらっしゃる方がいるという事実。そんな『病気や能力、後遺症』を大胆に描くこの作品。一般的にはほとんど知られていないというその現実とのギャップがこの作品から受けるインパクトをより大きくしているのだと思います。
そんな『病気や能力、後遺症』の中で最も衝撃を受けたのが四編目の〈フー・アー・ユウ?〉でした。『ぼくは人の顔が識別できない』という衝撃的な一文から始まるこの短編。そのことを『カミングアウトすると、たいていの人は「なんだそりゃ?」って顔をする』というのは、私も全く同じです。『俳優のブラッド・ピットが、自分がそれかもしれないと告白した』という事実とともに語られるその症状。それが『相貌失認』でした。なんと『だいたい人口の二パーセントくらいに現れる』というその症状は『人の顔だってことはわかる』ものの『AさんBさんCさんの区別がつかないというもの。下手すると男女の別も、年寄りと若者の区別もつかない』というその症状に苦しめられる主人公の佐藤。そして、そんな佐藤は名札のない中学校に入学したことで『僕はただ一人、のっぺらぼうのただ中に放り込まれてしまった』という事実に衝撃を受けます。しかし一方で、人の顔の区別がつかないと言われても私たちはなかなかにその症状を思い浮かべるのは難しいと思います。人は人と出会った時、まず顔を見ます。そして、会話をしながらも相手の表情の変化に最大限の注意を払いつつコミュニケーションをとっていきます。この能力が欠如した状態で果たして人と人とのコミュニケーションが取れるのか?という疑問も沸くその症状。実際、人の顔が認識できないことで『すっげー空気読めないヤツ』と認識されていく佐藤の苦悩は、私たちの想像を遥かに超えるレベルのものだと思います。そして、『どうしてこんなにも、生きにくいんだろう?』と思い悩む佐藤が主人公のこの物語は、読者の予想のはるか上を行く展開を経て、まさかの幸せな結末を迎えます。人間社会のある意味での多様性を深く感じ入ることになったとてもインパクトのある短編でした。
『他の人とは少しだけ違う病気や能力、後遺症』に苦しめられる主人公たちを描いた六つの物語は、それだけ聞くと主人公たちが悩み、苦しむ陰惨な展開が予想されます。しかし、この作品の作者は加納朋子さんです。『小説を書いていていちばん思うのは、ハッピーエンドにしたいなということです』とおっしゃる加納さん。『世の中がままならないことばかりだからこそ、話の中では救ってあげたいなという気持ちがあります』という強い気持ちをお持ちの加納さんが描くこの作品は全て大団円の結末をそこに見る物語です。苦悩を経て歓喜に至る六つの物語。それは、それぞれの今を必死に生きる主人公たちがその先に確かな未来を見る物語でもありました。
『トオリヌケキンシ』の先に続く、その先にもきっと続いているであろう未来を見るあたたかな物語。取り上げること自体とても重いその内容の数々を、敢えて軽く、分かりやすく読者に提示してくれた加納さん。そんな加納さんの温かい眼差しをとても感じる作品でした。
Posted by ブクログ
加納朋子のトオリヌケキンシを読みました。
病気や症候群をテーマにした短編が6編収録されています。
一番気に入ったのは平穏で平凡で、幸運な人生でした。
形から音につながる共感覚を持っている女性の物語でした。
普段は特に役に立つわけでもないのですが、いざというときに幸運にもその能力が役に立ちます。
そして、最後の短編が無菌病棟から生還した加納朋子の実体験を元にした物語でした。
加納朋子が生還して新しい物語を読むことが出来る幸運を慶びたいと思いました。
Posted by ブクログ
病や悩みを抱えながら、でも最後はみんな幸せになっているから良かった。バッドエンドだったら、読むのを途中でやっめていたかも。
作者の方が大病した経験があることを知らなかったけど、やはり病気をした前と後では、考え方が変わるだろうな。
そういう視点で、病気前の作品も読んでみたい。
Posted by ブクログ
きっと人は、自分が周りと違う部分を見つけては悩んで、苦しんでいるんだと、この小説を読んで思った。もちろん、私だってその一人だ。
加納さんはそんな人たちを、持ち前の優しさで救い上げていく。
タイトルのように、トオリヌケキンシの袋小路に迷いこんでしまったとしても、出口はあるのだと背中を押してくれる。
きっと、きっと、大丈夫。
Posted by ブクログ
大好きな加納朋子さんの短編集。
相変わらず安心して読める優しい話が多いです。
幻想的な話かと思いきや、現実的な話で、だけど結末はファンタジーと言えなくもない。
真面目な人が報われる、親切な人達が沢山いる、こんな優しい世界だったらいいなという希望と、そうなるかどうかは自分次第という叱咤激励と。
そして最後の「この出口の無い、閉ざされた部屋で」で泣かされてしまった。
加納朋子さんの書くお話は一貫しています。
生きているものは、生き続けなければならない。
逃げても迷っても立ち止まってもいいけど、いつかは前に歩き出さなきゃいけない。
読み終わるといつも、世界がほんの少し明るくなったように感じられます。
Posted by ブクログ
場面緘黙症、共感覚、被虐待、相貌失認、半側空間無視…
少し繊細な事情を持ち、自分は他との人は少し違うという事に戸惑い傷ついたりする人達。
場合によっては世界を閉ざしかける彼らを引き戻してくれる誰かの手、それは恋人だったり友だったり家族だったり。
加納先生らしい心にじわっと染みる、優しく温かい短編集。
Posted by ブクログ
この作者お得意の、事情を明かされるとこれまで読んでいた世界がガラッと違った世界に見えてくるお話が6つ。
話のミソに“他の人とちょっと違う疾病や感覚”があって、その使われ方にちょっと無理筋を感じる話もあったが、ソウボウシツニンにもめげず可愛い彼女(これがまたシュウケイキョウフ)との関係が微笑ましい「フー・アー・ユー?」と、ハンクウカンムシのおじいちゃんを巡って周囲の人が温かい「座敷童と兎と亀」が良かった。