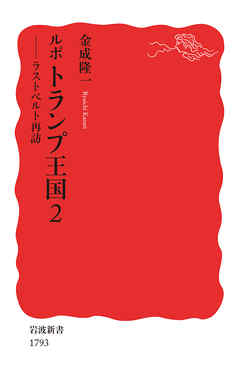感情タグBEST3
Posted by ブクログ
トランプがなぜあの時勝ったのか。既に今のアメリカはトランプが1期やってバイデンになってさらに中間選挙が終わったところ。トランプを積極的でも消去法でも応援、投票した人々の顔がくっきりと見える。
『貧困になるのは「働かない人だけだ」「教育を受けなかった人だけだ」と。全部私には当てはまらない。両親や国家から、やるべきだと言われたことを私は全てやった。私は働き、学び、軍隊にも入った。それでなぜ、私は空腹なの?なんで借金返済ができないの?』
この人はトランプを応援している人ではない。オバマからトランプの間もずっと生活に苦しんでいる。そして自分の声を届けてくれると信じた候補者のために活動している。
選挙の時に活動するということがどういうことなのかもまた、彼らに教えられる。
Posted by ブクログ
ルポ トランプ王国2: ラストベルト再訪 (岩波新書) 新書 – 2019/9/21
もう私達の知っていたアメリカ合衆国は無くなった
2020年5月31日記述
ルポ トランプ王国2 ラストベルト再訪
金成隆一氏による著作。
2019年9月20日第1刷発行。
1976年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒。
(大学の恩師は久保文明氏)
2000年朝日新聞社入社。
大阪社会部、米ハーバード大学日米関係プログラム研究員、国際報道部などを経て、2014年9月からニューヨーク特派員。教育担当時代に「教育のオープン化」をめぐる一連の報道で第21回坂田記念ジャーナリズム賞(国際交流・貢献報道)受賞。
好物は黒ビールとタコス。
他の著書に「ルポ トランプ王国 もう一つのアメリカを行く」
『ルポMOOC革命―無料オンライン授業の衝撃』がある。
トランプ大統領を支持、不支持をしたアメリカの市井の人々の話を取材しまとめた本。
回答した人々の顔写真もついていて良い。
とのトランプ王国2は前著に比べるとあまりヒットしていないようだ。
しかし、未来に当時アメリカの人々は何を思っていたのかという
第1級の資料になる事は間違いないと言える。
いつインタビューしたのか西暦、年月日が入っている点も良い。
今コロナウィルスの影響で2000万人もの失業者が出たアメリカ。
本書で出てきた人々にも多大な影響が出ていると思う。
そういった中で果たしてトランプ再選がなるのかどうか・・・
バーニー・サンダースが民主党候補として今回も出てこれない。
バイデン氏で果たしてトランプに勝てるのか・・・・
現職有利であることは間違いない。
ただ分からない要素が多い。
今回はどのメディアもまだ勝敗予想とかを出していないように思う。
相当に変数が多くて難しいという事だろう。
また別件で意外だったのが、ベトナム戦争時に
アメリカ兵が地上にいたにも関わらず枯葉剤をまいていた事だ。
ベトナム人だけではなくアメリカ兵も犠牲になっていた。
関税を引き下げて自由貿易を推進することで互いの国々が交易の利益を得ると経済学では解説される。
しかし現実社会ではそれは難しいというという実例をこれでもかと紹介された思いがする。
結局そこに人間が介在している以上は簡単にはいかない。
ただ同時に同じ仕事をずっと続けることができるほど幸福な時代はもう過ぎ去ってしまったということも言えるだろう。
常に勉強や努力を(方向性を大きく間違えず)続ける。
可能ならば住居地も動くことができる。
そんな生き方を模索するしかない。
ただ全員が全員そうは動くことも出来ない。
大変に難しい問題だと思う。
印象に残った点を下に列挙していきたい。
ラストベルトの労働者たちは、一般的に労働組合に属し、民主党を支持する傾向が強かった。彼らに「そもそもなぜ民主党支持だったのか?」
と質問しても、「そんなこと考えたこともない」
「この街で生まれ育てば、親の代から、みんな民主党支持だた」などと答える人が多い。
同じ街で暮らしていると昔の人間関係が戻ってしまうのね。小さな街だから。
後で調べると、ティモシーの「オバマフォン」発言は間違いだった。
「オバマフォン」とは、実際は連邦通信委員会が共和党レーガン政権下の1985年に始めた低所得者向けの制度「ライフライン」で、通話や通信を提供する。月額9ドル25セントで「無料」でもない。
ワシントン・ポストによると、オバマが就任した2009年ごろから、誤った情報が匿名メールなどで拡散し、ラジオ番組は「オバマがマイノリティや
貧困層を選挙に動員する道具として無料配布中」という陰謀論まで流していたという。
私はオバマフォンを理由にオバマ政権や民主党を批判する人に多く出会ってきた。
シンプルな偽情報は広がりやすく、何年経っても修正されない。
そんな典型例のように感じた。
トランプは「雇用を戻す」と連呼してきた。
この日の集会でも「出て行った仕事は「全て」戻ってくる」と言い切っていた。
ただマークもジョーも、それが無理なことは「わかっている」という。
非現実的と批判されることが多いトランプの言葉を、彼らはそのまま信じているわけではない。
ここにトランプ政権が一定の支持率を維持できている理由がある気がした。
↓
トランプが約束の1割でもやれば十分だよ
溶鉱炉の建設には膨大な資金が必要で戻ってくるわけがない。
そんなことはわかっている。トランプには環境規制の緩和やインフラ整備などでビジネスを刺激し、若い世代に少しでも仕事をつくってもらいたい。
地元の民主党トップ、デビッド・ベトラス
トランプのヤングスタウン集会の評価
私(著者)はこの民主党委員長ほど、この地方の実情を的確に説明する人を知らない。
彼は、アメリカの都市と地方の分断を皮膚感覚で理解している人物だと思う。
「あの演説の最大の見せ場は、「家を売るな」です。この意味がわかりますか?
この地域の労働者たちは、地元から仕事がなくなってしまったから、
価値の下がった自宅を二束三文で売り払って、どこかに引っ越すべきかと悩んできたわけです。
知ってか知らずか、トランプは「家を売るな」
「私が仕事を取り戻す」と言った。つまり、「私が仕事を取り戻すから、皆さんは大切にしてきたコミュニティにとどまって下さい」という
メッセージです。みんなそんな言葉を待っていた。
だから彼の演説に夢中になるんです」
オハイオ州などラストベルト諸州で連勝し、トランプ大統領が就任して半年。
民主党は敗北から立ち直れていますか?
民主党全国委員会はまだ敗因を十分に理解していない。
党の将来を全く楽観していません。
まず、トランプの言動一つ一つを
非難することをやめることが重要です。
非難ばかりしていると、
それが当たり前になり、誰も聞かなくなる。
民主党は失敗を今も繰り返している。
トランプや支持者を、人種差別主義者や
外国人嫌い、バカなどと侮辱すれば、彼らは二度と民主党に戻らない。
怒りにまかせての批判をやめないといけない。
批判は(自身への)支持にはならない。
有権者に響く方向性を示し、
メッセージそのもので勝たないといけない。
選挙期間中、街中にはトランプの看板があふれていました。
公式の看板だけでなく、手作り看板も多かった。
支持者が自宅ガレージで気持ちを込めてトランプ支持を呼び掛ける看板やポスター、バッジを作っていたのです。
あれは本物の支持者ですよ。
クリントンのメッセージが労働者に響いていないことは明白でした。
同じことは、ミシガンやペンシルベニアなど
他州の労働者にも起きているはずだ、と思ったのです。
製造業の流出に拍車をかけた自由貿易協定や貿易赤字などの争点で、立場を変えたクリントンは信頼されていなかった。
労働者の立場から声高に一貫して自由貿易を批判したのはトランプだけだった。
彼は黄金の便座に腰掛けながらラストベルトの労働者に
「皆さんはだまされたのです」
「私がワシントンに乗り込み、既成政治家の
問題を一掃してきましょう」とツイートを送り続けた。
彼には執事もメイドも調理人もついているでしょう。
アメリカ人の普通の暮らしがどんなものかも知らないはずだ。
そんな候補者に我々は負けたのです(頭を抱え込む)。
民主党は今後、どう変わるべきですか?
配管工、美容師、大工、屋根ふき、タイル職人、工場労働者など、
両手を汚して働いている人に敬意を伝えるべきです。
重労働の価値を認め、仕事の前ではなく、
後に(汗を流す)シャワーを
浴びる労働者の仕事に価値を認めるべきです。
彼らは自らの仕事に誇りを持っている。
しかし、民主党の姿勢には敬意が感じられない。
「もう両手を使う仕事では食べていけない。教育プログラムを受け、学位を取りなさい。パソコンを使って仕事をしなければダメだ」。
そんな言葉にウンザリなんです。
労働者たちに民主党は自らを「労働者、庶民の党」と伝えてきたが、民主党や反トランプ派はメディアを通じて(性的少数派の人々が)
男性用、女性用どっちのトイレを使うべきか、
そんな議論ばかりしているように見えた。
私が選挙中に聞かされたのは
「民主党は、私の雇用より、誰か(性的少数派の人々)の便所の話ばかりしている。」という不満だったのです。
そもそも、この地域で民主党支持だった労働者の多くは自らをリベラルとは認識していない。
リベラル派の争点は、彼らにとって最重要ではないからです。
労働者の関心は、よい仕事があるか、きちんと家族を養えるか、子供の誕生日にパイを用意できるか、教育を用意できるか、十分な休暇を取れるか、
自分の仕事に誇りを持って引退できるかなのです。
かつての製造業をラストベルトに戻すのは容易ではないと多くの人が言います。
そんな言葉は候補者の口から聞きたくないんです。
労働者の再教育という訴えも何度も聞かされた。
40歳代や50歳代になってプログラミングなんて出来ませんよ。
そんなメッセージは響かない。
なぜ労働者のための政策を実施すると訴えないのか。
インフラ整備は代表例。
古びた橋や道路を補修すれば多くの雇用になる。
彼らは汗を流して自分の腕で稼ぎたがっているんです。
トランプはそれがわかっていた。
労働者には、彼がワシントンに乗り込み、
既成政治家や利益団体と闘うファイターにうつった。
その気概がうれしかったのです。
具体例を挙げましょう。
トランプは就任前から工場移転に介入し、
「1千人超の雇用を守った」と誇った。
でもね、そのとき民主党側は
「ウソだ、守られたのは500人だ」と反発した。
必死でした。
それを聞いて、私は再び頭を抱え込んだ。
500人でも守られればプラスじゃないか、と。
その500人の雇用を本来守るのが民主党の仕事ではなかったのかと言いたかった。
今の左派の振る舞いは、保守派の思うつぼだ。
ICE廃止を掲げる政治家なんてアメリカ大陸の真ん中では信用されない。
最もマヌケな政策だ、頼むから黙っていてくれ
懸念するのは、保守派メディアが民主党の左派の主張をあたかも民主党を代表するものであるかのように報じ、警戒心をあおるからだ。
代表格がFOXニュース。オカシオコルテスの映像を流し、
「極左」「彼女は全米の人々が自分と同じ考えだと思っている」と伝えてきた。
アメリカ人の大半は、警察官や消防士ら最前線で法律を執行する人々に敬意を払う。
公務中に命を落とすなど危険な職務だ。
一翼を担うICEの廃止を掲げることには反発が起きやすい。
都市部で歓迎されても、地方では党内の候補者の足を引っ張る、という懸念だ。
大学の同級生は、みんなハイパーリベラルだ。
ところがここに帰省すると(ペンシルベニア州ルザーン群)
周囲はトランプ支持者になり、超保守的になる。
僕は明らかに同級生の中では保守派。
でも、移民を悪く言うトランプには完全に反対で、
そんなことを言うのは心が閉じているからだと残念に思う。
ところが、ハイパーリベラルの側も、異なる意見を持つ相手に「間違っている!」と非難するばかりで、まったく聞く耳を持っていない。
僕は、2つの「心の狭い」人々に挟まれていて、ちくしょう!という気分だよ」
帰還兵は一般に比べてトランプ政権を高く評価しているようだ。
公共放送PBSによると、2018年の中間選挙で投票した人のうち、
帰還兵の男性の58%が政権を「支持」していた。
これは一度も軍隊に属したことのない男性の46%に比べて高かったという。
一方、帰還兵の女性の58%は「支持していない」と答えており、
これは軍隊に属したことのない女性の61%と大きな違いはなかった。
全体では、帰還兵と軍人の56%が大統領トランプの仕事ぶりを「支持」しており、
43%が「不支持」だった。
一度も軍隊に属したことのない人の間では
「不支持」(58%)が「支持」(42%)を上回ったという。
Posted by ブクログ
本作は、トランプが大統領になった後の取材をもとにしたものです。
トランプ支持者(大統領になる前は支持していた人)への取材がメインですが、著者はトランプ支持者という訳ではなく、なぜトランプなのかというような立場であり、トランプの発言の誤りや支持者の誤解も適宜指摘しているため、バランスのいい構成になっていると思いました。
前作と本作を読んだことで、アメリカ大統領選挙関連のニュースや記事の捉え方も大きく変わりました。
色々論点はあるでしょうが、福祉制度や雇用創出といった課題に対する政策に注目していきたいなと思いました。
トランプは移民排除や貿易協定の見直し、オバマケアの廃止などをアピールしていましたが、今回の大統領選挙はどうなるのでしょうか。
Posted by ブクログ
前作に続いて丹念な取材が積み重ねられた作品。副題のラストベルトに加えて、深南部の超保守的なバイブルベルトについても1章分が割かれることで、米国社会の多様性が浮き彫りにされる。
トランプへの投票理由としてしばしば話されるのが、「ヒラリーが嫌いだから」ということだ。1970年代以降に民主党がエリート主義化し、白人ブルーカラーの声に耳を傾けなくなったことが、トランプ当選の背景として指摘されている。
Posted by ブクログ
前作に引き続き、地道な取材を通して等身大のアメリカを描出したルポ。
加えて本書では、専門家へのロングインタビューも収録されており、これがたいへん面白い。市民取材による各論と、専門家取材による総論。この両輪があるお陰で前作以上に読み応えがある。
Posted by ブクログ
トランプ王国の続編となる、ルポ書籍。
アメリカンドリームというのは、一攫千金で成り上がることだと漠然と思っていたが、「親の世代より裕福になること」のようだ。それはサービス業ではなく、製造業で成り立っている。
残念ながらそうなれなかった人たちにトランプのメッセージが刺さっている、という構造。
結局トランプが公約を全て達成できるわけでも、紳士的な振る舞いをするわけでもない現状に対し、引き続き支援する人、離れる人、理論的、感情的な実情について。
本筋とは離れるが、アメリカでは、(製造業のような労働集約型では、)時給ベースでの賃金体系で雇用されているようだ。
Posted by ブクログ
トランプ王国1からの続き。とはいえ2020年の大統領選のかなり前までの記述。前著と同じように丁寧な取材でアメリカの多様性を描く。明るい未来を描くことができない市井の人々という図式は日本も似たようなものかも知れないけど、逆説的に考えるとそれでもアメリカは(生き方の困難さですら)多様性に富んでいる。とはいえ第二次世界大戦後1950年代の黄金時代は日本の高度成長期と同じように二度と戻らない時代であることは受け入れざるを得ないだろうし、本当に身近にいない他人のことを自分のことのように気にして生きることも現実にはできない。ではどこに解決策があるのか。いや、そんなものはないのだろう。それでも人生には期待を持たないとやっていられないし。というように出口のない話であることは確かなので読んでいるとかなり落ち込む。
トランプの敗戦後の姿を見た人々の、特に東西海岸でない場所での声を聞きたいけどそこは含まれない。
Posted by ブクログ
トランプ大統領を支持した人々の生活する街をめぐり、様々な人から話を聞く。
単純に旅とともにある取材の様子が生き生きと描かれており、すごく面白かった。
トランプ前大統領は演説の言葉も荒々しく、なかなか個性的すぎる人物だっただけに、なぜ支持を受けているのかという点は非常に興味があった。
また、これだけ個性的な人物が大統領となっても堅持されている政策もあり、アメリカという国がどのような国家なのかも改めて興味を持って眺めることが出来たような気がする。
Posted by ブクログ
ラストベルトから新南部まで、トランプ支持者の当選後の話を聞いて回ったルポ。
民主党支持からトランプ支持に変わった労働者の多くは、トランプの政策を支持して、次もトランプに投票するという意見が多いようだ。
民主党が労働者の意見に耳を傾けなくなってしまい、エスタブリッシュメントな人達の政党になってしまった事がその大きな要因と思われる。
左派の候補者の政策は極端で、民主党主流派の支持は得られず、サンダースではトランプに勝てないだろう。困ったものだ。誰でもいいからトランプを引き摺り下ろして欲しい。
Posted by ブクログ
外交史やってる人間からすると、
アメリカの国内問題ってどうしても
忘れられてしまうエリア。
アメリカの内政の歪みを垣間見れてとても面白かった。
「トランプは原因じゃなくて結果」
そんな事を言う人がいたけど、本当に納得する。
一人一人に分析できてないから大方の選挙予測ははずれたわけで。
移民の問題とか日本にも起こりうるし、
イギリスはアメリカと同じような様相だし、
なぜトランプは生まれ、支持され続けているのか、
を人に焦点当ててるこの本は一読に値する
Posted by ブクログ
朝日新聞の記者が、ここまでトランプ支持者に寄り添う取材をしているとは、ちょっと驚き!トランプ現象を理解したくて読んだが、印象に残ったのは、2人のリベラルな著者へのロングインタビューの中で出てきた、民主党の変貌への言及。民主党は、ベトナム以後、「もはや労働者階級の政党ではない」路線を選び、「見識があり、高等教育を受け、裕福な人々の政党」になってしまった。ルーズベルトは、なりふり構わず、ダムを作り、インフラを整備し、多くの労働者を雇った。失業した労働者の側に立っていた。今でも、人々は、これはルーズベルトが建てたものだと認識できる。が、同じ巨額なお金を使って、オバマは、同じエリート層が運営している大銀行を助けた。言われてみると、そうだったなぁ。日本もそうだが、「労働者」に寄り添えるかどうかは、リベラルの課題。「労働者」のイメージも変わってきていると思うけど。
Posted by ブクログ
いわゆるエリートが闊歩するNYやワシントンでなく、庶民が暮らす労働者の街を巡ってトランプ大統領政権下のアメリカの実情を探る著書。
米国民主党員が前回選挙の敗因として挙げた「トランプが『今晩のメインディッシュは大きくてジューシーなステーキ(=労働者の雇用、賃金といった経済問題)です』と売り込んでいる時に、民主党は『メインはブロッコリー(=LGBTQ優遇や移民難民救済、BLM)。健康にいい』と言っているように聞こえてしまった」という例えが言い得て妙。
国民が本心で望んでいることを外してしまったと。だから本来民主党側であった人々もトランプ支持に回ったという。
また、トランプが勝ったのでなくクリントンが酷すぎたという意見も多い。あと、トランプの政権運営は支持するが人格が下品だから人前で支持していると言えないという意見も。
トランプ大統領の支持・不支持の大まかな理由が見えたような。2019年9月発刊なのでコロナ後の評価がどう変わったかは興味ある。その審判が明日からの大統領選で明らかになる。その前に読めてよかった。
あの反日反トランプで定評のある朝日新聞記者が結構公平な目で記述しているのが意外といえば意外。
様々な人種がアメリカの理念の下に溶け合うるつぼであったはずが、今は英語も話さず各人種の価値観を維持しようとするサラダボウル状態になっている。それをトランプ大統領は「アメリカグレートアゲイン」の号令で一つにまとめようとする。
しかもその給料は1ドル。残りは全額寄付してるという事実はもっと知られていいと思う。
Posted by ブクログ
トランプ当選後のラストベルト(中北部州)とバイブルベルト(南部州)でインタビュー取材した本です。ラストベルトの経済凋落や労働者の失業という現実は今の日本と合わせ鏡。労働者の党だった民主党に職を失った製造業労働者は完全に愛想を尽かしており、次もトランプにという。決してトランプが彼らの生活を回復させているわけではないのにこのような状況が。何が彼らをそう思わせているのか、ぜひとも読み取り、現在日本と比較してみて欲しいと思います。
また、現代アメリカを憂う2人の著名なジャーナリストにもインタビューしています。この部分だけでも現代アメリカの抱える病理を理解できると思います。