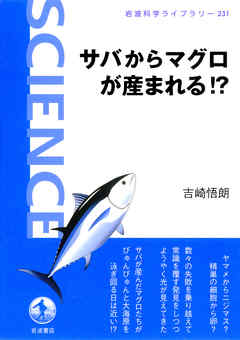感情タグBEST3
Posted by ブクログ
サバにマグロを産ませるという壮大な試みが成功に近づいている。
サバとマグロはそれぞれサバ科で近縁種。
既にヤマメにニジマスを産ませることには成功している。
卵、精子の形成過程は、「始原生殖細胞」→「卵原・精原細胞」→「卵・精母細胞」→卵もしくは精子 ができる。ニジマスの「始原生殖細胞」をヤマメに移植することでニジマスを産ませることに成功した。このときヤマメには処置をしてヤマメの卵や精子は出来ない処理を施す。
しかし、マグロの場合は「始原生殖細胞」を取ることが困難な魚であった。広大な海で行きており、マグロはその数が特にすくないという特性を持っていた。
そのため、「精原細胞」を使うことを試みた。成功!オスに「精原細胞」を移植するとその精子をつくった。次に、なんとメスに「精原細胞」を移植した...卵ができたのである。
現在の段階では、まだサバがマグロの精子や卵を産むまでに至っていないがもう頂上はすぐそこというところに来ている。
著者の誠実で粘り強い研究姿勢や研究室の人たちへの温かい配慮などがにじみ出ている文章でその面も好感の持てる内容でした。
Posted by ブクログ
基本的に僕は「生物」という科目が苦手だったので知らないことだらけだったが、一番驚いたのは、細胞が移動するということ。トンデモ話以外でも、世の中、不思議なことだらけ。
Posted by ブクログ
ちょっとキワモノのようにも思えるタイトルだが、興味深い1冊である。
クロマグロをはじめとするマグロは、乱獲による絶滅が心配され、近い将来、食べられなく可能性も囁かれている。
近畿大学の「近大マグロ」岡山理科大学の「理大マグロ」など、養殖の試みもなされ、成果も上がってきている。
本書の著者らのアプローチは、もうひとひねりあって、ユニークだ。
養殖を継続して行うには、種苗(養殖用の稚魚や幼魚)が必要だ。完全養殖のためには、親マグロも管理下におかなければならない。だが、マグロは体が大きく、また成熟するまでの時間も長い。クロマグロの場合、食用サイズは30kgだが、親マグロとして成熟したものの大きさは100kg、平均すると5年掛かる。親マグロを育て上げ、維持するには、大きな労力と費用が必要となる。
ならば、もっと小型で成熟も早い別の魚、例えばサバをマグロの代理親とすることはできないのか・・・? サバは1年ほどで成熟し、重さも300gくらい。水槽での管理も容易になり、そうなれば水温の調節などを通じて、計画的に種苗を得ることだって可能になる。
こう聞くと利点は多いようだが、さて問題は実現可能かどうかである。
「サバにマグロを産ませる」というのは、サバのおなかからマグロの稚魚がぽこぽこ出てくるということではない。魚は体外受精を行う生きものであるから、「サバがマグロの精子や卵を作れるようにする」ということである。
この目的に向けて、著者らが試みている戦略は、サバの仔魚に、卵や精子の元になる細胞を移植し、性成熟した後、サバがマグロの卵や精子を作り続けられるようにするというものである。
卵と精子の元になる細胞は元を辿っていくと始原生殖細胞という1種類の細胞に行き着く。哺乳類の場合は、受精時に、性染色体によって性が決定され、通常、生涯の間に生物学的な性が変わることがない。しかし、魚の性はそれほどかっちりとは決まっておらず、種によっては外的要因によって性転換するものもいる。魚の始原生殖細胞は仔魚に存在する段階では、卵を作るのか、精子を作るのかが決まっておらず、精巣・卵巣が発達するにつれて、その運命が決まる。
著者が学生の時、魚の生殖細胞で特異的に発現する遺伝子が発見され、著者はこれを手がかりに、仔魚から始原生殖細胞を探して取り出すことができないか、と考えた。
始原生殖細胞を取り出し、別種の魚に移植すれば、代理親の性にしたがって、精子も卵もどちらも得られるはずである。
著者はこれに成功する。生きた魚の中から始原生殖細胞を取り出すに当たっては、2008年ノーベル化学賞を受賞した下村博士の緑色蛍光タンパク質(GFP)が活躍した。
最終的な目的はマグロを増やすことなのだが、海洋魚の卵は小さく、始原生殖細胞を持つ仔魚も非常に小さいため、扱いが困難である。そこで、著者らはまず、卵が大きいサケ・マス類で実験を始めた。ニジマス(rainbow trout)をヤマメ(masu salmon)に産ませることが可能か、という実験である。
その試みの中で、いくつかおもしろいことがわかってくる。
当初は始原生殖細胞を精巣や卵巣に直接注入しなければならないと考えられていたのだが、実は、腹腔内に入れてやりさえすれば、生殖細胞は仮足を出して「勝手に」卵巣や精巣に移動していく。卵巣や精巣から、何らかの誘引物質が出ているようなのである。
また、仔魚からあまり多くは採取できない始原生殖細胞の代わりに、豊富に得られる精原細胞を移植実験の練習に用いていたところ、何と、これを雌に移植すると、卵に変化できることもわかってきた。基礎生物学的にもすごい発見である(PNAS vol. 103 no. 8, 2725-2729)。後に、卵原細胞が精子なりうることも確認されている。
一方、実用化のためには、仮親となる魚が自分の子供を作ったり、雑種が生まれたりすることのないようにしなくてはならない。このためには、仮親を不妊化する必要がある。養殖漁業では、食用にならない卵巣や精巣の発達を抑えるために、不妊個体を作る「三倍体化」という手法が知られている。この三倍体化した魚に、生殖細胞を移植したら、無事に生殖細胞由来の仔魚が産まれるのだろうか? 最終的にはこの実験も成功し、こちらはScience誌に掲載され、大きな反響を呼んだ( Science Vol. 317 no. 5844 p. 1517 )。
全体として「無茶」とも評されるような実験を通じ、応用を目的としながらも、基礎的にも興味深い知見が多く得られた事例と言えるだろう。自由な発想と熱意を持った多くの学生が著者の研究室に集まっていたのも大きかったようだ。
著者らはこの技術を、マグロだけでなく、絶滅の危機に瀕した魚の保全にも使えないかと考えている。凍結が困難な卵ではなく、生殖細胞を凍結することで、絶滅危惧種の保護バンクを作ろうという試みである。精巣を凍結し、ここから卵や精子を得ることが可能であることは確認されている(PNAS vol. 110 no. 5, 1640–1645)。
さて、壮大なこのプロジェクトがこの研究室でどのように育っていくのか、今後も期待されるところである。