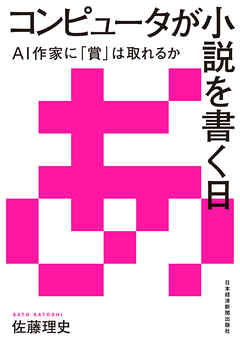感情タグBEST3
Posted by ブクログ
著者の佐藤さんは、小説の賞の1つである星新一賞に、コンピュータを利用して書いた小説を応募したグループの中心人物。
その過程と、その過程からわかったことをまとめた1冊。
本の後半に書かれている、「『理性-感性』という対立ではなく、『センス-後付け論理』という対立の方がしっくりくる」とか、「独創性や創造性を信頼しない」、「文章を書くこととは、伝えたいことを伝わるように文を構成するパズル」といった考え方は、自分が何となくイメージしていたことの明確な表現で、それらに出合えたことは、この本から得た最大の収穫かもしれません。
AIにできること・できないことや、人間の認知の仕方などに対する著者の考え方は、非常に参考になると思います。
今年、自分が読んだ本の中では、文句なくNo.1です。
Posted by ブクログ
<AIはベストセラー作家になる夢を見るか>
文学賞は数々あるが、その1つに星新一賞というものがある。
周知の通り、星新一はショートショートの名手であった。ショートショートは一般に短編小説よりさらに短く、ウィットの効いた印象的で意外な結末が持ち味のものが多い。
星新一賞は、2013年に日本経済新聞社が始めた、理系的発想に基づくショートショートや短編を対象とする公募文学賞で、2017年1月現在、第4回の選考中である。
この文学賞の第3回はちょっとした注目を集めた。人工知能(AI)の研究者らが4編の作品で応募し、一次選考に残った作品もあったというのである。
アルファ碁と呼ばれるAIに韓国のトップ棋士が敗北したニュースが同時期に出たこともあり、AIの可能性について期待する声、逆に人の仕事をAIがどんどん奪ってしまうのではないかとする不安の声が上がった。
本書は、この応募の顛末を巡る、研究者自身の報告である。何を目標とし、何を考え、どのように研究を進め、どのように作品を作ったのかを、一般向けにわかりやすく綴っている。
AIとはどのようなものかを知り、そしてまた文章を綴るとはどういうことかを考える上で、極めておもしろい本である。
AIに関しては、大きく期待される反面、大きな誤解もあるようだ。AIは、大容量のデータを取り扱えるなど、非常に優れている面もあるが、それが即、人の能力を超えていくことになるかといえば必ずしもそうではない。
それを表すのが、本書でも大きなテーマである「文章を読むこと・書くこと」である。
会話するロボットというのはいるが、実のところ、一度にしゃべるのはごく短い1~2文で、覚えたパターンによってふさわしい(と思われる)答えを返しているに過ぎない。
大量の言葉をデータベースに投入して、それをランダムに出力させることは出来るが、それでは意味のある文章にはならない(確率的にはゼロではないが、文章が長くなればなるほど、その確率は実質的にはゼロと言ってよいほど小さくなっていく)。長編小説ともなれば10万字以上が常である。ランダムに10万字分の言葉をつないで物語になるかといえば、まずならない。
本書の著者らの目的は「コンピュータによる文章生成の実現」である。ショートショートを書くこと自体は直接の目標ではなく、文章を書くとはどういうことかを考える一つの手立てと言ってもよい。
コンピュータによる文章生成は、文の構造を分析し、主語である名詞や述語である動詞、これらを修飾する言葉に分け、それぞれに該当する候補をデータベースに入れておいて、ランダムに選び取り、語順や語尾、活用形、口調などを整えて出力するといった形を取る。短い物語では、プロットを作っておいて、導入部、展開部、結末部のそれぞれにいくつもの選択肢があり、それをコンピュータが選び取り、推敲して修正を加え、出力するということになる。
設計図は人が整え、部品をコンピュータが選び、多少磨きを掛ける。
これをコンピュータが書いたのか、というと難しいところだが、現状ではコンピュータの文章作成能は、そういう段階にある。
著者らは星新一賞応募プロジェクトと平行して、「東ロボ」プロジェクトにも参加している。「東ロボ」は「ロボットは東大に入れるか」を試みるプロジェクトで、大学入試問題を題材として複数チームが取り組んでいる。まずはセンター試験で好成績を収め、ゆくゆくは東大二次試験に合格するレベルの答案を作成することを目標にしている。「数学」や「物理」は複数の強力チームだが、「国語」は著者らのグループのみが奮闘している。それだけ困難であるということでもあろうし、取っ掛かりが掴みにくいこともあるのだろう。
試験問題に取り組むということは、書いてある文章の意味を読み取り、問われている内容を理解して、出力することである。
だが、実のところ、コンピュータは文章を読むことが出来るとは言い難い。著者の出している例を挙げると、
1.川端康成は「雪国」などの作品でノーベル文学賞を受賞した。
という文を人が読めば、
2.川端康成は「雪国」の作者である。
ことはすぐわかるが、コンピュータにとっては「自明」ではないということだ。1から2を導き出すためには、コンピュータに読み取る手段を教え込まなければならない。
これには、人が文を理解するのはどういうことかという問題が絡む。
受験テクニック本なども参考にしながら試行錯誤が続いている。
詰まるところ、コンピュータが文章を自動生成するためには、人がどのように文章を読み取り、蓄積し、自身が書き出しているかを理解する必要がある。それを倣いながら、システムを構築していっているのが現段階である。少なくとも、AIがベストセラー作家になる夢を見るのはまだまだ先のことであるらしい。
本書には袋とじで、星新一賞に応募した作品も収録されている(『コンピュータが小説を書く日』『私の仕事は』)。さて、本書の内容を踏まえて、成果物を読んでよく書けていると思うかどうかは人それぞれだろう。
1つおもしろいと思ったのは、登場人(?)物であるAIが暇つぶしとして書く小説である。AIはこれを「ラノベ」ならぬ「アイノベ」と呼ぶ。人がおもしろいと思うようなストーリーではなく、延々と続く数列なのだ。コンピュータが自発的な感情を持ちうるか、嗜好を持つかはともかく、もし持ちうるとするならば、案外とその好むものは、なるほど人とはまったく違うものかもしれない。
もしかすると、人が思うシンギュラリティとAIが想起するシンギュラリティはまったく違うものかもしれない・・・。
さまざまな意味で刺激的な1冊であった。
Posted by ブクログ
AI作家の正体とは?
星新一賞は人工知能による作品も受け入れている。この本が出版された2016年から10年近く経って、私はこの研究がどうなったのかも、星新一賞がどうなった(AI作家が受賞したかどうかも賞の要項が変わったかどうかも)知らない。しかしChatGPTなどが文章を書いてくれると話題になって、レポート課題を肩代わりさせる事例が出てくる今、気になった。人工知能が文章を書くとは?
この本を読んで私が気付いたことは、プログラムによって型が決まった文章を生成することはできるということ、また、文章を生成するプログラムにどれだけ労力をかけるかが問題だということだ。著者の挑戦を読んだ限り、文の構造を決めて、そこに入るパーツを入れていくことで文章を生成するわけだから、本文でも触れられているが、定型文のメールなどや、天気予報やマーケット情報など報道関係で型が決まっているものは十分にできる。
文章を書く力、特にChatGPTのような文章生成AIが登場した今、人間はプログラムに頼りながら文章を作れる。では、人間に何ができて、プログラムには何をしてもらえばいいのだろう。出版された時点では、文の意味が通るかどうかの判定はまだプログラムには難しいようだ。ではそれが人間の役割だろうか。
プログラムが生成した文章を人間が修正しつつ使う。芥川賞受賞作家も生成AIを使っているそうだ。コンピュータには意識もなく自由意志もない。「書きたい」気持ちは人間にしかない。それならば、AIへの恐怖を語るより、AIと共になら何ができるか考えたい。適切な役割分担でよりよい小説ができるなら、楽しみである。
Posted by ブクログ
最近めちゃくちゃ気になってるAIの執筆について。
実際の研究(意味の通る文書を機械的に作る方法の実現)と、その成果(AIがかいた※小説)の星真一賞への応募について。
論文まではいかない、その一歩手前で、だからこそ研究の真意や見通しも噛み砕いてわかりやすく書いてくれていて、とても読みやすく面白い。
言語をAIに認識させる研究、というもの自体にすごく興味がわく。
結局、AIはゼロからは生み出せない。
でも人間だって。これまでのインプットがなんらかあってのこと。
それはともかく、AIの場合は、いろんな制御パタンを与えて、パラメータを与えて、パラメータ同士の関係を与えて、、と、ルールに継ぐルール。ランダムなパラメータ設定でも、意味を成すように、ギリギリのラインの設定はされてたみたい。
最終的なAIのゴールとしては、世の中にある文章を限りなく読み込み、起承転結のトリックも含めて認識し、パラメータ化し、どの入力をさせるのかを決め、その結果としてはじきだす、ということなのだろうか?
後半の、AIを東大に合格させる研究も非常に面白い。
入試問題の各教科で、ベースになるのはやはり語学力。AIも、日本語を"理解"できないと(正確には、"理解""しているかのように")、いくら数式がつくれたって、問題文から直接数式を組み立てるところまではできない。
そして、今回の小説はAIが書いたといえるのか問題。北極システムと南極システム。レゴのセット。
境界は間にあって、つまりは受け取り方しだい。
コンピュータが○○をできた、というのは擬人的な表現でしかなく、本来の意味は、"○○のためのアルゴリズムがわかった"ということ。賢くなったのは人類であり、機械ではない。
→それを勝手に実装していくのがAIなのでは?それがシンギュラリティなのでは?
文法を満たす文を作っても、その文が意味が通る文かを判定する機械的な方法は明らかではない
研究者自身の言葉で書かれていることの意義
理性↔︎感性、ではなく、センス↔︎後付け論理で研究を語る筆者。直感で選択してから、うまくいったあるいはうまくいかなかった理由を論理で考える。納得。
現在の科学では、意識というものが説明できない、ゆえにコンピュータが意志を持って何かをするなど、現時点ではありえない。
→AIが意志を持たずとも勝手に"学習"していった結果、意志なき意志が生まれてしまうのが、こわいのかも
理系の学者が、ことばを扱うということの面白さ。
書かれている文章自体が非常に明晰で軽やかでわかりやすい
Posted by ブクログ
5章までは小説生成器の仕組み、6章から10章はAI作家の小説応募とその周辺で起こったことや筆者の考えが書かれている。あまりプログラムに縁のない人だと前半はそれほど面白くないかもしれない。6章からは小説に限らず創作に少しでも興味のある人なら面白く読めると思う。
Posted by ブクログ
タイトルに惹かれて手に取った。最初は工学系の話で全然わからなかったので、工学系の人に勧めて解説してもらおうと思ったくらいだ。しかしながら、コンピュータに小説を書かせるということは、それに至るアルゴリズムを作る「人」がおらねばならないというところから、小説はいかにしてつくられているのか、を綿密に勉強され、分析されている。文系(元理系)の私にも非常に参考になり、なるほど日本語というものは、小説というものはこうなのかと改めて目から鱗が落ちた。さて、コンピュータは果たして作家となりうるのか。
Posted by ブクログ
気まぐれプロジェクト(星新一賞への応募)と、東ロボ(ロボットは東大に入れるか)。実に興味深くスリリングな2つのプロジェクトの歩みと実態。ある程度の成果と、次への足がかりが見えない状態が伝わってくる。違うテーマでポンとブレイクスルーがあるかもしれないので、色々トライしてほしい。
Posted by ブクログ
現状のAIは知能と呼べるものではなく、入力をごにょごにょして出力してるにすぎない。
書いているというよりはフレームワークに各パラメータに従って指定の語句節を突っ込んでいるだけのようだ。
もちろんこの意味の通る文章を作るという機能を実装するのも難しいとは思う。
自分たちは文法や文意を意識せずに日本語を使っているが、それをプログラムで実装することが困難だと分かることで、人間の不思議さを実感させられる。
マスコミの中には速報性とインパクト重視のために著者の意図とは異なる報道(不安をあおったり)をする輩がいたとのことで、本当にマスゴミだなぁと思った
一方でフリー記者やこども記者、文芸記者はしっかりと見ていたそうで、マスゴミでくくるのもアレだなと思った
Posted by ブクログ
コンピュータに小説は書けるのか。小説を書いた(生成した)のは、単なるコンピュータプログラムであり、そのプログラムを開発したのも、小説全体のプロットを構成したのも、そこに埋め込む部品を準備したのも、すべて人間がやったことで、小説は、これらの用意周到な事前準備から、コンピュータプログラムが自動生成したものである。したがって、賞を取れるような小説を書ける人がプログラムを作れば、賞を取れるような小説を生成するコンピュータプログラムを作れるだろう。
では、人工知能は小説家の仕事を奪うのか。人工知能が労働環境に影響を与え、職業を変質させてきたのは事実である。しかし、単なるコンピュータプログラムが、小説家にとって代わるなどありえないことである。メディアが、ことさら人工知能を取り上げて、不安をあおるのは、いかがなものか。
現在、新聞などで報道されているAIシステム発表の半分以上は、単なるコンピュータ化(自動化)であり、ちょっと気の利いたコンピュータ化は、すべてAIと呼ぶことにしているようだ。長い冬の時代が終わり、真夏になったのはいいが、すぐにブームが終わってしまうのではないか、と危惧している。
Posted by ブクログ
小説コンクールの日経「星新一賞」はプログラムで作成された小説も受け付けています。それに応募した自然言語処理研究者である著者が、どのようなアプローチで機械的に小説を生成し、どのような結果になったのかを著しています。コンピュータが小説を独力で生成するのは現代のテクノロジーではまだまだ困難であるとし、そのなかでもできることは何かを説明しています。そういうアプローチがあるのか、と勉強になりました。技術的な話は少ないですが、読み物として面白かったです。
Posted by ブクログ
星新一賞(理系的発想力に重きを置いた文学賞)に「コンピュータが書いた小説」を投稿するプロジェクトを研究者本人である著者解説したもの。
てかこのプロジェクトは結構報道もされて話題にもなってたのね。恥ずかしながら知らなかった。
ある意味では文章とは何なのか、小説とはどんなものでどう書くのか、の本にもなっている。エンジニアがプログラムを作成するときの考え方の紹介にもなっている。
何かを別の手段で行うにはその物事の本質を知ることから始めなくてはならない。
また何かをするには設計図を書かなくてはいけない。そして設計図で出来が決まる。
そんな教訓を学んだ(それはこの著書の本質ではないけれど)。
当たり前だけど、いきなり目の前にあるコンピュータに「小説書いて」とお願いしたところで小説を書けない。
小説を書くプログラムを人間が作らないといけないのだ。
コンピュータの仕組みをよく分かってない層、擬人化してイメージしちゃう層(私もだ)はこのことが分かってないのだ。
プログラムの内容等については知識がなくて詳しくはわからなかったけど、プログラムをどのような過程で組んでるかはわかって面白かった。