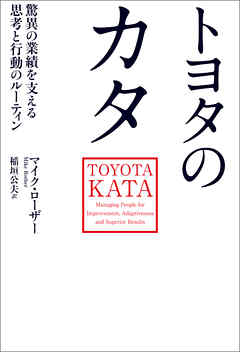感情タグBEST3
Posted by ブクログ
長年トヨタのプロセスを研究している著者がようやく発見した仕組みというか考え方と、トヨタじゃない会社でそれを適用する方法の紹介。
「ターゲット状態」「改善のカタ」「コーチングのカタ」などいろいろ紹介されている。
「ターゲット状態」とは、いわゆる理想的な状態のことでもあるし、現在よりも少しだけ理想に近づいた状態のことでもある。
製造業の会社では「1個流し」が理想とされているそうで、どんな活動もそこに向けて進んでいることが「正しい判断」だとされる。
「改善のカタ」とは、目標として設定した「ターゲット状態」に近づくための障害を解消していくこと。
現状分析、根本原因分析、対処、評価を数分とか数十分とか数時間で繰り返すことが重要なのだという。しかも1度に1つづつ。
「コーチングのカタ」とは、メンティーが「改善のカタ」を習得するために支援するメンターが学ぶべき行動様式。
一緒に問題を見て、メンティーが次の行動を考え出すための質問をする。考え方のコーチング。
一緒に過ごすようにしなければ効果が出ない。
組織が世界の変化に適応して存続し続けることが目標である、というところが、市場に価値をもたらすことが目標である、という他の方法論の話とは異なるところ。
実際、市場の要求というか顧客の要求は、タクトタイムのようなメトリクスとして登場するだけであり、まるで人間味のない扱いだった。
本書の考え方はそのままではソフトウェア開発に当てはまらない、という意見も聞いたことはある。
Posted by ブクログ
世界に冠たるトヨタ。その生産管理手法として、リーン生産方式、ジャストインタイム、タクトタイム、セル生産方式、アンドン、カンバン方式、平準化、自働化、などの仕組みが広く知られている。しかし著者は、それらの生産管理ツールや管理手法は表面的なものであり、トヨタの持つ行動様式が組織として身についていなければ、そのツールを導入しても成功はおぼつかないという。トヨタの競争力の源泉は、その行動様式である「トヨタのカタ」だというのがこの本の主張だ。
トヨタにおけるその核となる行動様式を、著者は日本語で「カタ (Kata)」と呼ぶ。英語ではそれに当たる丁度よい言葉がないということなのだろう。その「カタ」はとても深くトヨタの社員に浸透しているため、社員自身では決して言葉でうまく説明することができないものだという。本書は、その「カタ」を何とか言葉にしたものである。
トヨタのカタには「改善のカタ」と「コーチングのカタ」がある。 「カタ」には、継続的改善の仕組みと伝承の仕組みが組み込まれているため、トヨタは環境の変化に対応し、厳しい競争の中で他社に対して優位に立つことができる。カンバンのような目に見えるツールを取り入れるだけではなく、その背後にある考え方を学ばなければ決してトヨタで行われているような継続的改善は望めない。
著者は、マネジメントを次のように定義する。
「人間の能力を協調的な方法で利用することで、望ましい状態を系統的に追求すること」
結果ではなく、状態に着目するべきだというこのテーマは、トヨタで実践されている行動様式であるとして、この本の中で何度か繰り返される。欧米式の結果による管理ではなく、手段による管理がトヨタとその他の多くの企業との違いであると強調する。結果ではなく、その経緯・状態に着目することで、最適な状態を全体で求めることができるようにしているのである。
「組織を長期にわたって成功させたいなら、組織が社内外の状態とどうやりとりをするかが重要であるということだ。そこには「結果がすべてという「フィニッシュライン」はない。目的は勝つことではなく、組織が改善しつづけ、適応しつづけ、変化する顧客要求を満たし続けられるような能力を身につけることだ。」
【改善のカタ】
著者は、継続的な斬新的進歩の仕組みが行動様式に組み込まれていることをもってトヨタ最大の優位性と見る。それが「改善のカタ」と著者が呼ぶものである。いくつかそれを示す言葉を本の中から引用してみる。
「私たちが確実に知るべきことは三つしかない。それは、「いまどこにいるのか?」「どこに行きたいか?」、そして「こことあそことのあいだの見通しがきかない区間をどのようにうまく進んでいくか」ということだ」
「小さな漸進的ステップを歩むことで、私たちは途中で学び、方向を調整し、目指す場所にいたる道筋を発見することができる。私たちはあまり遠くまで見えないから、事前の計画だけに頼るわけにはいかない」
「技術的イノベーションだけに依存することは、しばしば、一時的な競争優位しかもたらさない。技術イノベーションは重要であり、競争優位をもたらすが、それは稀にしか起こらないし、競争相手が真似できるものである」
「コストと品質の競争力は、長期にわたる多くの小さなステップの蓄積に由来する場合が多い」
トヨタの各種の生産方式の神髄を、生産効率の最適化の仕組みではなく、最適な状態からのずれをあぶりだすための仕組みであると見る。誤解されていることが多いが、すべては問題を顕在化するための仕組みだと考えると合点がいく。たとえば、カンバンシステムは、在庫を減らすための改善のための方法ではなく、現状の問題をあぶり出し、在庫を整理し、利用しやすくするための仕組みなのである。言うなれば、カンバンシステムの目的はカンバンをなくすことにあるのだが、それを理解しない人には何のことかさっぱりわからないだろう。
ターゲット状態を目指す。そのために問題を顕在化させるための仕組みを導入し、漸進的に改善を行う。それが、トヨタの「改善のカタ」である。
「プロセスが毎回同じ方法で行われるからではなく、プロセスが毎回同じ方法で行われるようなターゲット状態に向かってトヨタが改善を続けているからだ」
計画とは変化するものだ - 張富士夫
その意味で、現地現物というのは、つねに変化する状態を確認するために生まれた言葉でもある。
トヨタにとっては、問題がないときには、会社が立ち止まって進歩していないことを意味する。異常はいいとか悪いとかではなく、学びの機会と捉える。その前提となる哲学はこうだ。
■ 人は最善の努力をしている
■ 問題はシステムの問題である
■ すべての物事には理由がある
問題を発見したいから問題をチェックしているのあって、問題をなくすためにチェックしているのではないのである。
① ターゲット状態はなにか? (チャレンジ)
② 現在の実際の状況はどのようか?
③ ターゲット状態の達成を妨げている障害は何か。いま、そのどれに取り組んでいるのか?
④ 次のステップは何か? (PDCAサイクルの始め)
⑤ このステップを実行することで何を学んだのか、いつ現場に行って見ることができるか?
【コーチングのカタ】
トヨタでは、そのトヨタのカタの伝承のために、「コーチングのカタ」というものが存在する。チームリーダーやグループリーダーが、部下を教育する時間は全体の五十パーセント以上を占めるという。監督者の役割は改善そのものよりも人材育成にあるというが、それが徹底されているのがトヨタを特徴づけるものでもある。
そこから産まれたメンター制度やA3フォーマットは有名である。またメンターは、問題の解決策を見せるのではなく、部下に見つけさせることを徹底することで、その「カタ」を伝承していくのである。
著者は欧米企業にトヨタ生産方式の導入を指導してきたコンサルタントであるが、トヨタ生産方式のハウトゥーものではなく、その背後にある核を説明したものであり、非常に腑に落ちるものであった。仕事で絡むかもしれないので手に取ってみたが、結構おススメ。