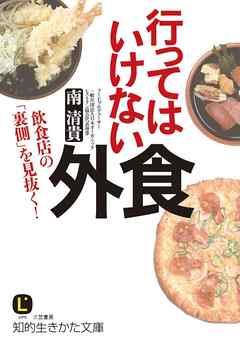感情タグBEST3
Posted by ブクログ
『「読む」だけで終わりにしない読書術』
(本要約チャンネル)で紹介されていた本。
外食好きな自分にとって目からウロコの
予感がする。
P4
工業的に加工された食品には
栄養価はほとんど残っていない。※
Posted by ブクログ
一言感想を言えば、
「怖くて、何も食べられないよ。」ですw。
主食、海鮮、肉、野菜、揚げ物、調味料を章別に、危険な食べ物について解説しています。
・サラダーバーの野菜はどうしていつまでもパリパリなの?
・安い弁当やファーストフードで出てくるご飯は洗剤を食べているようなもの。
・豚肉100gとハム100g。豚肉の加工品であるハムの方が安いのはなぜ?
上記のどれか1つでも興味があれば、読んでみる事をオススメします。
かねがね「無知は恐怖」と考えてます。
知らないことで、損をすることは往々にしてありますし、それが「健康」「お金」となれば、後悔はより一層強くなります。
とても勉強になりました。今後の食事の参考にしたいと思います。
Posted by ブクログ
あの時給で出てくる食品・・・ 推して知るべしかな・・・ 食べるときは開き直っているけど。しかし 作った人が食べたくないような飲食店で 働いたり経営したり食材を納品したりしてるなんて 哀しくないんだろうかね。
Posted by ブクログ
外食産業の問題点、お店の裏側で何が行われているのか、店側のこういうところがだめなんだよ。
そういうことが書いてありますが、最終的に悪いのは消費者なんだよ、というのがこの本の本旨でした。
安いから、便利だから、という理由で受動的な食事をするのではなく、本当に食べるべきもの、食べたいものはなんなのか、吟味して食事をする。
消費者側がこういう意識を持って変わっていけば、生産者側も変わっていかざるを得ないでしょ。
なんたって売れなくなったら困るわけです。
この本を読むとファストフード店には行かないほうがいいと思うようになります。
僕はこの本をファストフード店で読んでましたけど……
Posted by ブクログ
半分都市伝説的なものだと思って読んでみた。全部鵜呑みにするのは大変。
食事を摂るにあたっての選択肢として頭の片隅に置いていてもいいのでは?というようなことが書かれている。
塩分には気をつけたいが、ミネラル豊富なものであれば差し障りない。らしい。
この筆者が通う飲食店の数々が、この人のわがままを受け入れて特別メニューを出してくれるようなお店ばかりらしく、私の知らない世界だった。ほんとにある?シンプルにわがまま客??
Posted by ブクログ
要するに加工食品や、外食は添加物が多いので気をつけてという本。
この本に書いてることを全て実行しようとするとそれだけだストレスフルな生活になるので、これらの食品が体に良くないことも頭に入れて自分で取捨選択すればいいと思う。
Posted by ブクログ
いいのは外食やコンビニなどの食材の時日だけを書いていて決して感情的に非難していないところだ
要は 消費者が自分で食べるものはちゃんと理解して賢く使い分けをする、高いお金を払ってとる必要があるかないかの判断をしないといけないということ
Posted by ブクログ
安い物には安いなりの理由がありますよ、という本。既知の内容も多く、完全な健康食というのは半ば不可能な現代であるが、食の安全に対する意識について改善するきっかけになりそう。
Posted by ブクログ
食品について考えるきっかけを与えてくれる書籍だと思う。
毎日、自分の体に食物を取り込んで生活をしています。
毎日行うからこそ、食品に対して関心が薄くなっていると思っています。
いくつかのモデルケースを挙げながら「安定した食品提供」について解説をしています。
その主旨は示唆に富むものであり、改めて考え直すきっかけになりました。
しかし、どうしても作者の主観で見通すため、客観視できる情報の提示がほしかったと思います。
もし、資料を載せる紙面がなかったとしても参考資料で、作者の意見に同意できるように資料の提供をしてもらえたらと思いました。
そこから食品に対して深く探索できたらと思ったので、残念に思えました。
Posted by ブクログ
◎フライドポテトの食べ過ぎは禁物。
◎寿司はもともと江戸のファーストフードのような物で
安価なものだった。屋台から始まった。
ネタはイワシなどの腐りやすいものは使われてるなかった!
マグロでも、トロの部分は脂が酸化して腐敗しやすいので捨てられていたくらい!
今では高級品のように使われているが。。
◎ネギトロも、元々商品価値にならない骨の周りについたもので、弟子の賄いとして食べられていたが、有名になり高級になったため、脂肪分の多いマグロがたくさん育てられるようになった。
◎蓄養
成魚を捕まえてきて餌を与え、大きくすること。
マグロな泳ぎっぱなしで有名だけど、蓄養だと運動量が少なくなる。さらに、餌に脂肪分を大量に入れるので、全身トロみたいな、赤みが20〜30%しかないマグロが出来上がったりする。そのおかげで中トロとか大トロが気軽に食べれている。
そもそも、高級なものを安く食べたいという消費者志向に合わせて生産者や飲食店もそういう物を作り出しているから、貴重なものは値段相応で買うようにしないと自然な物ではなく、人工的になんでも作られて、質の悪い食べ物ばかりが増えてしまう。
◎コンビニサラダやレストランのサラダブッフェは、新鮮なもののように見えるが、添加物が加えられ、色味などが落ちないようになっているので栄養素が少ない。
原価20〜30%でやっているレストランが多いため、300円売価なら、60〜90円程度のサラダ原価になる。
◎ポテトサラダより、トマトサラダやキュウリなどマヨネーズなどの和え物でなく、生野菜よりのサラダを頼もう!
◎この本を読んでいると、外食ってなんでもかんでも添加物とか消毒がされてて怖いなと考えさせられます。
また、家で使ってる調味料などもなかなか成分まで確認して使っている人は少ないのでは?!
揚げ物は極力避けて、生野菜をたくさん食べたり
野菜中心の食生活が重要だなと感じました(^^)
Posted by ブクログ
外食に使用するレストランの裏側というか実態について刺激的に書かれています。もちろんそうでないレストランもあるのですがと一言置いて語られていますが、結構ドキッとするような内容も書かれていて、今後の外食することに注意が必要に感じられる(というよりも外食そのものをしないようにしていく必要を感じるほどでした)内容でした。一番問題ないのは、産地が分かっている食べ物であるという、まあ当たり前のことなのですが、コンビニ通いについても見直す契機になりました。
Posted by ブクログ
外食店や持ち帰り総菜の危険性について注意喚起している本。少々あおりすぎのような気がしないでもないが、このようなリスクがあることは知っておいたうえで、外食や中食をした方が良いのだろう。
Posted by ブクログ
以前は頼めるレストランでは「大盛り」をお願いしていましたが、数年前から、それほど食べれなくなりました。大食いを止める代わりに始めたのが、美味しいモノを食べることです。
美味しいものは値段が張りますが、多く食べなくても満足できるようになると、また、夜ではなくランチにすればそれが可能になることを発見しました。
そんな私にとって、この本のタイトルは大いに惹かれるものがありました。価格が高いものにはワケがあって、それでお店が成り立っているのは、それを理解して通う人がいるからです。その謎を解いてくれそうな本でした。
以下は気になったポイントです。
・食事をするというのは、基本的に自分の身体に栄養素を取り込む行為(p17)
・野菜類の箱があるかは、店のレベルを判断する一つのチェックポイントになる(p23)
・お店でチェックするポイントは、調味料・塩(p25)
・揚げ物を食べた後に酸っぱいゲップが上がってくるのは、揚げ油が酸化していた証拠(p31)
・朝食を果物だけにすると、頭もさえるし、一日身体も軽いまま過ごせる(p50)
・なるべく加工度の低い物を選ぶことが大事、同じサラダなら、ポテトサラダではなく、トマトサラダが良い(p52)
・イモ類を揚げたものは特に危険(p54)
・マグロは、トロの部分は脂が酸化して腐敗しやすいので、捨てられていた。赤身が中心、保ちをよくするために、醤油と煮切った酒を合わせたような各店秘伝のタレに漬け込んで、「ヅケ」にしていた(p57)
・回転寿司の場合には、近海の小魚、イワシ・アジが良い、次のチョイスとしては、天然物のタイ、イサキ、イナダ(p59)
・焼き鳥は、まず「塩」、劣悪な鶏を使っている場合、塩を振って焼いただけだと臭い(p67)
・ショートケーキとは、もともとショートニング(トランス脂肪酸)を使って作られていた(p84)
・白い小麦粉、白米、白い砂糖、こういう単純炭水化物は、体内に入ると一気に血糖値をあげる食品である、できるだけ摂取しない(p101)
・ピザは、シンプルなキノコ、ズッキーニ、トマト、バジルといった野菜類が良い(p102)
・パスタは、シンプルなペペロンチーノ、キャベツ・アンチョビの野菜系が良い(p105)
・本来のシメサバは、サバの中骨を抜いて塩でしめて殺菌し、塩分を抜き取ってから酢にくぐらせるという工程をとる(p110)
・カツオやイカにも寄生虫がいるので、安全に食べるための知恵、酢につけたりした。(p116)
・肉とは本来硬いもの、フワフワの柔らかい肉には、ホルモン剤などの薬品が使われている(p145)
・と殺場に来る豚の半分以上は、病気の豚(p130)
・色をきれいに見せるために、多くは亜硝酸塩、または亜硝酸ナトリウムと呼ばれる発色剤が使われる(p155)
・ハンバーグステーキは、本来ものすごくシンプルな料理、ひき肉に玉ねぎを刻んで入れて、塩コショウで味をつけて練る(p163)
・良質の肉を少量、野菜類、できれば生の野菜と一緒というのが賢明な食べあわせ(p166)
・本当に良質な赤身の肉、せいぜい3枚程度、焼くのではなく炙る程度、野菜を焼いたもの、野菜のスープ、生野菜をたべる(p168)
・サラダバーには、良質でない野菜を次亜塩素酸ソーダという商品で消毒・殺菌して、何度もジャブジャブと水洗いして匂いを消す(p180)
・コンビニストアのサラダは食べないほうが良い食品(p199)
・野菜でよい調理法は、蒸す、あるいは茹でる方法を勧める(p217)
・ポテトは、高温で揚げると、アクリルアミドという発がん性物質が発生する(p226)
・最初のマヨネーズは、卵黄・オリーブオイル・レモン・白ワインビネガーであり、塩も入っていない(p238)
・醤油の材料は、大豆・小麦・塩だけ(p243)
2017年1月8日作成
外食好きが読んでも抑止できない
だいぶ煽りが酷い。
そもそも外食が好きな人間と著者とは価値観が違いすぎる部分が多いのではないかと読んでいて感じた。科学的根拠も少ない(何が混ざっているのか分からないなど表現が曖昧でただ不安を煽っているだけな部分がある)ので、説得力に欠ける。なぜ、ここまで食品添加物や化学合成品が普及してきたのかの時代背景が無視されていて、ただの時代錯誤と思われても仕方がないと思われる。
しかし、畜産農家や野菜農家が進むべき道を考える良いきっかけと成り得る。
人口増加に伴う量産化は仕方のない道だったとはいえ、人間の美味しいものを食べたい欲のために家畜や野菜といった生き物を振り回していくのはそろそろ止めにするべきなのではと思えた。
また、栄養素に興味を持つ良いきっかけにもなりそうに思えたので、食の原点に立ち止まって考えるという視点で読む分には良本と思える。