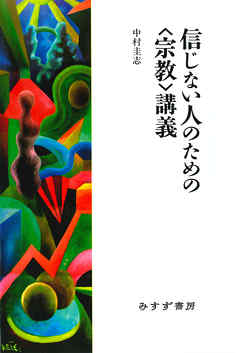感情タグBEST3
Posted by ブクログ
宗教について関心をもったらまずこれを一冊、というくらいによくまとまっていると思う。いわゆるキリスト教とか仏教といった創唱宗教から始まり、「宗教」にカテゴライズするべきか迷う儒教や神道、果ては名前のない信仰や文化といった「見えない宗教」までカヴァーしている。
特に筆者が強調している中で重要だと僕も思うのは、1)「宗教」とひとくくりにされているそれぞれの内実が”構造的”にまるで違うことがあるということ、そして2)「宗教者」はそれほど私達と違わないし、ドラマチックな存在でもないということだ。
1)については、特にイスラムが例としてわかりやすいだろう。イスラムは法律や政治にまで影響力をもたらす宗教で、これは多くの先進諸国における宗教の考え方と相反するものになっている。事実、日本人の多くは「個人的な信仰」は認めるが、それが他人や政治といったところに影響を及ぼすことを快く思っていないし、そういった宗教の私事化を当然だと考えている。
しかし「宗教は私事化したものであるべきである」というのは極めてプロテスタント的な考えであるということはよく言及されるところであるし、また島薗先生の「国家神道(皇道・道徳)の下に個人の間でだけ宗教が許される土壌が日本では作られた」という指摘にもかなり説得力があると思う。ようするに、「宗教」という観念はそこまで自明のものではなくて、文化の影響を多分に受けているということだ。
本文中では宮古島の人々を例に出し、「『地元ではこんにちはってどう言ってる?』と聞いたら『何も言わずに家にずかずか上がる』とのことでした。宗教だってじつはこんにちはのようなものかもしれません」と著者は述べているが、これは端的にこのことを説明している。極めてファジーな概念である「宗教」だからこそ、この言葉を用いるときにはその拡張性と多様性について考慮に入れる必要がある。
2)については村上春樹の『約束された場所で:アンダーグラウンド2』でも触れたが、こちら側とあちら側はそこまで違わないという指摘である。確かに「宗教」者は、様々な技法を用い精神に影響を及ぼすことに余年がなかったり、外部に対して排斥的なグループを形成したり、あるいは慣習と異なる理解に苦しむ戒律に従っているかもしれない。そしてそのことはある種の得体のしれない恐怖感をもたらすかもしれない。
けれども、やはり同じ人間である以上、それを行うに至ったメカニズムの大半は体感的にも理解可能であるものだと思われるし、少なくとも僕の経験上それはかなりの部分において言うことが出来る。彼岸と此岸に分けてしまうことはたやすいし認知的に付加もかかりにくいけれど、ここを放置し続けてしまうことは端的に「もったいない」。宗教者を理解するということは新たな人間理解の鍵になるし、そしてそれはひいては自分自身の理解にも繋がることなのだ。
Posted by ブクログ
さすが、ロバート・ベラーやタラル・アサドの翻訳者といった感じ。宗教に生半可な興味を持っている人や、宗教を毛嫌いしていて適切に批判したいと思う人は最初に手に取るべき本のひとつかもしれない。(※読書案内もあっていい感じ)
わかりやすさという点で、これは最良の、そして瑕疵の少ない入門書(先日の本はいささか専門的だった)。喩え話も豊富で、細かい事例をカットすると共に、しっかり「場合分け」を行なう。宗教という概念そのものに潜むいかがわしさへの配慮もある。
とはいえ、異論も多々あるのだけど。。。まぁ、入門書ですので。
Posted by ブクログ
宗教的な著作の翻訳の仕事を多く手がけてきた雑誌編集者が書いた初めての著書。大学の宗教学の先生が書いたんじゃないというところが、ちょっと注目。
あまり宗教に関心のない、ほとんど無心な若い世代向けの宗教入門としてはやや高度な内容も盛り込まれた、読んでいて夢中になれる格好の入門本。たとえも、語り口も平易でユーモアにあふれてて、好感が持てる。高校生くらいなら、読ませてみてもいいかなと思える一冊。
Posted by ブクログ
神をコカコーラの缶に喩えると、父、子、聖霊は、それぞれ缶の上面、底面、ぐるっと回った側面の三つに相応する、即ち三位一体。
この缶をテーブルの上に立てる、テーブルは人間世界、広い面上に救いを求める哀れな衆生がうごめいている、そこに神=コーラの缶が出現する、といったかたち。缶の底面と机との接触面がイエス・キリスト、この円い接触面は缶の底面-子なる神-として神に属するが、同時に机の面でもあるから、併せて人間界にも属し、キリストには神と人間の二重性があることに。
このように人間の歴史的世界という苦界-机の面-と神なる救済の原理-コーラの缶-との境界面にあるキリストは、たんなるシンボルでも絵物語の登場人物でもなく、歴史的人物であることによって救済のリアルな根拠が示される。キリストは人間であり、かつ神でもあった、ここに信仰の要訣がある‥、と。
-2010.11.24
Posted by ブクログ
宗教に関してはまったくの門外漢、素養が無いという人のための
恰好の入門書。ざっくりとはしているが、決してポイントは外さずに
各宗教を紹介したあと、現代における宗教というものに対しての
問題点やあり方を問う。人間や社会を考えるに当たっては、宗教や
信仰というモノは決して外せない。その学習の端緒としては最適の
本だと言えよう。
宗教学を専攻し、日頃からよく宗教書を読む私のような「こちら側」
の人間にとっては、一度「あちら側」に立ち返り、向こうからの
視点で宗教を考え直す、解毒のような作用を持っている、そういう
本だと思う。
Posted by ブクログ
レポート用に借りたけど、普通に読むにもよかった。読みやすいしわかりやすい。一部しか読んでないけど、「デジタルなアイデンティティー」の章がよかった。
Posted by ブクログ
世界中の宗教という現象について、「無宗教」の日本人の立場から概観。17章?以降は、宗教についての著者の考えを述べている感じ。もともと宗教と非宗教の境界は曖昧だったが、それを「宗教」として切り出して、国籍や標準語や民族と同じようにアイデンティティーを与えたのがヨーロッパ近代の社会システムだったという説明があって、なるほどと思った。