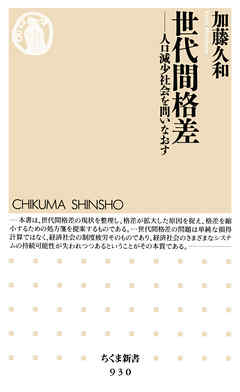感情タグBEST3
Posted by ブクログ
誠実がゆえに、若しかしたらつまらないかもしれないけれど、非常にバランスがいい良書だった。感情論に落とすでなく、高度経済成長期に設計されたシステムの劣化だという結論に向かった客観的な論理展開が私には美しく思えた。
巻末に解決案も提示されていて、やや深掘りができていないのではないかと思ったものの、冷静で妥当性はあった。ただ、なぜ関係者が合理的な行動に至らないのかという点に焦点をあてないと、机上の空論に終わってしまうのではないかという点が唯一残念だった。
Posted by ブクログ
世代間格差モノは何冊目だろうか・・・
この本も何度か繰り返し読んだけども・・・
世代間格差について・・・
イコール日本の社会システムの問題点について・・・
そして、どう改善していくべきかについて・・・
ちょっと小難しさはありつつも・・・
非常に良くまとまっている本・・・
生まれてくるのが遅い人ほど社会的に不利になる国、日本・・・
主要国のなかでもズ抜けて世代間の不均衡が酷い・・・
とにかくご年配の方々との差が大きい・・・
ボクは29歳だけれども・・・
周りは結婚のムーブメントは落ち着き、今は出産のムーブメントが・・・
今まさに生まれてくる子供たち・・・
これから生まれてくる子供たち・・・
後から生まれてくる子供たちほど社会的な負担が大きくなる・・・
これって、イイの?マジで!
と何となく感じていたら、ゼーヒーで読んでみて・・・
おじいちゃんおばあちゃんたちは確かに大変な時代を過ごし、今の豊かな日本を築き上げてくれました・・・
なので・・・
もちろん老後ぐらいはボクらが支えてあげたい・・・
あげたいけど・・・
でも・・・
実はちょっと寄りかかり過ぎじゃない?
後先考えず・・・
つまりはカワイイ孫たちのことを考えずに・・・
自分たちは弱者なんだから優遇されて当然と・・・
思いすぎじゃない?
もちろんおじいちゃんおばあちゃんと世代間で対立すべきではないので・・・
クールに行きたい・・・
何で、若い人ほど負担が大きくなったのか?
それは・・・
人口構造が以前と変化したのに・・・
いわゆる少子高齢化時代に・・・
少なくなっていく若い人に増えていく高齢者を支えさせる社会保障制度を、未だに変えずに続けているから・・・
そして労働市場にしてもしかり・・・
以前は、それで上手くいっていた制度を変えずにそのままやってきたことに原因がある・・・
ちゃんと、それなりの経済成長をしていれば、問題はたいしたことなかったけども・・・
失われた20年といわれるほど、長期低迷していることにより、問題が余計に大きくなってしまっている・・・
そして・・・
まさに世代間の不均衡が酷い国ほど、経済成長率が低いという・・・
するとますます世代間格差が広がるという・・・
負のスパイラルが起きている・・・
じゃ、どうすりゃイイのさ?
と、この本にはそれに対する案もザックリとだけども、シッカリ書いてある・・・
あとは・・・
この世代間格差という日本に巣食うデカい問題を・・・
この本を読んで若い人も高齢者も共有し・・・
この問題にちゃんと取り組んでくれる政治家を、政党を・・・
国会に送りこむしかないよね・・・
結果、世代間格差を解消できるような社会制度を築いていければ・・・
経済成長率も上昇してくる可能性が高いよね・・・
つーことで、まずは問題意識を共有ってことでオススメる!
いや、ホント・・・
世代間格差って、マジでスルーされがちだからね・・・
意識しないとね・・・
Posted by ブクログ
明治大学経済学部教授(経済学)の加藤久和(1958-)による、世代間格差の概説。
【構成】
第1章 世代間格差を考える
1 世代間格差を捉えるために
2 財政と労働市場からみた世代間格差
3 世代間格差の何が問題か
4 世代間格差拡大の背景を探る
5 本書の基本的な立場
第2章 疲弊した社会保障制度
1 社会保障制度の概要
2 社会保障制度の問題点
3 社会保障制度改革の動向
4 海外の社会保障制度と改革のヒント
第3章 変貌する労働市場・雇用システム
1 日本型雇用システムの崩壊と変遷
2 企業主体の社会福祉の終焉
3 若年層と高齢層の労働市場
4 積極的労働市場政策とセーフティネット
第4章 立ち後れる人生前半への社会政策
1 少子化と世代間格差
2 人生前半期の社会政策
3 少子化対策としての家族政策
4 女性労働と就業環境
第5章 いかに世代間格差を縮小するか
1 世代間格差と財政システム
2 経済成長と整合的な社会制度とは何か
3 財政制度の持続可能性と世代間格差
4 精度の持続可能性を目指して
第6章 新たな経済社会システムを目指して
1 年金制度の改革
2 医療制度の改革
3 雇用システムの見直し
4 財政運営のあり方
5 少子化対策と人口減少への対応
6 世代間公平性をどう担保するか
世代間格差が世間で声高に議論されはじめたのはいつ頃だろうか。いつの時代も世代間の格差は存在するが、団塊の世代がすでに60歳定年に到達し、年金受給を迎えようとする現在ほどその問題が明瞭に示されている時期はないだろう。
本書は、所得の再分配と低所得者への生活保障を目的とする社会保障の負担・給付が、若年層と高齢者層の間で「分かち合う」というレベルを越えて格差が生じていることをコンパクトに論じている。もちろん、中にはこれまでさんざん議論されている事項の確認もある。
本書は、代替案を提示することが極めて難しいこの問題に対して、諸外国の社会保障制度を引き合いにだしながら、積み立て方式への段階的な移行を示す。これが第5章・第6章の議論である。
ただ、社会保障改革の実際のところの問題は、給付水準の引き下げという極めて難しい政治課題に対して、政府与党が政治生命をかけてこの問題に取り組み、投票率が相対的に高い年金受給世代の有権者の支持を取り付けられるかという点にある。
民主党政権による「税と社会制度の一体改革」が提示されているこのタイミングで、読むべき一冊である。問題は刻々と悪化している。有権者は、感情的な「世論」ではなく、理性的な「輿論」を形成して、この問題の答えをだす時に来ている。
Posted by ブクログ
日本の人口構造はこの数十年の間に激変を遂げた。しかし、社会保障制度の見直しは遅遅として進まない。若い世代が高齢世代を支えるというシステムが温存された結果、世代間に大きな格差が生じている。
本書は、こうした問題を「世代間会計」という新しい考え方を用いつつ、きちんと数量的に明らかにするとともに、経済学的に持続可能なシステムの構築を提言している。将来への不安が増しつつある今、広く読まれるべき一書だろう。
たとえば、今年の政局でも大きな争点となった「子ども手当」に関しても詳細な分析を行ないつつ、今後は「直接的に出生促進を目的に掲げることも検討すべきである」というような提言を行っている。具体的には「フランスのような子どもにかかる手当についての対象を第二子以降に定め、かつ第三子以降は増額するという傾斜配分を行う」とする。
ちなみに、この給付方式は江戸時代版子ども手当ともいうべき「赤子養育仕法」とまったく同じ考え方である。先人の知恵の重みということについても考えさせられる提言といえそうだ。
Posted by ブクログ
2013.10記。以下、再掲。
歴史家の阿部謹也氏だったか民俗学者の宮本常一氏だったかが、「中世とはつまりは『保障なき時代』であった」との趣旨のことを述べている。一たび怪我をしたり、いや単に老いたりすればどうなるか分からない。その不安が社会や精神の不安定さ(そしてまれに芸術的衝動)を招く。これをなんとかしようとして、我々は長い期間をかけて社会保障という互助の仕組みを整えてきたのだ。しかし今後この制度の運用次第では、これから生まれてくる世代は未曾有の「不安」を抱え込まされることになる・・・。
社会保障(とくに財源)について考える上でのスタンダード本として評価が高いので一読。具体的な数字を根拠に、冷静で、フェアで、しかも問題解決への意志を強く感じさせながら議論を進める姿勢が心地よい一冊であった。
Posted by ブクログ
世代間の格差がどのようにみられ、どのように拡大してきたかを概観できる。格差是正の提案は実際に実行するには抵抗が多いだろと思う。既得権はだれも離したくないだろうから。
Posted by ブクログ
世代間格差は深刻だ。社会保障、経済成長率、人口構造、雇用、医療、選挙制度など多方面で対策を講じなければならない。簡単でないし、これで万全という対策はない。
感想としては、総花的でキレが少し足りなかったように思う。対策が大事なのだが、そこの検証がいまいちのような気がした。
・年金は破綻しない
・高齢者と若者の雇用は正の相関がある
・現物給付が出生率を高める
・女性の就業環境の整備は、世代間格差の解消に寄与する。
女性の労働力率と出生率は正の相関の時代に入った。
・出生率とGEMも正の相関
・年金の収益率は、経済成長率、人口増加率、物価上昇率に応じる。
・世代間不均衡と経済成長率は負の相関
・経済成長率と社会保障支出は負の相関
・日本の政府債務の大きさは先進国の中で群を抜いている。
・
Posted by ブクログ
世代間格差というと、高齢者と若者の間の損得というイメージを持っていたが、経済社会の制度・システムが制度疲労を起こしており、持続可能性が失われていることにあるということなのだということがわかる。
Posted by ブクログ
世代間格差について詳細なデータなどを元に様々な問題、事象を取り上げ、今後私たちが何をしていくのかきっちり提案まで落とし込んでいる良書。
上の世代が下の世代から搾取している、国の借金を次の世代へ先送りしているなどよく耳にする一次的な問題の言及にとどまっていない。
個人的に大きな問題は社会保障費の増大とGDPの成長率が釣り合っていないことのように読み取れるが、もちろんそれ以外の問題が複雑に絡み合い、なんとも難しい状況というのが現状だ。
提案にある積立式の年金制度等、有用性が高くみえるアイデアを実現できる政治的な受け皿を望んでいるのは私だけではないはずだ。
Posted by ブクログ
世代間格差がなぜ生まれるのか。その原因や医療保険や年金、正規就業者と非正規就業者の問題、それに関わる雇用保険、また、人生前半における社会保障など多岐にわたって日本と各国の制度やその違いを取り上げて言及している。
Posted by ブクログ
公務員試験対策で読んだというのと、少子化問題に相当の危惧を覚えており、手に取った。
完全に斜め読みなのでアレだが、世代間格差にかかる社会保障の問題について幅広く扱っており、参考になる。もっとしっかり読まねばならないが、試験で時間が割かれるので仕方ない。
Posted by ブクログ
人口減少社会からくる世代間格差について数多くの指標やデータを元にとても良く整理されており、いろいろな角度から世代間格差について知ることができた。以前から人口減少社会には問題意識を持っていたが、あらためて問題の多さに気づかされた。その中でも特に、雇用システムについての内容は、各世代の所得が増えなければ世代間格差は埋まらないが、同じ労働をしても、正規雇用と非正規雇用との賃金に差があることや、寿命が伸びているにもかかわらず、定年制があること、働き方が多様化していないことなど、自分の問題意識に対し、次なるステップをいただいた。
Posted by ブクログ
【読書その14】先月1月30日、国立社会保障・人口問題研究所が発表し、世間で大きな反響を呼んだ、新たな人口推計(12年推計)。
50年後の合計特殊出生率は前回の推計値(1,26)より上向き、1,35に改善すると予想されているものの、50年後には日本の人口の約4割が高齢者となり、その時点での生産年齢人口が半減するという。
そのような現状におおいて、問題視されているのが広がり続ける世代間格差。
本書では、そのタイムリーな政策課題について、かなりわかりやすく説明をしている。世代間格差拡大の背景などの基本的なところから、我が国の社会保障制度、労働市場、雇用システム、少子化対策、諸外国との社会保障制度の比較に至るまで、本書が扱う範囲は非常に幅広い。
特に現在、目下、議論の的になっている現行年金制度の問題点、新年金制度の課題等についての記載も多く、年金制度について考える上で非常に良い本。
Posted by ブクログ
今、とてもホットな論題だと思う。
年金や、若者の就職の問題、少子化など。
日本が直面している問題は、人口構造がもたらしているものがほとんどであるといってもいいのではないだろうか。
そして、この問題は、いまだかつてどの国も直面したことのない問題である。
それぞれの課題について、解決策があげられているが、著者が一番言いたいのはベーシックインカムの導入なのかな~と思った。
先ほど、企業の定年引き上げの義務付けが話題になっているが、なんというか、導入の手順がおかしいような気がする。
世代間の軋轢を無駄に生じさせてしまうのではないか、と懸念している。
Posted by ブクログ
私たち現役世代が最も憂慮していることの一つ、年金などの社会保障問題。
ちゃんと貰えるのか、どんどん保険料値上がりしてくのかなど、現役世代と引退世代を比べた格差問題を書いている。
著者は年金受給額を減らせ、保険料を下げろなど、現役世代中心な意見を言っているのではなく、世代間で不公平がなく均衡した社会保障システムの構築の重要さを提議している。
全般に渡って詳しく書いてあるが特に注意すべきだと思ったのが、若者層の雇用拡大と高齢層との世代間格差の縮小ポイントは経済成長でパイの奪い合いではないと言うこと。
本著によると、高齢層が定年を伸ばしそのまま就業しているから現役世代の仕事が無くなるのではなく、経済成長が鈍化しているから相対的に仕事が無くなっているのだと研究結果に出ている。
つまり、現役世代の就業率を上げるには高齢層から仕事を取るのではなく、あくまでも経済成長を上げることが重要だと。
それと、これも本著によると、出生率増加には、社会保障としての現金給付より、現物給付の方が効果があると詳しく書いてある。
これも感覚的に理解し易い。
世代間で奪い合うのではなく、あくまでも全世代で協力して格差縮小していくことが大切だということがわかった。
世代間格差について本当に詳しく書かれている。
TPP問題や原発問題なども確かに重要な問題ではあると思うが、この世代間格差とゆう問題が今最も重要課題であると強く感じました。
若い世代の方に特に読んでほしい著書です。
Posted by ブクログ
20200903?〜0912 この本は2011年11月発行だから、民主党政権下での社会保障政策を論じている。それから10年近く経ったが、ここで述べられている世代間格差は解消されたとは言えない。少子化は治らないし。税方式への移行とベーシックインカムの導入、医療保険改革は必要だろうな。
Posted by ブクログ
世代間格差について、定義、問題点、解決策について述べられている。具体的な数値などや政策提案がされている。
今は出版からある程度時間が経っているので、通用しない部分もあるが、基本的な考えについては参考になる。社会保障の充実は経済成長を押し下げるという分析がある。
年金、医療、労働、財政、人口減少と多くの制度的問題がからむ。
世代間格差の是正についての具体的な枠組みはまだ挙げられておらず、その部分の観点が今の政策には弱い。
Posted by ブクログ
タイトルにもなっている世代間格差について序盤で俯瞰、その後は既に色々なところで現行制度の疲弊が指摘されている医療保険や年金問題を取り上げ、世代間での不平等や格差がどうして生まれているのかといったところについて、かなり細かく論じられています。これまた色んなところで論じられている少子化による社会全体の負担についても、きっちりと触れられています。
解決策に関する指摘や持論の展開があまり無かったのが残念なポイント。あくまで、現状の問題点を総論的に改めて整理するための本という捉え方をするならば、読んでも好いかと思います。もう少し各論について詳しく知りたいようなら、他に読むべき本はいくつかあります。社会保障なら、鈴木亘さんあたりでしょうか。
Posted by ブクログ
少子高齢化に年金や雇用問題など、いまの社会システムの不具合について、経済学者の視点からわかりやすく解説してあります。
「社会福祉が充実してくると、経済発展が停滞する」という指摘がおもしろかった。不安定な環境のほうが、働く人々のモチベーションを高めるらしい?というのは、妙に納得のいく理屈です。
この本を読んで、とりあえず消費税UPは急務なのかなぁ、と覚悟が定まってきました。(私はもともと北欧型の福祉社会が好みなので、消費税高めの政策に転換していくといいな、と思っているのですが)
あとは、これだけ経済やIT情報がグローバル化したことで、「国」という単位で世の中を動かしていくのは限界にきているのかも、という印象も受けました。今後は「都市」にシフトしていくのでは・・。