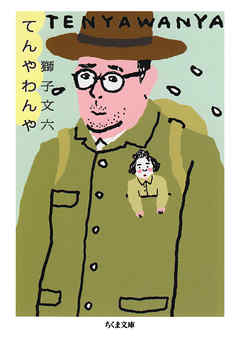感情タグBEST3
恐怖からの自由
戦前と戦後社会の連続性について、この作品は描いている。この指摘や示唆は丸谷才一「笹まくら」が最も成功していると感じているけれど、「てんやわんや」で書き込まれているのは庶民感覚により近く、山口瞳が「卑怯者の弁」で絶唱に近い声で、戦争も殺し合いも絶対に拒否したいといったものと近似値である。いろんな自由が戦後憲法に書き込まれているが、恐怖からの自由がないのだという指摘は切実である。主人公は立派な人間ではなく、うまく立ち回ることを常に考えている小市民であるのでユーモアとシニカルが入り混じり、日本社会のシステムに翻弄される。巻き込まれタイプの典型であるので、志も決意も常にグラグラと揺れてしまう。あとがきに獅子文六氏が言われたという「君はエログロを書かないから良いね」が紹介されているように、庶民が保持していた倫理や道徳が潔癖ではない程度に保たれていることも、作家の現代性を示していると感心させられた。こういう物語がしっかり生き残っていて今も読める状況にあるのは、新聞小説としての連載だったらしいが、当時の読者の見識や感覚に寄り添っていた証拠であるので、読み継がれてほしい作品のひとつである。それにしても、戦争、災害、暗殺、犯罪などの恐怖から自由になれる時代という壮大で素朴な理想を、ジョンレノンよりずっと前の日本作家が書いていたことに驚きました。借り物ではない、手づくりの思想は好ましいと拍手喝采。
Posted by ブクログ
平松洋子によると、獅子文六 敗戦三部作の一つ。主人公 犬丸順吉が、戦後、流されるままに伊予 宇和島近くの相生町に居候して過ごす 1年間を描く。花兵は言うまでもなく、勘左衛門、越智、拙雲といった脇を固める登場人物が誰もかれも個性的で、土地の風俗や食べ物、言語とあいまって独自の小説世界を作り出している。もともと終戦直後の混乱期を描いた小説は好きなのだが、これはそれらの中でも秀逸な部類に入るだろう。獅子文六を平成の世に紹介した平松洋子自身による解説も良い。
Posted by ブクログ
主体性というものを持たず
「先生」のいいなりに利用されてきた男が
戦争の時代を経て、侮辱されていると気づき
呪縛を脱していく話
自我の目覚めというよりも、絶望からくるニヒリズムなんだが
1950年代の日本では、これが大変に売れて映画化もされた
話の舞台となった宇和島市では
作品にちなんだ饅頭が、今も土産物として売られている
「先生」の推薦で、軍の情報局に勤務していた主人公は
戦犯として逮捕されることを恐れ
やはり「先生」の勧めで
惚れた女に心を残しつつも
東京から愛媛県の南予地方へと逃れるのだった
長閑な田舎ぐらしのなかで東京者は珍しがられ
いろいろといい思いをさせてもらううちに
「先生」への反感も育てていく主人公は
やがて四国に根を張ろうと考え始め
地元民の提唱する四国独立運動にも、積極的に参加していくことになる
しかし新たな恋に破れ
新税制のために、居候先の家は傾き
さらには終戦翌年発生した南海地震の大混乱に巻き込まれて
結局は東京への帰還を余儀なくされるわけだ
今風にいえば
戦後文学であると同時に、震災後文学ということにもなるだろう
話の舞台は、大江健三郎の生家に近いので
「森」のサーガと比較してみるのも面白いと思う
Posted by ブクログ
ヒロイン?の花輪兵子がツボ。
「アッハッハッハ」って笑い飛ばす性格が最高だった。
もうちょっと本筋に絡んで欲しかったな。
今まで読んだ文六作品は全て三人称で書かれていたので、一人称がまず新鮮だったし、戦後の町や人々の描写が克明で、なんだか感動してしまった。
本作は四国に疎開していた文六先生が東京に戻って6年ぶりに書いた長編小説で、戦中〜戦後の様々な経験がこの小説に反映されていることを窺わせる。新聞小説だし、娯楽映画として愛された作品かもしれないけれど、歴史的価値のある小説だと思うので、もっとたくさんの人に読まれてほしいな。
Posted by ブクログ
「てんやわんや」。獅子文六さん。1948~1949に連載された小説だそうです。
原爆、終戦が1945年夏。憲法施行が1947年。
獅子文六さん、というのは、徐々に再評価されている人だと思います。
いわゆる、流行作家だったひと。
その当時から、言ってみれば「軽い」のが持ち味で、決して純文学でも重いテーマでもなかった。
この「てんやわんや」も軽いんです。
そして、連載物っぽい。つまり、ラストを考えずに適当に書いているんだろうなあ、という。
主人公の犬丸順吉さん、というのが、まあ恐らく30凸凹のサラリーマン。
上役社長の言いなりになってきて、終戦を迎え。
ホッと一息と思ったら、社長が戦犯になりそうで。つまりまあ、社長はかなり戦前社会で美味しい思いをしてきたわけです。
対岸の火事かと思ったら、「君も戦犯になるよ。逃げたまえ。この書類の包みを持って逃げたまえ。決して見ないように」。というわくわく展開。
この犬丸さん、実は社内の、積極的なパワフルガールとちょっといい感じになっていたんですが、命が大事、と紹介された愛媛宇和島に逃げます。
ここから、愛媛宇和島に舞台を移すや、荒廃した東京とは打って変わって桃源郷。食べ物はあるは、人心は穏やかだわ。
ここンところで戦後直後の都市と田舎の風俗の差を見せながら。
話しはこの地方での、さまざまな風俗や祭りを織り込んでのてんやわんや。
犬丸さんは、辺境山地の娘に恋い焦がれたり、このままではイカンと思い直したり、このままでずっといようと願ったり。
かなりイケてない主人公の右往左往を、あははと笑っているうちに。
件の社長がやってきたり、パワフルガールが社長の愛人になっていたり(そうかと思うとそうではなくて純潔だったり)。
つまりは、面白そうなトコロに向けて、実に節操も無くよろめいていくストーリー。
ところが、そのはざまで煩悩に焼かれてみっともなくてんやわんやを繰り返す主人公には、戦後直後でも、きっと多くの人はこうだったんだろうなあ、という「人間味」が溢れていて、実に飽きない。
最終的には、どうやら伏線を回収しきれないままに勢いで終わった、という匂いが充満するのですが。
それでも、なんだか楽しいからいいや、というのも、これまたある種の完成度。
うーん。噺家で言えば...昔々亭桃太郎...。独特の味わい。志の低さをテクニックの高さと確信犯なアドリブ感。
この軽さ、テキトーさ、なんとも腰砕けな明るさ。
こんな小説が、太宰治や坂口安吾と同時代にのほほんと完成度の高さを醸し出していたことを思うと、なんだか灰色で重苦しく勝手にイメージしていた戦後直後っていうのも、結局はひとの営みでしかなかったんだなあ、という視野が開けてきて、楽しからずや。パチパチ。
Posted by ブクログ
獅子文六の小説3冊目、またしてもダメ男登場。小説の舞台は戦後の日本なのに登場人物は現代にもいそうな人々だから面白いのかな。ダメ男を追いかけ回す花輪兵子の迫力がスゴイ、笑える。映画では淡島千景が演じたんだって。スピード感のあるストーリーに引き込まれ、今、4冊目を読書中です。
Posted by ブクログ
ずっと読みそびれていた獅子文六さんをようやく読むことができました。
噂通り面白かったです。
主人公の性格がそのまま作品のテンポになっている感じで、この主人公の考えや行動がいちいち面白いのです。クスッとするような面白味というか、「こういう人っているよなぁ、分かる分かる!」という面白味があります。
THE娯楽という感じで本当に楽しく読めました。
主人公とその周りのキャラの濃い人々、舞台が愛媛というとちょっと『坊ちゃん』を思い出します。わざと『坊ちゃん』を思い出させるように書いたのではないかと思いました。『坊ちゃん』のコメディ。真っ直ぐでやんちゃな坊ちゃんに対し、こわがりで逃げ腰で長いものに巻かれて火中の栗は絶対に拾わない犬丸潤吉。『坊ちゃん』も主人公坊ちゃんの性格がそのまま作品となっているし、この作品が新聞小説ということもあって漱石を意識したのかなぁ、なんて思いました。
最後に掲載されている、獅子文六さんが書いた「【付録】てんやわんやの話」を読むと、獅子文六さん自身がとっても面白い人なんだなぁと分かります。目のつけどころや感じ方が多分今でいう芸人さんに近いような気がします。
装幀のイラストも好きです。ゆるっとしていて作品に合っていると思うし、こういう表紙なら若い人も手にとりやすいように感じます。
てんやわんやという言葉はこの本で改めて広まったそうです。びっくり。
Posted by ブクログ
終戦間もない日本、生活の基盤を失って確たる目標も持てずにいる男が遭遇する珍事件の数々。いかにも頼りなさそうな主人公とは対照的に、彼をとりまく人々がみな生き生きとしており、そんな彼らが逞しく世を渡らんとする姿が愉快に描かれる。