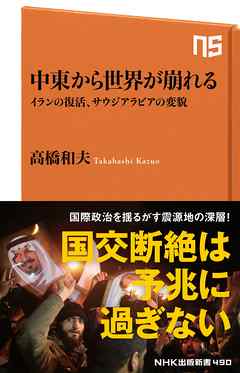感情タグBEST3
Posted by ブクログ
2000年代の中東情勢を概観。中東には「国」と「国もどき」があり、後者の代表格がサウジアラビアである、という解説に最初ギョッとしましたが、読んでいくと、なるほど、国もどき…と腑に落ちました。
良書だし、重版されないのかな。
Posted by ブクログ
「中東イスラム世界の諸問題には、共通した構図があるように思えてならない。 一つめは、イラクやシリアのような人工的につくられた〝国もどき〟が持つ本質的な矛盾である。つまり本人たちの同意なく、多くの宗派・民族の集団が無理やりに一つの国境線に押し込まれたという現実である。 二つめは、アフガニスタンやイエメンが経験したような、伝統社会から近代社会へと移行する際の困難さである。両者の間を隔てる深い亀裂がある。アフガニスタンやイエメンは、この亀裂を無理をして一気に越えようとした。それがともに失敗し、亀裂に落ちて出口のない内戦状態から抜け出せないでいる。 こうした失敗を見ると、これまで秩序を保ってきた伝統社会のあり方にも敬意を払う必要がありそうだ。」(『中東から世界が崩れる イランの復活、サウジアラビアの変貌 (NHK出版新書)』(高橋 和夫 著)より)
Posted by ブクログ
2016年1月に第1刷発行された本書であるが、
2022年8月現在でも、大変分かりやすい。
現在でも混迷を極めている中東情勢の、
どこに注目して見ていけばいいかを分かりやすく解説してくれている。
ニュース報道で知るだけではまったく理解しきれない中東情勢も、
本書のように分かりやすい著作で補足していけば、
もっともっと身近なものになるのではないか。
Posted by ブクログ
中東に関しては、高橋さんの書籍が一番信頼が置けます。
中東には“国”は3つしかない(イラン、トルコ、エジプト)。あとは“国もどき”だ。という主張は本当に目からうろこでした。
Posted by ブクログ
ニュースの断片的な情報くらいの知識しか持っていないので、大きな中東の情勢を理解することができた。自分自身の理解レベルに合っていたので、とても分かりやすく、興味深く読むことができた。
Posted by ブクログ
第一章 サウジ、イラン「国交断絶」の衝撃
第二章 イスラム世界の基礎知識
第三章 「悪の枢軸」・イランの変質
第四章 「国もどき」・サウジアラビアの焦り
第五章 国境線の溶ける風景ーアフガニスタン、イラク、シリア、イエメン
第六章 テロと難民
第七章 新たな列強の時代へーアメリカ、ロシア、中国、ヨーロッパ、トルコ、エジプト、イスラエル動向
終 章 中東と日本をつなぐもの
中東本を何冊か読んだがこれは良い。
中東研究のスペシャリストがわかりやすく書いてくれた。
難しすぎない、ちょうどいい、でも深い。(なかなかない)
Posted by ブクログ
私は、中東の政治について、全く疎いが、ニュース等で中東のことが知りたいと思ってた時に出会った、非常にわかりやすく、うれしい本。
中東は「国もどき」≒国家として体をなしていない国がほとんどという表現が、乱暴な表現のようでいて、「そうなんだろうな」と思える説明がしてあった。王様はたまたまその国の中心を治めているだけで、地方は地方で独自に有力者が収めている。王様は内政/外政ともに微妙な駆け引きを行い、国を治めている。という。日本の江戸時代も、ヨーロッパも国といっているが、地方は地方の文化があったということと同じだろう。
そんな「国もどき」の代表がサウジアラビアであり、そのサウジアラビアの、動きが最近、強国風になっている。。。
また、シリアについての記述など、民衆を殺戮しているアサドは気の触れた悪魔としか思っていなかったが、アラブの春の流れから、放っておくと自分の命がなくなるため、対応方法を冷静に選択すると、このような非情な結論となるということが分かった。色々な周辺国との駆け引きも「政治」的な判断が重々されていることが分かった。また周辺諸国のそれぞれの視点から見て、アサドを容認するかしないかの差もよくわかった。
正義は国の数だけあるし、利害関係でそれぞれの国は動いている。
Posted by ブクログ
中東関係の本を読んでいますが、一番理解しやすかったように思います。現在の中東情勢を近代の歴史からひも解いて解説していただいているので、とても「バックボーン」が理解できたように感じています。
Posted by ブクログ
イラクやシリア、サウジアラビアを国もどきとする表現は他の本でも読んだ。確かに、原油利権で国民をコントロールしながら、しかし、実際には、宗教だけではなく、民族、聖地なども含めて複雑な成り立ちを持つ国境線は確かに一筋縄では言い表せない。こうした複雑な構造をもつ中東から、自国のエネルギー自給の目処が立ったために急速に興味を失ったアメリカ。日本は、信頼をベースに外交をすべきであると結ばれるが果たしてどうか。脱化石燃料が進む中で、価格調整が為される、日本はもう少し、狡猾な外交をしても良いのではないだろうか。
本著は、イスラム教の解説から中東国の歴史、成り立ちを分かりやすく解説してくれる良書である。
Posted by ブクログ
イラン人=ペルシャ人と、その他のアラブ諸国=アラブ人という違いがあること。サウジが国家の程を成していないこと等、眼からウロコな話が多く出てきた。まだまだ、マスコミの報道からは知り得ない事がたくさんありそうだ!
Posted by ブクログ
近年の中東での動き、特にシリアからイラク、トルコとサウジについておおまかにではあるが概要を解説した本書。ISはイラクの鬼子であったり、トルコのイラン憎しのあまりISへの支援、サウジのムハンマド副皇太子によりOPEC掌握等、ざっくりした流れはこれで理解できるだろう。著者は今後、中東国家からチーフダムへの変革を予言する。これについてもさもありなんと考える。もう少し中東については追いかけてみたい。
Posted by ブクログ
中東問題は宗教戦争ではなく、単なる地政学的問題であることを解き明かす。
イギリス・フランス等の列強が国境線を引いた結果、近代国家としてはなりたっていない国家もどきの国が沢山あるのが中東。
サウジも国家もどきの国の一つだが、今後石油のもつ戦略物資としての性質の変化(米国でのシュールガス開発等)により国家の戦略を変えざるを得ない状況に追い込まれている。アラムコの上場もその一環だが上手くいくか否かは不明。
国家もどきの国の境界線が政治要因で変更される可能性が今後高い。(シリアはその典型例)
Posted by ブクログ
なんとなく、最近、中東問題に関心があって(きっかけは忘れた)、新書を少しづつ読んでいる。
イラクに詳しい酒井さんの本を読んで、中東問題は、宗教、宗派の対立というより、欧米中心の国際秩序の矛盾のしわ寄せが中東にきていて、そこに国や民族ごとの経済的利益、安全などを求めたリアル・ポリティクス、ジオ・ポリティクスの問題なのだ、という視点を学びつつある。
あと、これまで中東といえば、パレスティナが問題の根源と思われていたのだが、いまやそれは問題の背景に下がっているという認識に驚き。
というなかで、別の著者のものも読んでみようと思って、こちらも読んでみたが、基本、大きな話は一緒なんだな〜。
こちらは、イランとサウジアラビアの問題がわりと丁寧に書いてあって、イラクに詳しい酒井さんの本と組み合わせるとさらに絵柄はクリアになってくる。
そして、ISの問題も実は収束に向かいつつある。が、中東に根源的な矛盾が解決し、現状に不満の人々が減らない限り、テロはなくならないという認識にわかってはいても、暗い気持ちになる。
で、この本を読んでいると、本当にパレスティナ問題への記述が薄いのに驚く。
この著者は、イスラエル関係の本も結構書いているのだが、この分量の少なさは、本当に印象的だな〜。