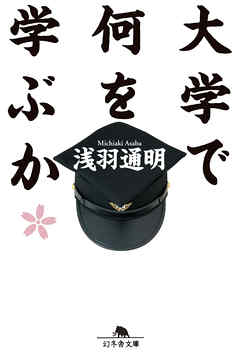感情タグBEST3
Posted by ブクログ
逃げで勉強しちゃいけんのですね、、。エスケープはダメかぁ。私にとって勉強は趣味止まりだな、じゃあ。と思いました。読むの遅すぎた!一年の時に読みたかった本です。就活生として読んだけど、それはそれで面白かったかな。
Posted by ブクログ
学校は、勉強をする所なので勉強だけを学ぶ所だと思っていました。しかし、この本を読んで、学校は、勉強だけを学ぶ所ではないことが分かりました。ただ先生の話を聞いて家に帰ると言うだけでは、学校に来ている意味がないことに気づきました。先生の話を聞いて、何を吸収して活かして帰るかがかなり重要だと言うことに気づきました。学校は、勉強をする場所ではなく、勉強を吸収して活かすことを学ぶ場所だと思います。みなさんもこの本を読んで考えてみて下さい。
Posted by ブクログ
今年大学1年になったものです。
僕自身は理系ですが、この本を読んでとりあえずは他にやることもないから勉強しようというような考えはもたないでやっていこうと思いました。
Posted by ブクログ
大学とはどのようなところかを説明する書。高校と大学の教育の違い、一般教養の授業の問題点、教授が先生でなく研究者であること(教育のプロでない)など日本で当たり前に行われいる大学教育の問題点を指摘。
もう一つ、日本という国が「個」よりも「世間」を重んじる傾向にあることに注目。例えば東大生をほしがる企業があるが、これはその東大生の能力というより、「東大」という大きな背景をほしがる。「世間」に属さない人間は相手にされない。これが日本特有の(学歴)社会であることを指摘。これはなかなか面白かった。
総合的に見て非常に良書。ただ、SFCプッシュし過ぎ。確かにSFC教育はユニークであるが、日本の教育にあってない点もあり、問題点もある。それに理念にそった教育が完全に行われていない点もある。
大学生より高校生におすすめ。進路の参考になる。また、SFCの学生にもいいかも。客観的に自分の大学を見るきっかけになる。
Posted by ブクログ
外から見た大学の姿。
一般教養とか専門の講義とか、それって就職や生きていく上で意味があるの?
企業が見ているのは学歴(どの大学に入れるほどの基礎学力があるか/同門の人脈)。
有名大学でなければ、どんな仕事でもこなす、というバイタリティーを活かせ。
上記が多数派であるが、こうした社会生活を営むのが困難、という人はその道を深め、宗教者、哲学者のように他人の頼りとなる道がある。
10年以上前に出版された本なので就職事情や企業体質の記述に若干の古さは否めないが、大学に対する見解は今でも当てはまると思う。
Posted by ブクログ
一見すると、単なる大学批判の本にすぎないと感じるかもしれない。大学はコネを作るために行くものであり、会社もそれを求めて学生を採用しているという事実を改めて思い知らされた。所詮、この世は学歴社会なのかもしれない。読み進めていくうちに、そう感じることだろう。
しかし、この本の不思議なところは、その逆境の中で自分がこれから何をすべきかを考えさせてくれるところである。自分の本当にやりたいことは何なのか、それをもう一度心の中から呼び戻し、学習への意欲と変えてくれる。事実、なぜかはよくわからないが、気象予報士を目指してもいいのでは?という考えにシフトしていった。自分ならなんとかできる。必ずできる。そう感じさせてくれる一冊だった。これからやるべきことは、その情報収集である。狙う価値があるのなら、徹底的に攻めてみる。自分の長所を生かしてスペシャリストを目指せ。そう暗示した本なのかもしれない。
Posted by ブクログ
大学に大きな期待を抱いて入ってきた人々を戒める書。
確かに、大学の教養はつまらないとか、大学は世間であるなどといったことはうなづける。
ただ、(たくさんの本を読んで身につけるような)教養には意味がない、は言い過ぎでは。
まぁ、そのような反論が出ることは予想して書いているのだろう。
非常に痛いところをついてくる、読んで損のない本。
Posted by ブクログ
読みながら、「世間」「教養」の定義など、そうか!と思うこと多数。大学生に対する目線はやさしい。この日本で、就職以外に大学に行く意味って、趣味の世界よねやっぱり。
Posted by ブクログ
主に文系の大学生の就職について当てはまる事は多いのかもしれないが、理系の場合はどうなのだろう。
多くの大学の英語教育は教授の趣味で英文学の名著や古典を訳読させているだけ、と書かれているが出版された当時はそうだったのかもしれないが今はそんな事ないのでは。
証券のディーラーやコンサルティングも学歴不問ではなく、高学歴を採用しているように思う。
大学入試の進路選択での大学の学部学科に関する情報不足は頷ける。
教養とは同じ仲間で共有される知識のカタログで、そこから引用する事で話の種の供給源になるもの、という捉え方を浅羽はしていて、テレビで流れる情報(バラエティ番組、アイドル歌手、人気ドラマ)の話題も教養だという。
日本社会の機軸たる企業にとって、大学は人材の配給所である。では、その企業から見て大学とはどんなものか。それは、入口と出口のみある土管みたいなものである。企業人としての教育は会社でみっちりとやる、大学ではなにもならってこなくてよい。大学の教育内容自体はどうでもいい。必要なのは、どこの大学の入学試験に合格したかを見ればわかるその企業内教育を消化吸収できる基礎能力で、入口はだいじなのである。つぎは出口だ。その大学を出た者(これから出る者もふくめて)全体がつくるゆるやかな連合である「世間」に属する一員であることが、モノを言う。企業は、キミという個人がほしいんじゃない。こういう、キミの「世間」がほしいのだ。だから、出口もまただいじなのである。入口は、キミの能力。出口は、キミの「世間」。企業はこれを買う。
「ハンディは自覚しただけではまだ足りない。強い自覚によって、将来の不安に他人より先に気づき、早くから憂いをなくす備えを促す。ここまでしてようやく、きみのハンディは強みへ転換できる」
「多数者は世の中ほとんど同類ばかりというだけで、自分を正当化できるのに対して、少数者は自分の位置だの人生の意義だのをいちいち意味づけしないとやっていけなかったりする生きにくさである」
「ただいまをみんなと生きる多数者なら関心を抱かない「教養」へ精神を向けてしまったきみが、多数者のためにできるのは、まずこうしたことばをカタログのなかからとりだして見せることくらいではないか」
Posted by ブクログ
しかし、自分は特に誇るべき技能もなくほかよりも優れているとも思わ無いが、そんな自分で十分足りていると自己肯定できたとき、彼は「標準的」人間と呼ばれてよい
Posted by ブクログ
大学っていうのは、机に向かう勉強する場所でもあるし、いろんな人と出会う場所でもある。とりあえず大学側に何かをしてもらおうとただじっと待ってないで、自分から行動したいですね。要は自分次第。
Posted by ブクログ
この本は大学新入生向けの本ですね。
私も大学に入って数年が経ちますが、今読んで思うのはもう少し早く読んでみたかったなと。
本書の想定している読者層は、かなり大学という知的空間に期待を寄せている高校生の方向けに書かれています。
昨今、厳しさを増す就活の仕方についても書かれていますから、現役の高校生や浪人生が今のうちに読んでおくことは有益だと思います。
特に文系の人文学系に進みたい方は必読といってもよいと思います。なぜかというと、人文学系は非常に面白い学問区分ですが、市場を分析する経済学などと比べると社会に出てから使いにくい学問区分です。
というよりも、大学で学んだ人文学系の知識を就活で使おうなんて基本的にNGというのが通例です(本文にもそのような記述あり)。となると、人文学系の知識というのは基本的には、実用的な知識ではなく、教養みたいなものとなるでしょう。
では今後、人文学的な知識は教養であるという前提で話を進めますが、なぜそのような教養は必要なのでしょうか。
--後日、記述します。とりあえず、今日はここまで。--
Posted by ブクログ
主に文系大学生向き。タイトルから連想されるイメージ(堅い、真面目)とは裏腹に、「すれた」大学観が語られる。大学教育が大衆化した現代(出版当時のだけど)では、もはや大学生がエリートとしてもてはやされることはない。真面目に学問やったとしても、院に行くのでなければ、その努力は報われにくい。では大学生活をどう過ごせばいいのだろう。「学生は勉強が本分」という建前は置いといて、そもそも世間は大学・大学生をどう見ていて、そして世間から評価される大学生とはどんなものかを、世間を見てきたジャーナリストの著者がかなりあけすけに語る。ただ結局は「高学歴ほどいい」という身もフタもない結論なので、もう大学に入ってしまった人にはあまり役に立たないかも。
まとめると、学者にならない学生なら、大学で学ぶ教養は「趣味」程度に考えとく方がよい、というアドバイスになるのだけど。それでも教養を求めてしまう学生はやっぱりいるだろう。本の最後の部分では、そうした学生に向けて、現代における教養・インテリの意義を語っている。教養の意義とは、世俗に根付いている既存の価値観が通用しなくなったとき、(たとえば時代の変わり目とかに)全く異なった価値観を提示できるところにある。よく学問は浮世離れしていると言われるが、だからこそ、浮世が行き詰ってしまうような特殊な事態に対応できるのだ。著者は教養とは価値観のカタログであり、インテリとはそのカタログを持っている人間だという。インテリはもはや特権階級ではないが、人類が新しい時代を迎えたとき、そのときこそ教養はその真価を発揮するという。そんな話。これから大学で勉強しようという人には、良い刺激になるかも知れない。
Posted by ブクログ
いわゆる優等生的な大学論とは異なり、いまの大学およびそこでの教育についての多くの疑問点を指摘している。ただ筆者のいう大学での学問的な学びには期待を抱かず、自分のしたいことをしようという論は就職ということを考えるなら最もだと思うが、みんながみんなそういうスタンスをとってしまうと日本の将来はどうなるんだろう?という不安を抱いてしまったのも事実である。またこの本が書かれたのが1996年であり、今から12年も前であることを考えれば考え方が古いと思う箇所もある。2008-5-26
Posted by ブクログ
ネットの書評をみて思ったのだが、現実と理想。 もしくは、現状と社会とでも区別したほうがいいわけで、絶対、この本を読んで、誤解しない方がいいのは「大学」」と「大学生」は違うということと、著者が通っていた大学とはどこなのかを著者紹介で、よく確認したうえで、今の自分の立場をよく弁えたほうがいい。簡単にいえば、騙されないことだと言うのが適切かな? なんせ、私は、彼(著者)の生の声(waseda)を聞いて思ったが, 慰め=騙し(理想)=読者納得 より、 批判=現実=読者反対 という方程式を受け入れたほうが、実際に勉強している読者、受験勝ち組なら、余計な方程式に悩まされなくてすむんじゃないの?と一言いいたい。