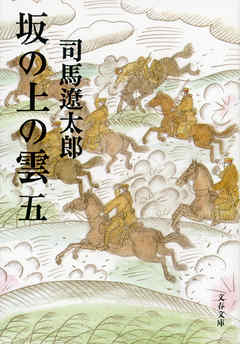感情タグBEST3
Posted by ブクログ
▼旅順が落ちない。なんともストレスである。ただ、通読3回目にして、司馬さんの「なんとなくの小説的意図」に気づく。司馬さんは旅順描写がストレスであろうとわかっていて、加減してはる。でも後でスカッとするためにはある程度ストレスも与えねばならぬ。▼司馬さんの取材もすごいが、それ以上に語り口がすごい。何かといえば「前代未聞」、「古今に例がない」、「史上初であろう」、みたいな文句が手を変え品を変え。それくらい、つまりは「面白いんだよこれ〜、ね?面白いでしょ?」、「この人物のこのエピソード、最高なんだよね〜、ね?最高でしょ?」ということ。▼これが逆に非難する場合も同じくになる。旅順の作戦司令部とか。▼というわけで語り口に引きずられ引き込まれ、とにかく面白ぇ。
Posted by ブクログ
二〇三高地、乃木希典
目を見張る闘いの場面を想像していましたが、多くの日本兵が亡くなるという読み進めることが辛い描写が続きました。司馬遼太郎氏のこの坂の上の雲では乃木希典が海軍からの要請を受け入れず、ただただ兵を失うという愚策を続けたと記されています。日露戦争で日本が勝利したと歴史上では知っていますが、日本が勝利したことは薄氷を踏むようなギリギリのところだったと想像ができました。
Posted by ブクログ
本日晴天なれども波高し の有名な言葉の主 秋山真之が主役の壮大な長編小説。今の時代にこの小説の登場人物が生きてたら、ちっとは日本はましになってるだろうと思わずにはいられないほど、魅力的な人物像が描かれている。おもしろかった。
Posted by ブクログ
旅順要塞における勝利は、多くの犠牲の上に成り立っている。いかにそれを指揮する人の優秀さによって、死者の数が変わるのか、痛感した。
柔軟性と信念、持ち合わせるのが難しいが、このバランスこそが必要であると感じる。
Posted by ブクログ
バルチック艦隊だが、アフリカ最南端経由での大遠征により、日本領海に到着しても戦闘するどころの話ではないくらいに疲弊してしまったと思われる。
次巻以降の展開に注目したい。
あと、この巻で語られた乃木による203高地の攻防戦だが、結果的には児玉の介入で薄氷の勝利を得たが、ここに至るまでに膨大な戦死者、損失を被った。
なぜ、早い段階で乃木を更迭できなかったのか。それは、乃木の人格人徳によるものなのか、それとも日本軍組織の意思決定における弱点があらわになったのか。これらも見ていきたい。
Posted by ブクログ
これまで面白いようで今ひとつ盛り上がりに欠ける印象で読み進めてきましたが、この巻より俄然面白くなってきました。
戦争の行方は戦場での戦闘のみならず、兵站など表には見えない部分が左右することもよく分かりました。
Posted by ブクログ
ついに旅順での戦いに終止符が。
児玉源太郎かっこいいなぁ。
そこから、旅順港が見えるかのところはグッときます。
つい感情的になりやすい部分も、乃木希典に対する配慮も、人間味があっていいなぁと思ってしまった。
Posted by ブクログ
第5巻。陸軍総参謀長の児玉が旅順に入り、乃木大将が苦労していた203高地を見事に占領した。また北の方では、いよいよ秋山好古率いる騎兵が大活躍するところ。面白い。
Posted by ブクログ
戦闘の描写が多くを占めているが、ロシアのウクライナ侵攻中の現代に読むと昔からロシアという国は基本的に変わっていない。変わらないのはロシアだけではないが、ロシアに関しては悪い意味で昔からの考え方が踏襲されたまま現代に繋がっていると感じざるをえない。
以下、印象的な一文。
・ロシア人が国家という神以上の命令者をもって以来、この航海ほど、人間どもに対してはなばなしい支配力を発揮したことはなかったかもしれない。
Posted by ブクログ
漸く203高地を確保。もっと早く児玉氏が指揮していれば、、、。表にあまり取り上げられないが、バルチック艦隊に対する日英同盟の効果。その後のロシアの騎兵を主力とした大作戦。それを事前に察知しながら取り合わなかった司令部。日本騎兵部隊の活躍や、敵騎兵隊の失策。歴史は紙一重と感じました。
Posted by ブクログ
乃木さん司馬さんにdisられまくり。ただ得てして最終的に評価を得るのは…事実と向き合って現場に檄を飛ばし結果を出すものより、現場と協調して波風を立てない者なのかもしれない。
Posted by ブクログ
ついに旅順陥落。それにしても戦争というものの実態を把握するということが、いかに難しいかということを思い知らされる。それは巨大なロシアであっても、政治的に軍人が官僚化していることと、また個々人の才能では素晴らしく、少数を率いて善戦以上の結果を残している日本人であろうともである。
それはたんにこの時代だからというものではなく、恐らくインターネットが普及した今日でも(いやだからこそかも知れないが)言えるのではなかろうか。
それは情報を、正確に捉えるだけの組織と、それを正確に伝える最前線側のどうしても生じてしまう彼我の差があるからであろう。
そして話しは秋山好古がコサック隊との激戦へと続く。
Posted by ブクログ
知られざる戦場の真実の姿を垣間見ることができる
自分の境遇がそこにあったとして、極寒の悲惨な環境に耐えられるのか、恐怖を乗り越えて突撃できるのか…色々と考えさせられる
両国それぞれの視点から情報がある点は画期的
国の政策として戦争は不可避な時代だったかと思うが、命を顧みずに戦った兵士達に対しては、日露関係なく畏怖を持って然るべき
Posted by ブクログ
ついに旅順要塞陥落!
手に汗握る展開で常にハラハラ状態。
自分は観戦武官にでもなったような感覚で、戦いを眺めているような感覚。
なかなか主人公の秋山兄弟が登場しないにも関わらずに300ページを綴ってしまうほどのリサーチに感服。
僕の尊敬する一人にさせていただきます。
Posted by ブクログ
大本営、海軍、満州軍から再三、二〇三高地の攻撃・奪取を要請を受けながらも、その戦略的重要性を理解せず、要塞の正面攻撃を少数の兵員の逐次投入を繰り返す乃木軍に対して、ついに満州軍参謀総長の児玉源太郎が動いた。満州軍総司令官大山巌の代理として現地に出向き、乃木に代わって二〇三高地の攻撃を開始するのである。そして、敵の猛反撃を受けながらも、二〇三高地を奪取することに成功する。山頂に28センチ砲を据え付けたことで、旅順港内の敵艦隊を自由に狙い撃ちすることができるようになった日本軍は、いとも簡単に敵艦隊を殲滅することとなる。日露戦争で英雄とされてきた乃木であるが、本書では決断できない無能な司令官として描写されており、これまでのイメージは覆される。児玉の行動がなければ、旅順艦隊はバルチック艦隊の到着まで温存され、日露戦争そのものの勝敗すら代わっていたかもしれない。
一方、当時世界最強とも言われたロジェストウェンスキー率いるバルチック艦隊はバルト海を出発し、一路極東へと向かったものの、その足取りは悲惨を極めたといっていい。日本艦隊の待ち伏せという、幻想におびえ、イギリス漁船群を誤襲撃し、その後もいるはずのない敵艦の幻影におびえながら航海を続ける。また、途中日英同盟の相手国であるイギリスの支配地域は無論のこと、フランス圏においても、イギリスの圧力が働き、ロシア艦隊は燃料である石炭の調達と、兵員の急速に支障をきたしながら極東をめざしたのである。情報の管理や外交戦略の稚拙さと、兵員の士気の低さなど、外身には協力な戦力に見えるものの、実態は張り子のような存在であったということであろう。また、地球の外周の3分の2に相当する3万キロにもおよぶバスコダガマやマゼランなどの大航海時代を再現するような大航海の後では、日本艦隊に出くわしたときには既に戦闘に足りるだけの体力や士気は尽きていたであろうと思われる。ロシアの敗因は、戦力ではなく、その腐った官僚的国家体制と、体制に不満を抱えながら徴兵された農奴を中心とした兵員の士気の低さということだ。
Posted by ブクログ
組織内部の争いにエネルギーを取られたり、
必要な情報を入手しなかったり、
強すぎる先入観で判断したり、
それが勝敗につながっている。
しかし今より厳しい自然環境で、設備も限られ、情報入手もかなり困難な時代ならしょうがない判断だったのだろうかとも思う。
Posted by ブクログ
<本の紹介>
強靱な旅順要塞の攻撃を担当した第三軍は、鉄壁を正面から攻めておびただしい血を流しつづけた。一方、ロシアの大艦隊が、東洋に向かってヨーロッパを発航した。これが日本近海に姿を現わせば、いま旅順港深く息をひそめている敵艦隊も再び勢いをえるだろう。それはこの国の滅亡を意味する。が、要塞は依然として陥ちない。
-----
読んでて、色んな立場の人が色んなものを背負って戦ってるのを改めて感じました。
特に、上層部の面々の描写。本当に多岐に渡って取材して、魂込めて書いたんだろうなって、中身もそうだけど司馬さんに感謝を伝えたいと思いました。この人、本当にすごいですね。
「売れる本を書こう」とか、そういう次元の本じゃない。
同じ日本人に伝えたいことがあったんだろうな、残したいものがあったんだろうな、自分も日本人の端くれとして、それを感じて読まずにはいられない。時には日本のダメさ加減の描写も、一時的には反感を買ったとしても長い目で見て「後世に伝える」って意味じゃ宝になってると思います。
自分たちの本当の歴史をリアルに描くことで伝えたかったのは、この人が日本人として生まれて、歴史を創る戦争に自らも参加して感じた、「日本に生まれたことへの、同じ国に生まれた人たちへの感謝」だったんじゃないかな。とか、思いました。そういう想いを感じるからこそ、いろんな人が共感する作品な気がします。
この戦争を戦った人たちはたくさんの同じ時代に一緒に生きた人たちの生死に直面して、自分の限界も何度も味わって、何度も死線を越えて、でもそこから逃げることもできない。およそ彼らの想像できなかった未来を生きてるだろう自分は、その彼らへの感謝も少なくとも今までしてこなかった。
「イチ(1)どハク(89)うにっシン(4)やきそば」とかってロゴで覚えた日清戦争と、その10年後の日露戦争。年号を語呂合わせで覚えただけだった日本の歴史上の出来事は、今、リアルに脳裏に刻まれていってる。「これをどこかで教科書にしたらいいのに」とか思うけど、多分中学、高校の俺がそんな授業を受けても余計読まないと思う。焼くか捨てるか売るか。。。今思えば恥ずかしいことだけど、多分そんな感じ。
でも、仕事を始めて、自分の生き方を考えるようにもなって、戦場に駆り出された人たちはその先に「死」が待っていようとも上官の命令は絶対で、逆らうことは許されない。そんな人たちと比べたら、自分はまだまだ甘ちゃんだと思うし、けどそれでもこの時代にこの平和な国に生まれたことを感謝したい。そしてそういう世の中に生まれたんだったら、したいことを思う存分させてもらおうかな、なんて気にもなってくる。
口で言うのは簡単だ。そろそろ、自分も形で見せなきゃな。
Posted by ブクログ
軍人としての乃木の能力が本当にいまいちなのか否かは置いておいて、同世代の軍人仲間から慕われたり心配されたり、敵将を敬ったり敬われたり、無口だけど漢詩などの表現のセンスに長けていたり、といった人としての魅力に富んだ人だったのかな、そしてその点は司馬も認めていたのかな、ということが感じられた。
Posted by ブクログ
激戦はますます佳境となり、その凄まじさ、彼我の犠牲者の数の多さには驚きと傷ましさしかない。
何千何万の兵士達のそれぞれの人生を思うと気が遠くなります。
余談なのですが、司馬遼太郎氏の小説は、その流れの中で、『余談だが』『先に述べた』『話を元に戻す』『○○は既に述べた』、など出来事が前後したり、ある人物を掘り下げたり、色々な要素が盛り込まれて話に奥行きが出て、話は長いがとても面白くて引き込まれてしまう大学教授の講義を受けている様な印象を受けます。私だけかも知れませんが(笑)。
Posted by ブクログ
ついにニ○三高地を奪う。
もっと早く児玉さんが指揮をとっていれば
失われる命が少なく済んだのに…!と
つい思ってしまう。
戦いが終わる、という情報が耳に入ったとき
日本軍、ロシア軍が互いに抱き合った、
というシーンが一番印象的。
戦争がなければお互いにただの人で
楽しく過ごせるのに
国のために、殺し合う、殺し合わされるって一体
戦争ってなんなんだろう、と思ってしまった。
Posted by ブクログ
大学2年または3年の時、同期から「読んだこともないの?」と言われてくやしくて読んだ。
長くかかったことだけを覚えている。
文庫本は実家にあるか、売却した。
そして2009年のNHKドラマの数年前にまた入手して読んだ。
秋山好古・真之、正岡子規について、初期など部分的に爽快感はあるが、とにかく二百三高地の長く暗い場面の印象が強い。
読むのにとても時間がかかった。
その後3回目を読んだ。
バルチック艦隊の軌跡など勉強になる点はある。なお現職の同僚が、バルチック艦隊を見つけて通報した者の子孫であることを知った。
いずれまた読んでみようと思う。(2021.9.7)
※売却済み
Posted by ブクログ
ロシア軍が一旦戦闘を休止するために、白旗を掲げた時に、日本兵、ロシア兵が抱き合って喜んだというシーンが印象的でした。
軍人とはいえど、本当に揉めているのは人同士ではなく、国同士でしかないということですね。
ロシア軍内部のまとまりのなさも見えてきました。