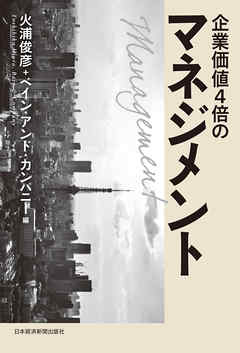感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ベイン・アンド・カンパニー火浦俊彦氏の著作。スターコンサルタントによる書籍や著作は経営者への営業活動であり、それだけだと概念的過ぎて活用できないものが多く本書もその範疇に類する部分はあるものの、冒頭の『「定石」どおりにやらないから結果がでない』という指摘は的を射ている。まずは王道として「序破急」の「序」を忠実に実行する大切さを再認識。ほか「経営トップの仕事は意思決定」や「社員の心を奮い立たせる力」、第3章第4章などは基本を振り返るよい内容だと思う。
NPSやたら推しといったベイン社宣伝はやや気になるものの、企業戦略の再点検としてよい本である。
Posted by ブクログ
企業価値4倍のマネジメント
◼️第1章 正しい戦略で、大きな結果を出す
事業戦略の定義
①顧客に対して競合より優れた価値提供するための自社固有のアクションの集合体
②希少な経営資源の配分の意思決定の集合体
・勝つべき競合は誰か
・その競合はどう出てくるか
・それに自社はいかにして勝つか、が必須要素
企業戦略
・本社が存在する事で企業全体の価値を高めてるか
・企業戦略の論点は以下
①企業全体のビジョン、価値観
②事業ポートフォリオ戦略
③財務、資本政策、など
→全て緊急度が低く先送りされがち
・本社の役割、関与度の規定が必要
コア事業
・市場成長していてリーダーならそこに集中
・そのためにコア事業の正しい定義が必要
→顧客、ケイパ、差別化した価値は何か?
・業績が底堅いと機会損失が争点にならない事も
周辺事業の拡大
・まずは安定的な地位をコア事業で確立してから
・コア事業の以下いずれか1つだけ新たな領域へ
→①顧客、②チャネル、③技術、④生産設備
→⑤仕入れ先、⑥バリューチェーン
・日系は顧客チャネルより技術生産設備を優先
→IBMはハードは捨てて顧客を共有した
・来るべき産業構造変化の取り込みを目指すため
コア再定義
・隠れた資産にフォーカス
・顧客や取引先、社外出身者が想起しやすい
・ハーマンは自動車メーカーの引き合い増加に注目
→カーオーディオに移行
・テルモは医師とのパイプに注目
→心臓や血管の治療機器に移行
顧客セグメンテーション
・細分化の事、それによりどこで戦うかを明確に
・絶対に勝つ領域を特定
→総花を回避、量産効果と累積経験を狙う
・計測可能な切り口で市場と顧客を分割
→年齢や性別など外形的な切り口でない
→顧客の行動をベースにする
・中長期では環境変化に応じて見直す
差別化の徹底
・大手に出来ない特定業界特化で負けない実績作り
・大手でも地域特化で幅広展開しリーダーへ、など
フルポテンシャル
・市場や競争環境を踏まえた最大限到達可能ポジ
・戦う場所を決めそこで圧倒する
・役員の在任期間、株主の保有期間は短縮傾向
→より短期に成果が必要な時代
・そのためにやることは沢山、12点
→規模拡大、人材獲得と配置、売上最大化
→コスト競争力、指標合理化、ケイパ獲得
→意思決定力向上、文化改革、株価対策
→運転資本政策、資産負債最適化、設備投資
・何からやるかは相対ポジで決まる
→リーダーは更なるシェア獲得、など
→相対収益低いなら成長より収益改善
◼️第2章 差別化と競争力で「どう勝つか」を定義する
「どう勝つか」が「どこで戦うか」より重要論点
・競合にどう差別化するか、その源泉はどこか
→この問いに同義
・コアケイパは一朝一夕に構築出来ないから
まず自社の競争力を明示する
・差別化の源泉は3カテ15類型ある
①経営体制→本社の優れたケイパやノウハウ
②機能オペ→現場の優れたケイパやノウハウ
③独自の資産→他社に勝る有形無形の資産
・優れた企業でも4-5個優れていて組み合わせで差別化している
顧客ロイヤルティ
・製品サービスあるいは事業に対する包括的顧客体験による顧客の推奨度
・これも他社との相対値が重要
→自社、他社のロイヤルティを把握すべき
・セグメンテーションして総花対象にしないが大事
・最も左右する瞬間に資源を投入
→Appleは故障時は迅速かつ新たな使い方も提案
→ユーザーをますますファン化
製品の複雑性は持続成長の阻害要因
・多数の製品種類があって個々に利益を出す企業
→管理事務工数や金型調整時間、材料分散の割高
→sku削減による増益(売上は減少可能性)
組織の複雑性
・事業、機能、エリアの3軸がグローバルで必要
→会議が増え意思決定プロセスは複雑化
→現場が見えない、意思決定事項が伝わらない
・組織の複雑性は所与とし競合より意思決定を強化
・意思決定=起案、情報提供、合意承認、実行
→起案と決定の1箇所集約
→承認箇所の最小化のプロセスが競争力を付ける
→役割のシンプル化、明確定義
KPI
・ボトルネックや高業績要因を特定するためのもの
・財務的成果の先行指標にするためのもの
→打ち手の財務効果が出るまで時間がかかる
→アクションやその結果の指標で管理する「
◼️第3章 戦略実行のためのM&A
コア事業でリーダーとなるためのM&A
・企業戦略の基本は圧倒的な市場地位を作る事
・望ましい地位を獲得するまでが1つのストーリー
→複数買収可能先をリスト化し時間かける
→M&Aを繰り返しポジションを強化
・製品や地域が分散すると複雑性が増える
→時間のロス
→時間を買うためのM&Aで時間を取られる
親会社のコアケイパビリティが買収先価値を決める
・ABIは低コストビールシステムを移植
→導入率は95%
→優れたケイパが移植されないと買収の意味無し
・コアケイパビリティの明確化が必要
→明確化が後回しになると買収先が伸び悩む
→それに時間を取られ時間ロス、明確化出来ない
◼️第4章 「オペレーティングモデル」で結果を出す組織に
オペレーティングモデル
・戦略、事業の価値源泉を作る組織運営の原則の事
・戦略と組織の橋渡し
戦略が含むべき事
・戦略実行にあたっての組織要件
・組織構造やレポートラインだけでなく、以下
①価値創造の源泉の明示
②強みが具体的にどう利益創出に繋がるか
4つの要素
・最初に組織の青写真を描いてから詳細化する
①組織の骨格
→顧客や製造プロセスの重複度で決める
→本社の役割、関与度を戦略に照らして決める
②責任役割分担
→誰が情報提供、起案、意思決定、実行するか
→経営ダッシュボードも活用
③ガバナンス
→経営と現場の溝を埋める
→KPIをアクション、その結果、財務効果へ分解
④会社のDNA
→変わらなければならない理由、向かうべき方向
→これを事実とデータで分析して明示
→取るべき行動様式として厳格にモニター
→人事評価に組み込む
3つの実現に向けたケイパビリティ
①鍵となる人材
②鍵となるオペレーション
③鍵となるテクノロジー
オペレーティングモデル見直しのタイミング
・大規模M&Aなど特別なイベント
・環境変化早いので見直しは恒常的に必要
・そのための以下質問から見直し必要性を評価
①施策実行が迅速着実に出来る設計か
②事業間シナジーは担保されているか
③意思決定は迅速に出来る設計か
④全体のコスト効率を一定に抑えられるか
⑤実行のため自社の価値観文化を強化出来てるか
・上を縦軸、横軸に4要素3ケイパを並べる
→その討議のWS
オペレーティングモデル設計のステップ
①戦略要件の抽出
・差別化すべきケイパ
→経営管理系の能力
→オペレーション(SC、マーケなど)
→自社特有の資産(工場、店舗、ブランド)
・鍵となる意思決定項目
・コスト効率の許容値
→どこを強化しどこを手を抜くか、メリハリ
②組織の現状評価(強み弱みの項目)
・マネジメントのリーダーシップ
・施策の優先順位と役割分担明確度
・組織構造のシンプルさ
・意思決定の質とスピード
・人材の適材適所度
・結果を出すことへの執着度
③設計原則の立案
・ビジョンやゴール
・ターゲットとする顧客
・差別化すべきケイパ
・重要な意思決定項目
・組織のDNA、価値観
④オプション出しと評価
・組織の骨格、責任役割分担、ガバナンス、DNA
⑤チェンジマネジメント
・変革理由をシンプルに説得力をもちまとめる
・どこに向かっているかを伝える
・コアグループを変革に巻き込む
・定期的なリスク評価と対策、など
◼️第5章 社員の心を奮い立たせる力を身につける
◼️第6章 顧客ロイヤルティ向上で成長を実現する
CX強化に向けた品質測定
・CX=ブランドや提供価値、顧客接点の関わり
・ブランド=広告、マーケコミュにおけるシグナル
・提供価値=整備サービス自体、ネットワークなどが提供する価値を含む
・顧客接点=営業、販売員、流通業者、店舗、ウェブサイト、コールセンター、SNSなど
・製品サービスがコモディティ化
→差別化のためにCXが流行る
→品質測定が必要になる
アンケートの質問
・満足したか?
→過去を問う質問
→自分1人に関する低ストレスなもの
・親しい人に勧めるか?
→未来を問う質問
→周囲に影響を与える高ストレスなもの
→実際に今後その行動する可能性が高い
重要顧客接点
・企業と顧客のやり取りは何度も往復がある
→その中に重要な顧客接点がある
→そこにだけ重点的に投資する
→これが顧客志向の分析
・顧客の優先順位付けも大事
B2Bにおける顧客ロイヤルティ
・顧客は合理的に価格や機能に基づき判断
・ただ大企業は意思決定に関わる人数が多い
→担当者だけでなくその上席まで
→それらの情報を取り全体像の把握が重要
→担当が変われば切り替え、とかある
→顧客ロイヤルティはやっぱり重要
ロイヤルティの高い従業員がロイヤル顧客を産む
・より一歩踏み込む努力をするから
・労働人口は減る一方の中、そんな社員獲得は困難
→エンゲージを高め長く働いてもらうべき
→研修コストなどにも影響
◼️第7章 コスト最適化と成長への集中投資による業績改善
組織の箱を増やすと複雑になり非効率に
・製品×機能部門の数だけ調整機会が増えるから
・クロスファンクションチームがその悪い例
→時限的なら良いが定常化させてはダメ
・会議の資料準備、データ集め、情報共有のためだけの会議、更なる質問の発生、フォロー会議…
◼️第8章 創業者目線復活で再生を果たす