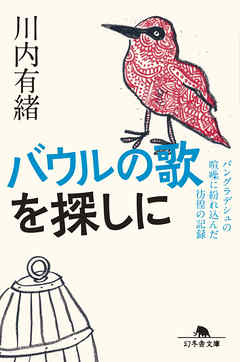感情タグBEST3
Posted by ブクログ
大好きな本
何度読んでも、川内さんの明るさ、行動力、調査能力、聞き出す力に心を奪われる
情景描写もうまく、旅記としてもおもしろい
バウルの考え方・生き方を、どのように理解していったか、過程が丁寧に書いてある。
バウルの哲学をわかりやすく言語化しているので、文化を学び、自身の生き方・価値観について考えるきっかけともなる本
Posted by ブクログ
川内有緒さんの文章ってどうしてこんなにすーっと心に入ってくるんだろう。バウルを初めて知ったけど、この中に出てくる事を色々調べたくなってきた。
ノンフィクションから湧き出てくる表現がとても素晴らしい!
Posted by ブクログ
4冊目の川内さんの本。
不思議なバウルを探し求めるバングラデシュへの旅。バウルを追う中でバングラデシュという国の歴史、バウルに込められてる哲学が明らかになり、その全てに深く考えずにはいられませんでした。
人生の行き先はいつだってココロが決める。
自分を、知る旅を最後まで続けたいと思わせてくれる一冊でした。
Posted by ブクログ
もう一度読み直したい。今この時期に読んでよかったな、と。本当の自分なんて言葉は使い古されたありきたりな言葉かもしれないけど、自分は誰なのか?は何か肩書きなどを抜きにして語れるようになりたい。
Posted by ブクログ
単行本の時も 五つ★だったはず
その本が 文庫で再販されると
ついつい 手に入れてしまう
そして また読み始める
すっかり忘れていたところもあり
ぼんやり そうだった
と思い起こすところもあり
それでも やはり
川内有緒さんの紡ぎ出す
ノンフィクションの海に
心地良く漕ぎいだしてしまう
どきどき するところも
はらはら するところも
ふーむ なるほどの ところも
確実に 増えている
バウルの魅力も さることながら
川内さんの存在そのものが
バウルと同化してくるようだ
きっとまた手に取ってしまう
一冊が増えました
文庫の解説が
高野秀行さんであるのも
いかにも 似つかわしい
Posted by ブクログ
バウルの歌を探すという旅。バウルとは何なのか。こういう精神性に触れた話が好き。バウルは見つかるのか、答えがわかるのかもワクワクしながら読めた。
Posted by ブクログ
元国連職員でパリの国際機関に勤めていた川内有緒氏の著書。自分が今まで読んだいわゆる「面白い本」には一つの法則があって、それはプロローグからすでに面白いという事なのだが、この作品も例外にもれず面白い作品となった。
著者の川内氏は国連職員時代の出張先バングラデシュで、「バウルの歌」の噂を聞くことになる。バウルとはバングラデシュや、インドの西ベンガル地方に住む吟遊詩人の事なのだが、地元の人でも詳しいことはよくわからないらしい。この訪問から数カ月後に国連を退職した川内氏は、知り合いのカメラマンと現地ガイドの3人で、バウルを探す約2週間の旅に出るのである。
実はこのレビューに、バウルについてもう少し詳しく記そうと思ったのだが、とても簡単には説明できそうもないので、詳細は作品を読んでほしい。しかしバウルの思想や教えがノーベル文学賞を受賞したタゴールや、インド独立運動の指導者であるガンジーにも大きな影響を与え、インドとバングラデシュの独立につながって行ったことに間違いはなさそうだ。
バウルの歌の歌詞には多くのメタファーが含まれているのだが、クシュティア行きの列車の中で聞いた「知らない鳥」、また旅の終わりに船上で聞いた「盲人の祭」という歌には非常に深く考えさせられるものがあった。先進国に生まれ、物質的には恵まれた生活を送っている自分自身も、バウルが表現する盲人の一人なのだろうと思う。
Posted by ブクログ
6月目前の東京、梅雨の気配を孕んだ風を頬に受けながら、思考は熱気と土埃と人いきれのバングラデシュに飛んでいく。
ほんとうに素晴らしい本に出会った。
「自分を探す旅」と言うと酷く陳腐だけど、著者は意図せずして自分を見つけに行ったのだ。
バウルの歌に引き寄せられて旅をしながら、思考は過去(国連での仕事、学生時代の経験、そして父親のこと…)と現実の間を行き来する。
まるで鳥籠の中と外を気紛れに飛び交う「見知らぬ鳥」のように。
バウルに出会うには2週間では短すぎると言われた旅で、信じられないくらい多くの邂逅があった。
彼女が引き寄せたのか、バウルが引き寄せたのか、いずれにせよ出会うべくして出会ったのだと思う。
時を得、人を得る。
いわゆる「持ってる」人だ。
旅先で出会うやさしい人々や、旅を共にしたカメラマンの中川さん、通訳のアラムさん、みんな抱きしめたくなるほどに魅力的だった。
バウルについて、もっと知りたくなった。
そして、私も心だけでもバウルになりたい。
見知らぬ鳥、つかまえたなら、「心の枷」をその足にはめたのに…
Posted by ブクログ
バングラデシュで言い伝えられている伝説の吟遊詩人・「バウル」を求めに旅に出た著者の話。
記録もない。歴史的資料もほぼない。口伝で伝わる世界無形文化遺産であるバウルの歌。「本物のバウルの歌」を聞くためにバングラデシュの街から村、祭りや聖者廊をカメラマンの友人と、現地の仲間と旅をする。旅をする中で、バウルはただ歌い手なのではなく、その裏の哲学を伝える人であることに気づいていく。
文面からバングラデシュの喧騒、香り、ほこりっぽさ、カレーの味などが事細かに伝わってくるリアルさに取り憑かれて、一気に読み進められた。「バウルはどんな人たちなの?」「なぜ子供を作らないの?」など色々な疑問をひとつずつ解決していくストーリー、その道中で知らない人との会話から生まれるほんの一瞬の出来事も、目に浮かぶほど細やか。何より、バウルの考えが、何百年前から人が考え続けている「自分は何者なのか」という問いに行き着くところも面白い。結局答えは死ぬほんの少し前にわかるのかもしれないけれども、その問いが宗教も、世の中の流行も、時も、国も全て超えた究極の不思議なのかもしれない。
ガイドブックには書かれていない世界を求めて旅をする、というコンセプト自体が新鮮で、読んでいて旅をしたくなった。
Posted by ブクログ
この本を読んで少しでも感動した時点で、本当の自分を知りたいとか全ての事象にもっと寛容になりたいとか余裕を持ちたいとか、何ならバウルの様に生きてみたいとか、今の自分からは到底辿り着けないものを望んでるのは確かなんだと思った。だってそんな思いにふけっていたら今の日本での豊かな生活は不可能だし、もし両立させたとしたらそれは多くの矛盾を孕むから。
読みながら内面の旅へ誘ってくれる本で、いつの間にか読むのを止めて何か考え事をしてる事が時折あった。この本を読んで小さいけど確実な変化は、今後の人生は今自分が望むものと生活の矛盾と葛藤しながら生きる修行が始まったと言う事だろう。
ちなみに元国連職員として様々報告書を書くのに追われていたというご本人のキャリアからなのか、文化や宗教に関しても分かりやすい解説でさらにバウルへの理解が深まる助けにもなってとても良かった。
Posted by ブクログ
解説で高野秀行さんが、「酸欠になった肺に新鮮な空気がいっぱい入ってくるような爽快感」と書いている、まさにその通りの読後感だった。これ見よがしの感じが全くない自然な書きぶりが好感度大。お気に入りの一冊になりそうだ。
「パリの国連で夢を食う」を読んだとき、この方のスーパーな経歴や、それをまたあっさり捨ててしまう度胸の良さに驚いたものだが、この本で書かれている旅も「普通」からはほど遠い。観光地とはとても言えないバングラデシュに、ちょっと興味を持った「バウル」を探しに行く。連れは男性の友だち(川内さんには夫もいるのだが)。
本当におもしろいと思うのは、そういうことをなんでもないようにごく自然に行動する著者のスタイルだ。肩肘張らないとはこのことで、読んでいてとても気持ちいい。悪路をオンボロバスに何時間も揺られたり、寝袋で車中泊したりしながら、探し求めるのは、なかなかはっきりした姿をとらえられないバウルの歌。読み進めるうちに、いつの間にかその不思議な魅力にひかれて、著者とともに探索の旅をしているような気になる。
連れである写真家の中川さんも飄々としていていい感じだ。さらに、現地通訳のアラムさんがまたいい。アラムさんは日本に住んでいたことがあるのだが、その経緯はバングラデシュの厳しい歴史を物語るものだ。旅をともにするうちに打ち解けた彼が、そうした事情を語り、「日本のおかげで生きのびることができた」と言う場面では胸が熱くなる。
ほかにも、行く先々で忘れがたい出会いがある。これは川内さんたちの人柄だろう。また、ベンガル人は困った人を放っておけないのだとアラムさんは言う。人なつこいという感じではないが、優しい心を持った人たちなのだなあと思い、ほとんど知らなかったバングラデシュという国が少し身近に感じられたような気がする。
それにしても実に不思議な国だ。すし詰めの列車のなかで、著者に懇願された男性がバウルの歌を歌い出すと、皆熱心に聞く。それだけでなく、その歌詞の解釈について乗客同士で熱い議論が始まるのだ。アラムさんが「ベンガル人はテツガクとか宗教の話が大好きなんですよ」「ショウバイの話よりまずはテツガクなんですから」と言っていたそうだ。「アジア最貧国」バングラデシュの別の姿がそこにある。
「パリの国連で~」で詳しく書かれていたが、ここでも亡くなったお父さんについて触れたくだりがある。ここはちょっとしんみりする。子どもの頃からずっと、自由にさせてくれ、いつも応援してできる限りのことをしてくれた、とある。著者ののびのびした個性はそういう環境で育まれたのだろう。また、アメリカ留学時代、コスタリカを訪れたときに出会った女性とのエピソードも強く印象に残る。バウルの歌を探すなかで川内さんが見いだすのは、「人はココロに導かれて生きていく」ということ。その「ココロ」は人との関わりが作るのだろうと思う。
Posted by ブクログ
川内さんの本を見つけてすぐさま購入。バウルを追い求めていくなかで、バングラデシュの様子やそこで川内さんが感じたことが描かれていておもしろい。川内さんの文章が好き。引き込まれるし共感できる。