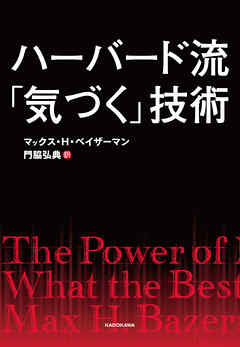感情タグBEST3
Posted by ブクログ
異常を示す兆候は出ているのに、それを見逃してしまう人間の心理が解説されていた。著者がハーバード・ビジネススクールの人なので「ハーバード流」というフレーズが題名についているらしい。
Posted by ブクログ
9.11、スペースシャトル・チャレンジャー、エンロン、サブプライムローン、サンダスキー、ビル・クリントン、ハリケーン・カトリーナ、、、それぞれの事例に、問題化する前に気づき対処できたでろうこと、それにも拘わらず放置されてしまうメカニズムが説明される。
二者択一のワナにはまらず、その他の解決法も選択肢として検討すること。目の前の情報以外に判断に必要な情報があるのではないか。直感によるシステム1の思考ではなく、システム2の理性的思考で一歩先を考えること。インセンティブがもたらす効果がマイナスの誘因になっている可能性を検討すること。部外者の視点と内部情報とを合わせ持つこと。
企業買収の問題など、正解を説明されても、きっと正しく判断できないであろうと思ってしまったが、本質に気づけるよう少しでも視野を広げ、考えを柔軟にしたいと思った。
15-140
Posted by ブクログ
つい見逃してしまう、気づかないことに、どう見逃さないか、気づくようにするかの示唆に富む。カーネマン、サンスティーン、アカロフ等といった行動経済学の権威への言及は行動経済学に触れる基本パターンと化しており、「この本もか。。。」と少し残念。
Posted by ブクログ
「気づく」が多義化している気がするが、予測可能な危機に気づき、それを避けるために行動するために意識すべきポイントを行動心理学の見地から解説している。確かに、このご時世、判断が早いことがそのまま決断力と呼ばれて悪戯に推奨されていることには頷ける。