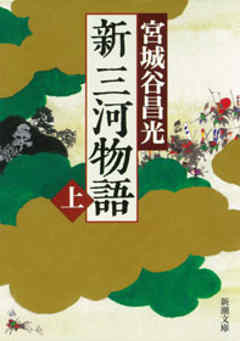感情タグBEST3
Posted by ブクログ
徳川家康の活動を描く物語ですが、原著者の大久保彦左衛門が描いた三河物語が底本になっていることから、徳川家の柱石の一つである大久保家を主として描いた物語。よくある徳川家康や織田信長を描いた歴史小説とは違って徳川家の家臣目線なので雰囲気が大分違う。悩める青年大名として描かれやすい徳川家康が、常に厳然としたリーダーとして描かれている。上巻は三河の一向一揆鎮圧が主たるテーマ。とても丁寧に描かれていて、読み進めるうちに本書に惹き込まれていった。
Posted by ブクログ
<上中下を通してのレビュー>
徳川家康を支えた大久保一族を描いた小説。
松平家を古くから支えてきた大久保一族の結束と忠誠心。
大久保彦左衛門が執筆した「三河物語」がベース。
家臣の視点が面白い。
歴史的事実の裏側で家臣たちがいかにして主君を支えてきたのか。
それに報いてきた主君家康。
徳川家が巨大な権力を手にしてからの大久保一族の変遷。
やるせない事も多々あっただろう…
大久保彦左衛門が「三河物語」を残してくれたからこそ、
後世の我々が知ることが出来た部分も大きい。
Posted by ブクログ
一向一揆の一つの見方として、家康に対する「審判」というキーワードが浮かんでくる。温情裁定の裏に隠された忍耐は、乱世を生き抜いた家康の処世術を象徴するかのよう。だからこそ長きにわたって民を掌握することができたのかもしれない。
Posted by ブクログ
松平家が一城の主ですらない時代から始まるだけに、スケールの大きい話は少ない。だが、それだけにとにかく描写が細かく、具体的で緊張感がある。武将たちの息遣いが感じられるよう。大久保家だけでも何人もの人物が出てくるので、登場人物が分からなくなりがちなのは仕方ないか。
Posted by ブクログ
徳川家康に仕えた大久保一族の話。
そんな一族は存在すら知らなかったが、忠世、忠佐、忠隣のキャラがそれぞれかっこよくて強くてぶれがなくて、もっと知りたかった。
Posted by ブクログ
「風は山河より」と舞台が重なるので、
話も重なるところがあるのかと思いきや、
視点はあくまでも大久保家なので、新鮮さがある。
よくよく考えてみれば、「風は山河より」でも、
大久保忠俊に関する記述、松平家に関する記述は多かったので、
その頃から、今作の着想があったのかもしれない。
Posted by ブクログ
大久保家の名前が皆似通っていて混乱するけど、家康の若かりし頃を知るにいい本だと思う。
こんなにも一向宗の勢力は強かったんだなというのと、人質時代も含めて家康の人格形成がされていく背景が垣間見えておもしろい。
Posted by ブクログ
徳川家に仕える大久保一族を書いた小説。山岡壮八の徳川家康と比べると、作者の違いによって異なる家康像が見えてくるのも面白い。綿密な研究で歴史をより忠実に描こうとしている作者なため、歴史について学べるところが大きい。物語としての面白さは少し半減するのだが。
一向一揆について、山岡壮八著では家康の母であるお大が、家康に無益な戦をやめるように諭し、慈悲を持って一向一揆収めたように描くが、この作品では家康を母を高めるためにそんなフィクションを作らない。リアルな一向一揆と、その特に感動的ではない収束を描く。
長篠の戦いも、鉄砲の魅力が事を決したように描かないのが、新鮮だった。
Posted by ブクログ
徳川家康の家臣、大久保一族の物語。上巻は家康が今川から独立し、一向一揆に立ち向かうところ。
登場人物も多く、読み進むのに苦労したが、それを差し引いても、充分読み応えある作品。
家康か天下人となった一因がよくわかる。
Posted by ブクログ
題名の一部となっている三河物語は,徳川家家臣の大久保忠教が,主に徳川家康の戦の記録を記した書である。本書はそれを,著者による独自の解釈や調査により歴史小説として仕立てたものである。
家康は松平元康と言い,幼名は竹千代である。実家の岡崎松平家が西から伸張してきた織田家の勢力に耐えがたくなったとき,人質として今川家に送られることになったが,その途中に田原の戸田氏に拉致され,今川の敵方である織田信秀のもとに届けられた。その後,今川軍が信秀の子を捕らえ,人質交換が成立したため,竹千代は駿府へ移住した。それが八歳のころで,以後,人質の身分から解放されることなく,駿府にとどまり,妻帯し,男子を儲けた。それが竹千代十九歳の頃である。
元康の父の広忠と祖父の清康は,信義と勇気に欠ける者を侮蔑したことはあるが,弱い立場の者をいじめたりさげすんだりしたことはなかった。岡崎松平家の家風は,情性にあたたかさとあわれみがある。それが政治の根幹であった。人は徳にしか頭をさげない-というのは中国的哲学である。強大な武力や権力に多くの人々は頭をさげて見せるが,それは上辺だけのことである,と元康は誰よりも知っていた。永井人質生活が教訓をさずけてくれたのであり,人とは何であるのかを熟考させてくれたのだろう。栄華のただなかにある今川義元に心服していない自分がある,というのがそうである。義元が討たれた時も,義元は信長に殺されたのではなく,自滅したのだと考えた。義元には徳がなかった。徳を失えば人が離れてゆき,孤独となる。人は独りでは生きてゆけない,というのが世の条理であるとすれば,独りになった義元は斃死せざるをえなかった。合戦がなくても,義元の死は必定だったのである。人質になって岡崎城を出たのは六歳であった。それから十三年後の元康は義元の死によってようやく自分を縛っていた綱が切れたとおもった。
遅くなったが,ここで大久保氏のことについて触れよう。話は前になるが,元康の祖父清康が兵を率いて尾張に討ちいったとき,守山の陣中において家臣の安部弥七郎に斬られてしまう。弥七郎は清康に深い恨みを抱いていたわけでなく,妄想により凶刃をふるった。後に三河物語では,日本一の阿呆弥七郎メ-と最大限に罵っている。当然清康の死は家中を混乱させた。事態の収拾のために岡崎城に乗り込んだ桜井松平の信定は清康の叔父であり,清康の批判者でもあった。信定は清康の遺児の広忠を追放して強引に松平宗家の地位を得た。その地位を覆して,広忠を帰城させ,復位させたのが大久保忠俊である。この功により大久保家の名声は大きくなったが,今川をたのむ広忠の才徳は亡き父清康に及ばず,松平一門のなかで離反するものを抑えられず,西からくる織田家の侵攻を退けることも出来なかった。大久保一門は,本拠を上和田という岡崎城の南に置いている。この頃の大久保一門は,忠平,忠俊,忠次,忠員,忠久の5人兄弟からなっていた。宗家の当主は長兄の忠平がつくべきであったが,はなはだしい肥満で軍事に堪えられず,その座を次兄の忠俊に譲って隠遁した。大久保兄弟は他家の者が羨むほど仲がよい。それこそ財より優ると忠俊は常々言っている。いかなる名声と家産をもっていても,兄弟が争えば家は衰退する。また,大久保忠俊の三男忠員は,わが家には母は一人しかおらぬということを徹底していた。忠員の側室が子供を生んでも,母は三条西殿という忠員の正妻であると。これは,この家では子の生母の貴賎が問われることはなく,全ての子供が三条西殿の子であるとされるので,嫡庶の差別がない。そういった家風が忠員家におおらかさを与え,忠世,忠佐,忠教などを育み,後に大久保家の宗家となっていく。
清康の横死以降,家中の争い,今川への臣従,信長の伸張など,長い間,三河衆は現世を悲観的に見ざるを得なかった。生きているのが苦痛であった。せめて死後はその苦痛から免れたい,そういう願いから浄土真宗の本義と合致した。が,家康の帰国とその後の躍進は,この世も捨てたものではないという情想を家臣たちに芽生えさせた。生に苦があり,死に楽があるという心理の定型を壊すほど,家康の存在は明るく大きかった。主君への忠がすべてを超えてゆくという武士道の創始は,宗教との格闘を経なければありえなかったということである。そういう意味では,家康が帰国後にすぐ起こった三河の国一向一揆は,家康にとって苦しくはあったが,臣下との関係を確固たるものとし,天下統一に向けた第一歩だったともいえよう。苦難を経ない者は大きくなれない。というより,傑出する者に天は必ず苦難を与える,と言った方がよいということだ。
永禄九年,家康は姓を松平から徳川へ変えた。年の瀬も迫った12月29日だったと言う。また,同時に,家康は群臣の意識を改進させるため,三備という軍制を固めた。全軍を3組に分けて,家康の牙旗の元に,旗本という集団を置くのである。その3組のうち2組を率いるのが,酒井忠次,石川家成であった。その中の隊を率いる長を御旗本先手侍大将と呼び,大久保忠世もそれに任ぜられた。それに対し忠世の父の常源は,良将であろうとすれば,おのれを養牧する場は戦陣にあるのではなく,日常にあると思わねばならぬと,さとしたという。
家康は,常に信玄の侵攻に晒されているが,三方が原の戦いで手痛く敗北する。しかしながら,徳川勢と干戈を交えた武田の将の馬場信春は,『日本国中で越後の輝虎と三河の家康を除いて剛の大将はいますまい。このたびの三方が原の合戦において,討ち死にした三河武者は下々まで戦わなかったものはひとりもいない。その証拠に,こちらに倒れた死体はみなうつむき,浜松の方に倒れた者は仰向きになっていた。家康に親密になり,家康を先陣に立てていれば,数年後には日本の全てを従えることが出来たでしょうに』と,信玄の外交の失敗を暗に批判したようなことを言った。家康は,今後も,三河武士の真髄を体現するような者を重用することになるが,菅沼定盈など,城は死ぬまで守り抜くといった気概の者を信用し,小笠原氏助のよう,金に目がくらみ武田方に開城するような者を怨んだ。大久保氏もそんな三河武士を体現するような家風であり,長篠設楽が原の戦いで功をあげた大久保忠世・忠佐兄弟にも目をかけ,特にこの戦で首功第一であった忠佐のことを,髯,髯と呼んで,可愛がっていくようになる。そして,それにあやかる様に,弟の平助も元服し忠教と名乗り,歴史の表舞台へと駒を進めて行く。
平助が父忠員から学んだことに,寡欲であれということがある。忠員は勇気だけでなく才覚もある人で,欲が大きければその二つの才を前に出して本家と対等な家を作ることが出来たはずだ。が,そうすれば兄弟の親睦関係は断たれ,兄を失ったも同然となったであろう。”兄は愛し,弟は敬う”という言葉が春秋左氏伝にあるが,まさに忠世と忠員という兄弟はそれで,人の風景としてはもっとも美しいもののひとつであり,若い平助はそれを見て感動したのであろう。そんな寡欲を実践する平助は,誰も残りたいと手を上げない籠城戦で,忠世に知行を与えるから残ってくれと言われたとき,首を縦には振らず,ただ望みを捨てて命を捨てて残ってくれと言われたとき,すかさず頭を下げて諾と言ったという。著者が本書で書き残したかった場面と言うのはここではないだろうか。知行をちらつかされて残留するのはごめんだが,いかなる報酬もないが,ここで死んでくれと言われれば承知した平助の真骨頂というのはここにあり,三河物語を書いた人物の真髄はまさにここであると言うしかない。
言葉が不滅の力を持つということは,読書家である平助は一番知っていた。平助は三河物語を記すのはそんな言葉の力を信じていたがゆえである。平助は戦については,邪であるとまでは言わないが,人を殺してゆく仕業であることは違いないと考えていた。徳は,小さな徳を積み重ねることで大きな徳となるが,戦は積み重ねるべきものではない。兵は詭道なりということばもあり,正しくないやりかたで,やむなく国を保つというのが戦である。それでも大きな戦に敗れれば,国を失う。ゆえに戦の数を減らし,乾坤一擲の戦には勝たなくてはならないのだ。
年は進み,家康は秀吉と対立し,秀吉が没すると,事実上,家康の天下となったも同然となる。そんな家康にも,他の歴史で繰り返すことと同様に,だんだんと驕りというものが現れる。狡兎死して走狗烹らるのことわざにあるように,大久保一門も次第に家康に疎まれ,退けられていく。猜疑のかたまりとなった晩年の今川義元,織田信長,豊臣秀吉となんらかわりない。生殺与奪の権をにぎったものが過去の復讐をする。欲がおのれを滅ぼすもととなるのは分かりきったことであるが,恨みもおのれを滅ぼすもととなるのであろうか。家康のために尽くしてきた大久保一門の者が,なぜ,怨まれ,家康におびえなければならないのか。まさにそんな問いが,忠教に三河物語を著させるきっかけとなったのではないか。忠世の嫡男忠隣は,上意を得ずに婚姻を結んだと言う,半分言いがかりのような罪を本多正信にきせられ,改易され,家臣は追放された。ただ,二代将軍秀忠は,忠隣が昔,秀吉から自分を救ってもらったことを感謝しており,家康と正信の死後,無実の申し開きをせよと薦めてくれるのであった。が,忠隣は,『もしも,ご赦免となれば,ご公儀の誤りを顕すことになる。わが身を立てるために,ご政道を歪めてはならないのです。このまま生を終えるとも,わが忠誠は天がてらしてくれるでしょう』と断ったという。
一方,平助は,家康の嫡男信康が信長の命により切腹するまで,懇切に接した事を家康は知っていた。大久保一門の中でただ一人平助のみを家康はゆるした。ゆるされた平助は筆をとる。やがて,愛読書の曾我物語から引かれた一節を冒頭に書く。『それ迷の前の是非は,是非共に非なり』と。これが三河物語の冒頭の文になった。迷う心で道義の有無を考えても,そこに浮かんだ正邪善悪はなんの意味も持たないと。
三河物語は,忠教が著すが,それは家康や徳川家のために書いたのではなく,天に命じられて書いた。天子や君主の悪にも目をつぶらず悪としるし,例えそれで殺されても天職を汚さないという,不動の信念をもった史官あるいは歴史家が日本のどこにいるのか。中国にいるように,日本の真の史官として我は記すのだと言う信念で書かれたのが三河物語だ。これを読んだ3台将軍家光は,忠隣の孫である忠職を赦免した。たった一本の筆が大久保家を救ったのである。
本書は中国古代史を専門としてきた著者の日本歴史小説である。中国古代では文献も少なく,著者の想像力が否応無しに発揮され,私は大好きだが,日本の歴史を書いた本作品は,主役となる忠教以外の大久保一門の人間についての説明など寄り道が多く,あの人は誰だったっけかなと,家系図を何度も見なくてはならず,読むスピードが上がらなかった。やはり宮城谷氏は中国歴史小説がよい。
全3巻