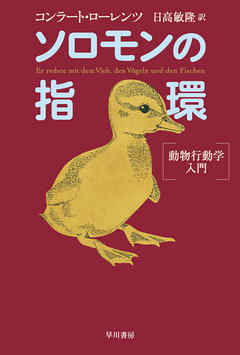感情タグBEST3
Posted by ブクログ
興味深い本でした。わたしが読んだ本は,1976年発行の単行本。
ずっと前に古本屋から購入して本棚にあったのだけれども,やっと読んでみた。
ローレンツのこの本は,大学で学んだ教育心理学の時に知った著作なので,出会いはずいぶんと古い(40年以上前)。「動物行動学」「比較行動学」という学問を世に知らしめた人といえるかな。有名なひな鳥の刷り込み理論のもとになった実験など,貴重な話を読むことができる。
訳者の日高敏隆氏は,「訳者あとがき」で「ローレンツのこったドイツ語には,かなり頭をかかえたこともある」と書かれているが,翻訳ものにしてはたいへん読みやすくて,ここに取り上げられている動物たちとローレンスとのかかわりが手に取るようにわかる。
いやー,わたしも動物を飼うのが好きなんだなあって思えたわ。アクアリウムもゴールデンハムスターもマヒワもインコも買ったことあるしね。さらに,ずっと犬も飼っているし。
Posted by ブクログ
1900年代前半に、ほぼ野生状態の動物と共に過ごしたすごい動物行動学を成立した人の自伝的なやつ。
実際にその人が体験したエピソードがてんこ盛りでとてもおもしろい。ガンの鳴き声を把握して会話できてるのがもはやおとぎ話かのよう。
そこらの沼から水をひとすくいしてアクアリウムを作るという話を読んで自分もやりたくなったが、今はそんな池や沼なさそうなんだよなぁ…
肉食動物は、うなり合うだけで実際に殺し合ったり、弱い相手を殺すまで戦うということはなく、勝敗が決まった段階でもう争いは止まるものだが、ハトなど、相手を傷つける力を持たず、逃げ出す力を持つ動物を檻の中など「逃げられない環境」に置くと、弱いほうがいじめ殺されるという、平和の使者ならぬことになる。
というエピソードがとてもおもしろかった。
Posted by ブクログ
副題にある通り、動物行動学入門としての名著中の名著。
学者らしく教養深く、かつ、自然動物への愛にあふれた文章に満ちている。
科学的な姿勢と、ユーモアあふれる詩情豊かな表現が両立する事を教えてくれる。
科学者のエッセイや文章というと、高度に知的である人の書くものでとっつき難いかもと思ってしまう。でも、この本はとても読みやすい。愛情深く自然と生き物に寄り添い、その自然のままの姿を愛するローレンツの文章は、特に泣かせにかかっているわけでもないのに、自然と涙が浮かんできた。ハイイロガンのマルティナの話は、とくに。
ソロモン王の指環が無くても、動物を理解する事は出来るのだ。
Posted by ブクログ
『はだかになり野生に帰って、野生のガンたちの群れの社会に溶け込み、ドナウの堤であるきまわったり泳いだりするのが、私の研究の本質的な部分を占めていた。なんと幸福な科学だろう』(P170)
著者のコンラート・ローレンツは、オーストリアの動物行動学者。
動物とともに生活し、刷り込みなどの研究を行い、ノーベル生理学・医学賞を受賞する。近代動物行動学を学問としての基礎を築いた。
題名である「ソロモンの指輪」は、旧約聖書のソロモン王が「魔法の指輪をもち、獣、魚、鳥たちと語った」と(※これは誤訳で、正しくは「大変な博識で、獣、魚、鳥たちについて語った」なのだが)いう記述からとっている。
読んでいる印象でのコンラート・ローレンツは、動物になると周りの目を気にしないし、挿絵も文章もユーモラスな印象。しかし写真のコンラート・ローレンツはまさにゲルマン紳士という外見なので、この紳士博士が鳥に警戒されないために毛むくじゃらの悪魔の着ぐるみで鳥小屋に入ったり、カモの母親代わりとして奇声を挙げながら屈み込み歩きをしていたり、という姿とのギャップにちょっと頭がついていけない(笑)
研究内容もさながら文章能力が非常に素晴らしく、読みながら唸ったり声を上げて笑ったり感動したり…と非常に楽しめた。
挿絵も面白く、カラスが餌を持ってきて食べさせてくれようとするんだけど、草と虫を唾液でグチャグチャにさせたものを口や耳に突っ込まれて「ゾワワワ〜〜」となっている姿などは思い浮かんで笑ってしまう。
最終章で、動物による攻撃から、「人間は今後相手を完膚無きまでに叩きのめす方向になるのか、力の差を認識試合紳士的な降参と許容が行われるのか、どちらだろう?」と問いかけている。
以下自己索引用に各章メモ
『動物たちへの憤懣』
幼い頃から動物に対して尋常ならざる愛情を持っていたコンラートが送るローレンツ家の日常生活。家中で動物たちが放し飼いになっているため、絨毯が糞だらけになったり、自分たちの子供を檻に入れて動物たちの爪から守ったりのでした。
『被害を与えぬものーアクアリウム』
動物を描いたいけれど、↑のように家中を汚されたくない、人間に被害を与えない飼育として、アクアリウムの紹介。きちんとした環境を整えれば、川の生態系と同じ物が作れる!
『水槽の中の二人の殺人犯』
そんなアクアリウムに入れてないけない殺人者(殺魚者だけど)、ゲンゴウロウの幼虫とトンボの幼虫(ヤゴ)について。その食事の仕方の違いとか。
『魚の血』
魚の闘い方、結婚や子育てのこと。魚も互いを個体として判別しているのか?の実験では、夫婦を取り替えてみたりと興味深い結果が出ている。このあたりの記述は事情に面白くて唸りながら読んでしまう。
『永遠に変わらぬ友』
雛から育てたコクマルガラスについて。鳥が人間を番相手として求愛したり、餌を運んできたり。鳥の集団生活における鳴き声の違い。鳥社会の順位の付け方など。面白いエピソードとして、番だったカラス夫婦のオスにちょっかいを出してくるメスが出てきてしばらくは三角関係を繰り広げ、最終的には夫と愛人が駆け落ち?してしまったんだとか。
もうこの観察記と文章力には感嘆の声をあげながら読むしかない。
『ソロモンの指輪』
動物と人間とのコミュニケーショについて。犬や馬が、相手(人間でも動物でも)のちょっとした仕草や雰囲気で相手の意図を読み取ることができる様子を驚きを持って観察している。さらに言葉を”話す”鳥たちのびっくりするような学習面。怪我をしたオウムが自分が怪我をした理由を人間の言葉で説明した(おそらく助けたらてたときに人間が言った言葉を一度で覚えて発音した)という事例など。動物行動学者は鳥の言語(鳴き声)を理解しているが、カモに向かってガン語を発してしまった!などという、動物学者にはわかるらしい大笑いエピソードとか。
『ガンの子マルティナ』
生まれたときにコンラート・ローレンツを見たため、母親と認識したガンのマルティナとの交流と観察の日々。ただただコンラート・ローレンツを慕うマルティナの姿は感動的。
『なにを飼ったらいいか』
ペットには何を飼ったら良いのか?というエッセイ。同じ鳥、同じ小動物であっても種類に違ってぜんぜん違うからね!ということを書いている。
『動物たちをあわれむ』
動物園や家庭で飼育の動物のことなど。でも家から逃げた動物は、自由になりたいわけではなくて本当に家がわからないんだよ、という事例もある。
『忠誠は空想ならず』
ローレンツ夫妻はお互いの飼い犬の事で喧嘩になった。だってコンラートの飼い犬はオオカミ系のシェパードで、妻マルガリータさんの飼い犬はジャッカル系のチャウチャウで、性質がぜんぜん違うんだ。…というわけで犬のことについて色々。なお、夫婦喧嘩は、コンラートの犬の息子が、マルガリータの犬の柵を食い破って結婚したことにより一応解決し、さらなる研究に前向きなコンラート博士でした。
『動物たちを笑う』
動物を笑うときは、動物に人間を見るからだよね、というエピソード。
『モラルと武器』
非捕食者であるウサギやハトは、喧嘩になったときには相手の毛を毟り皮を剥ぎ弱った相手をさらに押さえつけ完膚なきまでに叩き潰す。捕食者であるカラスやオオカミは決定的な殺し合いになる前に力の差を認識試合紳士的な降参と許容が行われる。
さて、人間は今後どのような関係を作ってゆくのだろう?ウサギ型だろうか、オオカミ型だろうか。
Posted by ブクログ
高校生の時に、生物の先生に薦められて読みました。
動物の行動学とか全く興味なかったし、そんな内容の本とは知らずに手に取りましたが、とても面白い内容でした。
研究者とはいかなるものか、観察とはどうするものかが分かります。
お勉強の本ではなく、タイトルの通り、動物と対話するため本です。
作者の動物を観察するときのワクワク感や
家のなかで動物を放し飼いにするために子どもを檻に入れたりなどちょっぴりクレイジーなところが楽しいです。
昨今、ろうそくの科学が有名になりましたが、
個人的には生物ばんのろうそくの科学的な位置にある本だと思います。
Posted by ブクログ
動物行動学を創始した学者の、動物に対する愛情にあふれたエッセイ的な行動学入門書。このテのもので一番有名な一冊にして、この分野に興味がある者に必読の書である。
Posted by ブクログ
すごく面白かった、特に魚の話が最高。
ハトは衝撃的だった。
人間だけがある種の感情や理性を持っているなんて考えは、おこがましいんだなと再認識させられた。
人間だって結局動物でしかないんだあ。
Posted by ブクログ
【動物と過ごす喜びと犠牲】
動物と暮らすという覚悟とはこういうことだ! ということがひしひし伝わるエッセイ。
動物学者の著者の目を通した動物行動の面白さは言うまでもなく、動物を観察するための狂気じみてるような努力も読みごたえあり。思わぬものに夜中叩き起こされる羽目になったり、ご近所からヤバい目で見られたりする悲喜こもごも。
何度読んでも電車を乗り過ごすくらい、内容は折り紙つき。
Posted by ブクログ
動物行動学という分野の学問を拓き、ノーベル賞を受賞した研究者による動物の本。オーストリア在住で1930-1940年代に活躍したらしい。
著者は魚類や鳥類、哺乳類まであらゆる動物を飼い、様々な実験などを通して動物たちの行動や習慣を観察した。その観察記録やオリジナルな考察は面白く興味深かった。
最後の章は印象的だ。動物の多くは闘いの際に、自分が負けそうになると首を差し出してやられるのを防ぐそうだ。もともとそういう社会性がない動物は、そもそも種を殺すことができる機能を持ち合わせていないとあった。人間だけが、防戦の能力を超えた殺傷武器を持っており、人類の存亡は自分たちしだいであるようだ。
動物たちとのエピソードが微笑ましい。著者の動物たちへの深い愛が感じられる一冊。
Posted by ブクログ
コンラート・ローレンツ(1903~1989年)は、オーストリアの動物行動学者。近代動物行動学を確立した人物のひとりといわれ、1973年にノーベル生理学医学賞も受賞している。
本書は、研究エッセイをまとめたローレンツ博士の代表作のひとつで、1987年に邦訳が出版されている。
題名は、偽典(旧約聖書の正典・外典に含まれないユダヤ教・キリスト教の文書)のひとつとされる『ソロモン書』に記された、あらゆる動植物の声までも聞く力を与えると言われる「ソロモンの指輪」の伝説を踏まえて、その指輪がなくても多少は動物の気持ちがわかるものだという意味を込めて付けられたのだという。
本書には、ハイイロガン、コクマルガラス、ワタリガラスをはじめ、数々の動物や昆虫が登場するが、いずれのエッセイにも博士の動物に対する愛情が溢れており、読みながら何度も微笑んでしまう。
特に、ハイイロガンの子マルティナが、生まれた日から博士を(刷り込みにより)母親と思い、「・・・あわれなヒナは声もかれんばかりに泣きながら、けつまずいたりころんだりして私のあとを追って走ってくる。だがそのすばやさはおどろくほどであり、その決意たるやみまごうべくもない。彼女は私に、白いガチョウではなくてこの私に、自分の母親であってくれと懇願しているのだ。それは石さえ動かしたであろうほど感動的な光景であった。・・・」という有名なエッセイは、何度も読み返してしまう感動的なものである。
ユーモラスな挿絵も素晴らしい。
動物(の行動)への興味が格段に高まること間違いなしの、楽しい一冊である。
(2010年6月了)
Posted by ブクログ
非常にユーモアのある、動物に関する本だ。本書は、動物行動学をつくりあげてノーベル賞を受賞したコンラート・ローレンツ氏によって書かれた。
もっとも有名でおもしろい例は、鳥類の刷りこみだろう。通常、人間を含むほとんどの哺乳類では、性的な愛の対象は遺伝に刻まれており、しかるべき時になれば適切な対象に気づく。しかし、鳥ではまったく違っている。ヒナのときから1羽だけで育てられ、同じ種類の仲間をまったくみたことのない鳥は、自分がどの種類に属しているかをまったく知らない。すなわち、彼らの社会的衝動も性的な愛情も、彼らのごく幼い、刷りこみ可能な時期をともに過ごした動物に向けられてしまう。ニワトリとともに育てたメスのガチョウは、オスのニワトリに夢中で、オスのガチョウの求愛など見向きもしない。ある動物園で巨大なゾウガメの部屋で育てたれたクジャクは、ゾウガメにばかり求愛し、メスクジャクの魅力には盲目になってしまった。著者の家庭で飼っていたカラスは、世話をしていたメイドに恋をした。
動物の世界には私たちの知らない、おもしろい話がまだまだたくさんあることを教えてくれる良書だ。知的な中高生にぜひ勧めたい。
Posted by ブクログ
著者と翻訳者、ふたりの動物学者による動物への愛に溢れたユーモラスな二重奏。
動物行動学の第一人者で、動物の"刷り込み"の研究で知られるコンラート・ローレンツの1949年刊行の名作です。
動物との微笑ましい交流と、動物の行動に見られる不思議さが描かれます。堅苦しさのない軽やかな文体で、エッセイのように楽しめます。翻訳の日高敏隆先生もまた温和な動物行動学者で平易な文体の方なので、この読みやすさは著者と翻訳者による、ユーモラスな人柄の二重奏によるものかもしれません。
鳥や魚、犬たちに囲まれて暮らす動物行動学者である著者は、動物にメスを入れたり薬を飲ませたりという実験をせず、その行動をつぶさに観察しますが、その暮らしは驚きとトラブルと感動にあふれています。
刷り込みによって生まれたてのハイイロガンのヒナの母親になってしまい、ヒナが独り立ちするまで片時も離れられずになってしまったり、幼き我が子に動物による危険がないように、"我が子のほうを"檻に入れたり、町中でオウムを呼ぶためにオウムの鳴き声を出して周りに白眼視されたり等、、、楽しみながら動物の不思議さを知ることができます。
動物たちは、人間が思っている以上にこちらをつぶさに観察していると作中で書かれています。著者のように動物と会話できなくても、表情や挙動からこちらの気持ちや次の行動を読んでいるのです。これには私も確かに思い当たることがあります。私の実家の犬は「散歩にいこう」と口にせずとも、リードが置いてある棚の方向へ歩き始めた時点で散歩に行ける喜びで飛び上がります。さらに驚くことに、いつもの散歩ではない特別なお出かけ(キャンプ等)の時は、家族はいつもどおりソファから立ち上がっただけにも関わらず、彼は普段の何倍もハイテンションに鳴き声をあげ、半狂乱になって喜びを放出させます。
作品全体はユーモラスなエピソードに彩られつつも、最後の章「モラルと武器」で著者は読者にシリアスなメッセージを投げかけます。動物の争いについて触れているのです。オオカミ同士やイヌ同士など同種での争いの場合、旗色が悪くなってきた弱者は強者にあえて弱点をさらすような服従の態度をとります。その服従のポーズを取られた強者は、それがルールであるかのごとくピタリと攻撃をやめ、追い打ちをかけることができなくなってしまうので、敗者を殺すことなく戦いは終結を迎えるのです。まるでレフェリーが割って入ったボクシングのようです。しかしこれがクジャクと七面鳥といった異種の争いでは、服従のポーズが異なるために敗者が服従しても攻撃が終わらず、攻撃を受ければ受けるほど服従の姿勢を固めてしまい、果ては悲劇を迎えるという最悪な悪循環も紹介されています。
人間においても礼儀作法の中に、弱点をさらす服従の名残があります(お辞儀や脱帽など)。敗者・弱者が強者を抑制することは以前読んだ類人猿の本でも出てきました。地位の低いチンパンジーが、群れのボスにエサ場を譲ってほしいと近づくと、ボスは渋々場所を明け渡すといった習慣です。高度な知能と社会性を持った動物は、弱者に優しくあることが備わっているのでしょう。無防備に弱点をさらして「さあ殺せ」となると、殺しづらいのは人間も同じかもしれません。私は天安門事件の有名なシーン、戦車の群れと、その眼前に身一つで立ちはだかった一人の男性のにらみ合いが思い浮かびました。
この章の最後、"自分の体とは無関係に発達した武器をもつ動物が、たった一ついる。(中略)この動物は人間である"(p278)から始まる文章が、70年の時を超え、ロシア対ウクライナの戦争まっただ中である現在、いかにシリアスに胸に突き刺さることか。
あとこれもこの本を楽しむ上で大事な要素のひとつですが、著者(とアニー・アイゼンメンガー)の手による挿絵がかわいいんです!クラシックな名作絵本のような、過剰にデフォルメされていないのにかわいく、手書きの線の味わいがある数々のイラストたちも、読者を楽しませる立派な立役者です。
あとがきで初版刊行時の間違いや出版後の後悔などについて書いてあって、そういうとこも学者センセイ然としてなくて人間くさくていいです。「コンラートのおじさん、やっちゃった」って感じがします 笑。また現在では犬の祖先はオオカミと言われていますが、この本のなかで著者はオオカミ祖先とジャッカル祖先の二派に分かれる、と説いています。70年近く昔のものなので仕方のないことでしょうね。
Posted by ブクログ
読書会、面白いです。
読書会に参加したことが無い、という方が大半だと思うので、すぐ共感してもらえるとは思わないのですが、少なくとも私にとっては10年近く続けている習慣になっています。
テーマの本を1冊決める。参加者みんなでそれを読む。決めた日にカフェに集まる、そして意見を言い合う。
これだけ。発表者がいるわけではなく、資料を用意する必要もありません。(ノートを取ってくる時はありますけれど)本を読むという行為が、「5月8日にいっしょに意見をシェアする」と約束するだけで、いかに充実した行為になるか。お近くで催しがあれば、ぜひ参加してほしい企画です。
そんな読書会で、昨日とても良い本に出会いました。コンラート・ローレンツ著、ソロモンの指環です。
タイトルだけみると、一見ファンタジー小説か?と見紛ってします。しかし、れっきとした動物行動学の本。ローレンツ氏はこの研究でノーベル賞生理学・医学賞を受賞しています。
卵から生まれたばかりの雛は母鳥に限らず、どんな生き物でも母親と認識する。有名なプリンティング(刷り込み)という生態を発見した方、といえばご存知かもしれません。
この本を読んでいく中で面白い一節がありました。かれが犬、猫、カラスまで幅広い動物を観察し、本を著すと、ある批判を受けた、というのです。
曰く、「動物を擬人化しすぎている。嫉妬、怒り、喜び、楽しみ?彼の書き方は科学者にあるまじきものだ」というものです。それに対するローレンツ氏の反論は次の通りでした。
私は動物を擬人化しているのではない、逆だ。人間が動物の模倣をしているのであり、もっと正しくいうのであれば、人間も動物の一種に過ぎないということだ(本文の一節を意訳)
人間も動物の一種に過ぎない。このくだりを読んだ時はとても腑に落ちたものです。
なぜ、人間は嫉妬深いのか、怒りに身を任せるのか、そして楽しむのか。この質問は正しくありません。
人間は、ではなく、動物(この研究の中では鳥類、哺乳類が中心ですけれど)はこういった行動を、本能や経験から行う、ということ。人間に限った話しではないということです。
これを事実とした時に、残念に思うこともできるそうですが、私は少し安堵します。
そうか、浮気は不義だと言われているけれど、コクマルガラスの夫婦の間にも同じようなことがあるのか。
また、ヒエラルキーといった上下関係や、それに伴う嫉妬は、人の悪徳だと言われているけれど、ハイイロガンのグループでも垣間見れるのか。
これは面白い観察記録でした。
全く別のカテゴリーの本ですが、第二次世界大戦後に「堕落論」を書いた坂口安吾という作家がいます。
彼は特攻隊に向かう男たち、貞淑な妻達に違和感を覚え、文章に残しています。それは人間の本性ではない、戦中に作られた為政者にとって都合のいい価値観だと。
コクマルガラスの浮気グセと、戦中戦後の日本人の価値観の推移を比べると、ドイツ人研究者の自然洞察が、日本人作家の人間洞察につながったような気がしてなりません。
ソロモンの指環は、動物研究の名を借りた人間研究のテキストとして楽しめる。昨日の読書会での発見です。
Posted by ブクログ
動物に関する深い愛情と畏敬の心、そして探究心が紡ぐ動物論文。髄分古い著作だが、今見ても新しさを感じる。
今から動物を飼おうとする人、今も飼っている人はもちろん読むべき本だと考えるが、動物に興味のない人でもとても楽しく読めます。
この本を読みながら無性に動物を飼いたくなって来たところタイミングよく「8章何を飼ったらいいか」の章に至り嬉しくなりました。著者かおすすめのアクアリウムかゴールデンハムスターを検討してみたい。各章とも興味深く、何れも作者が動物と過ごす中での実験と経験に基づいており、楽しげではあるが相当に動物への愛情がなければこの苦労は背負えないな、とも感じる。印象深いのはコクマルガラスを飼う中でのエピソードで、確かにカラスとはいえ賢い動物に懐いてくれるのは至上の喜びだと共感しました。
作者も描いたというイラストもわかりやすく楽しく読める一躍を担っています。
Posted by ブクログ
犬の賢さすごい
動物がなつくことの微笑ましさと感動
どういう生き物を飼育したらいいか習性を元に書かれていて参考になる
作者のあくなき探究心
Posted by ブクログ
品が良くて楽しく読める動物エッセイ。ノーベル賞までもらった学者さんなのだが、鳥だネズミだアクアリウムだとそれはもう種々雑多な動物たちと暮らしており、ほとんどムツゴロウっぽい。昔のおおらかさがいい感じ。
最近の動物に関する研究でローレンツの系列に繋がりうるのはここらへんかな、と思い、本棚にあったテンプル・グランディンの「動物感覚」を読み始めた。
Posted by ブクログ
ここまで動物と語り合える、信頼しあえるって素晴らしい。
動物を飼うっていうより動物とともに暮らす。
動物がなぜ人の心や動きがわかるか、それは人間が知らず知らずに教えているから。
人は動物ほどには人のことがわからない気がしてきた。
Posted by ブクログ
研究者というのは、こんなにも観察するものなんだなと。
さまざまな動物と一緒にくらし、自分の快適な生活と引き換えにしてまで観察、研究。それが研究者にとっては喜びなのでしょうかね。ともかく、動物に対する愛情がとても感じられた。私には自分の生活を脅かされてまでの愛情はないから、こうやって本で読ませてもらってありがたいなと思った。
楽して動物の事を知れるので笑
Posted by ブクログ
動物行動学の始祖。最新の学説的には否定されている部分もあるのかもしれないが、ハイイロガンと心を通わせひたすら観察する姿には愛とロマンがある。アクアリウムを作ってみたくなる。
Posted by ブクログ
その後の研究等を吟味しないといけないが、当時の動物行動学の最先端を行く名著。間違いなくソロモン王より動物たちとの会話を実現した著者の神髄が語られる。自然を実感するのに必要なノウハウを赤裸々にした本作は永遠に読み、語られるべき良書。人とヒトとの間に交わされるべき会話・対話の根幹も詳らかにしているようである。
Posted by ブクログ
短かに接する動物たちにも知らなかった楽しい習性がたくさんある事をユーモア溢れる事例から教わることができた。近所にいるカラスやペットの犬、動物園ののんびりしたライオンなどこれまでより見る事が楽しみになった。
Posted by ブクログ
動物の生態を知りたくなったので読んだ。
動物行動学入門とあるがほとんどエッセイのような感じでさくさく楽しんで読める。
コンラート・ローレンツが多種多様な動物たちとともに暮らす中から見える動物たちの生態や行動、その意味するところとは。動物への愛に溢れる1冊。
普通に哺乳類がメインで出てくるものだと思ってたら、ハイイロガン、アクアリウム、コクマルガラス…といい意味で期待を裏切られた。
特にトウギョの話が面白く、ついYouTubeで動画を漁ってしまった。
また、8章の「なにを飼ったらいいか!」はペットに適した動物を紹介してくれる。現在飼われているような金魚、モルモット、インコなどをつまらないやつと言い切ってしまうところが面白い笑
ただこの本を読んだら安易にペット飼おう!とはなかなか思えないかも。動物には動物の本能と行動があり、共に生活するには人間が合わせなくてはいけない。
一番最後の「いつかきっと相手の陣営を瞬時にして壊滅しうるような日がやってくる。全人類が二つの陣営に分かたれてしまう日も、やってくるかもしれない。そのときわれわれはどう行動するだろうか。ウサギのようにか、それともオオカミのようにか?人類の運命はこの問いへの答えによって決定される」という言葉が忘れられない。
人間は相手が降参の態度を見せた時、攻撃しないでいられるのだろうか。
Posted by ブクログ
ヒヨコが生まれて初めて見た動くものを親だと思う「刷り込み」の概念を確立したという学者の著書。様々な動物(ペットではない)と一緒に暮らし、その実際の行動をつぶさに観察している。
様々な記録が盛り沢山だが、動物の種による行動について特に細かい。中でも凶悪獰猛なイメージである肉食獣・オオカミに騎士道精神が備わっており、か弱くて大人しいイメージのウサギやシカは相手が両手を挙げてもこれ幸いに弱点を攻撃しまくり死ぬまで戦う、というエピソードが面白かった。人間のイメージというのは実に勝手なものである。
あとイラストがかわいかった。線が細いがしっかりしててトーンの貼っていないリアルなイラストである。
Posted by ブクログ
ノーベル賞受賞ローレンツ氏による
動物愛に溢れた動物行動学入門書
と言っても全く堅苦しく無いご自身の動物達との経験談…いえ研究内容だ
「居間に取り付けた檻の中で動物を飼っておく事は、知能の発達した高等動物の生活を正しくは知れない、全く自由な状態で飼うことを身上とする」
という主義を貫いてさまざまな動物達と暮らすのだが、それに伴う家族の犠牲やご苦労、ご近所への損害はは計り知れない
人ごとだからこちらは笑って読んでいられるが…
例)
・家の中で放し飼いにしたネズミ
そいつが家中勝手に走り回り、敷物の切れ端から巣を作る
・庭に干した洗濯物のボタンを片っ端から食いちぎってまわるオウム
・大型で相当に危険な動物たちを飼っていた頃は、庭に大きな檻を作ってその中へ入れた
ーーー動物ではない、私たちの娘を
・子ガモの代理ママとして、庭を低くしゃがんだまま「ゲッゲッ」とわめきながら2時間の散歩
草むらに囲まれた場所で肝心な子ガモの姿は外を通る観光客からは見えない(笑)
■興味深かった内容をピックアップ
・コクマルガラス(オス!)に惚れられた著者(念のためだが男性!)
彼は自分が選り抜きの珍味だと思っている餌をしつこく私に食べさせようとする
彼は人間の口がものを飲み込むところであることを理解している
・飼い犬シェパードのティート
机の下で寝そべっている時でも、権威ぶった年配の紳士が私と討論中に「君はまだ若い」と言う態度をとったとき、ティートは必ずそういう人の尻に軽く、しかし断固として噛み付く
その人物の顔や態度が見えるはずがないのに…
・ハイロガンの雛
産まれてすぐ著者とハイロガン語であいさつをしたときから、親子の関係が始まる…
「哀れな雛は声も枯れんばかりに泣きながら、けつまずいたり転んだりして私の後を追って走ってくる」
昼間は2分ごとに、夜は1時間ごとに「まだそこにいる?」と言う問いかけを発する
・素晴らしく美しいメスのカタジロワシ
苦労せずして舞い上がれるおあつらえ向きの上昇気流が庭の上空にあるときだけ飛ぶ!
降りてこようとすると帰り道がわからなくなる
ご近所から「どこそこの屋根の上にお宅のワシが止まっていますよ」と電話がかかってくるので迎えに行くが、いつもそこまで歩いて行かなくてはならない
なぜならそのワシは自転車をやったら怖がるのだ
・ジャッカル系犬とオオカミ系犬の違い
『ジャッカル系犬』
シェパード
・従順
・誰とでも仲良くでき、事実誰がリードを引っ張っても喜んでついていってしまう
『オオカミ系犬」
エスキモー犬、チャウチャウ犬
・一度ある人に忠誠を誓ったら、彼はもはや永久にその人の犬である
知らない人はしっぽすら振ってもらえない
・並外れた忠実さと愛着の深さにもかかわらず、決して従順ではない
新旧石器時代ごろからの人間と犬との古い結びつきが、両者の自発意思に基づいて何の強制もなく契約されたと事実が心和む(通常の家畜は奴隷に等しいがイヌだけは友である)
〜犬でも他の動物でも、人に従順かどうか…
でつい判断してしまう
それって失礼しちゃうよなぁ
少しズレるが、飼ったことのある紀州犬とヨークシャテリアを思い出す
紀州犬は本当に手こずった
父以外の家族を自分より下に見ていた
プライドが高く、子供がとても嫌い
人相の悪い人や不審者に遠慮なく吠える
脱走はもちろん、散歩中に首輪から抜けて自由に走り回り、気が済むまで戻らない
それに引き換え、ヨークシャテリアはもう可愛くて仕方なかった
自分が居ないとダメなのね君は…
完全に小型犬の典型
何かあると膝の上に飛び乗り、上目遣い
散歩中に他の犬を撫でるとヤキモチを焼きキャンキャンアピール
どうしてもヨークシャが可愛くなってしまった
でもこの比較は間違っているよなぁ
ある意味紀州犬は誇り高くて賢く、とても美しかった
ふとそんなことを思い出した
本当はもっと重要で興味深い動物の発見や研究内容が多々あるのだが、どうしても面白ネタが印象に残ってしまった
動物と人間の心が通う奇跡的で心に暖まるストーリーがユーモア交え展開し、とても読みやすい
生物や生態系って本当に不思議で神秘的であると改めて認識できる良書である
Posted by ブクログ
僕は割と動物が好きな方で、昔は犬、文鳥、シマリスなどを飼っていたし、僕なりに彼ら彼女らの生態、というか表情みたいなものには慰められたり、幸せな気持ちになったりもしてきた。
特に犬は笑うし、怒るし、目を伏せてしょげ返る。
あの時、母親にしかられてしょげ返った子犬が僕の所に助けを求めに来た姿は今でも覚えている。
さて、ローレンツ先生のこの本。
面白いか、と問われると「思った程では」と答えるし、つまらなかったかと問われると「いやいや面白かったですよ」と答える。
なんとも優柔不断な感想で申し訳ないのだけれど、これが正直なところ。
ただ、ローレンツ先生のように、動物に囲まれて暮らせたらどんなに楽しいか、という気持ちはフツフツと沸いてきた。
あとは、ローレンツ先生が推奨しているアクアリウムの作り方に則って、自分でも作ってみたいな、という気持ちにもさせられた。