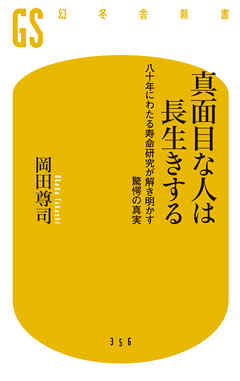感情タグBEST3
Posted by ブクログ
小手先の健康法で寿命を延ばせたとしても、たかが知れているという話。カギは、人や世界、人生との向き合い方にある。筆者がクライエントと向き合う中で見いだしたことでもあるので、説得力がある。自分自身が長寿になれなさそうなのは、ちょっと悔しいけれど。
Posted by ブクログ
長期のコホート研究による結果を紹介する。健康の指標として、寿命や死亡率は最も客観的なものと言えるだろう。
アメリカの心理学者ルイス・ターマンは、子どもたちの能力が何によって決まるのかに興味を持ち、1920年から10歳前後の知的能力の高い子ども1500人を選んで、成育歴や養育、生活環境、健康状態などのデータを集めた。ターマンの死から30年余り後、ハワード・フリードマンがターマンのデータを用いて研究を続けた。
性格の中で、長寿と最も強い結びつきを示したのは、まじめで、怠りなく、自己コントロールができ、信頼に足る、慎重な努力家の傾向だった。楽をした人よりも、勤勉に向上心を持って努力した人の方が長生きした。明るさや陽気さは、むしろマイナスの相関を示し、社交性は中立的だった。
調査した子どもたちは、非社交的、恥ずかしがり屋で人見知りが強く、集団行動には積極的ではない科学者タイプと、それに対照的なビジネスマンタイプに大きく分けられ、科学者タイプの方が長生きした。
運動については、ジョギングする人はしない人よりも寿命が6年長い。マラソンクラブに属する人は、一般市民に比べて20年後の死亡率が半分にとどまる。
食事については、炭水化物の割合が少なく、バランスのいい食事の方が長生きする傾向がみられる。カロリー制限については、調査によって結果が異なるが、多くの研究をあわせると、中年期には有効で、若年期や高齢者には危険と考えられる。抗酸化作用のあるサプリメントによって寿命が延びることを証明した研究はない。げっ歯類で寿命への効果が報告されているのは、お茶に含まれるカテキン、ウコンに含まれるクルクミンなど、ごくわずか。アルコールは、ビタミンAや肝臓に蓄えられたコエンザイムQ10といった抗酸化物質を大幅に減らし、老化を促進してしまう。
独身者のうち、長生きしたアンデルセン、ショーペンハウアー、カント、ニュートンは、社交よりも孤独な思索や読書を好み、規則正しい生活を送り、勤勉で、慎重で、節制した生活を送ったことで共通している。
他人の些細な点にも敵意をもって反応する人は、早く健康を害して早死にする運命にあった。他人に対して批判的にならず、言い争いを避け、自分のやり方や考えにこだわりすぎない人は、長生きした。
うつ病を予測する因子として認められたのは、怒りの感情にとらわれやすいこと、肯定的な感情が乏しいこと、伝統や慣習を軽視すること、文化的関心が乏しいことの4つ。
グラハム・ベルは、音声学者で、聴覚・言語障害者に発音を教える教師で、勤勉な人物だった。障害者を救いたいという一念から、空気の振動を電気の振動に変換する装置の研究を始め、副産物として電話の原理を思いついた。
本書のネットでの評価はあまり高くないのが不思議に思う。テーマが性格なので、自分にはどうしようもないものと思われることも理由のひとつだろう。タイトルや内容が常識に外れないことが刺激を与えないのかもしれない。そうだとすれば、本書の内容は至極まっとうなものであると思うのだが。
Posted by ブクログ
他の著書と同様愛着に着目して述べられている点に関しては一貫性があって良かった。
ただどのような話題も"真面目に生きてる人の方が得をする"という結論に辿り着くよう話の流れを意図的に生み出してる感は否めない。
個人的には全体を通してあまり腑に落ちなかった
Posted by ブクログ
1500人規模のサンプルを対象に、80年もの長期間のデータ収集による研究結果を基にした論文を頼りに、長寿の秘訣を解き明かす。論文紹介本であり、例えば、最近「独身男性は早死にする」というような発言をよく聞くが、その論調のルーツである。
酒タバコの寿命への影響、運動の効果、転職、離婚はどうか。だけではなく、性格が寿命にどう影響するか。結論は、本のタイトルにもなっている。
真面目である事は、医師の助言に対しても誠実であり、規則正しく、健康的にあろうとするだろうから、真面目イコール不真面目より長生き。これは自明であり、意外性は無い。暴走車よりも、真面目な運転手の方が事故死する確率は低いというだけの事だ。本著は、岡田尊司流の味付けで、チャップリンはどうだったとか、ショーペンハウアーは、とか精神病理を引きながら、説明的に当て嵌めていく。
学びがあるというより、やっぱりそうか、という感じ。どうやら長寿や健康については、我々は、感覚的に理解しているのかも知れない。