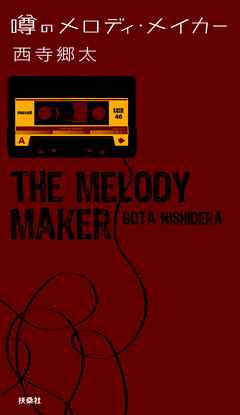感情タグBEST3
Posted by ブクログ
音楽フリークのみならず、80年代カルチャーの洗礼を受けた人たちすべてに読んで欲しい佳作。文句のない5ツ星。
まさかあのヒットチューンに日本のゴーストライターが存在していたとは。その真偽を追う旅の長さと興味深さに何度も感嘆してしまいそうになった。
ポップすぎるゆえ少し軽んじていた印象のあった「ワム!」だけれど(とはいえずっとiPodに入り続けていたが)、あの短い活動期間でこんなにも様々なエピソードと奇跡が生まれていたとはまったく思いもよらなかった。
マイケル・ジャクソン同様、ジョージ・マイケルはもっと評価されていいとすら思った。アンドリュー・リッジリーもしかりである。雰囲気を作る相棒が如何に大切かということだ。
ちょっと違うかもしれないが、この関係性は現在の電気グルーヴにも通じるものがあるような気がしたのは余談である。
Posted by ブクログ
メルマ旬報の連載で毎号読んでいたものが一冊に綴られている。連載から郷太さんが削りさらに増やしたこの完全版というべきこの小説はノンフィクション的なものをあえて小説として描くことで多重性を持ちえている。この多重性≒多層であることとは郷太さん自身が主人公でありワムのゴーストライターをしていた日本人がいるという話からその人物に迫っていくノンフィクションとメタフィクションが混ざり合うよう、そこにあるのは真実なのか虚実なのか。
小説として書く事でしか書けないものがあるからこの小説として書かれているのだと読めばわかる。
ワムのゴーストライターをしていた日本人がいるという切り口から郷太さんが取材をして小説という物語に落とし込む事でその時代や人物を知らない人にも通じてわかるものにしている。物語とは現実をよりよく理解するためのモデルであるのだ。
80年代という時代や音楽業界で働いていた人たち、そこにいた人たちはもう定年退職をされていたり現場からは第一線から消えている。歴史を再検証するようにあの時何があったのか誰が何をしていたのかを含めて文章にして残すという郷太さんの熱意が感じられる。と同時にそれがいまできるのは自分しかいないという使命感も持っていたはずだ。でなければ、このスタイル(小説)にはなっていなかっただろう。
郷太さんはこのゴーストライター説を巡る関係者の方々に取材をして当時の資料も読みあさり徹底して調べ上げたはずだ。そして知れば知るほどに書けないことが出てきているだろう、調べれば調べるほどに表には出せない事情を郷太さんは知ってしまったはずだ。書けないことが。知っているが書かない事で先に進めたのかもしれない。それは徹底的に調べたという行為の先にあるものだろうし、だからこそ最後のラストシーンに繋がったのではないかと僕は想像する。海に投げられたのはそんな語る事ができないなにかなのかもしれない。
小説というフィクションの中に様々なノンフィクションを取り込みながら完成した作品だが、ここに至るまでの流れは郷太さん自身が好きだからこそ好きだと言って動き続けた結果、自身の音楽活動を通じてそこから派生したものが結果繋がっているのはまぎれもない事実だ。
以前、郷太さんにツイートしてもらった
「あるで!しつこくまっすぐ進んだら、ある時から自分が吸盤になったみたいに好きなもんばっかりひっついてくるでー!」という言葉、先日ツイートしてもらった
「あるで。まじであるでーーー!三十代前半で一個ずつ穴あけたビンゴ。四十前後でなんか急に色々並んでビンゴ連呼する感じ。ちょっと若い君ら、あるでーーー!!」
ということの具現化のひとつがこの『噂のメロディ・メイカー』である。
ワムが日本でライブを再びする日はいつか来るのだろうと来てほしいと最後まで読むと思う。その時郷太さんはまたビンゴの穴を一つ推してビンゴを連呼しているはずだ。
Posted by ブクログ
ワムにゴーストライターがいたというある意味トンデモ話ではあるものの、真相に近付いていく過程は手に汗握るような展開だった。そして相変わらず自分と同世代の作者のポップスに対する言葉が悉く刺さる。