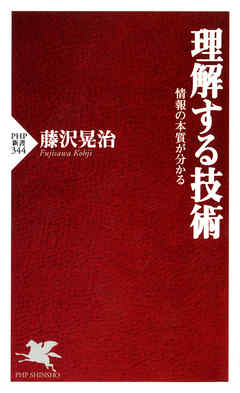感情タグBEST3
Posted by ブクログ
「情報は整理する」
「大きな枠組みをとらえる」
「説明してみる」
「図で考える」
「具体例を理解する」
「ルールを発見する」
「根拠と結論をセットにする」
「どうして?本当なの?を大事にする」
など、考えるための基本がコンパクトに掲載されていてとても良い。
Posted by ブクログ
本書を紹介してくれた仲間に感謝します。
タイトルのとおり、理解されるコミュニケーション技術および効率的に理解を進めるとき何を意識すべきかという点が、それこそ分かりやすくw 学べます。
そもそも「理解した」って言えるのは、どういう状態?から始まって、どうやって誤解は生まれるのかといった根本的なテーマも、深い納得がw得られます。
特に感心したのは「表づくりのメリット」の章にある、マニュフェスト比較の事例。どれも素晴らしいことを言っているように聞こえてしまうものですが、表にすることで何も政策を述べていない部分がよく見えてくるというもの。実は、書かれていない内容のほうに重要なポイントが隠れているとは、感覚的に持っていても、なかなか説明はお目にかかりません。
分かりにくい話をする相手が、いつまでたっても分かりにくいのは、あなたの分かる、を相手が理解してないからなのかも知れません・・・ね。
Posted by ブクログ
学生時代に参考書を何度読んでも頭に入らなかったり、新入社員時代に資料を幾度読んでも頭に入らなかった謎が解けました。①アウトプットを意識する②全体を俯瞰して自分の仮説を作る③頭は文でなく図表で保存されるので図表として覚える④根拠と結論をセットにして記憶する。などなどが衝撃レベルで頭を突き抜けました。受験で苦しんでいた頃に自分に是非読ませたい本。そして、知り合いにも布教したい本です。
Posted by ブクログ
人間の理解する仕組みと、どうすれば理解しにくい書籍や文書の内容を効率よく吸収できるかを著者の「わかりやすい文章」で解説した本。
専門書で独学しようとして、そのあまりのわかりにくさに呆然とし、挫折した人に読んでほしい一冊です。
Posted by ブクログ
読みやすい、おもしろい、ためになる、といった本。情報社会とも言われる今日において、情報の受信・発信は重要であるが、その中でそれをどのように行えば、より要領がよいかについて書かれている。具体的には「情報を手っ取り早くつかむテクニック」や「図表をつくりながら読むテクニック」など。文体も非常に分かりやすい。資格を取りたい人や社会に出ている人、これから出る人にオススメです。
Posted by ブクログ
情報をどのように整理しまとめればよいか、脳の情報処理の仕組みを踏まえて説明している。また、 情報の信憑性を確かめる方法が具体的に項目立てて書かれてあり、なんとなくそう思っていたことが明確に書かれている。忙しい生活の中で如何に効率よく情報を理解していくかが分かりやすく整理されて書かれている
Posted by ブクログ
情報の受信に絞ったノウハウの本。仮説を立てて、それに沿って聞くことで、情報収集の効率を飛躍的にあげようというもの。本書に記載されている技術は、Web検索を前提とした、現代における情報収集のノウハウと言える。
Posted by ブクログ
自分用メモ
・本や資料は自分がアウトプット(資料を作成したプレゼンをしたり)することを意識しながら読む
・本や資料を読むときははじめは細かいことは気にせずに大まかな流れを掴む
・資格の勉強について。自分が解けなかった問題をまとめて自分用の問題集を作成する
・仕事の段取りについて。簡単に済ませられるタスクから手を付けて「合計待ち時間」を減らす(優先度との兼ね合いもあるので一概には言えないが)
Posted by ブクログ
根拠とセットできるか?
読書:なぜと根拠をもとめながら読む。へーっといいながら。
文書の最初と最後に答えが書いている。
サブタイトルは読む必要はない。
何が言いたいんだろうと考える。5W1Hを理解しながら。
質問:もう少しくわしく
~ということですか?
ずはり聞きたい?
Posted by ブクログ
すごく膨大な資料を限られた時間のなかでインプットしなければならない時、この本に書いてある技を少し織り交ぜることで無駄な力を抜くことができます。
各々が体に合う技をこの本から得られれば良いと思います。
Posted by ブクログ
藤沢晃治著「理解する技術」PHP新書(1996)
携帯電話の分厚い取扱説明書をどのように読むか?大量の資料から要点をつかむには?一夜漬けで試験に望むには?本書の主張は、情報発信をすることを常に念頭においていると最も効率的な情報受信が可能になるという物である。本も同じで話すことを前提に読んでいれば、本に対して自分の視点ではなく、他人の視点からもアプローチすることになり理解が深まり、記憶も深くなるという物である。ネットなどからの情報の洪水の中で生き抜くには、効率よく本質を理解する技術が不可欠であり、情報を考えずにそのまま受信する人たちが多いこの世の中に、もう一度原点に立ち返ったつもりで、この手の本を読む価値はあるように個人的には感じた。
Posted by ブクログ
目次を読んだだけですっきりと中身の展開が理解できる、凄く読みやすい本です。第1章の「アウトプットしながら情報収集する。」これは以前、読書関連の本で書かれて納得した言葉と同じ、出来ていない自分に反省した。
「分かる」ってことは過去の体験、記憶の一致がおこること。
脳内辞書との一致項目が探し当てられること。
人生経験を積めば積むほど、脳内辞書内の登録項目数が増え、言葉の意味や人生の意味をより深く理解できるようになる。
その理解を深める工夫として、
・本を読む時は仮説を立てて読む。
・自分のことばに置き換えて読む。
・自分の良く知っている分野の言葉に置き換えて読む。
得た知識を身につけるために、
頭の中では情報は文章ではなく、図表として保存されていることを理解して図表で理解。単純な言葉に置き換えて記憶量を減らす。
どうしてって問いかけながら読むことにより、事実と根拠とセットで記憶すること。
基本が分かりやすくまとめられていいて、すんなり理解できます。
Posted by ブクログ
普段、本屋が好きでいろんな本を読んでるのですが、何故か
流し読み感というか、ただ単におやつを食べているような
だらだら感というか、地球資源の無駄遣いのような使い捨て
感覚を感じることが多かったのです。
そんななか、この本を読んで改めて情報収集の姿勢を
思い出すことができました。
要は「アウトプットを意識しながらインプットしろ」とこの本は
言ってます。
著者の他の名著「分かりやすい(表現、文章、説明)の技術」と
内容的に被っている点が多いため、上記著書を既読の方は
若干退屈と感じるかもしれません。
でも効率の良い情報収集について、非常にポイントを絞って
簡潔に書かれているので、私のように「ビジネス本あれこれ
買って読んでるけど、こんなのでいいのかな・・・」なんて
情報収集における「だらだら感」を感じている方には、お勧めの一品です。
■自分なりのポイントキーワード
・ビジネスマンは、プレゼンを前提にする
・一回ザッと読んで、自分の仮説をつくる
・「受信した量」よりも「残す量」のほうが重要
・背景にある理念だけをおさえて記憶量を減らす
Posted by ブクログ
理解する,と理解してもらうtipsについて述べられている.
どちらも並列して行うべきことであり,書かれているtipsは大体両者に適用出来る.特に情報の単純化,構造化(全体→詳細)は重要と感じた.インプットの際には仮説を持ちつつインプットすると効率が良いという話は役に立ちそうなので実践しようと思う.
Posted by ブクログ
文章は、「何が言いたいの?」「5W1H?」を問いかけながら読む、図表を描いて(想って)読む、仮説を立てて読む、と理解度が深くなる。
「AならばB」という情報では、「Aが真実か?」「AならばBは妥当か?」をチェックしながら読む。
Posted by ブクログ
アウトプットしながら情報収集する。文章から情報を読み取るテクニックは、メイン項目をおさえ、全体をざっと見て仮説を作り、図表化しながら読み、根拠とセットにして記憶する。
ひとつひとつは小さなことでも、数年単位で積み重なって差が出てくるんだろうな。
Posted by ブクログ
・章などのブロックごとに要旨を表すキーワードを書き込む(一言で要約する)ことによって全体の構造がわかりやすくなる。
・進行状況を表で管理すると、挫折を防止できる。
情報を整理する
・入手した情報を図や表にしてみる
・入手した情報からルールが見いだせないか考えてみる
・自分の過去の経験・知識の中に似たものがないか探してみる
記憶する
・作成した図表を覚える
・発見したルールを覚える
・背景にある理念を押さえる(例:法律が改正された理由)
・根拠と結論をセットで覚える
・情報に関連性を持たせて覚える
Posted by ブクログ
良い情報を入手するには、良い情報発信を、というのは聞いたことがあるが、まさに情報発信と受信はニワトリとたまご。他人から質問を受けて答えるプロセスや教えるプロセスそのものに理解力を高める役割があるのは確かに納得。
Posted by ブクログ
理解する技術、と言いますが、これは誰にでもできる方法なのだろうか・・・?と、疑問に思う部分がありました。
例えば、難解な文章を理解するために、図式にして考えたり、自分の言葉に置き換えて考えるという手法がありましたが
それは、その難解な文章を理解することができた人でないとできないことなのではないでしょうか。
図式にするのは手間がかかりますし、置き換えはもっと難しいことだと思います。
役に立った部分は、
・情報は、誰かに伝えるという気持ちを持って収集する
(自分だけわかればいいということではなくなるので、理解しようという意欲がわく)
・情報は、なぜそうなるのかという論理性と共に覚えなければ記憶されない
(ポケモンで言うと、水タイプはほのおタイプに強い。
これだけだと覚えにくいが、水タイプは火を消せるので、ほのおタイプに強いという理由と一緒に覚えれば記憶にとどまりやすい)
・情報は、ウエイトの強い20%の情報を理解すれば全体の80%は理解できる。
(本当か?と思うところはありますが、英単語何万語もあるけど、そのうちの2000語程度覚えれば何とかなると書かれていたので、少し信用してみたくなりました)
この本を読み、今すぐ実践してみようという内容はあまりなかったというのが正直なところなのですが
物事を理論的に覚えることは、意識してみたいと思いました。
Posted by ブクログ
「さまざまな情報源から、いかに効率よく情報を収集するか」について、非常に読みやすい文章でまとめられた本です。
が、大抵の社会人であれば意識的であるか無意識であるかは別にして、実践していることばかりだと思います。
私が興味を惹かれたのは、脳の記憶特性を活かす記憶方法として紹介されていた以下の部分。
本を読むときには 「なぜそうなるのか」 「どうしてなのか」 という根拠の部分を探しながら読む。
「根拠」と「結論」をセットにすると記憶しやすくなるというのが上記の理由だそうです。
あと、根拠のない情報では他の人を納得させることも難しく、情報としての価値も下がってしまいますもんね。
Posted by ブクログ
「初級者向け参考書の中で知らなかった一項目は、上級者向け参考書で知らなかった一項目よりはるかに重みがあり、自分にとって大きな価値があります。」
本文中の言葉です。本書も目新しい事は書かれていませんが、これらを無意識にキチンと出来ないと先に進めないなと感じました。
例えば一度立ち止まって図を作るのを億劫がり却って時間をロスした経験など山ほどあるので。