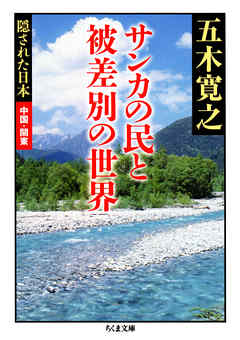感情タグBEST3
Posted by ブクログ
著者が戦後の引揚者であったことはよく知られていいると思うが、朝鮮でどのようなことがあったのかはあまり語られていなかったと記憶している。本書ではその頃、そして引揚後の九州での生活が少し語られている。差別をされていたのだという。その心持ちをアルベール・カミュの「異邦人」の心境になぞられているのは深いなあと感じた。
差別の原点は自らと異なるものを排除したい気持ちにほかならないけれど、その反意が寛容であるという主張には説得力がある。
Posted by ブクログ
副題は「隠された日本」。日本の歴史を語る上でまず表舞台には上がらない人々に焦点をあてるシリーズ。第1巻では海山に生きた漂泊の民と関東地域の被差別階層の人々を取り上げている。
日本人単一民族論について冒頭でイリュージョンと評しているが、私も知識の上ではそれらがファンタジーであると知っている。だが、民族的もしくは民俗的少数派の人々というものについて実感として持ちものはほぼないし、多くの人にとってもそうだと思う。
これは不思議なことであり、私の理解としては不当とか悲劇とかいう以前にもったいないことだと思う。こういう人間の力強さを感じる話は好き。
Posted by ブクログ
五木寛之 「サンカの民と被差別の世界」
海の漂白民として「家船」
山の漂白民として「サンカ」
賎民の王として「浅草弾左衛門」
旅暮らしの香具師として「フーテンの寅さん」
を取り上げ、社会に定住せず、流動する民を取り上げ、被差別の現実と生き様を論じている
原題「日本人のこころ」から考えると、本の主題は サンカなどの被差別世界の不条理ではなく、漂白民の生き方や海への郷愁に 日本人の心を見出している点にあると思う
サンカなど被差別世界の現実については、沖浦和光 氏の賎民史観を全面的に採り入れている
特に印象に残ったのは 浅草弾左衛門。江戸時代の関東八州(現在の関東地方全域)で賎民を束ねたリーダーとのこと。他の本を探してみようと思う
名言「流動する民が存在してこそ、社会は成り立つ。自分たちと異質なものが入ってこないと、活性化もしない」
サンカの起源 沖浦説
天災や飢饉により流浪した人々が川魚漁や竹細工で生計を立て、漂白民の小集団が生まれた
遊女 沖浦説
遊女はもともとは神に仕える女性であり、呪術的なシャーマニズムからきている〜ケガレ観念は畏敬と卑賎視の両義性を持つ
Posted by ブクログ
人種差別という言葉、普通に生活していれば聞かない言葉だ。
その言葉を聞くと、自分とは関係のない、むしろ宗教に似たいかがわしさを感じる。
しかし、かつて戸籍に登録されない人たちが日本には存在していた。
海の上、船で一生を終える「家船(えぶね)」
山の中で移動しながら生きていた「山咼(さんか)」
前半では戦後まで存在していた彼らの存在を炙り出す。
後半では江戸時代の階級、士農工商のさらにその下にいた穢多・非人に焦点を当てる。
関東一円の穢多を取りまとめていた穢多頭の称号「弾左衛門」とその下で非人を管理していた「車善七」筆頭四人の存在。
本人は穢多の被差別民ながら旗本ほどの石高と穢多に対する裁判権を持つという二面性を持っていた。
かつて日本に存在していた被差別民たちの存在が忘れ去られる前に書き記される。
日本には明治維新前後、そして戦前前後の二回、文化の断絶が起きている。
かつて何があったのか、失われた記憶記録を炙り出す作業は日本文化の流れを知るために必要なことだと思う。
かつての被差別民の存在を示すことで、現在は差別が表面に浮かび上がることがない平和な世の中になったことを実感できる。
ただし、それは北から南まで日本国民が均一化したことを意味する。
人と違うことをすると社会から爪はじきにされるという構造は昔から変わらないのかもしれない。