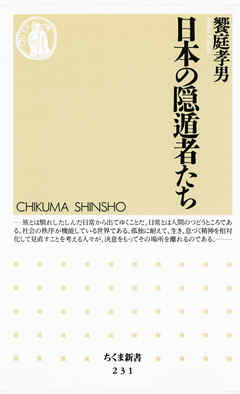感情タグBEST3
Posted by ブクログ
能因と西行、長明と兼好、芭蕉、山頭火と放哉の姿をたどりながら、日本における「隠遁者」のあり方について論じている。
「竹林の七賢」に代表される中国の隠者たちの背景には、権謀術数が渦巻く過酷な政治があると著者は指摘している。彼らは、時の政治権力に反抗的・批判的だった。彼らは、反政治的なトポスとしての農村=「自然」を、みずからの生きる場所としたのである。しかしそれゆえ、彼らは「可能性としての政治」に賭けているということができる。
他方、西欧にも隠者の系譜は存在する。彼らは、自己の内なる「悪」を退け、キリストへの「模倣」としての修業の道として、隠者という生き方を選んだ。彼らの内面劇がおこなわれているトポスは、反自然そのものというべき場所である。
著者は、中国の隠者も西欧の隠者も、日本における隠者のあり方とは異なると考えている。中世については、「無常観」が日本の隠者たちを脱俗へと促したと言える。西行は、世俗との交友関係はある程度保っていたが、「旅」をみずからのトポスに選んだ。長明や兼好は、庵というトポスを選び、俗生を生きる人間に対する認識者の立場をとった。さらに、「座」の連衆への深い絶望と孤独から俳諧という「道」を選んだ芭蕉、「行乞」の旅の中で一人生きることの苦しみと、自然や人情に癒される喜びを得た山頭火、俳句を作ることを存在の唯一の証とするほかなかった放哉なども、「隠遁」という生き方を選ぶことで、自分の内なる「自然」の促しと、外の「自然」との交感の場所に身を置いたと言うことができる。