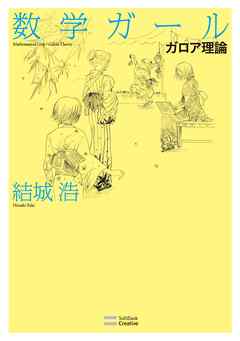感情タグBEST3
Posted by ブクログ
数学的対象を掌中のものにしようとする工夫と苦闘がこれでもかというぐらい丁寧に書かれている。
最後の10章の方程式の可解性を論じたガロア理論が難しいとの声が散見されるが、本格的な数学書や入門書を渉猟してきた体験からするとガロアの原論文の佇まいをそのままに解説してくれた本書はかえって新鮮だった。
不完全性定理の巻に比べると置いてきぼり感はない。
Posted by ブクログ
数学ガールシリーズ第5弾。
今回は、衝撃的な生涯を送ったエヴァレスト・ガロアが発見した代数方程式に関する理論がメインテーマ。そう言えば、ぼくも中学、高校の頃に、5次以上の方程式にはなぜ解の公式がないのだろうと疑問に思った事があったが、結局受験勉強が終わると、そう言う事は忘れてしまい、じっくりその問題に取り組む時間を作るなどと言う事はしなかった。
大学生の頃、度々代数方程式関係の本などに目を留めたり、ガロアに関する本など買った事もあるが、まじめに読み通す事はせずに、まだ実家に積ん読状態になっている。本書に出会って、改めて学生時代の疑問が解決出来た様な気がする。そもそも問題自体もきちんと把握してなかった事もわかり、それも含めて二次方程式や解の公式を違った視点から眺められた事が良かった。
今回もいきなり「あみだくじ」から始まって、ガロア理論とどうつながって行くのだろうと疑問に思ったが、同時になんとなく後の展開へのつながりについてわくわくする気持ちがわいてくる。数学ガールシリーズはこの「ワクワク感」が魅力の一つ。
体と群の二つの塔をたてる時は、またもや数学の別世界のつながりを体験出来た。コンパスと定規を用いた作図問題も、今まで知っているつもりだった事が、代数方程式との組み合わせでより深い意味にたどり着く事が出来た様にも感じた。
ユーリが言った、「解の公式がいままでと違って見える」という台詞が特に印象的。
Posted by ブクログ
頭がほぐれる.気持ちが沸騰する.面白い.
数学で「あっ!わかった!」ってなる感覚を連続で追体験する感じ.
全体的には,数学8割にラノベ2割といった成分構成かな.
数学の解説を,登場人物同士の会話で展開してて,しかも登場人物には
ちゃんと思考のクセが設定されてるので,多方面の視点を自然に提供出来ていて,ただ単にハーレムラノベにしたいから(たぶん美)少女をそろえたわけじゃないんだぞ,という感じする.
シリーズ5作目なのを知らずに初めて読んだけど,全く問題なかった.
ぶっちゃけ,ガロアの第一論文をまんま解説しにかかる最終章はちょっと寝室読書では追いつけなかったけど,非常に楽しめた.
シリーズの他の作品も読むか~.
Posted by ブクログ
あみだくじを使った平易な例からガロアの第一論文まで、徐々に難しくなっていくから、何となくわかったような気にさせてくれる。前々からガロア理論のことは知りたかったので、このレベルで書いてくれるのは嬉しい。
やっぱりガロアの人生は壮絶すぎる。20歳で、人生の半ばでその生涯を終えた天才。本当に心打たれる。決闘前夜に残したという彼の殴り書きは、これからの自分の人生の糧にしたい。
Il y a quelque chose à compléter dans cette démonstration.
Je n'ai pas le temps.
Posted by ブクログ
"5次方程式の解の公式は存在しない。そしてその事実は、角の3等分の作図不可能性ととても似ている。" "角の3等分について考えるのは、そもそも<作図とは何か>を明確にする必要がある。ここでいう作図は<定規とコンパスのみを有限回実行する作図(=有理数から加減乗除と開平を有限回実行する作図:引用者加筆)>のことだ。それと同じように5次方程式の解の公式について考えるには、そもそも<方程式を解くとは何か>を明確にする必要がある。方程式を解くとは<係数に対して加減乗除および冪根を求める計算を有限回実行して解を得る>ということだ。このことを<方程式を代数的に解く>という" ・・・体の世界、郡の世界にガロアの橋のかかるとき、方程式の深淵が垣間見える。
Posted by ブクログ
冬休み、予定以上に本が読めてる(^^)
相変わらず読みやすいです。
数学は、こうせつめいするっていうヒントをもらっています。こういう「ライトな理工学書」は大好きですね。
Posted by ブクログ
シリーズ五作目。方程式が代数的に解けるための必要十分条件を見出したガロアの理論を,ガロアの第一論文に沿って見ていく。といっても本書の大部分は体の拡大とか群論といった準備に充てられている。
理系の大学に行っても,数学をしっかりやらないとガロア理論なんてかすりもしないけど(自分がそうだった),そこにはものすごく豊かな世界が広がっているのが感じられる。数学の本質が垣間見えるというか,いろんなものがつながっていく。角の三等分と方程式の可解性にこんな関係があったとは。
受験勉強してたころ,高校数学の範囲でも相当目から鱗で,数学って面白いと感動したものだ。でも,本当の数学ってそんなの目じゃないくらいに面白い。数学ガールシリーズは,それを効果的に教えてくれる大変な好著だと思う。小説部分は苦手だけど。
「方程式が代数的に解ける」とは,方程式のガロア群から出発して,位数が素数の剰余群だけが出てくるように,正規部分群で次々割って群を縮小していって,最終的に単位群になるような正規部分群の列を作ることができること。
一般n次方程式のガロア群はn次対称群S_n。n ≧5については,S_nの正規部分群は自分自身と単位群のほかにn次交代群A_n(位数n!/2)しかない。 n!/2は素数でないので,一般n次方程式は代数的に解くことができない,つまり一般n次方程式に解の公式はない。
角の三等分の作図不可能性は,五次方程式の代数的不可解性と似てる。角の三等分が定規とコンパスで作図できないことは,有理数体から出発して開平を添加して体を次々に拡大していっても,求める角(の余弦)を含むようにできないことから分かる。
五次方程式が代数的に解けないことは,有理数体から出発して羃根を添加して体を次々に拡大していっても,方程式の解をすべて含むようにできないことを意味する。
開平が羃根をとる操作に変わったわけだが,このせいで,五次方程式の代数的不可解性の方は,体の議論だけでは証明ができなくなっている。証明には対応する群の関係も考慮する必要があり,それで現れたのが,方程式のガロア群。
係数体から出発する体の拡大が,ガロア群から出発する群の縮小に対応するというわけ。
Posted by ブクログ
久しぶりに読んだ数学の本。読むたびに好きだと実感する。
数学ガールは、いつもそこが知りたかったんだというところに言及している。今回の途中に出てきた基底と次元の話は非常にわかりやすかった。
こんな風に数学について話せる仲間が羨ましいなとつくづく思う。
再読時はもっと数学の理論をしっかり追おう。
Posted by ブクログ
読んでいて鳥肌の立つほどそそられる本でした。
あみだくじにはじまり、角の3等分問題、作図可能性の問題、正規拡大体、正規部分群、ガロア理論、、、と非常に興味深いトピックを無理なく自然に、とてもわかりやすく記述しているのは、驚嘆に値します。
おそらく著者自身が、これはどういうことなのか、ということを腑に落ちるまでじっくりじっくり煮詰めたからこそ、こういう本が書けるのだろうな、と思いました。「例示は理解の試金石」、確かに私もそう思います。
本当は有限体まで言及されていることを期待していたのだけれど、(それは言及されていなかったのだけれど)、私はこの本に、迷い無く5点をあげたいと思います。
超良書!
Posted by ブクログ
ガロア理論。いわゆる代数。
あみだくじで最後まで突き抜けるのはすごい面白かった。
こう、ひとつのゴールに向かっていろいろ周辺分野をぐるぐるしながらいつの間にか繋がってゴールに収斂するっていうこのシリーズの良さが出てた。
最後2章は結局よくわかってないので、代数でも勉強しようかという気になった。
Posted by ブクログ
あみだくじに始まり、体や群を通しての方程式の解法につながる。いつもながら後半は難解で高校卒業から十数年経っている私には厳しいが、登場人物たちの解説、ストーリー展開などで、分かりやすく、楽しく読むことができた。
同じ事象であっても角度を変えて見た時の威力や、素晴らしさを今回も体験することができた。
Posted by ブクログ
最後の2章が全く理解できなかった。
この辺が自分の限界なんだろう。
この本での収穫は、体が少しだけわかったこと。
加減乗除の定義された集合みたいなものだということ。
しかし、体が何のために存在するかがイマイチわからない。
自分なりの解釈では、主張を特定の範囲に限定するためのものなのかなと。
体の理解は今後の課題とする。
Posted by ブクログ
これまでと同じく、簡単な思考から数式と理論へ組みあがっていく構成+ラノベ要素、で数学の世界を紹介している。ただ、巻が進むに連れて専門へのシフトが早い気がする。
Posted by ブクログ
方程式を代数的に解ける条件について述べた「ガロア理論」についてのミルカ様の解説
相変わらず半分過ぎくらいまでは理解しながら読めるんだけど、後半はほとんど流し読みで「大体こういうこと言ってるんだな」的なことがわかったような気になりました(笑)
ていうか、ユーリとテトラは、もう普通に数学できる娘になってるじゃん(笑)
Posted by ブクログ
おなじみ、結城浩さんの数学ガール。
最初の方はさくさく読み進めることができますが、あとになるとだんだんと難しくなる。1つのテーマに対して、数学の初学者から大学生でも難しいぐらいまでの内容が1冊の中に書かれているのは本当素晴らしい一冊。
この本をまじめに読もうとすると、実際に数式をずっと追いかけないといけなくて、それはそれで楽しいんですが、さすがに骨が折れることなので、最初はざっと読んで流れを抑えておいて2回目から気になるところを手を動かすって形がいいのかな。毎回数学ガールは買ってますが、いい読み方がわからず、一冊読むのにかなり時間がかかってしまうのが難点といえば難点。
Posted by ブクログ
「数学ガール」シリーズの第5作。テーマはガロア理論。
9章までは知っていた内容で特に詰まらず進んだが、ラスボスの10章ガロア理論はかなり難解。理解するのに苦労した分、と言ってはなんだが、目の前に現れた体と群の結びつき・対応関係は非常に美しい。対応というのは例えば、ある補助方程式に関する体の正規拡大は方程式のガロア群の正規部分群への縮小に対応し(本文中の定理3)、しかも正規拡大の拡大次数は正規部分群による剰余群の位数に等しい、など。(もっとも、本書はガロアの第1論文の主張を紹介しているだけなので、証明等を知りたいと思ったら別の本を参照しなければならない。)
いつもながら女子ばっかりが出てくるラノベ的設定はどうも苦手だが、それ以上に、全体の構成に無駄がなく、予めこの問題を扱っていたのは後でこう繋がるのか、と最後には思わされるのが凄いところ。
本文中にもあるが、本当にガロアが決闘に命を散らすことなく長生きしていればどんな素晴らしい発見を手にしていたのだろうかと思わずにはいられない。
以下、僕が最初に読んだときに詰まったところのメモ。
・あみだくじの置換の記法は一般的な記法とは異なるものを採用している(p326にそれについての記述がありますが)
・p315の剰余類は、特に左剰余類のことを言っている(これもp319に記述があります…)
Posted by ブクログ
素晴らしい。今作も、安心の結城先生クオリティである。章の構成が洗練されており、最終章にて既習事項がすべて繋がる。理解した瞬間に、まるでミステリー小説を読んだ時のような爽快感を得られるはずだ。
Posted by ブクログ
数学を楽しむ少女たちの話。シリーズ5作目。
今回はガロア理論。群論は最近ちょっと興味を持っていたので、いいタイミングだった。昔からちょくちょく見てるサイトで、最近圏論の話が出てた。圏ってのは初めて聞く数学概念だと思って見てると、記事の中には群の話とか出てきてたから、気になってた。実際本書の中でも写像の話が出てたから、やっぱり集まりについての抽象概念の数学表現に近いような気がする。
まぁ、それはそれとして、本書の話。
本書の前半は4作目より大幅に簡単になったなぁという印象だが、後半の詰め込みぶりがすさまじかったw前半のボリュームを1としたら、後半のボリュームは3~5というところかな。登場人物の理解に自分の理解が徐々に付いていかなくなって、最後のほうは、自分の頭の中にイメージを持つことだけに集中するしかなかった。なので、ユーリの提示してくれる図はだいぶありがたかった。
数式を扱うのは形式をそのまま扱うので慣れると簡単だが、概念を記号化して数学的な形式で扱うのは難しい。なぜなら、数式を見て異なる概念をひとつの概念に収める作業を頭の中でやらないといけないから。
昔物理で数式の展開をやるとき、ある段階から別の教科書の内容をイコールで結ぶものが登場したことがあったのだが、このとき初めてイコールの左辺と右辺の物理概念がそれぞれあることを理解した。数学もこれと同じで、表現形式は記号なので変わらないが、その本質は概念的に異なるものとして教えられたものをひとつに収めるのがイコールだということが、本書を見ていると分かる。
本書を含めて数学ガールシリーズは、数学の楽しさを数学を知らない人に教えるために書かれているようだ。シリーズの中では概念を順に提示し、提示された概念は実は同じものの別の表現であることが順に明かされていく。こういうのは、知的好奇心が刺激されるため、何かを理解する楽しみを知っている人にはおもしろいと思う。
本書を読んで最後に思うことが、次作ではきっと今まで読んだすべての数学概念のイメージを持ってないと読めないんだろうな、ということwというのも、ガロア理論はガロアの3つの論文からなるらしいが、本書はガロア理論の第一論文の説明にフォーカスを絞っている。ガロア後半の詰め込みぶりから、1冊に収めるのは到底無理だったから、1つに限定したのだろうと考えてしまう。
次作を読む前に、とりあえず今までの概念を頭の中に用意しとかないとw
Posted by ブクログ
つい先日,前の巻を読み終えたと思ったらすぐに第五巻.今度はガロア理論.すばらしい.証明はほとんどないけれども,わかった気にさせる著者の力量がすごい.
さすがに第10章でガロアの第一論文を読んでいく部分は少し勉強したことがないと,なかなかついていくのが大変ではないかな.私はガロアの原論文を読んだことがなかったので,どういう論理構成になっているかわかって良かった.
小さな間違い p.419 群指標 --> 群指数
置換群とあみだくじの対応が普通の本と違うので注意が必要.この本の定義だとあみだくじを下にくっつけていく積はうまく対応するのだけど (p.76),
[3 1 2]*[3 2 1]
をあみだくじを描かずに計算しようとすると,あみだくじでは下にあるはずの [3 2 1] から計算しなくてはいけない.これは p.361 のように a1,a2,a3の式に作用させてみるとよくわかる.
[3 1 2]*[3 2 1] (g(a1,a2,a3))= [3 1 2]*(g(a3, a2, a1))
=g(a2,a1,a3) =[2 1 3] g(a1,a2,a3).
ある意味ではこの定義の仕方の方が自然なのかもしれないとは思う.
そしてもちろんこれはこの本の価値を損なうものでは全くない.