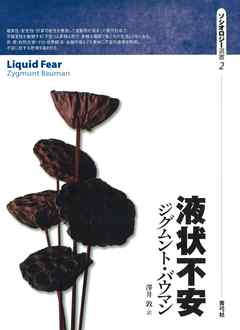感情タグBEST3
Posted by ブクログ
現代社会の不安は、外部に実在する(Solidな)ものではない。人の内側から湧き上がる(Liquidな)ものである。
かつての社会不安はもっぱら、自然災害や敵国の侵略など、人間の手の届かない外部の事態に向けられていた。たしかに存在する不確実性、だからSolid(固形)なものといえる。人は自分の手ではどうしようもないので、神に祈っていたのだろう。
しかし、科学技術の発展、社会の官僚的発展によって人間はあらゆる事態を管理可能になりつつある。気象予報、火山活動の予測、地震速報など自然災害も予め備えることができる。冷戦後の世界の連携をみると戦争という手段ももはやほぼ存在意義をなくしている。では、これらの確かな不安を克服しつつある現代社会において、不安が見事に減りつつあるのか!?
不安は外にあるものではなく、内から湧いてくるものへと変容した。
第一章「死への恐れ」第二章「不安と悪」第三章「管理できないものの恐怖」第四章「グローバルなものの脅威」第五章「不安を浮遊させるということ」、これらの章で不安という液体について述べられる。
① 不安の源泉を探れば、それは「死への恐れ」に行き着く。
フロイトによれば、身体の衰退への苦難、外的要因による破壊の苦難、他人との人間関係からくる苦難、の三つが人を脅かしている。これらはすべて人を死に追いやる可能性を持ち、だから脅威となる。人の恐怖・不安は、死への恐れ、この逃れようのない終焉から連想されている。(それと同時に、死は人が生きる価値を生み出す。人は死への歩みにあらがえない。だから今を輝こうとする。これは死の生み出す利益であろう。だが、死によって無限の挑戦の機会が得られる反面、その挑戦は尽きることがないという絶望も孕んでいる。ほら、また不安だ。)
②「不安と悪」は必要十分条件の関係である。
かつて、悪とは規律・規範を逸したもののことを言った。(それは神や政治が決めてくれた。)そのあるべき行動や現象が裏切られることが、恐れられていた。
しかし、モダンにおいて、悪は規律・規範に従っていても起きうることが分かった。例として、ホロコーストを指揮したアドルフ・アイヒマンの悪性について考えると、彼は上官からの指令を粛々とこなしていただけであった。そこに悪意はなく、彼における規律・規範に従っていたのである。悪の定義を前出の通りにすれば、アイヒマンは悪ではない。これはマックス・ヴェーバーのいう官僚制の負の側面が顕在化した例である。
現代の高度に組織化された人間社会には、アイヒマン同様ルールに従って悪が成される可能性が内包されているのである。この道徳観の矛盾への唯一の対策は、「誰も信用するな」である。
現代は悪が隠れられる場所が多すぎて、不安はやまないのである。
③死の恐れが不安の根源といった。では死を連想させるものはなにか。未知、理解不可能、管理不可能なものである。
我々は未知のものへの抵抗の術を知らない。宇宙人が来ても勝てるかわからないから不安になる。我々は狂人のそばに寄りたくない。何をされるかわからないから。我々は放射線とは友達になれない。奴らは常に牙をむいている。
しかし、現代の科学技術はこれらを広く克服している。我々におそれるものはほとんど残っていないはずである。
現代の管理不可能なもの、不安を導くものは「官僚制」に見ることができる。大戦中の軍部の暴走を見れば、巨大な機構が一度動き出したら進路を誤っても戻れないことがわかる。例として広島・長崎に落とされた原爆であり、イギリス空軍のヴェルツブルグ空爆である。
現代のテクノロジーや合理性が皮肉にも管理不可能を招く原因になるのである。
近年みられるものでは、グローバリゼーションがこれに追随する。
④管理できないものとして、グローバリゼーションの負の側面があげられる。つまり「テロリズム」
グローバルに開放された世界には何があったか。自由?平等?創造?我々を待っていたのは、不平等と相互不理解であった。先進国と途上国の厳然たる格差、資本主義が弱者を喰い物にする様、異なる慣習の否定・迫害など。怨恨と復讐を生み出すばかりである。
これらを原因に起きるテロリズムは、管理不可能といえる。誰が、いつ、どこでテロ行為に走るか特定するのは極めて困難だ。止めさせたくても、文化や信条が違いすぎて対話にならない。
現代人(特に上流社会に住む人々)はこの管理不可能がつきまとうグローバリゼーションの中で暮らしていかなくてはならない。自国に逃げ込んでみたくても、もはや国家という柵は、外国の影響から隔絶するには役に立たない。
⑤我々は史上最高に平和で幸福である。だから不安になる。
現代社会では、科学技術や合理性によって安全性・安定性が確保されている人ほど、安全性と安定性を強く求める。
彼らは彼らの持つセキュリティに不満を持つ。ただし、その防御力ではなく、守備範囲についてである。ひとつの不安が解決しても、また次の不安がやってくる。
たとえば、殺人事件の件数が減れば、軽犯罪の多さが問題になって治安はまだ悪いという。軽犯罪が減れば、いじめ・ハラスメントが問題になって人々の心が冷たくなったという。いじめ・ハラスメントが改善されれば、人々の間で腹を割った人間関係がなくなっているとかなんとか…。人々の不安は際限なく、重箱の隅の隅まで取り除いても終わらないのである。
外部にあった不安の原因は、自己の内側から生まれるようになる。自分の弱い心から、黒い水のようにあふれ出てくるのである。
我々は自分たちで不安の対象を上部レベルへ持ち上げる。不安を浮遊させる。自分たちの手の届かない高さまで…。
以上のように不安の本質を説き、現代の不安の尽きない社会についてまとめている。
ちなみに最終章の不安への対処法は、これからの宿題みたいに書いて終わってた。
たぶん、「皆あんま気にすんなよ!」ってことだと思う。
__
p135 原爆投下の真実
ルーズベルトは敗戦間近だった日本に原爆を落とす必要性はなかった。しかし、国家予算を20億ドル以上費やした技術をゴミ箱に入れることはできなかった。国策というシステムの歯車を止めることができなかった。
___
グローバリズムの章が分かりづらかった。散らかり過ぎって内容。
不安は未知、管理不可能、理解不可能による、とある。その解決は不安の根本を克服するしかない。今の世は不安に対する不安でいっぱいだ。だからこの本を読んで、不安の原因である何かわからない不安を勉強して、不要な不安に囚われない精神を養うしかないのだ。
翻訳が悪い…のか? こういうもんなんだろうが、話が散らかっている印象。ザッと読んで、フーンってなって、読み返して「なるほど」となる。軽くは読めないものである。
原書は2006年出版とあるが、2000年くらいには読んで知っておきたかった。でもその時私は中学生だった。