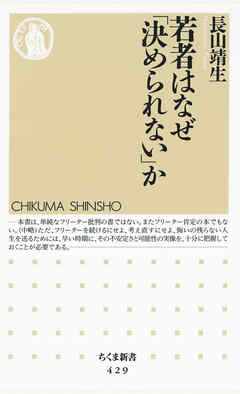感情タグBEST3
Posted by ブクログ
本棚にあった場所から見て、3年前に読んだ本のはずなんですが、内容にまるで記憶がありません。たぶんよく分からないままに流し読みしたレベルだったのでしょう。というわけで初読扱い。フリーターが問題視されていた頃に、若者の歴史もふまえて書かれた本。フリーターが世間で騒がれているほど現代的で大きな問題でないと同時に、フリーターになるにはそれ相応の覚悟も必要であることが分かります。
Posted by ブクログ
ちょっと硬い内容かな?と思いつつも、自分に当てはまる部分があるんではないかと、手に取ってみた。
心の中では前から分かってはいるんだけど、自分の今置かれている状況を真剣に考え直さないといけないと思った。
最近、自分でも思うことが、冷静に書いてあった。
オビにあったように、一方的にダメだというわけでなく、かといって擁護するわけでもない。
でも、そこがとても良かったんだと思う。
“親世代の普通の生活を普通過ぎると思う一方、そんな普通の生活を手にすることがいかに大変か。。。”
ちょっとまじめに、でも読みがいがあった本。
ちなみに夏目漱石の本についてもいろいろ書いてあって、それも面白かった。漱石を読みたくもなった。
Posted by ブクログ
フリーターについての本。
後半の、働くことについての記述が興味深かったです。
「労働=金儲け」「生き甲斐=自分自身の楽しみ」
ここが分離されずに論じられている、というのに納得。
生きがいとして仕事をしたい、というのはもしかしたら根本的におかしいことなのかもしれない。
「生き甲斐」と仕事が結びつけば一番いいのだけれど。
「社会的存在意義の確認」のために働くというのは、なんとなく分かる気がしました。
これは、「生き甲斐」ではなく、人のために働いていることを自覚する という意味だと思います。
Posted by ブクログ
フリーターという存在の、歴史や心理を分析する。結婚し、子どもを育てることを考えると、その後成長を支えるために何歳まで働かなくてはならないのか…という話は、現実的。
Posted by ブクログ
フリーターに関しての本。なぜフリーターが多くなったのか、当時の仕事観や社会通念を説明し、前半は重点的にフリーターに焦点を当てて面白く読めた。
でも後半は社会の現状・問題点をただ提示したり、筆者の好きな明治期の作家をあげて「この点はフリーターにも当てはまる」とリンクさせながら話が展開されていくので、少し冗長な文に感じた。後半少しつまらん。
Posted by ブクログ
著者の主張は全体的にすこし悲観的な印象を受けましたが、共感するところも数多くありました。
少子化や社会が衰退をすることを理由に、その人の生き方が制限されるべきではないという見方に賛成です。したがって、著者はフリーターという生き方を否定していません。その一方で、フリーターであり続けることのリスクを示し、若者が自分の希望と向き合って生きてほしいと締めくくっています。
Posted by ブクログ
古本屋で購入した本。「わかもの合宿」のテーマの参考資料にならんかと思って読んでみた。途中ちょっと間延びした感はあったが、著者のメッセージは伝わった。
若者はなぜ決められないのか、また決めつけるのか?興味深い一冊。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
八〇年代以降、フリーターの数は増え続け、今や就業人口のなかで無視できない存在となった。
日本の近代史をふり返れば、たとえば「高等遊民」という現象のように、「決められない若者たち」は過去にも存在した。
けれども現代のフリーターは、先進国のなかでも特殊な今日的現象である。
なぜこうした現象が生じたのだろうか?
自らも「オタク」として職業選択に際し違和感を抱いた著者が、労働(仕事)観を切り口に、「決められない」若者たちの気分を探る。
[ 目次 ]
第1章 フリーターに対する社会の困惑
第2章 フリーターは告発する
第3章 決められない若者
第4章 決めつける若者
第5章 勤労を尊敬しない伝統
第6章 一億総サラリーマン社会としての戦後
第7章 フリーターへのささやかな提言
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
タイトルの
「なぜ決められないのか」に対する
答えを記している本ではなかった。
職業理念に関する感想というか、なんというか。
真実でもあるし、彼の意見でもある。
でも読み終わっても特に何も考えない類の新書。
Posted by ブクログ
最近自分が将来の職を考え始めたせいか内容がそれについてになってしまった。この書では主に「フリーター」が取り上げられている。断っておくが私は断じて「フリーター」になるつもりはない。もし将来好きな事を仕事にした場合、「収入が主観的に満足いくものにはなりにくい」「気分転換にはならない」という悩みが噴出するらしい。自省しても、塾講師のバイトがそれにあたるなと感じた。そして改めて現代日本の労働はNot労使間But既得権益、新規参入希望層に労働対立があることを確認した。これでは数十年後の日本がどうなっているか心配ではある。余談ではあるが、「ドラえもん」に出てくるのび太のライフコースが印象に残った。79年に大学受験失敗、88年に就職失敗、会社を起こすも95年に会社がつぶれて借金取りに負われる毎日。そんなのび太を救うために未来から送られたのが何を隠そうドラえもんである。
ちなみにタイトルの【若者はなぜ「きめられない」か】には具体的には答えられてない気がした(笑)
Posted by ブクログ
若者がなぜ「決められないか」という疑問に直接答えるというよりも、働くということに関して様々な面から検討した本という面が強い。様々な面というのも、明治の文豪の小説や戦後の世相、著者自身の体験やフリーターにインタビューした結果までが収められているので、一貫して論理を積み上げていくタイプの展開ではない。そのため、読み終わってからタイトルに立ち戻ると、果たしてこのタイトルの答えは何だったのだろう、と思うことになるかもしれない。
しかし文豪の小説を使った働くことについての考察はなかなかユニーク。経済学者でも社会学者でも官庁の人間でもない視点から捉えた若者論、仕事論は、専門家の議論とは違った身近さを持っており取っ付きやすいと思う。