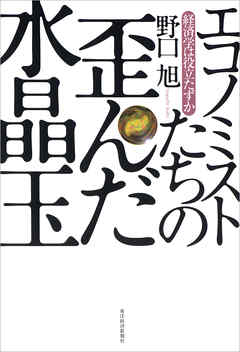感情タグBEST3
Posted by ブクログ
インフレ・ターゲッティングを通じた「デフレ阻止」が受け入れられるのはアダムスミスのいう「共感」に満ちた社会であるか否かにかかっている。小泉内閣の「痛みに耐える構造改革」に対する熱狂は、その痛みを味わうことになるのは「自分とは別の誰か」と考えたからかもしれない。残念ながら、我々の社会とは他人の「いい思い」には厳しく、他人の不幸には寛容な社会のようである。
Posted by ブクログ
「アンチ・リフレ派によるリフレ派批判その2
筆者が注目したもう一つのリフレ批判は、松原隆一郎氏(東京大学教授)のウエブサイト「思考の格闘技」に掲載されている、二〇〇四年七月六日付けのコラム的論考「バカさえ…」である。木村剛氏の場合とは異なり、この松原件の批判は、その対象はリフレ派であり、とりわけ『エコノミスト・ミシュラン』の三人の編者でえることを明示した上でなされている。それは形式的にも、それ以前に展開された一連の応酬、すなわち松原氏の同「思考の格闘技」における『エコノミスト・ミシエラン』批判「『バカの壁』について」(二〇〇四年二月一七日付)、それへの『エコノミスト・ミシュラン』の三人の編者による。ジョインダー「デフレ放置の無責任性」 (太田出版Webに掲載。)、
それへの松原氏の再反論「『バカ (略)』 につけるクスリ」、さらにそれへの飯田泰之氏によるリジョインダー「松原氏の反論に対する若干のコメント」 (同じく太田出版Webに掲載)を受けた再々反論という体裁をとっている。
インフレとインフレ期待の区別は重要
ここでの松原氏の議論の問題点については、やはり上記「バカさゆえ・・・」 で揶揄の対象とされている山形浩生氏による的確かつ詳細な指摘「松原隆一郎へのお返事‥ケインズが本当に言ったこと」 (二〇〇四年七月一七〜一八日、七月二一日・一一月三〇日加筆、がすでに存在しているので、筆者がここで改めて逐一指摘するつもりはない。ここではもっぱら、山形氏が指摘しておらず、かつリフレ派にとって看過できない問題点だけに絞って指摘しておこう。それは、松原氏が、「実物投資が増えないのも、消費が回復しないのも、ともにデフレが原因だと彼らはいっていたのだが、景気が回復しているここ数カ月、消費者物価指数はさらに下落している」とし、そのことをもって「リフレ派の理屈が総崩れになってしまった」と決めつけている点である。
結論的にいえば、松原氏がここで批判したつもりになつている「リフレ派」とは、本来のリフレ派ではなく、松原氏が勝手に作り上げたそれにすぎない。というのは、リフレ派の論理からいえば、投資や消費が回復しない原因は、デフレそのものというよりも、「デフレ期待」だからである。そして、景気回復に必要なのは、インフレそのものというよりも、「インフレ期待」である。というのは、人々の貯蓄・支出行動にとって重要なのは、過去のではなく将来のインフレあるいはデフレであり、それから導き出される将来の実質金利だからである。
つまり、松原氏のように、単に現状がいまだインフレではないことを指摘しても、それはリフレ派の論理への反証にはまったくならない。そのような反証のためには、現状の景気回復がデフレ期待のさらなる高まりととも生じていることを示す必要がある。ところが、いくつかの指標から判断する限り、現状においてデフレ期待は明らかに後退しっつある。松原氏は「消費者物価指数はさらに下落している」としているが、二〇〇一年から〇二年にかけてはほぼJ%弱のデフレが常態化していた消費者物価上昇率(前年同月比、生鮮食品を除く全国総合指数)は、二〇〇三年に入ってからはそのマイナス幅が徐々に縮小し、二〇〇四年にはほぼゼロに近い水準を前後している。さらに、二〇〇三年五月には〇・五%前後にまで低下した」○年物国債利回りも、その後はかなり急速に上昇している。この長期金利の反転には、デフレ期待の反転が織り込まれている可能性が強い。
要するに、現状は、インフレ期待の望ましい水準にはまだ程遠いとはいえ、少なくともデフレ期待は低下しっつあると想定することができる。そして、後述の理由から、こうした期待の望ましい変化が現実の望ましいマイルド・インフレとなって現れるまでには、まだ相当な時間が必要になると予測されるのである。
Posted by ブクログ
日本経済はなぜ回復したのか? 逆から言えば、なぜ15年もの長きにわたって低迷したのか?
経済停滞は何よりもデフレのせいであり、歪んだ政策思想に基づく阿呆な経済政策でデフレを放置しつづけた結果であるというのが本書。この本はいわば、リフレ派による「戦後総括」であり、デフレが猖獗を極めた2002年頃からの経済論争を振り返って、なにが正しくて、なにが間違っていたのかということを浮き彫りにしている。
じゃあ、2002~2003年以降、日本経済が回復基調に乗った原因はどこにあるのか?
「まず、その最大の牽引車は、外需の拡大であり、それをもたらした世界的な景気拡大であった。しかしながら、国内のマクロ経済政策がリフレ的な方向へなし崩しに転換されていたということも、同様に重要な意味を持った。それが具体的には、2003年秋から04年初頭まで行われた、財務省の巨額為替介入と日銀の金融緩和の同時遂行という形でのマクロ的政策協調である。つまり、今回の日本の景気回復は、世界的景気回復と国内マクロ経済政策の両方に支えられて、かろうじて定着したのである」
と著者は述べている。
景気の回復について「構造改革が成功したからだ」なんて考えてるバカは自民党の議員くらいしかいないとして、「銀行の不良債権が解決したからだ」とか「企業がリストラに耐えたからだ」とかいう議論はまだ見られる。それどころか「デフレにはよい側面もあった」とか、「中国がモノを安くつくり過ぎるから世界的にデフレになっている」とかいう論さえ、死滅したとは言えないと思う(本書には「いつの間にか消え去った」と書いてあるが)。
そういった「間違った経済政策」についてズバズバと批判してあるので、小気味よい。まぁ「バブルつぶし」のときはイイコトだと思ったし(若いしカネなかったしひがみ根性だけはあったし)、「財政再建」と言われると立派じゃんやるじゃんと思ったこともあるので、自分自身への批判としてもアイタタなのだが。
はやくも好景気はおわったとか、いやまだデフレを脱出さえしてないとか、まだまだこの本の賞味期限はおわってないと思う。「あの構造改革ってなんだったんだろう?」とか「デフレにはよい面もあると言ってた人がいたような」とか、そーいうことをいまさらのように振り返るのも、興味深いんじゃないでしょうか。
(2006年ごろの初読時のレビューです)