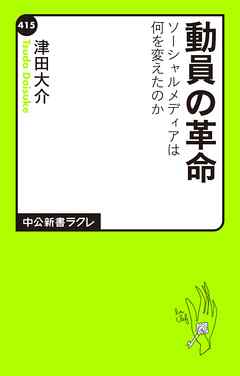感情タグBEST3
Posted by ブクログ
今起きているソーシャルメディアによる社会変革についてわかりやすく書かれている一冊。ソーシャルメディアのすごさに気づかされる。
僕たち90年前後に生まれた人たちが新しいイノベーションを起こすのだという一節が僕に自信を与えてくれた。
これからの時代は僕たち90年前後の世代が変えていくんだ!
Posted by ブクログ
「ソーシャルメディアは何を変えたのか」
確かに、「何か」を起こせそうな気はするようになった。具体的に。
でも津田さんの言うように、結局何かを起こすのは「人」で、そのドアを開けて外に出ていけるかが大事。そのドアを開けるために手を添えてくれる役割として、ソーシャルメディアが重要な役割を果たしているということ。同意。
「自分じゃ社会は変えられない」から「少しでも変わるかもしれない」へ。
1人1人が社会にコミットしていくことが、社会の変革につながるのなら、俺も何かを起こしたい。
Posted by ブクログ
わかりやすいし、面白かった。ソーシャルの勉強を少ししていたが、現状や今後の可能性や方向性についても考えさせられた。これは今のタイミングで読めてよかった。
Posted by ブクログ
3.11間もない頃のSNSに関する言論。
どちらかといえば、SNSの可能性に関する評価が多い。出版から8年経ち、どちらかといえばSNSによる弊害の方が大きく見えるようになってしまった世界だが、本来SNSに備わった可能性というものを再考する上では参考になる1冊。
Posted by ブクログ
タイトルの強さに比べて、内容はとてもオーソドックスでバランスがとれている良書です。津田さんのキャラクタも良く出ていて、twitterの「今」をポジティブな視点から、うまく切り取って表現していると思います。津田さんのリツイート連投を見て迷っている人は、とりあえず買って読んでみることをお勧めします。他人の意見表明はそれほど約にたちませんから。
Posted by ブクログ
ソーシャルメディアの第一人者とされる津田大介。彼が2012年春に著わした本。メディアに出ている彼の言葉とはまたひと味違った、それでいて読みやすい文章でソーシャルメディアを取り巻く環境を説明している。
Posted by ブクログ
ニコニコ超会議にて直接津田さんから購入。サインもらう。
・人は思考の焦点をどこに合わせて意識的に情報を収集しているのか?それによって現実の捉え方が変わる。(p143)
⇒それをしっかり残してアウトプットすることも大切。毎日行くところでも意識的に情報を収集することで、小さな違いに気付くことができると思う。その小さな違いが大きなキッカケになると信じたい。
・茨城県潮来市(イタコ市)も震災の影響で2ヶ月間インフラがだめだった。ただ福島原発という被災地によって、メディアから放送されなかった。このような「中被災地」の情報もソーシャルメディアでカバーする必要がある。(p188)
⇒ソーシャルメディアで小問題、中問題を仕事で探し出すことができるのではないだろうか。
・1955年生まれ前後(ジョブズ、ビルゲイツ)がパソコンによるイノベーション第1世代。1973年前後がインターネットによるイノベーション第2世代(堀江、東浩紀)。1990前後、今の学生たちこそソーシャルメディアに立ち会ったイノベーションを起こす第3世代である。(p238) by梅田望夫
自覚して行動、利用して行かないとね!
Posted by ブクログ
SNSを利用したNEXT STEPの提言。特に第4章「寄付」「マイクロペイメント」「クラウドファンディング」が面白い。ソーシャルメディアを利用した個人単位の小口決済、寄付(贈与経済)への移行は今後要注目。
Posted by ブクログ
主に社会運動を起こすときにSNSが使われた事例に基いて動員を起こすための理論を解説しています。
この本を読んでいた当時はとても納得したし、これはすごいと思いましたが、今ではソーシャルメディアで動員を起こそうとしてもそもそもあまり反応をしなかったり、「意識が高い(笑)」だのと言われ一蹴されるだけの存在になってきたような気もして寂しいです。
クラウドファンディングの話はとても素敵だと思うので日本でも流行ると良いのですが、まだまだ知名度は上がっていないようですね。
Posted by ブクログ
ソーシャルメディア×革命、情報発信、震災、未来の4章構成
この手の分野に疎い人でもわかりやすく流石、津田さんといったところ
各章には津田さんと実際にソーシャルメディアを使っている活動している著名人との対話があり、どのようにソーシャルメディアが活用されているのかが良くわかる
日本と海外によってソーシャルメディアによる影響の受け方が違う点
Posted by ブクログ
☝情報発信をしなければ、リターンはない
①リアルタイム 速報性と伝播力
→社会の現実と強くリンクする
②共感・協調
個々の思想や喜怒哀楽の感情をテレパシーのように共有しあう
③リンク
具体的行動が促進される、自発的なムーブメント
④オープン
参加も離脱も簡単、敷居が非常に低いコミュニティを形成できる
⑤プロセス
透明性が高く、興味を喚起するプロモーションに適する
ソーシャルメディア×未来は?
寄付や民意で世の中を動かすことの出来る未来!寄付やNPO、クラウドファウンディングの輪が広がる明るい社会、気持ちや想いをちゃんとした清い志しにペイ出来る健全な社会が描けてきた感じで、ワクワクです!
これにきちんと参画できるよう、情報や技術や政治にちゃんと参加して、自分を持てるように、そういう大人でありたいと思う。津田さんは冷静沈着であり、日本の未来に明るく、有言実行であるところが、同世代で誇りに思います。尊敬です!
Posted by ブクログ
本書を読み、久しぶりに未来に対して希望を持てた。
日々、スマホやSNSを利用しながらICTによる恩恵を享受している実感を持っているものの、本書に書かれたソーシャルメディアによるパラダイムシフトの実例は、正に「革命」的である。
本書には取り上げられてはいなかったが、「動員の革命」の具現者として真っ先に思い出したのは、群馬大学の早川由紀夫教授(@HayakawaYukio)。
火山灰の分布という自身の専門分野を活かして放射能汚染地図を作り、福島県中通り地区の激しい汚染や東葛ホットスポットの存在を早くから指摘した。
この情報をより多くに伝えるため「炎上ビジネス」と揶揄された過激な発言により、フォロワーを増加させ影響力を高めていった。そして1年前のパールハーバーの日、学長から訓告を受けるが、その後の記者会見をインターネットメディアIWJにより生中継したことにより、更にフォロワーを増やし、ついには氏の活動を支援する寄付活動へと昇華させる。
正に「動員の革命」だ。
Posted by ブクログ
第二章のコミュニティを立ち上げる際に三年が目安というのが妙に響く。中心メンバーなどが意志=モチベーションで頑張れる期限なのかと。様々な形態があるにせよ本業でなかったり利害関係がなければ、三年も変化がなければ離れるわな。
改めてTwitterを初めとするSNSの道具としてのポテンシャルがおもろく、人と繋がったり賛同を得る壁が低く薄くなる日が近いんだな!ってちと、感じれた!
Posted by ブクログ
「動員の革命」
あなたはこの革命を体感しているか?
この本の中で私が最初に読んだ箇所は「ソーシャルメディアのマイナス面」です。なぜかというと、特にtwitterやmixiに関しては、あらゆる問題が多発していますし、単純にデマも多いと思っているからです。勿論、それらは使う側の問題であり、ソーシャルそのものを否定する理由にするつもりは毛頭ありませんが、著者がこれらのマイナス面についてしっかり言及して欲しいなと思い、先に読みました。
実際、twitterで真っ先に挙がる問題点は「デマは必ず発生する」ということです。しかし、意外とデマの数は少なくデマを否定する人も多いので、現在では深刻な問題ではないそうです。しかし、問題は実は他にあったことに気づきました。それは「情報が消えないこと」です。この点は興味深かったです。ちなみに、マイナス面に関しては7ページほどであるので、さほど十分とは言えないかも知れません。まぁ、そこまで問題は無いからかも知れませんが。
また、ソーシャルメディアが革命を起こしたか?と聞かれると「はい」とは言い難いですが、大きな効力を持ち、今後表題にある「動員の革命」を起こし得るとは思います。というのも、著者も触れていますが、ソーシャルメディアは速効性や伝播力、共感などにおいては他の追随を許さないと思うからです。また、私は気づいていなかったのですが、物事に対しての「参加と離脱が簡単である」ということも大きな強みです。
本書はソーシャルメディアと革命、情報発信、震災、そして未来という形が章ごとにまとめられて進んでいきます。その章の中で最も興味深かったのは「ソーシャルメディア×未来」です。実際、私も今後ソーシャルメディアは大きな意味を持ってくると思います。特に、寄付との連動はとても良いと思いました。しかし、感謝=お金がどこまで倫理の線を守れるのかという気はしますが。そんな可能性を秘めているからこそ使う側はソーシャルメディアを賢く正しく使わないといけないと思います。今のように、○○発見器と言われないようにしないとw
また津田氏と著名人との対話も収められています。その中で「日本のデモが何故駄目なのか」という話と「デモを楽しく」という話は印象深いです。特にデモを楽しくというのは見解が大きく分かれそうです。例えば、アフリカでのデモではソーシャルが多くの人々を動員しましたが、そのデモに参加した人々の中に楽しいという意識は果たして本当にあったのか?そこは個人的に疑問ですし、話を読んで「ん?」って思いました。確かに楽しめるデモにも大きな可能性はあるとは思いますが。
ソーシャルメディアって必要ですか?って思う人にはまず読んで欲しいです。
Posted by ブクログ
同じ元割れ厨の身からしては非常に面白く半日くらいで読み終わった。
本文に比べて対談が面白くないのは何故なんだろう。特にモーリーさんとの対談は不要かと。niconicoの名司会ぶりからして対談はもっと面白くできるのでは?
ツイッター納豆論には参ったが、納得。
Posted by ブクログ
ソーシャルメディアとビジネスのかかわりについて考えたくて本を探したら、池袋の西武と東武ではソーシャルメディアといえばこの本くらいしかなかった。ただ津田大介は社会派の人で、冒頭に紙幅を割いているアラブの春のような事象に関心が強い。ただ津田さん自身も生きていく必要があるからだろうか、ソーシャルのマネタイズにも言及した構成になっている。
津田さんのリベラルな言動を考えれば、ソーシャルメディアマーケティングよりもクラウドファンディングの方に紙幅が割かれるのは当然の成り行きだろう。ソーシャルはマスメディアに比べ、マーケティング手段としての適正度は低い。しかし関わっていこうとする姿勢は必要だろう。ただ気になったのは、津田さんたちが楽観的に信じているネット性善説だ。
クラウドファンディンなどは現状、善意の人々で構成されているようだ。しかしNPOが玉石混淆になってしまったように、悪意の人々がそれに気づいてしまったら、という危惧はなくはない。ネット掲示板も最初は高尚なおしゃべりとしてスタートしながら、次第に荒らされるようになり、現在の2ちゃんねるはネット右翼の根城といった様相を呈している。ツイッターでも右翼と左翼が相互理解不能の論争を繰り広げられている。日本人の社会運動や政治意識が未熟なのはしょうがないとして、津田さんのようなオピニオンリーダーはオープンであることのマイナス面も見ないといけないと思うのだが、どうだろう。
Posted by ブクログ
タイトルの予想どおり、ソーシャルメディアがアラブの春に及ぼした影響から。アフリカでいちばんITインフラが進んでるというチュニジアで端を発したなんて、皮肉なことだ。
社会運動で重要なのは1人で飛びだしたときに追随する2人目をどうつくるか。つまりカギになるのは最初のフォロワーだそうだ。確かにソーシャルメディアの特性として、まず情報ありきで、そこに飛びついた人の反応如何でその情報の注目度は大きく振れる。考えてみればソーシャルメディア以前の、ある情報の「最初のフォロワー」って、ほとんどマスコミなんだよね。
2章は要チェック。これまで著者がソーシャルメディアについていろんな媒体を通して語ってきたことの、エッセンスが凝縮。
ニコ動とかUSTはほとんど見ないから、話したり動いたりする著者を見たことあるのは僅かだけど、著書やtwitterとかの文字情報のフォローだけで、精力的に活動を続けているのがよく分かる。アクティビストと名乗るだけのことはある。
Posted by ブクログ
色々と考えさせられることも多いが,確かにソーシャルメディアがもたらす影響を,人が動く・集まる?「動員」というもので捉えることは納得できる.
危うさを秘めている感じもするが.
Posted by ブクログ
最近はネットやその周辺の事柄に興味を持っているので、読んでた。
内容はSNSなどのもたらした(人を集め動かす)、効果や可能性、その将来について著者の経験や、対談などを通して語られるという内容になります。
2012年ですが、IT関係や最近の政治環境は変わっているのでもう古く感じますが、SNSの力に興味があるかたには楽しめると思います。
備忘メモ
・デモは楽しくてもいい。
・ネットだけでは現実は変わらない。実際に動かなければ何も変わらない。
・ほとぼりをさまさず、続けることが大事。
・呉越同舟の方法を探す。
Posted by ブクログ
Twitterで有名な津田氏が、ソーシャルメディアによって動員力が格段に向上したことを記述した一冊。
本人の説得力のある言説は元より、実際にその道の著名人との対談もあり、非常に勉強になった。
Posted by ブクログ
ソーシャルメディアによって情報を拡散することによって、今までより簡単に人を動かすことができる様になった。
ソーシャルメディアの台頭は情報の流れを大きく変え、個人と個人が有機的につながることを促す様になった!
Posted by ブクログ
「ソーシャルメディアがリアル(現実の空間・場所)を『拡張』したことで、かつてない勢いで人を『動員』できるようになった」p5
【インターネットはストック型からフロー型へ】p22
Cf. Twitterのタイムライン
「リアルタイム性が高く、社会的な情報交換に使われるメディア」という特徴に焦点を当てれば、最近のツイッターやフェイスブックなどは「狭義のソーシャルメディア」とも捉えられるでしょう。p26
事例:2009年小国モルドバでの抗議活動。
同年イランでの民主化活動。→ツイッターなど
2010年のタイの暴動。→ユーストリーム
中国では一部の富裕層がVPN(Virtual Private Network)を使ってグレートファイアウォール(Great Firewall:中国政府のネット検閲システム)を抜けている。
エジプト革命で象徴的な役割を果たしたのは、Googleの中東・北アフリカ地域担当マーケティング部門責任者を務めるワエル・ゴニム氏。彼は1/25にFB内に反政府デモを呼びかけるページ「We are all Khaled Said」を作成し、デモの呼びかけが大きなうねりになるきっかけを作った。p36
【外へ出て行き、「変われ!」と叫んだから変わった】p40
中東で起きた革命をソーシャルメディアが起こしたというのは、半分正しく、半分間違っている。なぜか。ソーシャルメディアは、それ単体で政治的な圧力になったわけではない。広場に何百万人も集まるという、民衆のデモが圧力になったのだ。
ソーシャルメディアというのは、モチベーションを与えてくれるもの―言い換えるなら、背中を押してくれるメディアとして機能している。
⇒★ソーシャルメディア革命とは「動員」の革命である。
【「出る杭」から「納豆」へ】p43
「ソーシャルメディア=納豆論」:誰かが出た時に付いていきやすい―まさに納豆を一粒つまむと、粘りが次の豆につながるようなもの。
Cf. デレク・シヴァーズのTED講演「How to start a movement?」
【多種多様な世界の人と知り合うきっかけに】p47
「ヒューマン・マイク」※スピーカーを使うと条例で逮捕されるため。p84
Cf. フラッシュモブ(Flash mob)
【ソーシャルメディアの5要素】
①リアルタイム―速報性と伝播力
②共感・協調―テレパシーのように共有し合う
③リンク―具体的行動につながる
④オープン―参加も離脱も簡単
敷居は非常に低いコミュニティを形成 Cf. ハッシュタグ
マイナス面:「熱しやすく冷めやすい」
⑤プロセス―細切れの情報が興味を喚起する
透明性の高さ
[セーシェル共和国の国家モデル]p118
体験型消費
東大教授・児玉龍彦「得手に帆を揚げる」p124
【ソーシャルメディアは拡声器であり、情報源】p127
Eg. 尖閣問題
ジュリアン・アサンジ「不確かな情報の検証はプロの仕事。ソーシャルメディアはニュースへの多様な視点を提供するもの。そして拡声器であり、情報源である」
アメリカ・シカゴのデポール大学で世界で初めて「ツイッター・ジャーナリズム」という授業を行ったクレイグ・カナリー「ツイッターは情報発信のサイクルをリアルタイムまで短縮したという点が最大の特徴。これは一過性のブームではなく、ジャーナリズム全体に"リアルタイム報道”という手法が確立されていくきっかけになる」p130
↓
▲速報はソーシャルメディアで、一次検証をプロが担当しマスメディアで報道を行う。そこから先はソーシャルメディアが再びいろいろな視点を与え、埋もれるニュースを拾い上げ、重要度に応じてニュースを伝播していく。p130
[「コンシューマライゼーション」の時代]p132
消費者のためのサービスが技術の最先端で、その後に企業向けに移行していく。
Eg. クラウドやソーシャルメディアなどのインターネット情報技術、スマートフォンやタブレット端末など。
【モバイル、クラウドの発展が動員の革命を支えた】
「ソーシャルメディア×クラウド×モバイル」
[ソーシャルメディアに対するテクノフォビア]p135
携帯電話黎明期とのアナロジー
【フリースタイルが求められる時代】p144
宇川直宏、重要なのは「スキル、アーカイビング、年齢」
【デマとどう付き合うか】p174
[ステーキのアナロジー]
マスメディア=ウェルダン、ソーシャル=レア
↓
救済情報が消えない。p177
モジュール化:「多数の異なる部品を要する生産において部品をグループ化して組み立てる方式」p195
【マイクロペイメントは世界を変える】p197
ソーシャルメディアはサイレントマジョリティの「賛」を拾うことができる。p199
【海外のソーシャルメディアが狙うのは個人間送金サービス】
Eg. Facebook Credits:仮想通貨を使ったオンライン決済サービス、Google Checkout+Google Wallet
クラウドファンディング:プロジェクトを実現したり団体を立ち上げたりするためにネットを通じて一般大衆(crowd)から小口の資金を集めること。
a. 投資型 b. 購入型 c. 寄付型
購入型クラウドファンディングの代表例:キックスターター
△クラウドファンディングは現状ではソーシャルメディアの動員力を金銭に換える、現時点で最も現実的なサービスといえるのではなかろうか。p211
「ドロップシッピング」:ネット上の通信販売の一形態。ショップ運営または注文をとって商品の製造元に発注し、製造元から直接購入者に発送。在庫リスクがなく、発送の手間もかからない。p219
【おわりに】p239
ニュージーランド大地震、"Volunteer Army”サム・ジョンソン
ここ数年で「ちっぽけな自分が何をやったところで社会は変わらない」というあきらめの心境が「自ら動くことで多くの人の共感が得られ、社会が少しずつ変わっていくかもしれない」という希望に置き換わった人は少なくないでしょう。ソーシャルメディアは何を変えたのか。もしかしたらそれは、人々の「希望」の持ち方なのかもしれません。p241
「サウンドデモ」p248
[東電の情報戦、戦略]p256
東電の有価証券報告書「普及開発関係費」65年度:7億5千万円、2010年:269億円。
Posted by ブクログ
FacebookとTwitter、今はほとんどこれしかやっていないけれども、世間一般の流れと一緒みたいで、それならもう少し突っ込んでソーシャルメディアに参加して行こうかなと思いました。
確かに、ソーシャルメディアが様々な動員につながるなと。自分もそれで動員されている現実があるし。
Posted by ブクログ
"Twitterの人"などと思われている津田氏がソーシャルメディアのこれからの期待的展望をまとめた本。対談をいくつか収録しているが、どれも津田氏の知識や経験の未熟さが感じられる内容であり、そこが本書の、そして津田氏の魅力でもあった。巻末の中沢新一氏、いとうせいこう氏との鼎談は、デモの音楽性などの話が面白く、読み応えがあった。
Posted by ブクログ
ソーシャルメディアにより人が行動しやすくなった。これによってこの先どういう時代になっていくのだろう、ということをわかりやすく解説した本。
対談に割かれているページ数が多く、雰囲気とともに作者の気持ちがありありと伝わってくる。
ただ、内容をそのまま納得できるかというとそこは疑問だった。基本的にはジャスミン革命とアラブの春を例に挙げてソーシャルメディアの凄さ、動員の容易さを伝えているのだが、日本にいるとそこがピンとこない。
twitterもfacebookもリアルタイムさ、気楽さが今までにないほど特徴的であり、ゆるく祭りに参加したり識者に対して気軽にリプライが送れたりする面は強く感じる。
でも、そこから動員の革命につながるにはファンドを募ったり、納得できるリーダーが必要になるわけで、それはソーシャルメディアじゃなくてもいいんじゃないかなあと思ってしまった。
どうもtwitterでは一過性のデモをよく起こしている(そしてそれをウォッチする人々の)イメージがあり、そこからどう脱却していくのかが分からなかった。
クラウドファンディングは確かに未来があるし、何度か寄付もしたしお礼が来てうれしくなったりするんだけど、リアルタイム性よりかはブログ的な性格のほうが、自分は重要視しているなぁなんて思ってしまった。
どんな手段を使おうとも、ネットよりリアルでの活動のほうが大事、という意見には大賛成。
Posted by ブクログ
津田さんには興味があって読んだ。 SNSでお金は稼げないが、もっとうまく使いこなしたいと思った。 震災後も結構な頻度で取材で東北にいらっしゃるようで、ありがたいと思う
Posted by ブクログ
ソーシャルメディア論で第一人者の著者による、今の社会の流れを語る。Twitter、Facebookによる情報の流れ革命は周知の通り。クラウドファンディングによる新しい通貨の流れは、これまでの経済とは違う価値を生み出していると実感。
Posted by ブクログ
なかなか興味深い内容だなぁと思いながら読んだものの、いざ記録しておきたいことが記憶されてない。さて、こまった。
どこかで、もう一度読んでみるベキかも知れない。
キーワード
・モーリー・ロバートソン
・ソーシャルメディアの5要素「リアルタイム」「共感、協調」「リンク」「オープン」「プロセス」
・コミュニティを作る際には「3年」を目安にする
・ソーシャルメディアから情報が「消えない」
・マイクロペイメントは世界を変える
・クラウドファンディング
Posted by ブクログ
・情報発信しなければリターンはない。
・ソーシャルメディアがリアルを拡張したことで、かつてない勢いで人を動員できるようになった。
・得手に帆を上げる。
・速報はソーシャルメディアで、一次検証をプロが担当しマスメディアで報道を行う。そこからはソーシャルメディアが再びいろいろな視点を与え、埋もれるニュースを拾い上げ、重要度に応じてニュースを伝播させていく。
・コンシューマライゼーション
☞消費者のためのサービスが技術の最先端で、その後に企業向けに移行していく。今までとは逆。
・コミュニケーション手段の変換に伴う変化を必然的なものとして受け入れ、いい面も悪い面も、両面認識した上で、現実と折り合いを付けていくという態度が何より需要。
Posted by ブクログ
筆者の、『ソーシャルメディアの革命とは「動員」の革命だ』という指摘は、まさしく要点を一言で言い表していると思う。
facebookやtwitterのようなツールの登場で、世の中の色々な部分が変わっては来ているけれど、それによって一番変わってくるのは、使いようによって、個人の「動員力」が飛躍的に増加するという圧倒的なポテンシャルだ。
このことを理解して意識的にソーシャルメディアを活用している人と、単にブームに乗ってソーシャルメディアを受動的に使っている人とでは、今後、埋めようのないほどの能力の格差が発生してくるだろうと思う。
この本は、対談部分と、モノローグ的な解説の部分とに分かれているけれど、対談は、それによって創発が生まれているような感じはせず、それほど感銘を受けなかった。
何故「動員の革命」であるのかという部分を拾い読みするだけでも、大きな意味がある本だと思う。
ソーシャルメディア革命とは、「動員」の革命なのです。
とにかく人を集めるのに長けたツールです。人を集めて行動させる。まさにデモに代表されるように、人が集まることで圧力となり、社会が変わります。そのソーシャルメディアの革命性が最大限発揮されたのが、「アラブの春」でした。(p.42)
当然ながらツイッターに対する悪口や批判はあります。「ツイッターをする暇があるならリアルを大事にしろ」とか、「ツイッターなんて暇人がすることだ」とか、「他人の<カレーライスなう>を聞いて何が楽しいんだ」とか、様々な悪口が(なぜか)僕に対して言われました。しかし、その悪口を聞いているうちにそこにある種の既視感があることに気づきました。それは、携帯電話です。携帯電話は1995年前後に急速に普及してきましたが、その頃はあえて「俺は携帯電話は持たない」と宣言する人が一定数社会にいました。「24時間仕事に追いまくられたくない」とか、「ケータイなんかに縛られたくない。俺は自分の今の自由を守りたい」とか。しかし、そう高らかに宣言していた人たちの99パーセントはおそらく、今携帯電話を持っています。(p.135)
(宇川)僕らのようなライブストリーミングにおいて重要なのは「実験と偶発的事故」を味方につけることなのです。「生」の現場においてはこのことが最も動員に関係していると思います。そして地上波では、その究極が鶴瓶さんなんですよ。(p.145)
(津田)ネット上でどれだけ叩かれても、結局はわら人形だから。五寸釘を打たれたところで、致命的なダメージを与えられないじゃないですか。
(宇川)全く何にもないですよね。懲りないし、血も出ないし、死なないし。
(津田)だから、これからソーシャルの中で生きていくには、わら人形的メンタリティーが必要なんじゃないかと。で、こういう話をすると出てきがちなのが「スルー力(何を言われても気にしない力)が大事だ」みたいな話なんですけど、わら人形になるっていうのはスルー力を持つのとは違うんですよね。だって、わら人形はスルーしない。受け止めているんだから。分かりやすい例でいえば、ソフトバンクの孫正義社長や乙武洋匡さんなんかはその典型ですよね。(p.161)
(津田)良い悪いではなく、ソーシャルメディア上ではあらゆる言論がわら人形論法にさらされるという特性を分かったうえで、いつ五寸釘を打たれてもいい覚悟を持ってわら人形になれる奴が強い。たとえ五寸釘を打たれても、込められたメッセージをすべてそのまま受け止めるのではなく、あくまでもあいまいな「思い」としてそれを受け入れ、自分の中で消化する。これを自覚/無自覚に行なっている人がソーシャルメディアで「動員」できているわけで、それは現実の知名度と、ソーシャルメディアにおけるフォロワー数や言論の影響力が比例しない何よりの証明になっていますよね。(p.163)