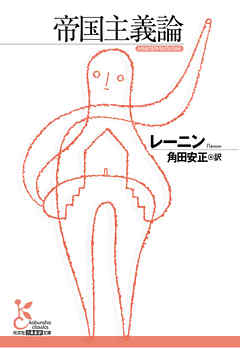感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
この本は今からおよそ百年前に書かれている
はずなのに、古臭さすら感じません。
そして、自国が富めるものになるためには
ただひたすらに外を侵略し、
そこから金の元を取らなければいけない時代。
そして富むものたちは…
そう思うとこの制度って
今の世界と全然変わりがないじゃないですのん。
100年近くたっているのに変化がないです。
植民地がなくなっただけ。
そして金の元が変わっただけ…
資本主義…当たり前の様に浸透している
主義だけれどもそこには
欠点があるものですね。
それを著者が指摘していたことに驚き。
Posted by ブクログ
【まとめ】
1860~1870年代、自由競争の支配する資本主義が驚異的な発達を遂げた。20世紀初頭、恐慌によって自由競争的な旧来の資本主義に代わって、生産と資本の集中化が徹底的に進む帝国主義が現れる。銀行は資本集中と取引高の増加を果たし、産業資本との融合を始め、実質的に産業に対する支配を強めた。帝国主義は資本主義が高度に発展した段階であり、金融資本が支配的となった体制である。従来の資本主義では商品の輸出が行なわれたのに対し、資本主義の最高の段階としての帝国主義では資本輸出が特徴となる。そこで大衆の生活は依然苦しい。しかし独占から生まれる莫大な過剰資本は、資本家の利益のため、後進国への資本輸出に用いられ、大衆の生活向上に費やされることはない。
金融資本の段階で、資本家は(その階級的利益に端を発する)経済的利益から独占体同士の同盟を結び一定の関係を保持しようとする。同時にそれにつられ国家間でも政治的な関係が構築される。私的独占と国家独占が一体化し、巨大独占資本家が世界分割を繰り広げる状況が生まれる。
金融資本における生産力の発展や資本蓄積の度合いは資本主義国家間の発展から不可避的に差が生じる。そして、その帝国本国の力は「勢力圏」の分割状況とは均衡しない。やがて力をつけた後発帝国主義国(植民地をもたざる国)は既存の世界支配での不均衡の是正を狙い、自らの力を反映する形で植民地獲得の分け前にありつこうとする。資本主義を維持しながら、分割された世界の再分割を巡る不均衡の解決は、独占的資本家=帝国主義国家間での不可避の戦争以外に存在しない。
【感想】
訳は非常に読み易く、訳者解説も本書内容理解を助ける良いものであった。訳者解説によると本書執筆時にレーニンがおかれた状況は、「ロシアは後進国であるので、社会主義革命を即座に成就するためにの前提条件を備えていない。したがって、ロシアのマルクス主義者は、帝政ロシアが戦争に敗北することを通じて社会主義革命を実現しなくてはならいない」。革命の前提条件として帝国主義戦争でロシアが敗北する必要があり、そのための戦争の必要性から「詭弁」的に革命理論を作り上げたのが本書(…その割には説得力ある主張が多々ある)。であるから、本書に散見されるやや感情的なカウツキーへの口撃は近親憎悪的なものである。
一方で、「ブルジョア経済学」であるホブソンを高く「評価」、というより敬意を払いつつ都合良く利用している点が興味深い。ホブソンの『帝国主義論』をよりいっそう読みたくさせる書きぶりである。
さて、またもや解説者の重要な視点を借りるが、本書を現在の国際情勢に照らして読む際に、注目されるべき点がある。それは、資本家の蓄えた資本を国内投資に振分け、所得再分配をするのであれば、植民地を保有せずともやって行けるという点である(レーニンは深くは言及しておらず可能性を否定するが)。実際、社会主義の可能性や、「改良主義」的な既存の枠組みを受け入れた社会民主主義的勢力の存在で資本主義の行き過ぎにたがをはめることが出来ていたことは事実であろう。であるからソ連崩壊後、資本主義が暴走している現在、尚更に読まれるべき本であるということだ。