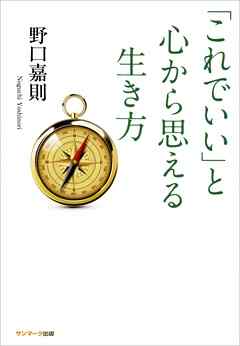感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
第1章 心の安全地帯を確立する
第2章 選択する力を養う
第3章 地に足をつけて
第4章 自己受容を深める
第5章 人生を最高の物語にする
○自分を大切に生きる
○アサーティブにノーと言うと自尊心が育つ
○日々の遊びによって子どもの生きる力が育つ
○「正しいか間違い」で考えない
○「選択するまでの葛藤」と「選択した後の体験」
の繰り返しによってアイデンティティーは確立さ
れる
○私たちが下す判断というのは相対的なものでしか
ない
○そのまま「これでいい」と受け入れる。そのため
に、自分のモノサシを手放す必要がある
ユング、河合隼雄、アブラハム・H・マズローからビートたけし、または、童話や日本昔話まで、幅広い良書からの引用があり、大変分かりやすい。
最初から最後まで、わくわく感を持って愉しみながら読みました。
多くを語らずも心に響く詩を一つ。
ビートたけしさんの詩集『僕は馬鹿になった』から著者の大好きな詩を。(第4章 自己受容を深める より)
「騙(だま)されるな』
人は何か一つくらい誇れるものをもっている
何でもいい、それを見つけなさい
勉強が駄目だったら、運動がある
両方駄目だったら、君には優しさがある
夢をもて、目標をもて、やれば出来る
こんな言葉に騙されるな、何も無くていいんだ
人は生まれて、生きて、死ぬ
これだけでたいしたもんだ
Posted by ブクログ
チェック項目9箇所。自分という人間の土台を確立すれば、本来の力を発揮できます、そのための生き方を本書でお伝えします。どのような状況においても、自分の気持ちを大切にできるような生き方をすること、これこそ、本当の幸せを実現する土台になることなのです、そして、自分の気持ちを大切にするためには、自分と他者の間の境界線を明確にし、心の中に安心できるスペースを確保する必要があります、そのことによって私たちは、自分の気持ちを大切にできるようになり、また、自分が自分であることの確かさを感じられるようになるのです。子どもにとって、親から拒否されたり、親に見捨てられたりすることは、自らの命の安全が脅かされるくらいの極度の不安に直結することです、ですから子どもは、自らの安全が脅かされるくらいならば、進んで自分の欲求や気持ちを抑えるほうを選ぶのです。人は子どものころに、「このように生きていこう」と、生きていくうえでの基本的な方針を決めるのですが、これを「幼児決断」といいます、幼い未熟な思考による決断ではありますが、これが大人になってからの無意識の行動を左右する源になるのです。人は、イヤなことに対して「ノー」を言うことで、自分にとって受け入れられるものと受け入れられないものの間に境界線を引くとともに、自分と相手の間にも境界線を引き、心の中に安心できるスペースは創り出します、このとき、しっかりした境界線を引けるほど、その内側のスペースは安全度の高い、より安心できるスペースになります、このスペースは、「心の安全基地」にもたとえられますが、この安全なスペースこそが、喜びが育つ場所なのです。相手の権利を侵害することなく、自分の要求や意見を率直に表現する態度を、「アサーティブな態度」といいます、これは、自分も相手も大切にする建設的な態度であり、また、自分と他者の間に建設的な境界線を引くために必要な態度でもあります。アサーティブに「ノー」を言うことを実践するにあたって、「自分の境界を守るためのルール」を作っておくと、それが行動をあと押ししてくれます。一人の時間は、とても豊かで贅沢な時間です、「誰にも気を使わなくてよい、自分のためだけの時間」であり、「他者との人間関係から解放されて、自分の心の声に耳を傾けることができる時間」であり、「自分と深くつながり、自分が自分であることを実感し、本来の自分に立ち戻ることができる時間」なのです。ありのままの自分を等身大に認めて受け入れるのが自己受容です、「こんな条件を満たしているから自分は素晴らしい」と、条件付きで自分を肯定するのではなく、どんな自分もそのまま認めるのです、自分を好きになれないときも、そのことを認めてゆるしたらいいのです。私たちは、「この状況さえ打開できれば自分の本領を発揮できるのに」とか、「チャンスにさえめぐり会えば、自分の持ち味を発揮できるのに」などと考えてしまいがちです、しかし、私たちの真価や本領や持ち味というのは、常に今この瞬間に問われているのであり、そして、今この場で発揮できているのです。