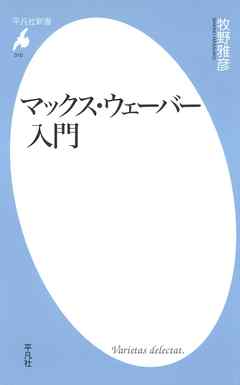感情タグBEST3
Posted by ブクログ
マックス・ウェーバーの入門書。著者は「あとがき」で、本書のタイトルが岩波新書から出ている山之内靖の本と同じであることについて、「山之内氏が左を向けば右をというかたちで違った方向を追求することになり、結果としては対照的な、ところによっては正反対のウェーバー像にいきつくことになった」と述べている。山之内氏の本は、ウェーバーの思想を同時代の精神史的潮流、とくにニーチェの哲学との関わりの中で論じていたのに対して、本書は当時の政治経済学のトピックとの関わりを中心にウェーバーの学問の意義を解明している。個人的には、今まで知らなかった当時の学問状況について多くを学ぶことのできた本書の方が有益だったが、両方読むことでいっそうウェーバーについての理解が深められると思う。
本書の前半は、ウェーバーの方法論がどのように形成されていったのかを解明することに当てられている。著者はまず、ランケ以降のドイツの歴史学の展開を、政策学から国民経済学への移行として見ることができるという。こうした展開を推進した歴史家たちは、学問的な歴史認識と実践としての政治との間に越えがたい溝があると考えたランケの立場を越えて、現実の政治へと積極的に参加していった。ウェーバーの論文『ロッシャーとクニース』は、こうした歴史学派の国民経済学の動向を受けて、その方法論的反省をおこなったものだ。そこでウェーバーは、経験科学は直接的に価値判断を導くことはできないが、一定の目的が設定されているときに、その目的に対して適合的な手段を教えることができると論じて、歴史的な科学としての政治経済学がどのような意味で政策科学としての有効性を主張しうるのかを明らかにした。
続いて、ウェーバーの主著『プロテスタンティズムと資本主義の精神』や宗教社会学の研究の意義が、ゾンバルトやビュッヒャー、マイヤーといった歴史学派の経済学者たちの思想との関わりの中で解説される。歴史学派の経済学者たちは、世界史を一直線に発展する過程とみなす考え方を批判し、民族に固有の興隆と衰退の過程の分析へと向かった。ウェーバーはこうした問題設定を引き受けながら、禁欲的プロテスタンティズムの宗教的・内的な動機とそれがもたらす帰結とを描き出し、「魔術からの解放」をヨーロッパ近代のもっとも顕著な特徴とみなす観点を打ち出すに至った。
Posted by ブクログ
『プロ倫』をようやくの思いで読み上げて、ウェーバーについてもっと知りたくなった。
この本は、「そもそもウェーバーって何ぞや?」という点で考えをまとめるのに役立つ一冊だと思います。