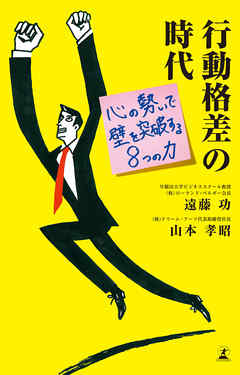感情タグBEST3
Posted by ブクログ
「出来るか出来ないかではなく、やるかやらないか」であると思う。変化が激しく、先行き不透明な時代の中で、つい、行動にブレーキをかけてしまいがちな日本人にとって珠玉の書籍である。
Posted by ブクログ
要するに行動がものごとを前に進める要である。ということ。知識や情報が氾濫する中で溺れていては駄目でそこを泳いでどこへ行くのか?実践知について書かれた本。
Posted by ブクログ
机にしがみつき自ら動こうとしない日本人ビジネスマン。他方、中国勢、韓国勢は常に動きながら判断し決断を繰り返している。内向き志向が強まり、行動力は劣化、弱体化している。不透明で不確実な時代だからこそ、行動することで初めて獲得できるものがある。行動を起こし何かに挑戦すれば挫折はつきもの。決して思い通りにはならない。ネガティブなことが必ず起こる。苦しみながらもネガティブをポジティブなことに変換することによって人間は成長する。挫折を乗り越えるための8つのキーワード。捨てる力、迷う力、忘れる力、ふられる力、知らない力、怒る力、失敗する力、落ち込む力。一見ネガティブと思われるこれらのことは実は人を成長させ強くする追い風。本書には果敢に行動するときに頼りになるこれら8つの力について紹介されている。泥まみれの直接経験こそが人を鍛える。挫折への耐性を高めればこその成就。肝に銘じたい。
Posted by ブクログ
忘れる力ー過去の失敗や挫折やそれまでの常識や先入観を忘れる。忘れる時はプラス思考で忘れる。忘れる時は積極的に主観を見直す。
ふられる力ーふられることで選ばれることに感謝することを学ぶ。
落ち込む力ー落ち込んだ時こそ、目の前のことに本腰をいれて取り組む?小さな奇跡を信じて、努力をし、実現に感謝する。
出会いを粗末にするな!
Posted by ブクログ
教育やネット環境の普及のため、今や知識格差→情報格差の時代ではなく、責任と情熱をもって主体的に行動できるかどうかの「行動格差の時代」。
事なかれに逃げず、前進していくために著者の二人が示すのが「捨てる力」「迷う力」「忘れる力」「フラレる力」「知らない力」「怒る力」「失敗する力」「落ち込む力」。
これらの力は、もとよりネガティブで、行動のために率先して選択すべきものでもないが、そうした状況を経験し、真摯に向き合うことで前向きな行動を起こす力になりうるものだと分かる。
著者の失敗に学ぶ姿勢やしぶとさは参考になり、面白くもあったが、責任と情熱をもって主体的に行動するために何をなすのかという観点からすると、やはり本質的なところではない奇をてらった内容のように感じられた。
13-128
Posted by ブクログ
各自の意思と決断と情熱に委ねられた行動の力が弱体化している。果敢に行動する時頼りになる8つの力。
タイトルを読んで、情報時代になるほどと思いました。
同じポイントについて、実際に行動を起こしているすごい方二人が交互に書かれてしるため、分析や理論としてはちょっと掴みにくい。
Posted by ブクログ
仕事の実力をつけるのには、8つの心の力が必要だと。「ふられる力」とかも必要だそうだ。著者たちの実体験などもあり、それなりに苦労した時代があったとだなあと思う。
Posted by ブクログ
先日講演を聞く機会のあった遠藤先生の最新本。行動を起こすことの重要性と、行動を起こすことを後押しする「8つの力」を解説した本。行動の有無が格差を生む時代。行動なくして、成長なし。下手な知識は、行動を起こす上での雑音にしかならない、というくだりは耳の痛いところ。当たり前なことだけど、本を読むことが目的でなく、本を読んでどう「行動」するかが大事。この当たり前のことがなかなかできないのだが。
以下、参考になった点、引用、自己解釈を含む。
・失われた20年と言われているが、失われたものをシンプルに突き止めるならば、それは「行動」である。IT革命行こう、情報や知識の差が競争力の差になることはない、今は「行動量」に左右される時代に突入している。アジア諸国をはじめ、元気に成長している国は、ハングリー精神が旺盛で、とにかく「行動してみる」というスタンス。一方日本は、成熟期に入り、上から目線でモゴモゴ批評を繰り返し、行動しなくなってしまった。かつての日本は、今のアジア諸国のように動いて動いて動きまくっていたのだが。ここが、日本が停滞しているもっとも根源的な要因。
・学習することは大事。だが、いくらインプットを増やしてみても、1つの行動に伴う体験には及ばない。行動して、躓いて、悩んで、もがいて・・・。そこに本当の意味での学びがある。泥にまみれた直接体験こそが重要。
・結果を出している人に言える1つの共通点は、事象の解釈力にある。挑戦すれば、必ず傷つくシーンがある。だが、このシーンを前向きに捉えることで、前のめりな行動を取り続けることが出来る。
・8つの力。「捨てる力」「迷う力」「忘れる力」「フラれる力」「知らない力」「怒る力」「失敗する力」「落ち込む力」。
・前に進む為には、「何をするか」という行動の選択の前に、「何を捨てるか」の選択が必要。リソースは限られている、選択と集中とは、何を止めるかと同義語。捨てるものを明確にすることで、するべきことが浮かび上がる。
・捨てることには、必ずストレスがかかる。捨てることは簡単では無い。強い信念を持ち、勇気をもって捨てるという主体的な態度が必要になる。
・情報氾濫社会の中にいれば、勝手に情報やら人間関係やら仕事は増えるもの。その増えてきた「入口」で不要なものを選ぶことが大事。1度抱えてしまうと、捨てることのストレスに屈指、不承不承に抱え込んでしまう。
・判断と決断の違い。判断は過去の事象について情報を精査するなかで下すものであり、迷う必要は無い。一方、決断は未来について判断を下すもの。未来という不確実なものへの判断、これは迷いが生じて当然。多いに迷い、自分と向き合えばよい。迷うことは力をため込むコト。迷ってため込んだ力を、信念を伴う「決断」で爆発させる。判断と決断の違いを理解した上で、迷いところ、時間の掛け方をコントロールする。
・ただし、マネージャーは迷っている姿を人に見せてはならない。迷っている姿は、メンバーに動揺を与え、組織全体に迷いが波及していく。トップは大いに迷いながらも、迷ってる姿を見せず、明るくふるまうこと。
・覆水盆に返らず。過ぎたことにクヨクヨしている時間はあるのか?過ぎたことはクヨクヨしても変えられないことにさっさと気づき、次の行動に移っていかなければならない。
・記憶とは、事象と事情に伴う「感情」のセット。事象は変えられないが「感情」は自分次第で変えられる。この感情をどうコントロールするかに意識を集中させるべき。
・悪い記憶だけでなく、良い記憶にも注意が必要。過去の成功体験という記憶ほど、慢心を招く根源。良い記憶こそ「忘れる」ことが大事。そのための1つの手法が、自分より凄い人に会う、こと。会いに行くという「行動」を取ってみる。
・自分が精根かけて取り組んだ仕事は、心のどこかで「評価されて当然だ」という想いがついて回る。努力した仕事が失敗に終わった時に、相手のせいにしてはいけない。そのような不遜な思いは、なぜか相手に伝わってしまうもの。どの会社、どの個人でも同じようなスタンスで取り組んでおり、自分だけが抜きんでた存在では無い。フラレルことが当たり前だと思うスタンスが大事。フラレテ当たり前と思うことで、成功した時に、素直に喜び、感謝が出来る。
・知識や情報というのは過去の産物であり、未来を規定するもではない。挑戦という2文字の前に、知識や常識は何の意味ももたない。中途半端な知識は、かえって自分の行動を制限する足枷となる。
・失敗につながるのは「知識が足らない」ということよりも、中途半端な知識にも関わらず、知ったかぶりをして行動を起こさないことに起因する。本当の知識人はまず行動をし、そこで足らないものは更に吸収し、その上で更に行動量を上げていく。行動に基づいた「知識」を吸収している。
・怒りのパワーを有効活用せよ。良い怒りは、人も自分も前に勧めるパワーとなる。怒る際には、人を怒るのではなく、事象そのものに対して怒ること。そして、怒るタイミングを見定めること、常日頃怒っていては慣れが生じて効果は半減。ここぞという時に、パッっと怒って刺激を与え、サッっと引くことが肝要。居合い術のようなイメージ。
・そして怒るときには「本気」であることが重要。相手のことを思い、事業のことを思い、今の問題点を本気で喝破する。本気で怒るのは労力がいるしシンドイ。でも、本気で怒らないと、怒られた方も粋に感じない。
・怒る際には、上下関係は関係ない。理不尽なことには、言葉を選びながらも、信念を持って怒るべき。牙を抜かれてはならない。
・やれることがあるのに、それをやり切らずに失敗したものを、失敗とは言えない。それは単なる手抜きである。失敗の多くは、手抜きからくるということを理解すべき。手抜きの失敗をまずはなくす。その上で、全力でやった失敗を大事にする。失敗からの学びこそが、成功への道。
・落ち込むことを前向きに捉える。仕事を長く続けていると、何をやってもうまく行かない時がある。藁をもつかむ思いで、もがけばもがくほど、何故か沈んでいく。しかし、このもがくことでどれだけの筋力アップに繋がるか。駄目だと思った時に、は安易な「逃げ」を打つことなかれ。長いトンネルは自分を磨く最大のチャンス。
・行動を起こす為には「ノリ」が重要。ノリという不可視なものながら、確実にその「気」は存在している。優秀なマネージャーはこの「気」のコントロールに心を砕く。難しい事象を前にした時に、ノリが悪ければ、批判を加えるだけで、行動を起こさない。が、ノリがよければ、やりがいがある!、という体で組織が動き出す。ノリを重視し、行動を起こさせることが必要。