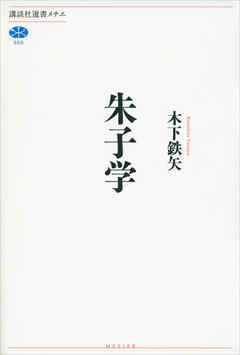感情タグBEST3
Posted by ブクログ
朱子学について学ぶ時、「性」「心」「善」といった語が重要であることはわかるものの、それが一体何なのか明確にとらえることがなかなかできず、いつも気持ち悪い思いをする。その点、この本は、それらを朱子の関係するテキストを丁寧に示しながら説き明かしてくれる。またそれぞれの説明において「すなわち・・・」として、明快適切にまとめもらえているのはありがたい。「格物」の「物」という語の捉え方も勉強になった。ただ、そのことに関係して陽明学について触れられているが(154頁)、これについてもう少し詳しく知りたかった。もし王陽明が「物」をモノ(物体)でなくコト(現象)と捉えていたならば、朱子の立場を批判することはなかったのかどうか。本書の最終章を読んだ印象では、王陽明も人間の心のあり方について、結局朱子と同じような捉え方をしているような気もする。理解が不十分であることを露呈するようではあるが、そんなふうに質問すれば、著者はきっと誠実かつ丁寧に答えてくれるだろうと思う。そんな気になる良書だ。
Posted by ブクログ
タイトルは「朱子学」となっていますが、伝統的な朱子学の展開を概説した本ではありません。朱熹のテクストを引用して、そのていねいな読み解きをおこないつつ、著者自身による朱熹の思想の解釈を提出している本です。とりあげられているテーマは、「学」「性」「理」「心」「善」の五つです。
著者は、「朱熹の思想は首尾一貫する体系性を持ち、中国史上に現れたさまざまな思想の中でも飛び抜けて完成された論理的整合性をその大きな特徴とする、という認識が実は相当に誤った断定であると感じざるを得ません」と述べています。本書では、朱熹そのひとのテクストのうちに思想の揺らぎを読み解くときつつ、とりわけ存在論と倫理学・政治思想を一体のものとして理解するような伝統的な朱子学の解釈に対する異議申し立てをおこない、朱熹そのひとの思想をテクストそのものに立ち返ることで正確にとらえることをめざしています。
ただし著者は「はじめに」で、朱子学をたんに朱熹そのひとの思想と理解することはできないと述べています。「日本朱子学」や「朝鮮朱子学」ということばに含まれる「朱子学」は、「趣旨の行い示した学」というだけではなく、「趣旨を先達、先覚と仰ぐ「学び」」であり、それを通じて「われ」の真実にいたることがめざされていたという指摘がなされています。このような立場から、あらためて朱熹の思索そのものと格闘し、「学び」の実演を示しているという意味では、本書を朱子学の入門書と呼ぶこともあながち的外れではないのかもしれません。
このように、かなり意欲的なねらいをもった本ではありますが、いわゆる朱子学の概説書としては、本書で厳しく批判されているとはいえ、島田虔次の『朱子学と陽明学』(1967年、岩波新書)の意義は現在でもうしなわれていないのではないかと、個人的には考えます。