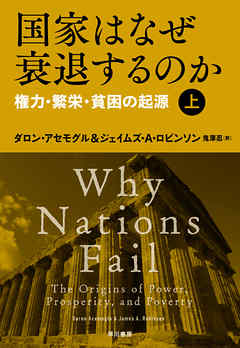感情タグBEST3
Posted by ブクログ
世界に裕福な国と貧しい国が生まれた理由を歴史的に解き明かす。緯度や気候などの地理的条件、宗教や民族ごとの価値観などの文化的側面は、世界的な不平等の説明にはならず、経済と政治の制度が重要であると説く。
ヨーロッパの植民地としての歴史を持つ南北アメリカ大陸に相違が生まれた理由がおもしろい。スペインが支配するアメリカ大陸の植民地では、金銀の略奪段階が過ぎると、労働力としての先住民を分け与える制度であるエンコミエンダなどの制度を導入し、土地を奪い、労働を強制し、低い賃金と重税、高い商品を売りつけた。コンキスタドールとその子孫は大金持ちになり、先住民の生活水準は最低となる不平等な社会となった。スペインは、1808年にナポレオンが率いるフランス軍に侵攻され、王が退位させられると、評議会が結成されてコルテスと呼ばれる議会を組織してカディス憲法を生み出したが、南米のエリートは、労働力としての先住民を分け与える制度であるエンコミエンダ、強制労働、絶対的権力による制度を守り、独立していった。
イングランドはアメリカ大陸の征服に遅れたため、先住民がたくさんいて鉱山のある場所はすでに占領されており、北米しか残っていなかった。入植者たちは先住民を支配することができなかったため、入植の支援をしたヴァージニア会社は人頭権制度を導入して土地と家を与え、1619年には議会が設立されて法と制度の決定権が与えられた。メリーランドでは荘園社会がつくられたが、議会が創設されると荘園領主の特権は剥奪された。1720年までに、アメリカ合衆国となる13の植民地のすべてに知事がいて、選挙に基づく議会があった。
ヨーロッパでは、14世紀のペスト流行による人口減少が、地域ごとに異なる結果を生んだ。イングランドでは労働力不足の結果、農民は強制労働と多くの義務から解放された。しかし、封建君主が組織化されていた東欧では、もともと広かった小作地はさらに拡大され、労働者の自由は奪われた。1500年以降は、西欧が東欧の農産物を輸入し始めたため、地主による労働者の支配は強くなり、無給労働が増えた(再版農奴制)。
政治制度の違いも重要な影響を与えた。16世紀末のイングランド、フランス、スペインは、いずれも絶対君主に支配されていたが、イングランドとスペインの議会は課税権を手に入れていた。スペイン国王はアメリカ大陸からの金銀から膨大な利益を得ていたが、イングランドの女王は税金を上げる見返りに、独占企業を創設する権利が奪われていった。イングランドでは、大西洋貿易と植民地化によって、国王とつながりのない裕福な商人が大勢現れ、政治制度の変化と国王の特権の制限を要求して、名誉革命において決定的な役割を演じた。名誉革命によって、所有権が強化・正当化され、金融市場が改善され、海外貿易における国家承認専売制度が弱められ、産業拡大の障壁が取り除かれた。包括的経済制度の下で、ジェームズ・ワットをはじめとする人々が機会とインセンティブを与えられて、産業革命が始まった。
Posted by ブクログ
タイトル通りではあるが、なぜ繁栄している国家と貧困にあえぐ国家があり、後者は貧困を脱することができないのかがクリアになる。やはり自由、信頼、イノベーションは必須で、行き過ぎた統制、独裁は進歩を妨げるのだ。ジャレド・ダイアモンドの説より腹落ちする内容で、国家だけでなく組織に当てはまることで学びが多い。読み応え十分。
Posted by ブクログ
繁栄する国家と、逆に落ちていく国家。その違いを、地理や文化といった(役に立たない)理論に求めるのではなく、経済と政治に関する、歴史の中では小さな選択にあるされています。なぜイギリスが産業革命で成功したのか、他のヨーロッパ諸国はそうならなかったのか。少々の偶然の要素もあったのですが、違う制度を取った国々の差を広げこそすれ、そのベクトルを決めたのは、その選択にあったということ。
具体的な歴史を、読みやすく、読ませる書き方で書かれており、現代の我々が立っている位置が、どのように出来上がっているものなのか。また維持するために、何に注意していなければならないのかを教えていただきました。
Posted by ブクログ
ジャレド・ダイアモンドは「銃・病原菌・鉄」で文明発祥と伝播には栽培可能な穀物や家畜が反映する社会を生んだ原動力となり東西には伝播しやすく自然環境の異なる南北には伝播速度が遅いと唱えた。それは一つの強力な仮説だが本書の調査結果によると歴史的に野生の牛や豚が棲息した地域の分布はヨーロッパからアジアの非常に広い範囲に及び米の原種はインドから東南アジアにかけて広く分布している。小麦の原種も肥沃な三日月地帯だけでなく地中海東岸からイラン、アフガン、中央アジアの「スタンズ」にまで広がっている。ダイアモンド自身も「文明崩壊」で同じ島でありながら崩壊しつつあるハイチと発展を目指すドミニカの違いを書いている。また、ニーアル・ファーガソンは西洋文明が優位になった理由を「競争、科学、所有権、医学、消費、労働」とまとめた。
それに対して本書では北朝鮮と韓国、フェンスを挟んで貧富の差が激しいアメリカとメキシコのノガレスなどを上げながら地理や気候と経済的成功の間には単純な、あるいは持続的なつながりはないことを明らかにしていく。そして政治制度が包括的で多元的であれば繁栄の好循環を生み、収奪的で独裁的であれば貧困の連鎖を生むとしている。包括的と多元的と言うのがわかるようでわからない訳なのだがinclusiveとextractiveの対比らしい。包括的な市場と言うのは個人の権利が尊重され、権力者による搾取がない市場、包括的で多元的な政治制度とは参政権が広く開かれ、色々な考え方が許容される政治制度と考えればいい。その最も極端な姿が民主主義だ。収奪的な独裁制の元では個人が努力するモチベーションが働かない。産業革命がイギリスで生まれたのは偶然ではなく、イノヴェーションが個人の利益を生むと言うモチベーションが後押しした。
しかし歴史的には封建社会が長く普通でイングランドで包括的な制度が生まれたのは偶発的なものだった。1688年の名誉革命によって王権の制限や多元的な制度を求めた商人達を含むグループが勝利したのは100年前にイングランドがスペインの無敵艦隊を破り大西洋がイングランド承認に開かれたことに端を発する。それでもイングランドで包括的な制度が力を持つにはまだまだ時間がかかり、1733年に飛びひを発明したジョン・ケイやジェニー紡績機のハーグリーブスはラッダイト運動でイノヴェーションに対する抵抗に会っている。それを黙認したのはイノヴェーションにより政治権力が脅かされることを怖れた権力者だ。君主制化の17世紀には王家や貴族は専売制の独占権の分配によって収奪的な制度を維持しておりこれが国家の大きな収入源だった。1642年独裁的なチャールズ1世に対抗した議会はオリヴァー・クロムウェルの指揮の下王党派を破りチャールズ1世を裁判にかけて処刑したがそれはただ、クロムウェルの独裁を生んだだけだった。そして王政復古後絶対君主制を復活させようとした弟のジェームズ2世は議会に破れ、議会はオレンジ公ウイリアムとメアリを招き立憲君主制を成立させた。王と議会の力関係が代わりより多元的になったわけだ。
逆に繁栄が上手くいかなかった例としては13世紀のヴェネツィアがある。定住し資金を提供する商人と自身は財産を持たず商人のパートナーとして旅をする貿易商からなるコメンダ(ワンタイムの合資会社)によりヴェネツィアの経済は発展し大評議会が生まれ毎年100人の新たな評議員が任命された。独立した裁判所、契約法と破産法が生まれ現代の銀行業の元が生まれた。しかし既得権益を持つ貴族勢力は評議会を世襲化し、コメンダの利用を停止した。1314年に貿易を国営化し、個人商人に高額の税を課すようになるとヴェネツィアの経済は衰退を始めた。ヴェネツィアは世界経済の中心から今では地方の観光地、よく言えば往事の繁栄を記録した博物館になっている。
「発見」された当時のアメリカ大陸では現在のアメリカとカナダの人口密度が最も低くこれだけでも地理説は力を持ちにくい。どこで差がついたかと言うとアメリカの入植はことごとく上手くいかず入植者に所有権と参政権を与える試みだけがうまく働いたのは収奪するほどの先住民がいなかったということでもある。メキシコや南米に入植したエリートは強制労働を元にした植民地制度を享受していたからだ。そしてクーデターはあっても制度は維持された。アメリカ合衆国が楽園とは言えずとも世界最大の経済大国になった成り立ちには自由主義や民主主義が大きなモチベーションとなったことは間違いはない。
では共産党一党独裁の元で収奪的な政治制度の下で繁栄する中国はどうなるのだろうか。収奪的な制度の下で経済的な発展を達成するケースはある。中央集権制がない政治制度よりはまだ条件としては整っている。「漢江の奇跡」の韓国の政治が包括的制度に移行したのは1980年代盧泰愚政権の時だ。しかし著者の見立てでは中国が韓国の様に包括的制度に移行する見込みは薄い。
Posted by ブクログ
人民に労働対価が与えられないと、その国は滅んでいく。ということを、実例をいくつも挙げながら説明している。特に、アフリカ諸国での絶対的権力政治が、現状に至っていることがよくわかる。ソマリランドの無政府状態が何故続いているのかが、判りやすく書かれている。平易な言葉で書かれているが、中身が非常に濃すぎるだけに、読むのに時間がかかる。3回くらい読み直してやっと、筆者の言いたいことが判るのかもしれない。
Posted by ブクログ
経済は政治の上にある。政治が正しく平等で安定していないと投資もできないし新しい産業は(既存の権力者に)つぶされる。で政治は民主的なほうが長続きしやすくて、王政や社会主義とかだと一時的に発展はするが継続しない。まっ100年ぐらいは持つかもしれないみたい。ソ連は持たなかったけど。
南米やアフリカの収奪的な政治を何とかしないと経済発展や飢饉の対策はできない。
となるとまずは地域の自治レベルでの民主制の萌芽を目指すのかな。フランス革命も三部会とかの影響もあったし。
Posted by ブクログ
世界にはなぜ豊かな国と貧しい国が存在するのか、本書は、政治・経済上の「制度」による違いがその理由であることを古代ローマから、マヤの都市国家、中世ヴェネツィア、名誉革命期のイングランド、幕末・明治期の日本、ソ連、ラテンアメリカとアフリカ諸国、現在の中国といった広範な事例を用いて説明するもの。
これからの日本を考えると、既得権益に縛られずに、世の中のニーズに応じた創造的な技術・仕組み・取組みが自由活発に進められる社会により良く変えていくことが重要で、政治・行政としてもその基盤を作ったり、後押しすることが役割になろうと感じました。
今後の日本、また世界を考えていく上で必読の良書です。ちなみに、筆者は同じヨーク大学・LSE出身の政治経済学者で親近感があります。
【ポイント】
・豊かな国には自由で公平、開放的な経済制度があり、技術革新・創造的破壊による持続的な発展のインセンティブがある(一方で、権力者が国家を食い物にして民衆から収奪する仕組みあり)。また、法の支配、民主主義、多元主義といった政治的基盤がそれを支えている。
・日本の明治維新とその後の経済発展は、イギリス名誉革命、フランス革命と並んで偶然性も相まった稀有の出来事。
・現在の中国の急速な発展も、既存技術の導入などに留まっており限定的で、政治的な開放がなされていない統制的な経済制度では、長続きしないのが歴史的な必然。
・あくまで制度という人間によって左右できるものが主要因であることは楽観的、一方で、人の問題であるがゆえ一度形作られた制度は硬直的でなかなか変わらないことは悲観的(奴隷制、植民地時代の制度が未だに残っているアフリカ、南米など)。
・これまでの国際機関や開発機関による「開発援助」は往々にして途上国の時の権力者を肥太らせ、また国際機関から現場に至るまでに幾重にもピンはねされるために、真の援助が必要な大衆には届かず、必要な制度を作るにも至っていないのが現状。一方で、何もしないよりは何かした方がマシなのも事実。
Posted by ブクログ
2014年25冊目。
わずか一枚のフェンスで区切られた「ノガレス」の北と南で大きな経済的格差が生じるのはなぜか。
地理・気候・民族が同じ北朝鮮と韓国でこれだけ貧富が違うのはなぜか。
国家の貧富を左右するのは「地理」「病気」「文化」ではなく、
“収奪的”ではなく“包括的”な経済「制度」とそれを構築する政治「制度」が有るか否かだというのが、本書の主張である。
■「収奪的制度」:絶対主義、一部のエリートによる支配、新技術導入への渋りや妨害、商業の独占・・・etc
■「包括的制度」:多元的政治体制、議会の機能、イノベーション(創造的破壊)への寛容性や促進、認められた財産権・・・etc
これらの制度の違いによって(たとえ小さな相違でも)、決定的帰路(たとえば、「新大陸の発見」や「産業革命」)が訪れた際に、その恩恵を享受して継続的な発展を手にできるかどうかが決まるという。
収奪的制度の元でも、一定の発展は見受けられる。
しかし、包括的制度の元での発展と違うのは、そこに「持続性」が認められないこと。
これらの主張を、原始時代、ローマ帝国、コンゴ民主共和国、ロシア、産業革命前後のイギリス・・・非常に広範な歴史を紐解いて論じている。
■巻末に出展と解説が多少あるものの、脚注がないため、やや信憑性に欠ける部分がある
■全ページが塗りつぶしたように文字ばかりで、箇条書きでのまとめなどがないため、読み辛さを感じる時がある
などの点は気になったが、「全ては制度」という明快な主張を通していて、一読の価値はとても高いと思う。
下巻では明治維新に至る日本の事例も出るそうなので楽しみ。
Posted by ブクログ
☆チャーリーおすすめの一冊!
非常に難しい内容ではありますが、とてもためになります。活用できる部分も多く、自分に取ってはバイブルとなる1冊です。
Posted by ブクログ
本書は気鋭の経済学者・ダロン・アセモグル(と、ジェームズ・ロビンソン)の経済成長に関する歴史実証の本である。普通、経済成長論と言えば、資本、労働、技術進歩などで決まってくると言うのが教科書的な説明であるが、本書ではそれらとは別に、政府の「制度」が経済成長を決めると主張する。すなわち、国民がより参加している政治における政治制度から生み出される経済制度こそが、経済成長に寄与すると言う物である。このロジッックは、より多くの国民が関わっている政治制度の方が、一部のエリートで構成される政治制度よりも国民の繁栄に対して積極的であり、また人々のインセンティブにも反応するような制度を作らせる傾向にあるため、経済成長を促進する、というものである。
第一章から第四章までは事例を交えながらの理論展開、第五章から第八章までは紹介した理論の様々な事例紹介という位置づけである。
経済成長には制度が重要である、そしてその制度と言うのは全員参加型の政治制度から形成される、という主張は、著者の知的貢献であるのは間違いない。しかしながら、その根本のロジックとなるのは、人はインセンティブに反応するという経済学の基本原理に他ならない。つまり、経済学の基礎にぶれない形で、その叡智を応用していると言いかえることもできる。
個人的には、この1年間で読んだ本の中でベスト5に入るくらい面白い本だった。もう少し経済成長論を復習した上で、それらと比較しながら読めば良かったと思うので、下巻は経済成長論を復習した上で読みたい。
Posted by ブクログ
「国家の衰退は制度がもたらす」「地理は関係ない」という主張に、思考が非常に刺激された。包括的制度(自由?)の重要姓を主張するので、人によっては自由主義野押し売りと感じるかもしれない。
Posted by ブクログ
長期的な経済発展の成否を左右する要因は、政治経済制度の違いである。
経済発展には、inclusive=包括的な政治制度(民主政治)と包括的な経済制度(開放的で公平な市場経済)との相互依存というメカニズムが存在する。
また、良いスパイラルとは逆の、独裁政治と収奪的な経済制度との悪循環も同時に存在する。
Posted by ブクログ
なぜいま国家や地域によって経済や成長にここまで格差が生じているのかを考察した本。名著「銃、病原菌、鉄」では「近くにいた動植物がたまたま飼いならしやすいもので食料化し、かつそれらにいた病原菌を欧州民族が最初に抗体をつけたから」みたいな要因に格差が生じる根本原因を見出していたが、本書ではそれを社会システムに求めている。(歴史的偶然性である、というのはどちらも同じ結論なんだけど。。)
つまり、多元的・民主的政治システムは包括的システムであり、その下にはやはり包括的な経済システム、具体的には人々が発展することへのインセンティブが生じ、経済が発展すると説き、莫大な量の事例でこれを証明している。
慧眼というか最大のミソは、権威主義的あるいは絶対主義的な政治システム下でも権力の集権化に伴う効率性により経済はある程度発展するが、前者と後者の違いは破壊的なイノベーションによる許容度の違い、つまり権威主義、絶対主義的な政治システムの下では社会を根本的に変革し、自らの政治基盤を脅かすことにつながるイノベーションは結局のところ受け入れず、発展に限界が訪れることを指摘している点である。イノベーションを起こさせるインセンティブを人々に起こさせ、変化を国家自体も受け入れられるような多様な人々を意思決定の中に組み込んでおくこと、これがもっとも重要なようだ。
この視点から、現在の中国の開発独裁的手法には自ずと限界が訪れることを本書では指摘している。これが当たるかどうかが、本書の真価を問う場になりそうだ。
ある体制が崩壊し、新しい体制が生じる際に、その体制が社会のあらゆる階層や意見を多元的に受け入れているものかどうか、それが次の発展を規定すると本書では定義している。なぜならば前者と同じ性質の人たちが次の体制を構築する場合、よりひどい収奪的構造がそこに生まれることが多いことが歴史の多くの事例から証明されているからである。このことを正確に理解していれば、今後の国際情勢を見る上でのひとつのものさしになるような気もする。
いずれにしても、上下巻全部読むと、人類の社会、経済システム史に相当に詳しくなったような気にならせてくれる良書である。
Posted by ブクログ
収奪の体制になると経済的な成長が止まるという理論。過去のいろいろな地域、国を事例として説明している。
政治体制によって経済体制が決まり、成長のインセンティブが働くなくなると国家は衰退する。国家の衰退を経済的な衰退ととらえている。
政治体制が民主的であれば経済成長が促される仕組みになっている。ただ、ローマを事例にとると民主から独裁へと移行しており、民主から他の仕組みに移行する可能性はある。
「隷属への道」では政治的な自由よりも経済的自由が重要と言われており、つながるところがある。というのも、収奪的な政治体制でなければ経済的な自由は保障されるので、民主主義にはこだわっていないと言える。
Posted by ブクログ
「国家はなぜ衰退するのか」(上)は「国家はなぜ衰退したのか」「国家はなぜ繁栄したのか」「国家はなぜ繁栄できないのか」の事例のショーケースでした。包括的制度と収奪的制度という本書の提示するフレームワークのもと、産業のイノベーションが事業者に対してインセンティブをもたらす政治体制かどうか、というシンプルな視点で古今東西の国家の盛衰を語っていきます。初めに結論をハッキリさせておいて次々とサンプルを繰り出してくるのでテーマの重さの割りには一気に読めました。そういう意味では本書でも何回も言及されている「銃・病原菌・鉄」がゆっくり読み進まないとならなかったのと違いを感じました。西欧と東欧の違い、イングランドとスペインの別れ道、名誉革命と産業革命の意味、アフリカの苦しみ、中国の不透明性などなど、なるほどの連発です。ただ、その主張の分かりやすさが新自由主義的な市場礼賛にも繋がりかねないような気がしてヒヤヒヤしながら(下)に突入します。
Posted by ブクログ
包括的な政治制度と包括的な経済制度が国家の繁栄をもたらし、逆に収奪的政治制度と収奪的な経済制度が国家を衰退させるという新しい視点がとても納得できた。しかし言ってることがそれだけで、ほとんどがその繰り返しである。豊富な例を挙げていると言えばその通りだが、私にはしつこく感じられた。
Posted by ブクログ
地理的要因と家畜化および農耕化可能な野生生物種の存在を文明発祥の起源としての条件を提示したジャレット・ダイヤモンドの名著『銃・病原菌・鉄』に対して、その統治形態によって、国家の趨勢が決まるというのが本書の要点だ。
しかし、『銃・病原菌・鉄』のスコープと本書はスコープと論点が異なっており、明らかに互いに排他的な議論をしているわけではない。名が通ったものを恣意的な解釈のもとにアンチとして定義し、それ対して自らを対置することで正当性を主張する手のように見え、あまりいい印象を持つことができない。
著者の主張をまとめると、ごくシンプルで、統治形態が収奪的である場合は経済的繁栄は持続しないし、包括的制度である場合は繁栄する、というのが主張である。その事例としてスペインとイングランドの植民地政策の違いを歴史的に考察し、南北アメリカの違いを説明する。
スペインとイギリスの植民地政策の違いは、マクルーハンにも取り上げられて、決して新しい視点ではない。また、収奪的システムが経済的自立を阻害するのは、社会主義国家の失敗やアフリカの多くの独立後の国家の状況、さらには南北朝鮮の明白な違いを見れば明らかだ。
本書のテーマに対応する本としては『銃...』よりも、ウィリアム・バーンスタインの『「豊かさ」の誕生』を挙げる方が適当だろう。参考文献には挙げられていないので、著者が読んだかどうかは分からないが、そのスコープや着眼点は重なっている。成功した国家としてイギリスやオランダ、明治維新以降の日本を挙げている点も同じだ。『「豊かさ」...』では、「豊かさ」の発展の必要条件として「私有財産制度」、「科学的合理主義」、「資本市場の形成」、「輸送技術と通信技術」の4つを挙げている。本書では、おそらくはそれらに先立ち統治形態がより根源的な支配条件だと主張していると考えることができる。特に、「私有財産制度」と「資本市場の形成」は、包括的制度の必然の要素である。どちらの本に説得力があったかと言われると『「豊かさ」...』の方に自分とした軍配を挙げる。機会があれば合わせて読むとよいだろう。
また売れている本では、マット・リドレーの『繁栄』も対比できる本だが、『繁栄』では、人間が獲得した「交換」の能力が繁栄を約束したという。その要因をより根源的なものに焦点を当てているが、国家間で繁栄の差があることについては、あまり気に掛けていないように思われる。その意味で、両者は互いに補完するような関係にあると見ることもできるだろう。個人的には、『繁栄』の方が視点に意外性がありかつ根源的な問いかけがされていて面白い。
いずれにせよ上下巻に渡る大著である。もう少し短くできたかとも思うが、かなりの史料をベースにした真面目な本である。
Posted by ブクログ
国が豊かかどうかを規定する因子を考察している。つまり、国民にインセンティブを持たせることができるか、どうか。それは、経済制度であり、政治制度が、どのような形をとっているのか。アメリカとメキシコの国境の街ノガレスを例に挙げ物語が始まる。
創造的破壊を拒絶するような絶対主義のもとでは、インセンティブは育たない。もちろん、創造的破壊によって、統治者やエリートは多くのものを失いうる。抜本的なイノベーションを導入するためには、常に新規参入者を必要とする。多元的なものを許容できる政治制度、つまり変化し続けることが生き残るための秘策なのだろう。
私のような基盤を未だ持たない者にとっては、本著はきわめて刺激的な内容に富んでいた。
Posted by ブクログ
マックスウェーバーは国家の本質を『合法的な暴力の独占』と定義した。中央集権していない国家は政情不安を招き、混沌となる。そしてその盛衰は文化や地理的気候が決めるのではなく、国家の政治・経済制度が決める。収奪的制度(≒共産主義?)を採る国は一部のエリートが富を得ることで、それ以外の人々との内紛や政情不安を必ず引き起こす。エリートは情報を操作し、自由な発想や創造的なものを破壊してしまうからだという。
つまり十分に中央主権された強力な国家と多元的価値観を認める政治・経済制度の共存が、繁栄できる条件なのだ。
植民地時代においても王に集権していたスペインと多元的なイギリスとの差がその後の繁栄を分けた。
更に植民地にされた国(特に資源が見込まれる国)は搾取を容易にするため、収奪的な政治・経済制度を強要され、繁栄を妨げられた。
人間の欲望が人間を支配する起源であることがよく分かる。
資源も少なく、タイミングよく明治維新が成功した日本は、こうした世界の潮流に飲み込まれなかったのかのように思えたが、やはり集権的な時代には数度の戦争に突入した。
集権・多元を繰り返すことが今後も国家の宿命なのだろうか。
まだまだ集権的な中国やロシアといった大国は、今後どのような方向に進むのか。
宗教で集権化されている国々はどうなっていくのか。
読んでいて根本的な問いが生まれるのは良書の証拠なのだと思う。
Posted by ブクログ
批判も賛同も多く出ているので、すでにそれに付け加えることもないのでしょうが、還元主義的というか説明のための歴史や制度の恣意的な採用をして書いているのではという違和感はありました
それでも経済学のブロゴスフィア的にはあまり扱われない国々についての詳しい説明があったのはおもしろかったのですが
Posted by ブクログ
世界には豊かな国(地域)と貧しい国(地域)があるが、それらを隔てる境界線が「包括的な政治・経済制度」か「収奪的」かの違いにある、という主張。「包括的」という言葉の意味するところは、自由主義や民主主義、多元主義といったイデオロギーを重視する政治であり、私有財産や市場経済を重視する経済制度を指す。
別に目新しくはない。日本の歴史教科書にはこの手のメッセージがすでに散りばめられている。啓蒙思想、西洋史観と言って良いかもしれない。実際に本書には「収奪的な政治・経済制度から包括的なものにうまく変革できた成功例」として明治維新が紹介されているが、深みは学校で学ぶ程度のものだった。でも本書には範囲の広さがある。世界各国の「豊かな国」「貧しい国」の紹介事例の多さだ。
少し残念なのは、各章のタイトルから「いつの時代の、どの国(地域)の、どのような統治制度」について解説してるのか?が判別つかず、また章末に「まとめ」もないので再読し辛いことだ。
Posted by ブクログ
国家の繁栄と衰退について、大きな要因としてテクノロジーがあると思われるが、それについては説明されていない。すべて制度に起因ささている。また、例えば日本についての例など、より歴史的知識のある日本人からすると、「オイオイ、よく知らないんじゃないの?」と突っ込みたくなる単純化が多いと感じるだろう。冒頭にそうそうたるメンツの賛辞を掲載しているが、それほどの本ではないような気がする。
Posted by ブクログ
ジャレッド ダイアモンドの「銃 病原菌 鉄」に対するアンチテーゼ?。地域性を主軸に論旨展開したジャレッド ダイアモンドに対して、社会システムに注目した本書。一つの歴史の切り取り方、という観点で読んでも凄く面白い。下巻が楽しみ。
Posted by ブクログ
上巻では国家が繁栄するには多元的な政治システム、経済システムが必要だと豊富な事例により説明されている。主張自体は理解できる(というかなんとなく先進国では以前から共有されていると思われる)が、全体的にアネクドータルで冗長な印象を受ける。著者の一人が経済学者なのだから、この著書の中でモデルを呈示するべきとまでは言わないが、グラフ等で相関関係が納得できる記述にしてもらいたかった。
Posted by ブクログ
ちょっと内容が私の趣向とは違ってました。経済の発展とその国の政策制度で変わって来るというのは理解できますが、いかにも欧米的な理論でちょっと辟易してしまいました。
Posted by ブクログ
国家のあるべき「カタチ」を考える指針を提示してくれる。
読みにくいけど。
長期的な発展に必要なのは政治経済制度の違い、と言い切る。地理や環境的条件、文化の違いも関係ないのだと。
包括的な経済制度と収奪的な経済制度、政治制度においても包括的(多元的でもある)と収奪的(独裁的)なものの掛け合わせで4つの組み合わせができあがる。歴史的にこれら4つがどう変遷していくのかを説明する。
経済制度を決めるのは政治だ。だからこそ包括的な政治のもとでなければ経済の長期的発展は考えにくいともいう。共産国家の計画経済の限界をこう説明するわけだ。
中国も政治制度が変わらない限り、継続的な発展は見込めないだろうと言いきる。
そうかな。
多元的な政治制度はどのように誕生するのか? はうまく理解できなかった。ここには地理的な要因、文化の違い、そして何より偶然性があると思うのだけれど。
競争的な市場を継続するために、アメリカが市場の活性化のためにMicrosoftを独禁法に問うたことを思い出した。かの国はボーランドもたたいたし、鉄鋼、石油産業ではカルテルを解体した。そのフィロソフィーはすごいな。
それにしても名誉革命ってやっぱりすごいことだったのですね。