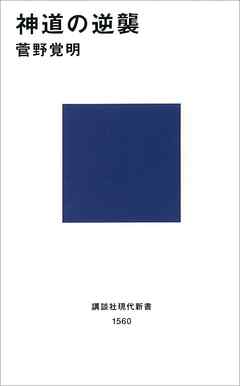感情タグBEST3
Posted by ブクログ
とても難しいです。
読んでは忘れ読んでは忘れをもうかれこれ3回ぐらい繰り返している本。
でも読めば読むほど面白いんだなこれが。
神道関連ではこの本が一番だと思う
神様って風景の反転のなかで直視され私達の日常を改めてそれとして確かめさせる日常の外部にある可畏きモノと言うことだけ覚えた
Posted by ブクログ
神の存在の曖昧さを考えると、この国それ自体の曖昧さをも考えざるをえなくなる。
天照大神、天皇、日本、戦争、アメリカ…。
「自分以外にも人がいる」から、他者があったから、思想が生まれ、神が生まれ、国家が生まれ、天皇が生まれたという気がしてならない。
要するに。
怪しい、不吉な「他者」を疑う心の働きが、歴史そのものなのではないか。
自らの安心・安定こそが追求すべき正しい事柄であるとして、様々な「ラベル分け」によって、時には排除によって、人類は幸福(とされるもの)を獲得してきた。
世間で事実とされている歴史の正体って、実はその程度のものなんじゃないのか。
「その程度」のものの表面のみをすくい取って、教科書に貼り付け、それを事実であるとしているだけなんだけど、学ぶ気力のない人間は(楽をしたがるから)本当にそれを信じて、おしゃべりを始める。
その無気力さが、神の曖昧さと交わって尊王攘夷思想に結実したのが、この島国の歴史。
「〜主義者」とやらに都合よく、歴史がねじ曲げられた。
歴史は、「あるようでない」の代表格。
「あった」としても、それは物凄く個人的な性質を持っているはずだ。
その個人的な編集作業を誰にどう引き継ぐのか、自分が参加したい社会をどう築きあげるのか…。
そういう「気付き」に歴史性が宿り、遺伝し、物を語らせ続けるんだと思う。
「もののあわれ」、「かなしさ」を人の最も根源的な神がかった経験であるとした本居宣長は、個性の重要さに気付いていたのではないか?
悲しさは、無常観とは違う。
喪失する悲しみが、自分がどれだけ「未完」であるかを物語るからだ。
「未完である」から、「可能性」がある。
子供の存在はただただ正しくて、どこまでも未完成。
だから、「世界は、生まれたもの、すなわち本来的に子供であるところの存在者を愛しかわいがる為に存するのである。(P270)」
おれは民族主義者でもなんでもない。
国家、民族、性別、宗教。
誰の目から見ても明らかな、人間の(最低限の)共通した性質、よく似ている部分を利用することでしか自分を主張出来ない、他人との違いを確認出来ない人というのは、悲しい人間だと思っている。
「個性」の大切さを知ると、自らの所属する社会のルーツを知る必要性が生まれる。
「学びたい」という欲求が、とても解り易い姿で目の前に現れる。
時々、快楽も一緒に現れる。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
日本人は神さまとどのようにつきあってきたのか。
古代から近世、そして今に至るまで、多様に展開された「神の形而上学」を検証。
[ 目次 ]
第1章 神さまがやって来た
第2章 神道教説の発生
第3章 神国日本
第4章 正直の頭に神やどる
第5章 我祭る、ゆえに我あり
第6章 神儒一致の神道
第7章 神道の宗源は土金にあり
第8章 危ない私と日本
第9章 人はなぜ泣くのか
第10章 魂の行方
結び 神さまの現在
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
友人に借りました。最初は、自分では読まないジャンルなのでしんどいかな、と思いましたが読みやすかったです。自分の国の成り立ちを知ることができて○。
Posted by ブクログ
神道の内側、というか教義無き教義を見ていく意欲作。神をおとなう「客人」(まらうど)として捉える。この見方に合点がいった。著者の「力量」が見える。p77
「このように、神国という言葉は、日本という国の神秘性や優越性を直接言い表しているわけではない。神と人との独特な緊張関係において統一の成り立っている特殊な国情を第一義としてあらわしている。天照大伸の命によって天皇がこの国を統治することが定めれた時点に確定し、それが天皇のある限りに続いているのである。万世一系の天皇の統治とは、国柄の優秀性を表すものではなく、神国の特異な内部構造の要の位置に、神と人とを媒介する天皇という軸があるということを意味している。」
吉田神道から、垂加神道、北畠親房の「神皇正統記」に於ける神道論など、気づかなかった論理の展開があって、読ませる一冊。
天皇の統治者としての側面が表、祭祀者としての側面が裏にある。この裏を自律させる方向が神道教説の発生を促した。
引用
「 神の国のそのすがた
北畠親房の『神皇正統記』は、次のような有名な書き出しから始まる。
「大日本(おおやまと)は神国なり。天祖(あまつみおや)初めて基をひらき、日神(ひのかみ)(天照大神)ながく統を伝給ふ。我国のみ此事あり。異朝には其たぐひなし。此故に神団と云也。」
このくだりは、戦前・戦中のわが国においては、まさに日本が「家系、血統、或ハ特殊ナ
ル起源ノ故ニ」「他国二優ルトスル主義」を初めてそれとしてはっきり規定した文言として
称揚され、いわゆる皇国至上の考えを端的にあらわすスローガンとみなされてきた。確か
に、『日本書紀』神話の伝統を背負うわが国の統治のありようを、「我国のみ此事あり。異
朝には其たぐひなし。此故に神国と云也」と定義しきった点は、『神皇正統記』の大きな特
徴であるといえる。近世の国学者や、儒学者のある一派の人々は、北畠親房のこの定義を、
神の子孫が治めるという神聖性、および王朝の交代がなく囚が安定していること、という
二つに要約し、それをもって日本が他国に優れていることの根拠とした。親房のいう「異
朝には其たぐひなし」は、神国イコール他国に優るという主張として読まれてきたのであ
る。
だが、第一章で見てきたことからもわかるように、神であるということを直ちに神聖な
もの、優れたもののイメージに置き換えてしまうのは、日本の神のもつ奇(くす)しく異しい、底知れぬ豊かな奥行きを、痩せ枯れた抽象へとすり替えてしまうことになる。繰り返しいう
ように、日本の神は、真にして善なる超越者などという単純なものでは決してない。神は、のどかな田園風景と集中豪雨で泥につかった田畑とが、あるいは愛らしい飼い猫と敵の喉
笛に喰いつく化生の猫とが、同じでありつつ異なるという連続と断絶のうちに、いわば景
色の反転それ自体としてあらわれている何ものかである。その限りで、神は私たちの日常
の道徳の延長上にとらえることはできない。神国イコール他国に対する優越という理解に
は、神を道徳的な善なるものにみなそうとする近世・近代的な先入見が強く作用している
といわざるをえないのである。
『神皇正統記』の記述を注意して読めば明らかなように、この文言のどこにも、神国であ
るということは正しく優れていることだとは書いていない。他国よりも優れているとする
読みは、神とは正しく優れたものだという先入見から出てくるに過ぎない。そして、北畠
親房の考え自体も、神国の優越といった主張とは、おおよそかけはなれたところにあるの
である。
では、親房のいう神国の本当の姿とは、一体どのようなものだったのであろうか。
この国の初発のありようを国常立尊が方向づけ、天照大神の命によって天孫が統治する
という形でこの図の形は確定した。『正統記』冒頭の語る神国の規定はこのようなものであ
った。この文言を皇国の尊貴性を説くものと解する読み方は、この箇所を、国家の統治形
態のゆるぎなきことが神によって約束・保証されていることを意味するものと読む。それ
は、王朝が一定しない他国(とくに中国)と比べたときの、わが国の「団体」の磐石さを示す
のだとされる。天皇による統治の絶対性を賛美するこの理解の仕方は、しかし、逆説的な
言い方になるが、実のところ全く天皇の立場に内在しないがために出てくる誤解なのであ
る。
親房は、南朝の重臣として、天照大神の正統たる天皇を、天孫降臨の際天孫に随侍して降った天児屋命(あまのこやねのみこと)の嫡流たる藤原氏が補佐する為政(摂関体制)のあるべき理念を追究した。
南北朝動乱のさ中で、すでに実質を失っていた天皇の為政の復興のために奔走していた親
房が、「日神ながく統を伝」えた天孫降臨神話の中に読みとろうとしたのは、神話の記述に
よって天皇の統治が保証されているなどという気休めではなく、天皇が統治するというこ
とが一体何を意味しているのかということであった。そのことの意味を正しくとらえ、そ
れにかなった為政が再び実現するならば、天地の初めに示されたこの国のあるべきありよ
うは必ず復活するはずだと、親房は考えたのである。
親房はいう「代(よ)くだれりとて自ら苛(いやしむ)むべからず。天地の始は今日を始とする理なり」と。
「神国の権柄武士の手に」前掲『太平記』〉帰してしまっている今日においても、神と天皇と
が根源的において一であるというこの団の基本のあり方は変わっていない。「神道に違(たが)ひては一日も日月を」戴くことができないという、この国のあらかじめ約束されたありように
かわりはないのであり・・・・。
p88三種の神器と「正直」
この国は、神を祭ることでのみ、国として保たれるのだ。親房は、このように考えた。三種の神器の象徴の内に彼が読み取ろうとしたのは、まさにこの点、つまり天皇が神を祭ることでこの国が治まるということの実質的な内容なのであった。親房はそれを、「政の可香にしたがひで御運の通塞あるべし」ととらえる。そしてこの「政の可否」の基準を示すのが、三種の神事なのである。
三種の神器は、為政のありようとして次のようなことを象徴するとされる。
「此三種につきたる神勅は正く国をたもちますべき道なるべし。鏡は一物をたくはへず
私の心なくして、万象をてらすに是非善悪のすがたあらはれずと云ことなし其すが
たにしたがひて感応するを徳とす。これ正直の本源なり。玉は柔和善順を徳とす。慈悲の本源也。剣は剛利決断を徳とす。智恵の本源なり。此三徳をあわせ翕受(あわせうけ)ずしては、天下のをさまらんことまことにかたかるべし。」
荒ぶる神の跳梁する混沌を、治まれる世へと反転させた動力は、正直・慈悲・智恵の三徳
であった。「天地の始」における景色の反転がこの三徳によってなされたということは、衰
えた今日の世にあっても、この三徳が為政の上に実現されるならば、ただちに乱世を治世へと反転することができる。「今日を始とする」と説く親房の信念は、このようなものであった。
親房は、三徳の中でも特に、正直を重視する。正直は、天照大神そのものである鏡に付
された徳である。『神皇正続記』 には、『倭姫命世記』 や『宝基本記』 に記された「正直を先とすべき」 ことを示す天照大神の託宣が三つ載せられている。
日月は四州をめぐり、六合を照すといへども、正直の頂(いただき)を照すべし。
神はあまねく世界を照覧する。しかし、神が最も親愛するのは、正直な人々である。正直
であるとは、「左を左とし右を右とし」て「太神につかふまつ」る、平凡で素朴な人々のあ
りようである。巾ヨたり前を当たり前として行う人々こそが、忠実に神の祭りを全うするこ
とができる。当たり前を当たり前にということこそが、為政の根本なのでもある。
神を祭ることに忠実な人々のありようとしての正直こそが、神団の為政の根本原理であ
ると親房は考える。最も深く神を引き受ける人々は、平凡で素朴な人々である。それゆえ、
平凡で素朴な人々の当たり前の生活こそが、神を祭る団である神国の本当の内実である。
平凡な日常世界の持つ重み、奥行きを真に知る者こそが、神を祭ることを全うできるので
ある。
Posted by ブクログ
――――――――――――――――――――――――――――――○
人々の平和で豊かな生活はお客さまとしての神さまを上手にもてなすことで実現するというのが、日本人の一つの価値体系の根拠をなすという見方ができる。(…)お客さまに良い物(幣帛)を差し上げ、その見返りないしお下がりで豊かに暮らすというのが、日本人の神さまとの付き合いの基本である。18
――――――――――――――――――――――――――――――○
神であるということを直ちに神聖なもの、優れたもののイメージに置き換えてしまうのは、日本の神のもつ奇しく異しい、底知れぬ豊かな奥行きを、痩せ枯れた抽象へとすり替えてしまうことになる。日本の神は、真にして善なる超越者などという単純なものでは決してない。79
――――――――――――――――――――――――――――――○
朱子学的な儒学が、人間を道徳的な存在者と定義し、道徳が完全に実現された人倫世界を理想としていたことと比較していえば、国学者による人間の定義は、歌を詠む存在者ということであり、その理想はすべての人が歌人として開花する世界なのである。202
――――――――――――――――――――――――――――――○