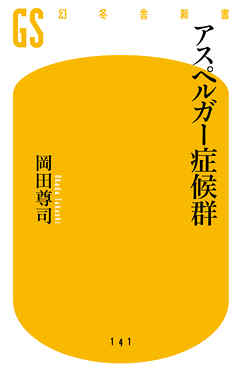感情タグBEST3
Posted by ブクログ
アスペルガー症候群とは知的障害、発達の遅れを伴わないASDのこと
(ASDは「自閉症」「高機能自閉症」「アスペルガー症候群」の総称)
アスペルガー症候群の傾向を持った人でも、診断基準をきちんと満たすのは一般人口の0.5%程度
それよりもはるかに多いのが、診断基準の一部を満たす特定不能の広汎性発達障害である
どちらの場合にせよ、大人になるにつれ診断名が変わるか、なくなる場合さえあるらしい
ASDは自閉症スペクトラム障害とも言われるように、軽度/重度といった線引がなく、スペクトラムの中には「健常」も含まれる
つまり、自閉症スペクトラム障害にみられるような特徴は、実は程度の差こそあれすべての人が持っているのだ
それを元に考えれば、誰にとっても、この障害の特性を知ることでその人らしい人生を歩むためのヒントがもらえるのではないかと思う
✏人とモノの違いは、顔をもつか、もたないかだとも言い換えられる
✏現代にアスペルガー的な人が増えているとすると、それは、アスペルガー的な遺伝子をもった人が子孫を残しやすくなっているということである。
✏唯一の欠点といえば、それは遺伝的な問題だろうか。似た者夫婦仮説について述べたが、遺伝学的には、自分と傾向が似すぎている人と結ばれることは、遺伝的な偏りを強め、とても優れた組み合わせになることもあれば、負の側面を強める場合もある
Posted by ブクログ
アスペルガー症候群と一言で言っても、症状は様々であり、程度の差も大きく、また環境的影響もやはり大きいようである。
実体験としてアスペルガー症候群と思われる方とも仲良くしていましたが、他の人から拒絶されているなと感じる場面は何度も目にしました。
その知人は問題行動と捉えられるような行動をすることも多々あり、その行動自体は問題だと私も思いましたが、必ずしも悪気があってしている訳ではないですし、何を言っても変わらないという訳でもないので、こういった本を読んで一人でも理解がある人が増えればなと思いました。
アスペルガー症候群っぽいから、なるべく関わらないでおこうではなくて、アスペルガー症候群のこういった傾向が見られるから、こういった接し方をすればいいんじゃないかというところまで考えられる人が増えれば、より多くの人が生きやすくなるのではないかと思います。
また、アスペルガー症候群の子供と接する際に気をつけることも書かれていましたが、これは症状の有無に関係なく大事なことだと思ったので、子育てに悩む方や多くの子供と接する機会がある方にも是非読んでいただきたいなと思いました。
Posted by ブクログ
とてもわかりやすく、知りたいことにまっすぐ答えて(応えて)くれた。新書の鑑みたいな本。
アスペルガー症候群とはなにか?特徴的な症状、診断基準、医学的(脳や神経の生理学的)な観点からみた事象や考えられる原因が前半で、後半はアスペルガー症候群の人とどう付き合えばいいのか?親、教師、同僚(上司)の観点からアドバイスしている。
印象的なのは、アスペルガー症候群に特徴的な行動や発想が現代社会ではイノベーションとして強く必要とされていること、そのためにアスペルガー症候群ならではの長所を活かしつつ周りとうまくやっていくためにどうすればよいかを具体的に挙げていること。歴史上の偉人を多くとりあげて「この方もアスペルガー症候群だった、こういう特徴的な行動があった、それをこう活かして偉業を成し遂げた」という記載も多い。
しかしそれより何より一番の驚きそして収穫は、私自身が本書を読みながら癒しあるいは救いを感じたこと。
アスペルガー症候群の診断テストをネットでみつけて何度かやってみても該当しないし、本書に載っている診断テストでも「違う」という診断結果になるものの、本書に登場する有名無名の該当者の言動やその背景にあるものの見方や感じ方が驚くほどしっくりくる。読みながら何度も「ああ、分かってもらえている。受けいれられている。」という静かな感動と安心に包まれた。
おまけ。ビジュアルな工夫や補助はほぼゼロで、文章と構成だけでここまで広く深く易しく分かりやすく的確な解説が可能ということを賞賛したい。岡田尊司さんは過去に5-6冊ほど読んで概ね好意的な印象を持っているのでバイアスがあるのかもしれないが。
Posted by ブクログ
アスペルガー症候群について知りたくて読書。
カウンセラーやセルフケアの勉強をし始めてから特に耳にするようになったアスペルガー症候群。いったいどのような症状で、回りにいる人たちはどう対応すればいいのかを理解したい。
ビル・ゲイツなど現在の著名人、歴史的な有名人も含めた事例を多く紹介している。日本人が少ないとレビューで書いている人もいるが、現役で活躍する日本人は誤解を与える恐れがあるので紹介しづらいのではないかと思った。
分かったことは、
(詳細に読み取ることはできなかったが)男性の方が多いこと。
障害の程度は家庭教育など思春期の接し方が大きく影響を与えること。
先進国と途上国では先進国の方が多いこと。
発症事例は年々増加傾向にあること。
注意欠落・多動性障害(ADHD)と類似、または連動すること。
無知から偏見と差別が生まれそうな感じもするので、正しく理解することが何よりも重要かと。
アスペルガー症候群の事例を見ると、自分にも十分に当てはまる要素があることが分かる。同時に得意な才能、技能もないので、厳密には該当しないと知る。もし私がアスペルガー症候群なら今頃は…なはずだし。
マイルール好き、妙なこだわりを持つ、一人での行動を好む、依存傾向が強い、集団競技が苦手、字が汚い、語学のセンスがないなど誰しも該当する要素は持ち合わせているようだ。その意味では私はアスペルガー症候群に近いとも思える。
エジソンやアインシュタイン、ビル・ゲイツ、スティーブ・ジョブズなどのように才能を開花させて成功する人たちは一部で、多くが空気が読めないKYな人と扱われている人なのではないかと思う。
アスペルガー症候群はIQは正常であり、前頭葉に何らかの障害があると推測されているそうだ。
本書でも触れられているが、発達障害であるパーソナリティ障害に近い部分を多く感じる。その辺も含めて今後、学びたいと思う。
私にとって重要な情報は、アスペルガー症候群やパーソナリティ障害を持つ人と接する周りの人たちの対処方法やメンタルヘルスマネジメント。人は往々にして目に見えない障害には優しくできないので難しい点だ。
読書時間:約1時間20分
Posted by ブクログ
著者である「岡田尊司」さんの書籍はとても読みやすいので、個人的に著書の多くを買っています。その中でもアスペルガー症候群に特化して書かれたこの書籍は、アスペルガー症候群の全てを把握できると言っても過言ではない一冊だと思います。
保育の現場で難しくなっている発達障害の一つであるアスペルガー症候群の理解を深める一冊として読んで頂くのはいかがでしょうか?
Posted by ブクログ
もともとアスペルガーっぽいねとは言われていたけれど、先日、妻の働く保育園での自閉症の子の花椅子を聞き、あまりに自分の小さい頃と同じで驚き、この本を手に取りました。
生きづらさは常に感じているので、薄々わかってはいましたが、かなり自分に当てはまるところが多い。特に人間関係の部分や、同じことをずっとやってられるところは全くそのもの。
人には、「この前言ってたことと違いますよ」とか、「ルール決めたのはそっちなのになぜ守らないんですか」とかすぐ言ってしまうのだけど、すぐ偉そうだとかうるさいとか言われてしまう。純粋に疑問に感じたから聞いているだけなのに、どっちがおかしいんでしょう?いつもミッシェルの「世界の終わり」の冒頭が頭をよぎる。
奥さんにもこの本の話をしたら、「私がすごく我慢してるのわかるでしょ」と、こっちが何も感じず迷惑をかけているだけのように返されたので、現在絶賛凹み中です。
Posted by ブクログ
アスペルガーを扱ったものではかなりの良書。自閉症との区別がハッキリされており一見普通に見えるのが辛い現状を上手く把握されていた。
言語力は高いが当たり前の状況処理ができないのは辛いの一言である。
やはり1番はカミングアウトと周囲の理解が大切である。
怒りに対するアプローチをもう少し詳しく知りたかった。
Posted by ブクログ
軽症アスペルガーの大人に関する情報という点ではどの本も似たり寄ったりだが、事例が載っているので、参考になる部分は多かった。読みやすいのも良い。
Posted by ブクログ
アスペルガーについての概要がわかるが、アスペルガー症候群の人とそうでない人のどちらが正常なのか、わからなくなってきた。もしも世の中がアスペルガーの割合が増えてきたら、そっちのほうが普通になるだろう。
また、科学者、哲学者、政治家、芸術家、経営者など多くの偉人がその兆候がみられたというのは、逆に考えるとアスペルガーであるほうが偉くなれるということ?
Posted by ブクログ
実直な記述でわかりやすい内容に仕上がっている。いるのだが、本書の内容を踏まえて上司に相談したら「対人関係のトラブルなんて誰でも抱えてる。お前はコミュニケーション能力を学ぶのを怠けたいだけだ」と言われて絶望した。もう駄目だ
Posted by ブクログ
アスペルガー症候群とは、ざっくりと言ってしまえば、こだわりが強く、対人関係が不器用な人のこと。
アスペルガー症候群について、行動パターン、症状、診断方法、発祥のメカニズム、原因、付き合い方、特性の活かし方、改善方法が記載されており、アスペルガー症候群を理解するために入門書として参考になりました。
自閉症との最も大きな違いは、言語と知能の発達に遅れがないこと。自閉症では、言語の遅れが必発なのに対して、アスペルガー症候群では、言葉の発達の遅れが見られない。
アスペルガー症候群では知能は正常範囲で、むしろ平均以上のことが多いが、自閉症では、低下が見られる場合が多い。
アスペルガー症候群は、社会的常識がわかりにくく、自分の欲求しか見えなくなりがちで、相手の都合や反応に関係なく、一方的な行動に走ってしまいやすい。
Posted by ブクログ
読んでいて、そうそうそうそう!!
ってなるくらい、きれいな言葉でアスペルガー症候群の方がとる行動について書かれている。
アスペルガー症候群のひとってどんな感じ?と言われても、ぽやーっとしか説明できないから、この本をかって、これを読め!と言ってやりたくなる感じ。
対応の仕方とかをタイプ分けしてかいているけど、そこについては、やや疑問が残る。有名人を引き合いに出して、説明する感じは、岡田さんらしい書き方です。
Posted by ブクログ
エジソン、アインシュタインからヒッチコックまで、身近な具体例と共に書かれているので、とてもイメージしやすい。
そして、対処方法も具体的かつ実践的で分かりやすい。
実践する場面はすぐにはないですが、一般の育児に当てはめて考えても、とても勉強になる一冊。
Posted by ブクログ
<目次>
はじめに
第1章 アスペルがー症候群とはどんなものか
第2章 アスペルがー症候群の症状はどのようなものか
第3章 アスペルがー症候群を診断する
第4章 アスペルがー症候群の脳で何が起きているのか
第5章 アスペルがー症候群が飢えている原因は何か
第6章 アスペルがー症候群と七つのパーソナリティ・タ イプ
第7章 アスペルがー症候群とうまく付き合う
第8章 学校や家庭で、学力と自立能力を伸ばすには
第9章 進路や職業、恋愛でどのように特性を活かせるの か
第10章 アスペルがー症候群を改善する
おわりに
<内容>
かなり丁寧に説明をしてくれている。が、対策などの具体性は表面的かも…。新書なのでしょうがない部分でしょう。また、あの人もこの人もアスペルガーだったかも、という話が多く、驚いたというか納得と言うか…。
Posted by ブクログ
ちまたで噂の『アスペルガー症候群』について専門家の立場から詳しく解説した一冊。
今までこの手の発達障害と言われる症状の人の扱いついて、カウンセリングの立場からの意見を聞く機会はあったけど、アスペルガー症候群そのものについて詳しく知る機会は少なかったので、非常に勉強になった。
そして、自分も含めて誰しもアスペルガー症候群に該当する可能性があることもわかった。
Posted by ブクログ
タイトル通りの病気? 障害について書いてある本です。
何だか、眉唾のような本もこういう本の中にはたくさんあると思っていたんですが、この作者さんについては、それなりに信用できる人だと、何かの時に教えてもらったので、物は試しで買ってみました。
というよりも、普段、新書なんてジャンルの本を読むことがあまりないので、この本がどの辺りの位置に当たるのかがイマイチよくわからない。
私の勝手な先入観では、それぞれの分野の専門家が、自分の専門のことについて自分の信条のままに書く本だって買ってながら考えているんですが、何か間違っているかしら?
なので、新書については自分の信条について、作者さんがなるべくそれが信じられることだ、とわかりやすく説明する話だと思ってるので、その「信条」の部分に合わなかったら、ものすごく反発を覚えざるをえない本、という認識をしています。
専門書よりももう少し主観的な事実が詰められている本。
と自分に言い聞かせながら読んだ本でした。
で、読んで見た感想なのですが、私が仕事で関わることがある彼らのことについて、とても丁寧に書かれていました。
この本の内容は、この病気が何の病気なのか知りたい。どうやってこういう人たちに関わっていったら言い聞かせのかを考える上ではとてもよい本だとは思います。
「自分はそうだ」「そうかもしれない」と考えている人たちにとっては、こういうことをすればいいのかという、ひとつのヒントになると思います。
ただ、「じゃぁ、どうしたらいいんだ」という人にはあまり向かない話だと思いました。
確かにそれならどうしたらいいと言うことも、多少は書いているのですが、実際にそれを生活の場で実践するためにはどうしたらいいのかというところが、少し弱いような気がします。
なので、どういう目的でこの本を買うかというところが問題になってくるのかなぁと思います。
こういう病気がどういう病気なのか知りたい、ということであれば割と基本的なことについて教えてくれるのでとても役に立つと思います。自分がそうではないかと考え、読み始めるのにもいいと思います。
ただ、もう自分がそうなんだと考えていてもっと何をどうしたらいいだろうと思っている人間には、物足りないと思います。
まぁ、そもそもがそう言う対象者向けではなく書かれている本だと思うので、そういう本が読みたい人は他の本を読んでみてください。
つまり、この病気について知ろうと思った人が、最初に読むのはいいと思いますが、詳しいことを知りたいと考えたら他の本を読んだ方がいいかなと思います。
まぁ、あくまでも専門書ではなく新書なのでその辺のことをお忘れなく。
それさえ忘れなければ、書いている内容としては私の知っていること も大体合っていたと思いますし、読んでいて損はないかなぁと思います。
本当に、入り口のためのおはなしかなと思います。
Posted by ブクログ
言葉は聞いたことはあるが実際はどのようなものか、はっきりとわからなかったアスペルガー症候群
その特性から支援方法までが分かりやすく実例も交えて書かれている。
教育現場に関わる人だけでなく、仕事で人に関わる方なら必読の一冊かと思う。
Posted by ブクログ
近年、度々紙面などで取り扱われるアスペルガー症候群について、その特徴や付き合い方、良いところの伸ばし方などが載っている本。
この類の本はまだ読んでいなかったので詳しいことはこれから知っていこうと思っている。
とりあえず、この本で分かったことは(以下アスペルガー症候群を「症候群」とする)
・ローナ・ウィングという学者は症候群を積極奇異型・受動型・孤立型の三つに分類した。18歳移以降ではさらに7つのパーソナリティタイプに分化していくと考えられている。
・大きな症状として社会性の障害・コミュニケーションの障害・反復的行動が挙げられる。
・この症候群が増加している背景には遺伝的要因・環境的要因(胎児期男性ホルモン説や自己免疫説など)・心理社会的要因が考えられている。
などであった。
症候群であった、またはあったであろう著名人(例えばビル・ゲイツ、エジソン、ヒッチコック、ダーウィン、アインシュタインなど)のエピソードが所々に散りばめられていて、彼らの性格・生育歴を大まかに知るのにも使えるかも知れない。
本の前半は症候群の発見の経緯・症状の概略であったが、後半は症候群である人との関わり方に大きくページを割いている。
参考文献まで含めると271ページという、新書にしてはボリュームのある本ではあるが、今後症候群である人と接することは十分に考えられるので、一度目を通す価値はあると思う。
Posted by ブクログ
学ぶうちに子供のころ文章が読めなかったり、状況テストができなかったり、かつての自分にもこの症候群に起因する様々な症状があることが分かった。この症候群の人が普通になりたいという願望を強く持つ点にも共感できた。
Posted by ブクログ
教養新書にしてはかなり専門的であった。基本的にアスペルガーをポジティブに個性としてとらえ書かれている。
筆者も述べていたが、アスペルガーと判断するための明確が基準がないことが問題ではないかと感じた。白黒はっきりつけることが困難で、グレーゾーンの存在を今後どう扱うかが鍵となりそう。
アルペルガー症候群の社会的認知は近年で格段と上がっているはずなので、今後の医療の発展に期待したい。
Posted by ブクログ
大笑いしながら読みました。もちろん、そんな内容の本ではないのですが。
義母から妻が譲り受けた本です。義母は読みながらアンダーラインを引いたりコメントを書き込む癖があるようで、新たな症例が紹介されるたびにアンダーラインを引いて、「○○さん?」とかコメントが入ってました。知ってる人も出てきます。「お父さん?」とか「私?」というのもありました。何を考えて人にあげちゃったんでしょう?
医学的な診断は置いておいて、こう言った症例と似た行動を繰り返す人はまわりにも沢山いますね。当てはめるのは良くない考えかもしれませんが、少し気が楽になるのは確かです。
基本、短所を無くすのではなく長所をのばしていこうという本ですので、治療法とかはあまり触れられていません。
アスペルガー症候群を少しでも前向きに捉えられるよう配慮してか、本書の前半にはアスペルガー症候群の有名人や社会的成功者が列記されています。
スティーブ・ジョブズ、アインシュタイン、トマス・ジェファーソン、チャールズ・ダーウィン、セーレン・キルケゴール、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ハンス・クリスチャン・アンデルセン……これ以外の存命の方も含まれているのはどうかと思いますが、この有名人疾患者名簿を見て、少しでも前向きに捉えられるのであれば、それも悪くはないのかも知れません。
Posted by ブクログ
アスペルガー症候群、今はASD自閉症スペクトラム症候群に含まれますが、こだわりや対人関係の苦手さなど、行きにくさを抱えており、周りの人の特性への理解、関わりが大切だと感じました。まずはそういう特性があると理解し否定しない関わりを意識したいと思います。
Posted by ブクログ
印象に残った言葉
・親がその子のために与えることのできる最上の贈り物は、安心感と自己肯定感である。
第6章と7章が特に参考になりました。
また、私はプライベートでは、きまぐれで、よく予定変更をするタイプなので、それはアスペルガー傾向の人には強いストレスを与えることがわかり、気をつけようと思いました。
Posted by ブクログ
日々の様々なコミュニケーションのために。
素人が決めつけで相手を予測することは問題になりそうだが、コミュニケーションの幅、対人対応の幅は広がるだろう。
Posted by ブクログ
社会の中に存在する軽度のアスペルガータイプの人達の多さにかなり衝撃をうけた。自分自身も例外ではないような気がする。だからこそ、みんなの「生きやすい」が私にとっても「生きやすい」ことにつながる気がするので、日々のお仕事でも特性に則したコミュニケーションをとることを念頭におきたい。
Posted by ブクログ
職場にアスペルガー症候群の方がいます。言われなければ分からないし、こだわりが強い人、人の気持ちが分からない人、ぐらいで済ましてしまいそうな感じです。
そういう障害だから仕方ないんだと頭では分かっていても、一見普通の人と変わらないので、どうしてもムカついてしまったり、どう接していいか分からなくなることが多々あります。もっと上手く関わっていくにはどうしたらいいかと思い、読むことにしました。
程度や症状にもいろいろあるんですね。アスペルガーの中でも正反対の特徴もあるようで、一概にこういう症状だとは言えない感じ。診断するのがとても難しそうな障害だなと思いました。
接し方や対処の仕方については、教育面の要素が強く、正直私の状況にはほとんど役に立ちそうにありませんでした。50代の方なので、今から性格を直すと言うのは難しいし、年上の方に教育というのは立場的にできないし…
筆者もこの年代の方が生きづらさを抱えているのではとおっしゃっているので、大人向けの内容や、家族以外の人がどう接したらよいかなど、少し違った見方の内容も是非出して欲しいです。
アスペルガー症候群のお子様を持つご両親には、とても参考になる内容なのではと思いました。アスペルガー症候群の方が増加傾向にあるとのことなので、世間にもっと理解され、新たな才能が開花することを祈ります。
Posted by ブクログ
アスペルガー症候群の方との付き合い方を以下に記します。
1)ルールや約束事を明確にすること
(日課をパターン化して視覚化する、ルールはできるだけ具体的にする)
2)本人の特性に合った役割を与えること
(得意分野の一つから広げてゆく)
3)聴覚や嗅覚などの感覚が過敏なので、その点を配慮すること
時間管理など本人の弱い部分を上手にフォローしてあげること
(お気に入りのことは、苦手な活動の後でする)
4)安心感と自己肯定感を与えるようにすること
(否定的な言葉をつかわず、できるだけ肯定的な言葉を使う)
5)「普通」を押しつけることなく、良いところ探しをすること
(良いことはまめに褒めて強化する)
6)勤勉さを身につけさせること
(ご褒美は、1回分は控えめで、積み重ねられるものがよい)
Posted by ブクログ
基礎知識を仕入れる為に読んだ。
領域がぼやけがりで千差万別だからそれぞれの人を見て丹念に対応していくのが一番という結論って専門家でなくても出せそうな・・・と思っちゃうんだけどまだ概念が出来て日が浅いしこんなものなのでしょう。