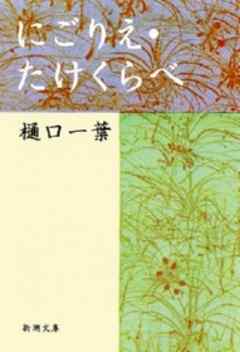感情タグBEST3
Posted by ブクログ
不定期で読む古典の名作、今回は樋口一葉・たけくらべ。明治時代の言葉そのもので読めるか?読めるわけがない。。。あらすじを読み2回目-->分かるわけがない-->現代版を読みこれこれ!ということで現代版で理解できた。親の職業によって美登利は花魁、信如は坊さんとなる運命である。この2人の噛み合わない恋心が何とも言えず切ない。吉原に行く美登利が門扉に見つけた水仙の花。信如は美登利に恋心を伝えたが時すでに遅し、2人は永遠に面と向かって恋心を伝えることができない運命だった。親による職業が決まるってなんて不条理なんだ。⑤
Posted by ブクログ
一葉が漱石・鴎外に比べて(たぶん)読まれていないのは、その文体がハードルだからだろう。かくいう私も、一葉は本書が初めて。長時間移動する機会ができたので(つまり、他に読むものがないので投げ出せない)、挑戦してみた。
案の定、細部まで追うのには苦労したが、短編なのでとりあえず最後まで読み切る。で、また重要な箇所を読み返すと、だんだん理解が深まった。ネット上にはあらすじ紹介もあるので、後でそれで確認することもできる。
肝心の内容だが、文体の美しさや女性を描いたことの意義は言うまでもなく、展開の巧みさを感じた。なので、先ずは予備知識なしに読む方が、読後の印象は深まると思う。所収作のなかでは「十三夜」が比較的読みやすく、かつ名作なので、これを先に読むのがよいかもしれない。
一葉が残した小説は22編だそうだ。本書は本文250ページ・計8編だけだが、これだけで3分の1以上ということになる。夭折が惜しまれる。
Posted by ブクログ
思っていた以上に、人間のレパートリーが多くて驚きました。貧しさに苦しむ庶民の短編しかないのかと勝手に思っていました。それぞれの短編で、もっと色々な種類の複雑な惑いが見事に人間関係の中に投影されていて、文語体なのも気にならないほどでした。
Posted by ブクログ
週間新潮「黒い報告書」シリーズの原点はこれか「にごりえ」、新派が上演しそうな「十三夜」は調べてみると「大つもごり」とともに新派の演目にちゃんと載っている!、そしてこれぞ珠玉の名作「たけくらべ」、一葉の肖像がわが国紙幣に採られたのもむべなるかな、参りました。
Posted by ブクログ
貧にまみれた切々とした話だが、不思議に読後に寒々としたものはない。人情が書かれているからだろうか。句読点が少なく、カギかっこもないので読みにくいが、次第に慣れる。音読するとわかりやすい。今はあまり使われないわかりにくい言葉には注解ついているのでありがたい。
Posted by ブクログ
文語体の文章が美しく、声に出して読んでみたくなる。一葉の描く明治の女性は、決して幸福ではなく、むしろ眼前に開ける未来は暗いのだが、格調高い文章のせいか、女性の姿がほの明るく感じられる。
(2015.10)
Posted by ブクログ
独特の文体➕江戸言葉と奮闘しながら読みましたが、結果、樋口一葉の大ファンに。鉛筆で句読点と鍵カッコをつけながら、分からない単語は辞書でひいて、何だか外国語の本を読むような作業。意外と楽しかった。各話とも日本らしい、余韻を残す終わり方が良かった。
Posted by ブクログ
文章が秀逸。リズム感といい、恰好良さといい。またセンチメンタリズムな展開も見事です。
一方で解説も合わせて読むと、いかに(樋口一葉自身の状況に照らし、悲しさも織り込んだ)リアリズムに富んでいるかも分かります。
Posted by ブクログ
最初は読みにくかったが、慣れると、流れるような文体に圧倒される。
今も昔も、男女は変わらないのね、と考えさせられるお話。
あと、樋口一葉ってちょっと思い込みの激しい女性だったのかな、と思わせられる一文も。
しかし、樋口一葉は昔の女性にしては相当気が強い方だったんでしょうね。
Posted by ブクログ
流麗に縷々として続く文章は、その一筆書きのようなスケッチによって、驚くほど的確に描写していく。
その言葉の美しさはもとより、因果の説明をかほど大胆に消し去れるとは。
しかも今から百年以上も前に!
言葉自体は文語だけれど、内容はほとんど現代小説の、しかもかなり優れたものだ。
現代の小説は、『夜明け前』はもう書けないが、「樋口一葉」はまだ書けない、のかもしれない。
それほどまでの、奇跡。
Posted by ブクログ
九州大会で3位に入賞したときの朗読作品。
これのおかげで、いろんな人に覚えてもらって、「古典の声」なんて言われたりして、印象深い作品。
現代文ではないので朗読しづらいのだけど、プロが読むのを聞くと、日本語の美しさを理解できる。
Posted by ブクログ
「と」の識別とか受験生の時にやったなぁ。まったく覚えてなかった。でもそれを思い出してからはようやっと読めるようになった。
うまく言えないけどすごく好き。たけくらべのせつなさは現代の小説ではなかなか出せないと思う。今までよんだ近代小説と違って登場人物に好感が持てる感じが良かった。
Posted by ブクログ
なによりもまず、そのあまりにも美しい文章について触れるべきなのかも。言文一致が生まれて間もない頃の文章であるにも関わらず滑らかに流れていく言葉と、そんな時期だからこそまだ使われていた古文調の言葉遣いで述べられていくその文章は、読めば読む程に魅力が増していく。
そして、そこに描かれる物語の大半は、世間という荒波に翻弄され、風習という名の運命の荒野に投げ出された男女の報われぬ物語。社会の進歩に対して余りにも早く自我というものに目覚めてしまった、早熟の才故に描くことのできたあまりにも報われぬのに美しき物語。僅か25歳で天寿を全うする、その最後の1年間に書かれた本書には、踏み躙られても尚衰えぬ輝きというものがある。
Posted by ブクログ
2021年 32冊目
これほど美しい文学を今まで読まずにいたことは自分にとって大きな過ちでした。文語体なので主語がなく場面の切り替わりが急なので多少まごつきますが、現代文でこの繊細な筆致を堪能することはできなかったでしょう。
・たけくらべ
フィリップ・アリエスの「子どもの誕生」のように、当時の日本も子どもって観念はなかったんじゃ。年端をいかないうちから奉公に出て、居住地区間の争いがあり、当然のように運命を受け入れる。あどけない子どもたちと思いきや、初潮を迎え遊女の将来を悟ったり出家したりの登場人物の境遇、心情を推測するのが難しかったです。
最後の1ページ、慈愛と悲壮と諦観がちりばめられたこんな美しい文章があったのかと感動しました。
・にごりえ
情死する男がどうしようもなくて情けない。。お力さんは最期何を思ったのかしら。濁水の中を生き、自分は幸せになれないわと諦めの女性だったけど、心中であれ一方的に殺されたのであれ死の間際彼女の命は一番輝いたのではないかなと。
・十三夜
「当時の貧困ってロクな人生送れないな」と二作読んで感じたあとのラスト作品。お関さんは美登里や力と違って資産もそこそこな家の人妻だし、両親も健在…けれど彼女の孤独感や悲哀は先の女性に負けず劣らず。DV夫から逃げ出したものの子ども可愛さに心鬼にし、流れに棹さす生き方しかできない当時の女性たちのうらめしさ。
Posted by ブクログ
脚注にない言葉の意味を確認するため、いちいち辞書を引く必要に迫られることも屡々あろうが、何より時代背景が違うのだから、それは致し方ないと言うべきなのであろう。
最初は擬古文の読みにくさを感じていたが、よくよく考えれば、明治時代に書かれたものを現代の小説を読むのと同じスピードで読むこと自体が不自然なのである。ゆっくり一つ一つの言葉を噛み締めながら読んでいくと、自ずと意味も通じて、暫し明治時代にタイムスリップしたかのような気分を味わえた。
Posted by ブクログ
明治時代を逞しく生き抜いた女性を鮮明且つ生々しく描かれており、当時の社会を知るには適当な書物である。また、ぼかした表現があり、謎に包まれたまま終焉を迎える点は、読者を引き込む力がある。
Posted by ブクログ
ミドリもシンニョもじれったい……これが時代の差異というものなのだろう。ただ、大人になっていく時の精神の不安定さや妙な見栄、小細工はそう大して変わらないものなのでしょうか……。
Posted by ブクログ
文語体の小説。
「。」が「、」になってたりするため、慣れるまではちょっと大変。
しかし一旦慣れると、樋口一葉の美しい日本語による洗練された世界観にどっぷり浸れます。
Posted by ブクログ
文体に慣れるまでに時間がかかるけど、慣れてしまえば心地よい、さらさらとしたとてもきれいな日本語。
内容も興味深い話が多く、樋口一葉のすごさを感じた。
Posted by ブクログ
にごりえだけ読んだ。古典が苦手なので現代語訳と照らし合わせて読んだが、あの若さでこの物語を書いた樋口一葉は本当に素晴らしい逸材だと思う。当時の状況もこの本を読むと分かる。最後は心中したんじゃなくて無理心中のような気もする。
Posted by ブクログ
君知らずや、人は魚の如し、暗らきに棲(す)み、暗らきに迷ふて、寒むく、食少なく世を送る者なり。北村透谷 雑誌「文学界」1893
美人の鑑には遠いが、物言う声は細く清(すず)しく、人を見る目は愛嬌に溢れて、身のこなしが活き活きとしているのは快いものである。樋口一葉『たけくらべ』1895
樋口一葉『にごりえ』1895
されど人生いくばくもあらず。うれしとおもふ一弾指(短時間)の間に、口張りあけて笑はずば、後にくやしくおもふ日あらむ。森鴎外『舞姫・うたたかの記』
人は性欲の虎の背に乗って絶望の谷に落ちる。森鴎外『ウィタ・セクスアリス』
おんなが裸になって私が背中へ呼吸(いき)が通って、微妙な薫(かおり)の花びらに暖(あたたか)に包まれたら、そのまま命が失せてもいい。泉鏡花きょうか『高野聖ひじり』1900
まだあげたばかりの君の前髪が、リンゴの木の下に見えた時、前髪にさした花櫛の花のように美しい女性だと思った。島崎藤村『若菜集』1897
与謝野晶子『みだれ髪』1901
美しき花もその名を知らずして文にも書きがたきはいと口惜し。正岡子規『ホトトギス』1897 俳句
悟りという事はいかなる場合でも平気で死ねることではなく、平気で生きて居ることである。正岡子規『病牀びょうしょう六尺』1902
高浜虚子
※明治、②ロマン主義。自我・個人。日清戦争前後
Posted by ブクログ
少し読みやすめの古典だったー!
恐らくニュアンスわかってない。
森鴎外は読めたのにな…明治の女流文学ってこうなのか?
これしか読んでいないのでわからない。
良いシーンとか絵になりそうな情緒はわかるんだけど、細かなところがね。
句点がなく1章まるまる1文で終わっちゃうところなんかもあったが、文章の節回しは完璧。さすが古典。
裕福な男子が哲学だヨーロッパだと遥かな未来を見据えているのと同じ時代に、貧しい女性は見え透いた未来に一歩ずつ落ちていくだけ。
生まれと境遇が切り離せず、涙を飲んで生きるしかない。
今の日本社会もきついが、この時代も苦しい。
いつの時代に生まれれば幸せだったんだろう。
お金さえあればどの時代でも関係ないのかもしれない。
一瞬で消えた士族の誇りも捨てきれず、お金がなく苦しみぬいて亡くなった彼女を、5000円札に決めたのは誰だろう。目にする度、彼女の無念が脳裏を過ぎる。同時にその筆で稼いだ逞しさも。もう少しの間よろしくね。
Posted by ブクログ
★3.5 「たけくらべ」
文章が美しく、話はせつない。
でも美登利が遊女になる以外の道はないということが頭では分かってはいても、現代の感覚ではいまひとつしっくり理解出来ない。わたしたちは恵まれているんだな。
Posted by ブクログ
お札になるほどの人なので教養として読んでおこうと手に取った作品。
しかし最初の数ページ読んで後悔しました。
とっても読みづらくて。
一文が物凄く長いんですよね。
その上、話者がコロコロ変わるので誰が喋っているのか
とても分かりづらいという。
話の筋を追うだけでも苦労するという感じだったので
読み切れるかなと不安になりました。
しかし、当初の不安もどこへやらという感じで。
当然現代とは時代背景が全く違うわけですが
当時の文化や習慣などを思い浮かべながら読むのが
途中からは楽しくなりました。
表現が多彩で登場人物が生き生きとしていて惹き込まれていきました。
こういうのを文才というのかと思い知らされました。
Posted by ブクログ
樋口一葉、たけくらべ、という単語は知っていたが、実際に読むのは初めて。明治時代の女性の悲哀を描いた物語が8編。これらは、一葉の実体験から着想されているものらしい。どの女性も切なくはかない人生を送っている。描写は皆まで言わないまでも、雰囲気から伝えるようになっている。しかし、句点はあれど、読点がないので、こういう文体にはちょっと面食らうね。現代語訳を別に当たってみたい。
Posted by ブクログ
日本文学概論1の教科書。
「にごりえ」を授業で読みました。
「たけくらべ」は入試の音読の練習にも使ったなぁ。
一葉さんの世界観は嫌いじゃない。女性目線で入り込みやすいのかなぁ。
Posted by ブクログ
ううむ、さすがに難しい・・・。
幸田露伴や谷崎潤一郎以上に難解な文体で読むのにちょいと一苦労。
詩のような美しい日本語を楽しむのには良いかもね。
Posted by ブクログ
日清戦争後の「言文一致」運動を尻目に圧倒的な魅力を持つ文語体で書かれた樋口一葉の傑作である「にごりえ」、「たけくらべ」。同時代の同じく雅文体で記されている鴎外の「舞姫」ともまた異なった雰囲気を漂わせているように感じられる。これが二十五歳で夭逝した女性作家によって書かれたものであることを考えれば当時においては衝撃的であっただろうことが容易に想像される。