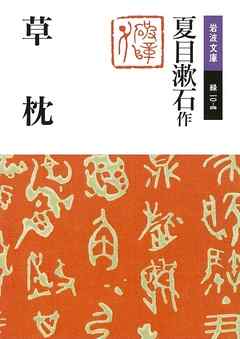感情タグBEST3
Posted by ブクログ
他の作品と同様、リズミカルな日本語が読んでいてとても小気味好い。凄すぎますね、一つ一つの言葉選び。正に文豪。
自分という人間を、芸術家という存在を、こうも深遠に描くことができるのは本当に圧倒されるし引き込まれる。分かりたい、と思いながら読むことができる。
私の未熟な読む力ゆえ分量の割に時間がかかったが、時間をかけるべき作品だった。それは間違いなくそう思う。
Posted by ブクログ
「非人情」とは「超俗」或いは「解脱」の露悪的表現か。智に働かず、情に棹ささず、意地を通さず。何物にも捉われない、自由な生き方ができたら…。でもそんな世界では、たぶん文学も芸術も、大したものは生まれない。「草枕」の境地に憧れる者ほど、その手の無為には耐えられまい。やっぱり人の世は難しい。
Posted by ブクログ
漱石さんが文豪たる所以はこれかという本著。
“智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。”という一文があまりにも有名だが、これは表す内容もさながら、リズムがとても心地良いのも一因ではないか。全体の描写も瑞々しく美しい文体からなっている。この本を読む為に適当な旅に出るのも悪くないだろう。
Posted by ブクログ
7/28
最後の章、汽車と舟の対比が面白い。
ただ一番は、風呂の場面で会話が一切ないこと。描写だけで全て書ききれる辺り、現代文学の力不足を感じる。
Posted by ブクログ
智に働けば角が立つ。情に竿させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。
昔も今も俗世間は変わらない。つくづく感じた文章だ。
あらすじには、「いやな奴」で埋っている俗界を脱して非人情の世界に遊ぼうとする画工の物語。とある。
ここでいう非人情とは、薄情とか情が無いという事では無い。ザックリ言えば、他者に煩わされないという事。
湯泉(ゆ)のなかで、湯泉(ゆ)と同化してしまう。流れるものほど生きるに苦は入(い)らぬ。
主人公が湯槽に浸かっているシーンだが、この文章は「本当にそうだなぁ。」と、深くうなづいた。
抗おうとすればする程、ストレスは溜まり苦しくなる。
湯水に流されるままに生きられたら、どんなに気楽か…。
本書は生き辛い世の中を如何に気楽に渡って行くか、その勉強になる事ばかりで、いつもは本に付箋を貼ることが無い私も貼りまくった(笑)
気になったフレーズも過去一だ。
漱石の作品の中でも、二番目に好きな作品で、唯一難点なのが読み難さ。特に漢詩の部分。
今度は、漢詩の部分に焦点を当てて、漱石の心中にお邪魔できたら…と、思う。
Posted by ブクログ
夏目漱石の本をちゃんと読んだのはこれが初めて。人里離れた旅館で画家が出会った人とのやりとりや妄想めいた話が淡々と描かれていて大きな事件がある訳ではないが、語彙なのか表現力なのか、難解な言葉ながら情景が目に浮かぶのがすごいなと。
夏休みに田舎で蝉の泣き声を聞きながら読むのにピッタリな本だと思った。
Posted by ブクログ
有名な智に働けば角が立つから始まる作品。俳句的な文体、漢文調で書かれているので、ややとっつきにくいが、ならてくればその独特の文体の世界を味わうことができる。新潮文庫解説の柄谷行人によれば、過去を切り捨てた近代文学に対しあくまでもそれらとともにあろうとした漱石。何かを表現しようとするのではなく、文体そのものを味わうことを求めた。筋自体も何かを表現しようとした刹那、宙ぶらりんのまま別の話に推移しており、独特な感覚を覚える。
Posted by ブクログ
【本の内容】
山路を登りながら、こう考えた。
智に働けば角が立つ、情に棹させば流される。
―美しい春の情景が美しい那美さんをめぐって展開され、非人情の世界より帰るのを忘れさせる。
「唯一種の感じ美しい感じが読者の頭に残ればよい」という意図で書かれた漱石のロマンティシズムの極致を示す名篇。
明治39年作。
[ 目次 ]
[ POP ]
『国家の品格』いわく文学・哲学・歴史・芸術・科学といった、何の役にも立たないような教養をたっぷりと身につけていることが真のエリートの条件の一つという。
ならば、役に立たない教養を身につけているだけではなく、役に立つことはしない百けんは超エリートではないだろうか。
その師にあたるのが、漢文に詳しく英国留学の経験がある明治のインテリで、日本を代表する文豪・夏目漱石。
『草枕』は、その文章芸を堪能できる1冊だ。
山路を登りながら、こう考えた。
智に働けば角が立つ。
情に棹させば流される。
意地を通せば窮屈だ
。とかくに人の世は住みにくい。
という冒頭が有名だが、遠くに見える山桜、雲雀の声、雨の糸など、自然描写が印象に残る。
日常会話では役に立たないけれども、美しい言葉がたくさん出てきて、読んでいるだけで楽しい。
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
草枕は眺めるように読む小説である。
主人公は日常の生活圏から逃げ、自己に沈静しながら、現れてくる世界をただ眺めようとする。それは「おのれの感じから一歩退く」ためである。漱石自身が苦しみに対処するためにそれが必要だった。
草枕は漱石が「自分の屍骸を、自分で解剖して、その病状を天下に発表」した小説である。余と那美さんは二人とも漱石の分身だ。漱石は自分の屍骸を美しい言葉で綴る。それが彼が苦しみから逃れるための方法だった。
読者はそれを眺める。しかし、漱石の言葉が美しすぎるがために、読者は自分が読んでいるものが彼の死骸だとは思わないのである。
漱石の病跡には諸説あるようだが、この小説に現れた病状は分裂病的だと思った。探偵に付け狙われ、屁をひったと言われ続けるという描写は、まるで精神医学の教科書に載っても遜色がない。
Posted by ブクログ
最初は随筆かと思った。
世故の話が紛れ込んでこない限り、美を追求し酔いしれていられるので、現実逃避にぴったり。
文学と言うより美学という感じ。
ところどころに入る、主人公の都会に対する辟易とした雑感が、現代にそのままあてはまり、驚いた。…これだから漱石は。
睡眠薬代わりに読んだので、再読したい。
Posted by ブクログ
漱石の中でも割に好きな方。
汚れた世を避けるが稀に俗っぽさを見せる画工と、妙な脱俗感を醸し出す那美さんの感じが面白い。
水死の美しさに関する描写が印象的だった。
Posted by ブクログ
いつにもまして美文。
いつにもまして何も起こらない。
そんな小説。
非人情な読み方を求めているのかしら。
春のうららかな陽の下で読みたい。
漱石の物の見方が地の文にありありと表れていて興味深かった。
読後感を一言で表すと、
「ああ、とても美しかった。」
Posted by ブクログ
実家から出られず母親の古い古い本をあさり読んで。
*
智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。
住みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。
人の世を作ったものは神でもなければ鬼でもない。やはり向う三軒両隣りにちらちらする唯の人である。唯の人が作った人の世が住みにくいからとて、越す国はあるまい。あれば人でなしの国へ行くばかりだ。人でなしの国は人の世よりも猶住みにくかろう。
越す事のならぬ世が住みにくければ、住みにくい所をどれほどか、くつろげて、束の間の命を、束の間でも住みよくせねばならぬ。ここに詩人という天職が出来て、ここに画家という使命が降る。あらゆる芸術の士は人の世をのどかにし、人の心を豊かにするが故に尊い。
*
以上が文庫1ページ目の、草枕です。
漱石すごいよね面白いよねと言いつつ、何が面白く何が楽しいかを説明するのは至極難しい。
『硝子戸の中』などは随筆だけに滋味あって読みやすく、幼少期のエピソードなどもあって読み物としても、自然に笑みの浮かぶようなものだった。
『虞美人草』は結末が唐突に思えてさほど好きではないが、お話としてまとまって疾走感のある物語だった。
教科書的に解釈やら何やらをせられた思い出もあるけれど、『こころ』も事件性があり、時代背景が書き込まれてあり、読み応えがある。
が、しかし暗い。
暗さでいえば『門』や『道草』の閉塞感こそ。
みたいな話を母親としていたけど、wikipedia先生に尋ねたらもっと全然作品数あるのですもの。
読もうかなー、と思うのは、暗かろうが何だろうがあまりにも読みやすい文章のためな気がする。
結局は読みやすくて、暗くても構わないが不快になるものは嫌いというだけの趣味傾向でしょうが。
*
洋画家を自称しながら本文中では一枚も絵を描かない主人公が、山あいの鄙びた町の温泉宿に泊まる。
温泉宿と行ってもそこは温泉街ではなく、町に一軒、裕福な主人の隠居所のような家で客が来たら泊めるというようなところ。
日露戦争中のことで他に客もなく、主人公は、宿の娘で傾いた嫁ぎ先から出戻ったという那美と話すようになる。
那美は、嫁ぎ先が「傾いた」というだけの理由で出戻ったことや、種々の奇行から村のひとの一部には「きの字」と言われている。
けれど、(絵も描かないで)非人情を語る主人公とのあいだに物語的な展開は起こらない。
ある日に那美の傾いた嫁ぎ先の夫が那美を訪ねて来、那美が夫に金銭を渡して呆気なく別れるのを主人公が目にする。
金を包んだ包み渡し、受け取る仕草に画題としての美しさを見る一方、那美が自分の絵を描くよう頼むと主人公は那美の顔は描けないといって断る。
那美のいとこが日露戦争に行くのを見送りに来た駅で、ひとり満州に出稼ぎに向かう夫の姿を見つけた那美の表情を見て、
その「憐れ」が出た表情をもって主人公の胸中で那美の画が成就する。
*
詩人/画家の立場としての「非人情」と、画題としての(構図の美しさ、西洋と異なる日本の空気を描く色の必要なども語りつつ)「憐れ」と呼ぶ人情味について語った漱石の芸術論。
Posted by ブクログ
「山路を登りながら、こう考えた」と始まる非人情の旅物語。
非人情とは世間的な人情を放棄して住みにくいこの世を離れた気分になること。人間の感情で溢れかえる住みにくい都会を離れ、非人情を求めて田舎への旅に出た画工。
当時の西洋化の流れで登場した「芸術」という観念で括られるようになった様々な表現活動。絵画と詩の対比がよく登場する。はじめは手応えがなくとも休むことなく続けるものだという詩作りと葛湯作りの比較がいい。
「菓子箱の上に銭が散らばり、呼べど待たれど人は来ず」
田舎で垣間見られる20世紀らしからぬ非人情の世界。
おばあちゃんが店番したままうたた寝していた近所の駄菓子屋さんのようなシーン。
旅先で出会った不思議な女性、那美さん。画工が彼女を見る目は俗人情そのものともいえるのだが、私を描いてほしいと言われ、非人情の立場から絵に描こうとする。しかし彼女には「憐」が足りない。
「汽車の見える所を現実社会という」
「汽車ほど20世紀の文明を代表するものはあるまい」
この小説のラストシーンはその汽車の行き交うステーション。
そこで昔の夫と視線を交わす那美さんに表れた「憐」を見た画工が小さく叫ぶ。「それだ、それだ、それが出れば画になりますよ」
Posted by ブクログ
夏目漱石という人は常に厭世観に苛まれていた人ではないか。
冒頭の一節で全てが語られており、残りはAppendixに過ぎないとさえ言えるだろう。
芸術は人生を救えるか。飢えた子の空腹を満たすことはできないとしても、幸福感を与えることはできるのではないかと今は思っている(それが文学であるかは別にして)。
Posted by ブクログ
2006年09月03日
どうしても寝付くことができなかった夜に、これなら副作用の心配がない最高の睡眠薬だろうと思って読み始めたのに、案外引き込まれてしまって結局その夜は寝れなかった、という本です。
決して大事件が起きるわけでもないし、複雑な人間関係が織り成されることもないのですが、作者の文章の巧みさだろうか、あるいは教養の高さだろうか、どうしても気になって読まざるを得ない小説でした。
Posted by ブクログ
ちゃんとした純文学を久々に読んだ。冒頭の「山道を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。情に棹せば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。」はあまりにも有名。
想像と妄想を重ねながら芸術を追い求める絵描きの話。芸術は自由の開放である…みたいな話はモームのサミングアップに準ずる。夏目漱石の漢文、英語など各文学への造詣の深さが窺える
Posted by ブクログ
夏目漱石の代表作の一つです。
冒頭の一文、「山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。」と、「吾輩は猫である」の脱稿から約2週間ほどで完成させたということで有名な作品。
夏目漱石の初期の作品の一つで、本作発表時はまだ職業作家ではなく、夏目漱石は教職の傍ら執筆活動を行っていました。
氏の初期の名作と名高く、エンタメ色の強かった全2作(「吾輩は猫である」、「坊っちゃん」)と違い、芸術に対する考え、存在意義や、西洋文化と日本の世の中のあり方に関する考えが滔々と論じられており、比較的読みにくい作品となっています。
人の世に嫌気がさすも人以外の世に暮らすこともできず、絵描きを生業とする主人公は、単身熊本まで「非人情」の旅に出る。
立ち寄った茶屋で宿の場所を聞くのですが、その宿には嫁ぎ先から出戻った娘がいて、その娘には悪い噂が立っていることを聞く。
宿にたどり着いて最初の晩、寝付けない主人公は宿の湯殿で不思議な女性に出会う。
この女性は結論として、この宿の娘「那美」であったことがわかるのですが、主人公はこの女性と、以前、身投げをしてこの世を去ったという別の女性をハムレットのオフィーリアの姿に重ね合わせます。
度重なる不幸な出来事に気が狂い溺死したオフィーリアを静物然とした姿で水にある儘の姿でミレーは絵画にしているのですが、そのミレーのオフィーリアと、画題としての那美の対比、そして芸術の有り様を、主に独白する形で書かれたものになっています。
物語として筋と呼べるものはあるにはありますが、この独白がメインで、ストーリーはその呼び水のようなものだと感じました。
つまりは作者の論説を呼ぶためのダシとして、オフィーリアを彷彿させる背景を持つ那美と、非人情の旅をする主人公が設定されており、ストーリーを楽しむというよりは、山奥の温泉旅館という幻想めいた舞台設定と主人公の芸術論、難解ですが卓越した文章を楽しむ小説だと思います。
ちゃんと読めば面白いですが、楽しめない人はダメなんだろうなと思いました。
主人公は結構おとぼけで、芸術について意識の高い論述を一人ブツブツ唱えながら、いざ実践しようとすると素っ頓狂な出来となるシーンが多々有り、そういう意味でも楽しめました。
個人的には夏目漱石は肩肘を張って読むものではなく、文豪では親しみやすい作品だらけなので、本作もラフに読むのが良いと思います。
Posted by ブクログ
大変有名な冒頭で始まる作品。
「非人情」を掲げて主人公が田舎へ旅をする物語である。
確かにそのテーマ通りに物語が進んでいく様に思われるが、正直私には意味が理解出来ないところが多すぎ、読むのには少し早かったかなと思った。笑
ただ、所々私の普段考えていることを、的確に表している。また夥しい程の比喩には流石夏目漱石。
一つ、nice表現!と思ったものを上げる。
「元来何しに世の中に、顔を晒しているか、解しかねる奴がいる。(多少、違っているかも笑)」普段からその様に思う事があったのだが、今後はこの様に表現しようと思った。笑
もう少し年をとってから、読み直そうと思った作品です。
Posted by ブクログ
難しくて理解できなかった本は久しぶりである。
非人情の旅を目指し放浪する画工の話。
旅先で出会うミステリアスな女性那美さん。彼女がこの物語のトリックスターであるのは間違いないが、あまりにミステリアスすぎる。
ラストの爽やかさは名状しがたい、二三度読むか、あるいはもう少し成長してから読むべき作品だったかもしれない。
Posted by ブクログ
筋を追っていくと辛いが、細部に目を凝らしてみると文章が美しい。
青味を帯びた羊羹の描写、那美さんが鮮やかな振袖を着て行きつ戻りつする描写、深山椿の艶然とした毒婦の描写が印象的だった。
画工が云うように適当に開いて文章を眺めてみるほうがいいのかもしれない。
55,78,86,125
Posted by ブクログ
リアリズムという方向から芸術を捉えている人との初めての出会いで、戸惑いました。
この時期ちょうど岡本太郎を読んでいて、彼の爆発という言葉で表現されるような、力強さや情熱が、夏目漱石のほっそい線から感じることができなくて、こういうのって芸術というんだろうか、と認識のレベルで考えてました。
Posted by ブクログ
語り手の画家は、都会での日々の生活に疲れてか、自身の芸術的思考で最も重視している“非人情”を求めてある山村を訪れる。そこでは彼が期待していた以上の非人情が溢れていて、日々絵になるものに包まれてのんびりした生活を送っていく。彼が居住いさせてもらっている家の美しい一人娘が少々問題アリの性格ということで一部ではキ●ガイ扱いすら受けているが、彼はこの娘に非人情を感じ絵にしてみたいと思う。 この作品は当時大変な人気を集め、そしてこれがきっかけで職業作家に転向したとまで言われています。この草枕の語り手の台詞に「小説は自分の好きな部分を気ままに開けて読むのが非人情である」みたいな部分があり、なるほどと思わされました。
Posted by ブクログ
イエローナイフへ行くのに借りたけど、ぜんぜん読まずに帰ってきてしまいました。漱石さんは高校生の時にいくつか読みましたが、これは今で良かった気がする。冒頭、共感できました。あの頃だったら分からないだろう。まだよみかけ。