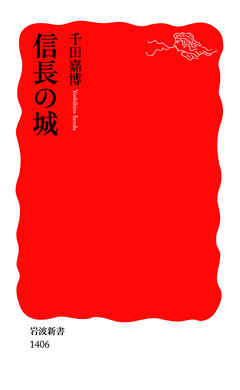感情タグBEST3
Posted by ブクログ
本書はお城巡りをしている方は、直ぐに読むことをお薦めします。またこれからお城巡りをする方には先ず読んでからお城巡りを、と何れにしても本書は織田信長が近世城郭〈石垣や瓦を使用したという定義とは違い、城主と家臣の館を並立的では無く、天守閣を中心とした権威を象徴する求心的な構造を持つ城と城下町〉を創築したことを、信長誕生の城から安土城までを、発掘調査や文字史料などで丁寧に解説されています。
今後は安土城に先立ち150メートルの直接的な大手道を持つ小牧山城や、安土城の天主閣に使用された懸け造りが見られる福山城、戦国期拠点城郭であった吉田郡山城や置塩城などの登城がより楽しみになりました。
Posted by ブクログ
歴史という大きな物語をひとりの人間に絞って見るから伝記は面白いんだろうが、この本はさらに「城」へと焦点を狭くする
ところが狭くしたことで逆に、信長が戦国時代をどう近世に変えたのか、そして如何に稀有な人物だったのかが浮かび上がる
Posted by ブクログ
重臣=有力者の連合という形態から権力の集権を進めていった信長の画期的な統一手法が、築城スタイルにも表れているという面白い視点。他の信長の施策も合理的で画期的だったのが分かり(寺院権力を滅ぼし交通権益を奪取するなど)、信長の革新性と実行力に感嘆。
小牧山城の山麓館の庭園、岐阜城山麓の絶壁に沿って作られた庭園、安土城の眺めのいい御殿、安土城内のいくつもの茶室。後の利休・秀吉の茶の湯ができたのは、信長の審美センスとそれを愛する心を二人が目の当たりにしたからこそだったのではと思わずにいられない。
Posted by ブクログ
信長の生涯に渡り、築城してきた城の変遷について記されています。
信長が愛知の勝幡城で生まれたとする説を採用し、その後、那古野城、清州城、小牧山城、そして安土城へと移り変わっていく中で、城と信長との関わり。そして、家臣団との関係の変化といったものが読みとれました。
初期の頃は、家臣団と信長との関係が対等だという説は、常に上下関係にあったと思い続けてきた私には新鮮でした。
当時の城の詳細な形や設計など見ていて楽しかったです。
特に、安土城は現在、信長の最高傑作に関わらず、現存しませんが、よくぞここまで調べたものだと思います。
武田信玄が「人は城、人は石垣」と言っていましたが、信長も自分と家臣との関係を城を通じて変えてきたのだと思えました。
後、現代に通じることは昔も今も権力者は高い場所が好きと言う事でしょうか。
Posted by ブクログ
信長の本はどうしても読みたくなります。この本は、信長の生まれた勝幡城から、那古野城、清須城、小牧山城、岐阜城そして安土城を扱います。小牧山城から稲葉山城(岐阜城)を見て見たくなります。
俗説を排する論理も説得力があります。「フロイスの『日本史』によると、摠見寺は信長が自分自身を神として拝礼させるためにつくったといわれています。」(248頁)。これに対し、摠見寺の本尊は毘沙門天であること。当時、城の中に寺院かあるのは珍しくないこと。摠見寺下層の信長の御座所遺構の可能性があることから、信長が天主に移り、御座所を寺院にすることで摠見寺がつくられたとすれば、信長を祀ったという言説がでて、フロイスの記述につながったのではとしています。圧巻は岐阜城での懸け造りの話が伏線になっていましたが、安土城の復元案の否定と懸け造りの指摘でしょう。
信長は楽市を最初にしかけたわけではありませんが、城と市の関係を変えたわけです。「安土では城下の町全体を「楽市」と宣言して、はじめて城と町とが一体化した近代的な城下町を実現しました。」(260頁)。信長の求めた求心的なあり方が近世城郭の象徴となったとしています。ヨーロッパの都市のように城と教会が並び立つ複合的なものにならなず、城が絶対的なものになったのでした。
Posted by ブクログ
すごく、ちゃんとした本です。信長が天下統一の進行・権力の集中とともに、築城・城下町作りの考え方も深化させて行ったことを丹念に証し立てて行く労作です。こちらが勝手に、もっとエキサイティングな内容を期待していたために高評価にはなりませんでした。でも、小牧山城や、岐阜城、安土城等の遺跡を訪ねてみたくなりました。