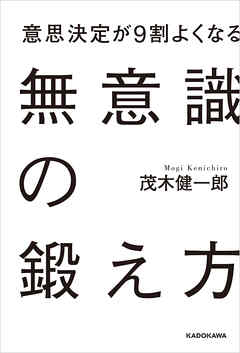感情タグBEST3
Posted by ブクログ
「無意識」とは何か?ということを脳科学や行動心理学を中心に解説している本です。そのうえで、自分の意思決定をよりよくするための考え方や習慣について触れています。
「へーそうなんだ」とさくっと楽しく読みました。
・モテる顔は『平均顔』。なぜ脳は平均顔に好感を抱くのか。それは、平均的な顔立ちであればあるほど、脳内の情報処理が効率的に行われるため。自分の好きなものがなぜ魅力的なのか、改めて考えてみよう。
・人は思い通りにならない不都合の理由を他に求め、心をラクにしようとする習性がある。何か課題が発生したときには、まず、自分の行いを正当化していないかどうか自分自身を省みること。
・日本人特有のハイコンテキストなコミュニケーションはAIには真似できない。この「人間っぽさ」がこれからの日本の強みになるかもしれない。
・「もののあはれ」といった日本文化の個性となるような概念は、紫式部などの女性が先導してきたのかもしれない。そのころの女性は政治に関わらなかったからこそ、ルールにとらわれない柔軟な視野でもの事と向き合えたのではないだろうか。
・他者とわかり合うことは難しくても、自身の内部モデルを多彩に構築して、他者への共感力を高めることは可能。人との触れ合いとそれに伴う経験値、あるいは身につけた教養が豊かなほど、内部モデルのデータベースも豊富に蓄積されていく。それに伴い「心の理論」も成熟され、共感の幅が広がり、他者の感情を汲み取ることができる脳が育成される。
・なぜ、続けることが大切なのか。 それは、脳が変化を嫌うものだから
・「落書き」はリラックスしながら集中しているクリエイティブを高めるための理想的な脳の状態。メモ書きする時は落書きを添えてみよう。
Posted by ブクログ
無意識をこれまでなんだと思って来たのか、そんな自分との向き合うきっかけになりました。
ジェンダーだったり国だったり、様々な枠組みの中で固定されたものがいくつもある。
それが今の自分だから、リラックスするマインドフルネスを実行するには、今の固定されたものを確認する必要があると感じる。
羽生善治さんの例があるが、とても共感するしそうなのかと腑に落ちるものだった。
ルーティーンについても、順番立ててやるのが好きなのかと思っていたけど、単にそれは決定することを減らす脳を労っている作業なのだと知った。
Posted by ブクログ
人の行動の約9割は無意識。一日に下す決断は3万5000回。フロイトが無意識を発見し、ユングが集合的無意識という概念へ。生活において判断される事案のほとんどが斯様に省エネ化され無意識で処理されるから、体性感覚に染み込ませる事が重要なのだろう。その鍛え方についての本だ。
平均的な顔に近ければ近いほど、情報処理がスムーズに行われるため、対象への親近性が高まる。この親近性の高まりが好感を抱いたり、美しいと感じたりすることにつながる。単純接触効果と言う現象では、何度も会う人、何回も聞く音楽、繰り返し目にするキャラクターなど摂取すれば接するほど好感度が上がっていく。
シャーデンフロイデのような脳科学的なアプローチ。マズローによるヨナコンプレックス。旧約聖書の中で自分の使命を果たすことから逃げてしまったヨナと言う名前の預言者。できない自分でいる事は一見困ったことのように見えるが、実際のところ現場の時間を維持する事は極めて安定性が高く心地の良いものだ、とか。
脳科学をハックすれば、結局人間との会話も、AIとの会話のように、ある種のクセが浮き彫りになる。自分自身を振り返りながら、他者の分析にも役立つ内容だ。あまり意識し過ぎると、人生が楽しくなくなりそうだが。
Posted by ブクログ
・無意識、は同時にいくつものことをこなせる
・本を読むことで集中力をつけられる
・腸は第二の脳といわれる
・やる気が必要、と言ってる時点でやる気なし。
やる気よりも、週間、が大事。
・無意識は脳の9割をしめる
・行動力がある人に運が良いという人が多い
・マインドフルネスがひらめきを産む
・メシウマ思考、人の失敗を喜ぶ、のは皆起きてしまう
ただ、現代社会において、人の成功は自分にも良い効果をもたらすこと多い。
おこぼれを預かろうというプラス思考が大事
本の評価
・手元に置いて、あちこち印つけたい本
・いろいろな文学からの引用があり、
文学の興味もわく
・タイトルの内容も記載してるが、
鍛え方の本、というより、無意識とは、という本と言った方が近い
・怒りを鎮めるには、鳥の視点
自分をいろんな角度から見て、恥ずかしい、と思う
・怒りを感じたら、座ること、食べること、は意外と大事
・悲しいから泣くのではなく、泣くから悲しいというメカニズムもある
・感情のタグづけ
心が動いた瞬間にフォーカスする
・全体を柔らかく俯瞰する視点
・人は分かり合えないものということの理解も必要
次に読みたい本
→スマホ脳
→茂木さんの他の本
Posted by ブクログ
脳科学者として有名な茂木健一郎さんの本。
記憶に残ったのは次の部分
・子どもの人生に大きな影響を与えるのは親ではなく、出会う人々や育つ環境
・親の重要な役割は「子どもの安全基地」になること
・行動力があるから運がいい
・閃きを得るためには、知識と経験が必要
Posted by ブクログ
読みやすかったので、一気にサクッと読めた。
●一日30分程度のデジタルデトックス
●読書をする
●行動してみる
●雑談中の落書き
●習慣をつける
書き出してみると、やってみようと思うことがこんなにあった。無理のない程度にやっていきたいと思える本だった。
Posted by ブクログ
個人的には好き。
まず読みやすい。
単なるハウトゥではなく、書かれてる内容で考えながら、でもひとつひとつ引っかかって先に進まないってこともなく適度だった。興味ひかれる実験やインタビューした結果、茂木先生の周辺にいる方々から聞いた話もたくさんあってたのしめました。
無意識の鍛え方のわかりやすい方法が知れると思って読んだら満足感ないかもしれない。
Posted by ブクログ
無意識というものが何か脳科学的に知ることができる。
【概要】
●無意識とは
●日本的無意識とは
●感情の抑制
●人間関係のアップデート
●無意識の鍛え方、高め方
【感想】
●本書は、心理学や鼓動経済学から見た無意識も説かれており、幅広く人の行動や思考について考えることができる。
●人は毎日多くの決断をしており行動のほとんどが無意識で行われているという事実に驚いた。
●日本人の特徴であるハイコンテクスト文化はAI導入の難しさを理解させるものであり、この内容には興味が持てた。
●自分が変わるためには、無意識の行為による習慣化が重要であると理解した。
Posted by ブクログ
人の行動の約9割は無意識で行われると言われている。
今私たちに必要なのは無意識との対話無意識を意識し、それを耕すことで日々の意思決定は確実に変わり始める。それは創造性を高め、日常を豊かにする。
ポジティブ思考、ネガティブ思考は無意識が決める。
抑えきれない感情はコントロール出来る。
マインドフルネス中は、脳内で情報の整理を行い、自分自身を振り返ったりしている。これにより頭がスッキリし創造性が高まる。雑談も脳を刺激する。
無意識力を高めるには、有酸素運動、物事のルーチン化、メモと一緒に落書きをする、読書(集中力を養う)が良い。
基本的に脳は安定性を求めるので、例えば行動パターンを変えようとするなら、長期的なプロセスが必要。
無意識を意識するか、、、短期的には難しいが、習慣化で獲得できることが学べた。