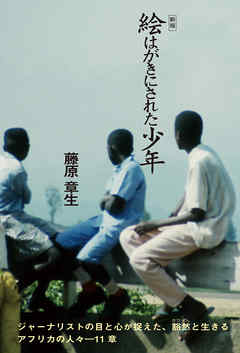感情タグBEST3
Posted by ブクログ
アフリカの朝は空気がひんやりとしている。確かに昼間は暑くて乾いていて埃っぽい。でも朝は手付かずの、今日という日に希望を抱かせる、そんな空気。もう8年の前のそんな朝の感覚をこの本は思い出せてくれた。
この本には出てこないが、僕が行っていた国マラウィも、南アフリカへの出稼ぎが最大にして唯一の外貨獲得手段だ。茶やタバコは白人資本が、商業はインド人が独占、地下資源に乏しいとくれば、出稼ぎしかない。南部アフリカにおいてとりわけ従順で穏やかな気性のマラウィアンは庭師や家事手伝いとして南アで評判だと聞いたことがある。
実際、本当にずるがしこくない。嘘はつくがすぐばれる嘘だし、悪く言えばとんま、よく言えば素朴。笑顔は素敵で、老人でも幼児のように笑う。
状況や生い立ちは違うけど、僕らも彼らも生活というレベルで考えることや感情はそんなに変わらない。それは今でも基本的にはそう思っている。でも、単なる諦念とか卑屈とか見得といった言葉では表せない感情が彼らにはある。それが「北」から来た僕らには分からない、ぽんと突き放されたような気持。この本を書いた動機はその辺じゃないだろうか、と勝手に想像した。
さて、この本の筆者が惹かれたのは老人たちだ。黙々という言葉が似合うほど勤勉ではないが、口数少なく、ある時には少年のように笑い、ある時は孤高の宗教者のようなアフリカの老人たち。彼らにまた会うことはあるだろうか?
僕にとってはすごく共感できたノンフィクションだったが、アフリカの朝の空気を知らない人にはこの本はどう映るのか分からない。
腰帯は誰が作ったのか知らないけど、あの文句よりも「語られない言葉」が本質だと思う。
タイトルにひかれて購入
軽いエッセイか旅で出会った人々の話かと思ったら、なかなか重いアフリカの人々の話を聞いたドキュメントだった。
私も例に漏れず、白人に搾取させている黒人と言う図式を思い描いていた。そんな単純な世界ではなく、人それぞれの人生が描かれていた。
Posted by ブクログ
コロナで旅行できないので(海外に行きたいわけじゃないが)外国についての本を読もうと。
1995-2001まで新聞社駐ヨハネスブルグ特派員だった藤原章生さんの本。カルチャーショックと言うのか、無知で申し訳ない気分。
「"inquisitive" (知りたがり)なのとそうでないのと、どちらが良いんでしょうか」という言葉が印象的。世の中で何が起きているのかを知ることは大事だし、そのような教育を受けてきたような気がする。でも、教育も情報もお金もなければ知ることになんかあまり意味がないかもしれない。
日本人はアフリカで「名誉白人」のような立場らしい。特権階級であり、同じく白人に対する憎しみも受容することになる。差別される側、搾取される側の黒人たちは白人たちに本当のことを言えない(言わない)という。いくら現地の人の本当の思いを知ろうとしても「名誉白人」の立場であり(その土地に生まれ育っていないという意味で)外国人である著者には限界がある。
アフリカに人種差別の歴史と生活があって、そこから遠く離れた特殊な島国の日本人。まるでアフリカの人から "inquisitive" であることを責められているような気持ちになる。知ってどうする、何が分かったのか、と。それでも、アフリカのほんの一面でも知れたことで、マシな人間になった気がする。それがやっぱりとても大事なことじゃないかな。個人レベルの平和貢献だとさえ思う。
それにしても南アフリカの治安の極悪さに恐れおののいた。藤原さんご夫婦が無事で何より。
Posted by ブクログ
初版からすでに25年経つらしい。けれど、本書に書いてあることを、私は全くと言っていいほど知らなかった。
自分がいかにアフリカのことを知らないか、知らずに勝手なイメージを押し付けていたか、そして、誰かが誰かを助けることがどれほど難しいことなのか。そんなことを考えさせてくれた。
ただ、胸に迫るものがあるかと言うと……アフリカとそこに住む人々への愛着やハッとさせられる指摘、考えさせられる内容には富むのだけれど。
海外の紛争地域や貧困の中にある人々を描いたルポとしては『もの食う人々』(辺見庸)、『アフガニスタンの診療所から』(中村哲)をこれまでに読んできた。アフリカだけに的を絞ったものは初めて読んだ。それらと比較して感じるのは、視点が「引き」であるということ。筆者が新聞記者であることと関係しているのかもしれない。辺見氏は「食う」者として取材対象と同化したところから筆を起こしている。中村氏には現地の医療者としての生活感情や生活を共にする人々への愛がある。それらからすれば、本書における著者の書き振りは「遠い」という印象が拭えない。いつでもその場所から抜け出せる立場から書かれた「観察記」「報告書」だと感じてしまった。