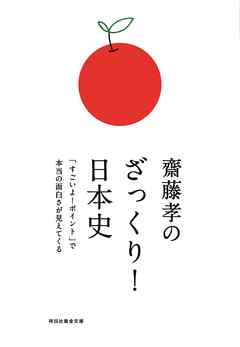感情タグBEST3
Posted by ブクログ
大人になってから、日本史の理解が乏しいと感じたため、読みやすそうな本書に手を出した。最初に読んだのが本書でよかった。非常に興味が湧く流れの説明で、歴史をさらに知りたいと思った。
その中でも、渋沢栄一の功績には
非常に感銘を受けた。
第一国立銀行を創設、多くの企業設立などの
資本主義の仕組みを作ったことは、
日本経済の躍進に大きな影響を与えた。
これが無ければ、今の日本はない。
まさに、私にとっての「すごいよ!ポイント」だった。
Posted by ブクログ
幕末、かな文字、古代、近代、戦後と縦横無尽。面白く読みやすい。各時代の人が生き抜いて今があるんだなあ。
現在は先人の遺産にあぐらをかいていて危険。歴史をよみ、今できることをやることが必要だと思った。※
Posted by ブクログ
面白かった!
日本人ってすげぇんだなと思った。そして日本に生まれてよかったと思える本。
日本史好きはもちろん、日本史に興味持てない人にも是非読んでもらいたいです。退屈は絶対しません。
多分、苦手な人が多い近代・現代史もちょっと楽しく思えるかも。
蛇足ですが、不意に伊達政宗の文字が出てきてうろたえたのは私だけかw
Posted by ブクログ
時系列に日本史を追いかけて解説するスタイルではなく、いくつかの歴史的なポイントと現代の日本人への繋がりを意識させる構成になっていると思われる。
日本史って、そんなに興味がなくて、、 それは、高校生のときに読んだ日本の私小説があまりに個人の内面ばかりにフォーカスしていたので、私小説が嫌いになって、、 中国の三国志やヨーロッパの歴史物・小説に入っていったこともあって、ある意味、日本史についてはじめて読んだ本と言ってもいいかも。
歴史物というと、戦争と統治システムの話であり、権力を持った者、勝者の話が多くなりがちだが、この本では、統治システムについての変革については、大化の改新、三世一身の法、鎖国、廃藩置県から明治維新、GHQの間接統治等が触れられているが、勝者の理論的な形ではなく、なぜ、そういうことが起きたのかという点についての著者の洞察が語られている。
日本人の特性として、お上のいいなり、ゆるさの他、良い物を他国から取り入れる(ビジネス・システム等)、みんなが一気にその流れに乗る(はしかのような物にかかりやすい)等を指摘しつつも、たとえば、漢字は中国から渡ってきたものだが、文法などのシステムは独自だったり、鎖国によって、独自の文化を開かせたことなどの話が提示されている。
感銘を受けたのは、GHQの圧倒的仕事力の最後に書かれた「日本は中国にひどいことをしたとよく言われます。言い訳や弁護をするつもりはありませんが、その罪を問うならば、アメリカが行った、一瞬にして20万人以上の非戦闘民を殺した原爆投下の罪も、問われるべきなのではないでしょうか。」と言う箇所です。
これは、アメリカによる対ソ連ストーリーがあってのことであれば、なおさら。
当時と比べれば、各国のたち位置、世界情勢は大きく変わっていると思いますが、日本は周到に練られた戦略に負けたと言う事実。そして、今の日本がどういう方向に進むべきなのかなどを考えるきっかけになりました。
Posted by ブクログ
何部かコラムがまとめられたような作りだった。
その中でも、三世一身の法とバブル崩壊というタイトルの章の土地に関する考察が面白かった。
なぜ人は土地を所有することに躍起になるのか。
三世一身の法により、荒れた土地を耕すイニシアチブを人に持たせ、さらに20年後、墾田永年私財法でそれを強化する。
荘園制ののち、班田収授法で平等を保ち、秀吉の太閤検地で一網打尽にする。
人々が土地をめぐるドラマ
すごく興味深く読めた!
Posted by ブクログ
すっかりメジャー化した齋藤孝先生の日本史観。教科書のようにすべてを網羅しているわけではないが、独自の視点で歴史を解釈している点はマクニール教授の世界史のコンセプトと共通している。その視点も、社会、制度、外交、国語、宗教、芸術そして身体論。さらにそれぞれの分野とその周辺領域を有機的に絡めているので、誰でも何箇所かは食いつくポイントがあるはず。
思考には何かしらのガイドラインが必要であるが、解釈を通さない広く普及した歴史物語はとても優れた指標となりうる。それにそって自らの歴史観や思想を論じるのはとても意義深い。とはいえ、その「解釈を通さない歴史」がまずありえないのではあるが。
あらゆる分野へと興味の矛先を誘ってくれる齋藤先生の特徴がよく表れている一冊。最近はすっかりおとなしくなっているが、ここらへんでそろそろ本格的な身体論も読んでみたい。著書が多いのでこちらが見逃してるだけかもしれないけど。
Posted by ブクログ
日本史の学び方のようでいて、実は作者の考える「日本のかたち」について言及した本。廃藩置県や三世一身法から見えてくる「土地所有」を巡る数々の変遷。万葉仮名や仏教に見る外来文化の消化力。鎖国や占領がもたらしたもの。殖産興業が成功した理由。日本の優れた点ばかりが掘り下げてるが、「歴史を学ぶ」という点では片手落ちではないかと思う。
Posted by ブクログ
齋藤先生の日本史の歴史観がうかがえます。だからといって別に批判をするつもりはありませんが。これを読めば外国に行ったときに自分の国のことを話せるのではないでしょうか?
この本を読んでいると齋藤孝先生の歴史観がよくわかりますね。だからってどこがどうだとか批判する気は毛頭ありませんよ。ただそうなんだなって言うだけで。読み物としてはいい本ですよ。さらりと読めますし、大体のところはカバーしていますから。
この本によると諸外国、特にヨーロッパのほうでは、自分の国の歴史をきちんと語れない人間というのはどこか信用が置けないというのだそうですが、僕が前に諸外国を渡り歩いてきた人間のから聞いた話を統合して、本書と照らし合わせた限りではどうもそれは本当のことのようです。
肝心要の内容については、個人的には知っていることばかっかりだったんで、さらっとは読めましたよね。もっとも、「ざっくり」ですからそれでいいんですけれど。特に読んでいて感動したりとかそういうことはなかったんですが、海外に行って自分の国のルーツを語ることがあるときにはこの本に書かれていることが何かの役に立つのかもしれない。そんなことを考えていました。
Posted by ブクログ
本当に説明の上手な方だと。
言い切るというのは勇気のいることで、まちがっているかもとか
反論を受けるかもとか、ご本人だって重々承知だと思うが、、
敢えて断言するということは、意思を判りやすく伝える際に
とても重要な手法だと思うのです。
Posted by ブクログ
全時代が網羅されている訳ではなく、歴史ものというよりかは日本の時代の分岐点や転機が興味深く解説されていた。そのポイントこそがいわゆる「日本史」なのでしょうね。読後は日本や日本人が好きになります。
Posted by ブクログ
2013.10.03-06
ざっくりだけど、所々切り出して解説があり、スラスラ読めて楽しかった。現代の日本人とのつながりを論じたり、ユーモアがある解説で飽きずに読めた。鎖国による圧がかかった上での文化形成。日本文化は奥深いということと、細部までもこだわる職人気質であることが書いてあった。
Posted by ブクログ
日本史の中から、とりわけ現代の出来事に関係の深い事柄をピックアップし、ざっくり解説した一冊。
歴史の一部分を掻い摘んで紹介した内容なので、歴史を総体的に勉強し直せるような本ではないです。
現代に起こっている問題も含めて、歴史の流れを解説しています。そのため、私にとっては興味を持ちやすく、いま起こっている問題について、考えるヒントを教えてもらった感じです!
読み物として楽しめました!
Posted by ブクログ
昔の歴史の勉強といえば、一生懸命に年号を覚えていたことくらいしか覚えていませんが、とにかく覚えることに苦労したことだけを記憶しています。振り返っていみると、苦痛だった理由は、年代順に覚えていて流れで覚えようとしていなかったからとこの本を読んで気づきました。
井澤氏も同様の主張で本を執筆されていたと思いますが、この本の著者である斎藤氏も基本的には同じ考え方のようです。テストの点を採るために歴史を勉強する必要がなくなった今、流れで事件を捉えて、必要なときに他の人に(特に外国人)話せるように、主要な事件の関連性を理解しながら歴史を楽しみたいと思いました。
特に最初の部分に述べられていた廃藩置県に関する内容は、興味深かったです。
以下は気になったポイントです。
・外国人と話をする場合、どんなネタでも良いのであれば、自国の文化や歴史について述べるのが望ましい(p19)
・廃藩置県による最大の変化は、大名に代わる存在として、県や府に中央が人を送り込めるようになったこと(p30)
・廃藩置県において、その意味を理解して欧米と肩を並べられると理解できた開明的な感性を持っていたことが、欧米以外で日本が近代化に成功した要因である(p40)
・武士階級が自ら、時代遅れであることに気づいて行動し、自分たちの社会を変えたところが明治維新の凄さである(p48)
・情報ツールの発明と普及によって、文明は加速していく、これは歴史を見ていく上での重要なポイント(p53)
・日本最古の歌集である万葉集は、支配階級以外の普通の人がつくった歌も含まれていて、それが残っているのも画期的、これは万葉仮名があったおかげ(p58)
・カタカナは漢字から余分なものを削ぎ落として極限まで簡略化させたものに対して、ひらがなは漢字をドロドロに溶かして刻限まで柔らかくしたときに生まれる流れを書き留めたもの(p64)
・天皇と将軍という二人が併存するということ、天皇制があるのは外国人から見ると変わった体制に見える、これは大化の改新に行きつく(p84)
・大化の改新は、蘇我入鹿という悪人から天皇が政権を取り返したことになっているが、手段は「テロ」、これが正当化されたのは、主犯が天皇の皇子であるから(p87)
・藤原氏の嫡流が五摂家(近衛、一条、二条、九条、鷹司家)として定着するのは鎌倉時代、それ以降に明治に皇室典範が作られるまで、摂政・関白は例外(秀吉、この場合も近衛家の養子)を除いて藤原氏の独占(p91)
・藤原氏は自分の娘を天皇に嫁がせるという方法(母系社会)によって、自らを安全な場所に置いたまま政治を思い通りに動かすシステム(摂関政治)を完成した(p97)
・三世一身の法は、公地公民制に例外を認めた(土地の私有を認めた)点で画期的、これから律令制を中心とする古代世界は崩れ去っていく(p148)
・秀吉は、全国各地を征服するごとに検地を行い、複雑な土地の権利関係をすべて整理した、これにより荘園を完全に解体させた(p164)
・江戸時代は、土地の所有というよりも、借地権を転売していたようなもの、庶民が本当の意味で自分の土地を持てるようになったのは、1873年(明治6)の地租改正から(p167)
・貧しい小作者は土地を持つことができず、大土地所有者に土地が集中していたが、これが解体されたのは1946年のGHQによる農地改革である(p169)
・江戸幕府は貿易を独占するために、貿易国を、オランダ・朝鮮・琉球・アイヌに絞った、場所は長崎等の4箇所にして、他をすべて禁止した(p184)
・現代と江戸時代には共通点あり、浮世絵=マンガ、歌舞伎=アニメ、かるた=ゲーム、春画=AV、俳諧・連歌=ネット文化、瓦版=テレビ、である(p187)
・日本の場合には、鉄が不足していたので、枕木に鉄の代わりに「木」を使った(p239)
・日本が太平洋戦争後に占領されたのは、1945年9月2日の降伏文書調印から、1952年4月28日の講和条約発効まで(p259)
・マッカーサーのやり方で特筆すべきことは、重要なことはほとんど口で言って、書類を残さなかったこと、5つの改革指令(憲法の自由主義化と婦人参政権の付与、労働組合、教育制度改革、秘密警察廃止、経済民主化)についても口頭のみ(p270)
・戦前の財閥の株所有率は非常に高く、1937年(昭和12)時点で、三井:9.5、三菱:8.3、住友:5.1、安田:1.7%であった(p278)
・終戦後の分割統治案では、ソ連:北海道、東北、四国:中国、九州:イギリス、近畿:中国とアメリカ、東京:4カ国、残り:アメリカであった(p292)