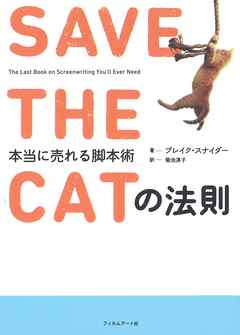感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
ハリウッド3幕構成法の理解が進んだ。文章がアカデミックしておらずエンタメ。楽しいし、わかりやすいし、おすすめ。
「Chapter2 同じものだけど・・・違った奴をくれ!」
自分の作品がどのジャンルに属する作品かを知る。全く新しいジャンルはまずない。自分の作品は、本質的にどのジャンルになるのか理解し、そのジャンルのストーリーの本質を理解する。
それぞれのひな形を研究し、ストーリーを構成する歯車がどう組み合わさり、どう機能しているのかよく考える。
これってパクリじゃない? と思ったら、パクるのをやめなさい。
これってお決まりのパターンじゃない? と感じたら、ひねりを加えなさい。
こういうやり方よくあるなあと思ったら、多分その通りだから新しい方法を考えるべきだ。
でもまずはお決まりのパターンを使いたくなる理由と利点を知ろう。
パターンやルールが生まれるのには、それなりの理由がある。
ルールをしっかり理解して、応用できるようにする。
そういったものに制約されている感覚がなくなり、ものすごく解放感を感じるはずだ。
打ち破りたいものを理解して、初めて創造性を発揮できるのだから。
「Chapter3 ストーリーの主人公は?」
設定された状況の中で一番葛藤する
感情が変化するのに一番時間がかかる
楽しんでもらえる客層の幅が広い!
主人公は、何があっても顧客が応援したくなる人物でなければならない。
少なくとも観客が、主人公の行動の動機や感情を理解できる人物でなければならない。
「Chaputer4 さあ分解だ」
(ハリウッド3幕構成法)
全体:110分
論理的ミッドポイント:55分頃
論理的第1幕(1~25)
論理的第2幕(26~85)
論理的第3幕(86~110)
<第1幕:1分~25分>
オープニング(1)
テーマの提示(5)
セットアップ(1~10)
きっかけ(12)
悩みのとき(12~25)
第1ターニングポイント(25)
<第2幕1:26分~55分>
サブプロット(30)
お楽しみ(30~55)
ミッド・ポイント(55)
<第2幕2:56分~85分>
迫りくる悪い奴ら(55~75)
全てを失って(75)
心の暗闇(75~85)
第2ターニングポイント(85)
<第3幕:86分~1110分>
フィナーレ(86~110)
ファイナル・イメージ(110)
セットアップ:主人公に必要なもの、足りていないものがある時は、最初の10分、セットアップでしっかり見せる。繰り返しのモチーフや伏線になる。
第1ターニング・ポイント:一幕と二幕の境目は、古い世界を出て、正反対の世界に進む瞬間である。二つの世界はあまりに違うため、明確な意志が必要になる。何故25分に第1ターニング・ポイントがあるのか? そうなっているからだとしか言い様がない。(映画たくさん見てこの理由説明実感)
サブプロット:メインプロットから抜けて一息つく場。第一幕から突然第二幕になると、観客は混乱する。観客にとってのちょっとした息抜き。作品のテーマを伝えたり、ストーリーを前進させるブースターロケット的な役割もする。
お楽しみ:映画の宣伝で使われるようなその作品の最大のアピールポイント。
ミッド・ポイント:上映時間のちょうど中盤。主人公が絶不調か絶好調の状態にある。絶不調ならその後好転。絶好調ならその後沈む。
全てを失って:75分頃。主人公が死や大きな喪失を経験する。直接の死ではなくても、死や喪失を連想させるイメージが出てくる。古い世界、古い考えが沈む。(本当にどんな映画やドラマでも出てくるから不思議)
心の暗闇:全てを失って絶望の淵にいる時。
第2ターニングポイント:絶望の淵で、天啓を得るところ。最善の解決策が見つかる。
フィナーレ:全てのまとめ。主人公の直すべき点が全て直り、勝利で終わる。新しい秩序が始まる。これも主人公が死を経験したおかげ。
コメディーでも何でも、映画はこの構成で作られる。批判したけりゃヒットした映画を見て見たらいい(実際そうなってました)。
「chapter5 完璧なボードを作る」
ミッド・ポイントで主人公は偽の勝利に酔いしれるか、偽の敗北にうちのめされる。こうしておくと、その後の展開が作りやすい。
「Chaputer6 脚本を動かす黄金のルール」
主人公は観客が出会ってすぐ好きになり、応援したくなるようなことをしなければならない。
ギャングなら、日常会話で親しみ持てる人にする。主人公が悪い奴なら、主人公よりもっと凶悪な奴を敵として用意する(「パルプ・フィクション」)。
マスコミはなるべく出さないようにする。主人公と観客である私の2人だけの物語でなくなってしまうからだ。本当に必要な時だけ出すこと。
「Chaputer7 この映画のどこがまずいのか?」
よくできた映画では、主人公と悪役は、一人の人間の表と裏のように対の存在になっていることが多い。強さも互角だ。
魅力的な登場人物は彼ら独自の話し方をする。日常会話でも、彼ら独自の魅力を感じさせる言い方をする。
台詞は、人となりを表現するチャンス。
直すべきところはきっぱり直す。それがプロとアマチュアの違い。頭の中で「うわ、ここ駄目じゃん!」という声が聞こえてきた時、本物のプロだったらこう答えるはずだ。「大丈夫! 直し方はわかってるから!」ってね。
「Chapter8 やってはいけないこと」
脚本コンクールははっきりいって時間の無駄だ。コンクールに出ても、エージェントやプロデューサーとコンタクト取れるわけじゃない。受賞した脚本を誰が出資してくれるんだ? どうしてもコンクールに出したいなら、レベルの高い審査員がいるか、きちんとした座談会やセミナーがあるものを選びなさい。
Posted by ブクログ
売れる脚本には法則がある。芸術特に時間芸術と言われているものは一定の「型」が見られるが映画脚本においてもそれがあるということである。「三幕構成」が有名だが本書が提唱するのが「BS2(ブレイク・スナイダー・ビート・シート)」である。
BS2は以下で構成されている。この構成がキモである。構成を作った人が「脚本家」として印税を手にできるのだそうだ。また全体を110ページとした場合は下記の長さはほぼ決まっており、業界の人はペラペラとめくって見るだけで良いものかどうなのかの判断ができる。ベンチマークの意味あいもある。なかなかシステマティックである。
1.オープニング・イメージ
2.テーマの提示
3.セットアップ
4.きっかけ
5.悩みのとき
6.第1ターニング・ポイント
7.サブプロット
8.お楽しみ
9.ミッド・ポイント
10.迫り来る悪い奴ら
11.すべてを失って
12.心の暗闇
13.第2ターニング・ポイント
14.フィナーレ
15.ファイナル・イメージ
Posted by ブクログ
「脚本術」とあるが、規模こそ違えど、プレゼン資料や読書感想文にも活用できそう。脚本家だけでなく、ビジネスマンや学生も一読の価値あり。
全体的にシニカルな口調でさらっと読めるし、映画の名前もたくさん出てくるので、映画評論的な目線でも読めるかと。
各チャプターには練習問題があるし、後半は完全に脚本家向けと感じた。
以下参考になった箇所。
・ログラインを最初に考える
→どんな映画なの?を簡潔に一行で表現
皮肉やパンチが効いているか
観客層が想定できるか
実際に興味を持ってもらえるかテストする
・共感できる主人公であること
主人公は最後には成長すること
・構成を考えてから描き始める
→ブレイクスナイダービートシート
・ボードにシーンを書き出して全体を可視化する
Posted by ブクログ
所在:展示架
資料ID:11300616
請求記号:901.27||Sn
エンタメ映画の殿堂、ハリウッド仕込みの脚本術。
王道なエンターテイメント作品をつくるにはかかせない知識が盛りだくさんの1冊。
読みやすく、わかりやすい(海外の本だから、わかりにくい部分もある)。初めて、物語や脚本、小説を書こうと思っている方にオススメの一冊。
スランプのブレイクスルーになる可能性も。
とりあえず、何かを書いてみたくなる本。
また、とにかく形にすることを可能にしてくれる本。
この本の指示に従っていれば、ある程度のストーリーができるため、一発ネタ程度の構想しかない場合にも便利。
プロットの作り方から王道映画の類型、脚本の売り込み方まで書いてある。
脚本の売り込み方はハリウッド基準なので、日本人にはあまり関係ないかも。ただ、知識としては面白い。
ブレイク・スナイダー・ビート・シート(BS2)という独自のシートを使った創作法が紹介されている。
曖昧で固まってなかったネタでためしてみたところ、たしかにそこそこのプロットができた。
著者は、このシートにあたる部分は何ページ~何ページまでと厳密過ぎるくらいの指示をしているが、脚本基準であるから、小説や漫画などの制作では気にしなくていいだろう。
使いやすくシートをカスタマイズすると、よりスムーズな創作活動ができるはずだ。
このシートで数~十数作分のプロットを完成させれば、意識しなくても物語の流れを生み出す力が身につくだろう。
ログラインという考えた方は、エンターテイメント作品を作る上では必須だと感じる。
今まで、意識せずに似たようなことをやっていたが、もっと精錬されてやり方があると知った。
物語は感覚で作るのも大切だが、それ以上にいかに理論的に考えるかも大切であると再確認させられた。
「魔法は一回」(手元にないからうろ覚えの表現)という考え方も載っていた。これは作中に不思議な要素は1つでいいということ。
日本の漫画を読んでいると、そこかしこに「魔法」がちりばめられていることが当たり前だが、一作でまとまっていることが前提の映画の場合、「魔法」をちりばめすぎるのは危険なのだ。
小説も基本的には1冊に1つの物語をまとめなくてはいけない。
まとまった作品にするには必要な教えのように思う。
尖らせたい場合は(ラノベや漫画など)あえて、この教えをやぶるのも手だろうが、バランス感覚が必要なので、最初の内はこの教えを守ったほうがいいと思う。
とにかく、初心者の第一歩になりそうな本だった。
s.s.