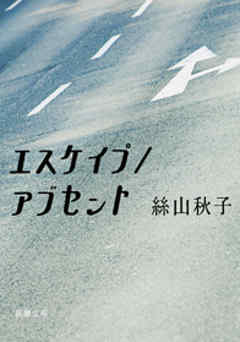感情タグBEST3
Posted by ブクログ
相対する双子の兄弟がそれぞれ主人公の二編。自由でいながら、挫折に影を潜めて生きる中年男の切なさが、軽く明るく描かれている。二編が構成から響き合っているので、短いながらも印象がしっかり残る名著。
Posted by ブクログ
久々に面白いと思える本でした。主人公視点の文体や、キャラクター設定も新鮮。いい加減なやつらなのに、嫌いになれない登場人物たちで、頑張れよって応援したくなります。最後はキュンとなりました。
Posted by ブクログ
これもよかったな~。京都へ少しの間逃亡する、元・活動家の男の語り。どうしてこんなにどこの方言も自然なんだろう?
祈りの描写が良かった。手紙みたいな、もっと言えばメールみたいな。
Posted by ブクログ
ふわふわと、テキトーに、ラクに、諦めながら、なんとなく浮き草みたいに生きてる。
それは、もう燃やし尽くしちゃったからなのか、もともと燃料が無いだけなのか…。
でも、どことなく、確実に寂しい。
捉えようもない寂しさに包まれた二篇。
Posted by ブクログ
あぁーこの軽い感じ。けど重い感じ。なんか矛盾した感じ。このメンドくさい感じ、自分とダブります(別に自分は活動家でもなけりゃ左翼でもないんだけど)。
「元」左翼活動家である正臣が、妹の家に転がり込んで「マトモな」生活を送る(送ろうとする)までの間に訪れた京都で過ごす1週間程の出来事。
左翼的思想だって、何かすごいものに思われたレコードだって、気が付けばなんてこともないものだった。ポケットに入れた「自由」も結局あっさり割れちゃったし。番ちゃんにとっての「神」だって、所詮はコスプレ、後付けの信仰。でも案外そういうものなのかも。世の中なんて全て茶番劇。それでも自分なりの意味付けをして生きていくしかないのだ。
Posted by ブクログ
もうこの絲山さんの作品って、文学の超最先端、って思った。
極限まで究極まで研ぎ澄ました、文学。
酸いも甘いも、喜怒哀楽も、個人も社会も、欲望も無碍も、生も死も、
全部感覚として分かっていて、最短でそれを表現している、気がする。
生まれて初めて、サイン会なるものに行ってしまった。。
今、世界で一番逢いたい人、に逢えた歓び。
緊張しすぎて、頭が真っ白、口が渇きまくり。
絲山さんの作品で最も好きな「海の仙人」にサインをいただいた。
あぁ、一緒に酒が飲みてぇ~な~。
Posted by ブクログ
評価が分かれる作品だろうなぁ。
文体が軽くて、すぐに読み終わってしまうので、何コレ?これで終わり?と呆気にとられる方もいるかもしれません。男性目線で書こうとしているので、多少無理があるかなと感じる個所もありましたが、そういうのを抜きにして、ストーリーの雰囲気がとてもおもしろい。雰囲気と軽妙な文章だけで読ませるというか。
神父のコスプレ、いいじゃない。
日々、生きることこそ革命です。
Posted by ブクログ
私も、行き詰ったら、神父のコスプレでもしよう。
などと思ってみる。
この本読んでたら、生きることが最早ちっせー革命だと思えた。
気づいたら終わってる――日々と似てる。
でも、毎日何とか積み重ねてれば、そのうち大きくなるかも。
この題材に、この軽妙な文章センス、いったい何なの!(赤面で)
あーもー絲山さんすげえ好きだ。
Posted by ブクログ
主人公は左翼運動の元活動家。革命を夢見て、闘争と潜伏に明け暮れること20年の果て、テレビでアメリカの同時多発テロを目の当たりにしたことで挫折を味わい、運動から脱落。40歳になってやっと気づいたことといえば、とりあえずの敵は国家権力とかじゃなくて、ただの退屈だった・・・ってこと。
人生を棒に振ったと気づいたときの虚しさ、寂しさ、空恐ろしさ。絲山作品の主人公はいずれも、世間にうまく馴染めない人。面白そうだけど、お近づきになるのは謹んでご辞退申し上げたい人などが多いようですが、この作品でも脱落者である自称元革命家の目を通して、生きていくことの嘘っぽさ、それでもなお捨てがたい人生の物哀しさを、絲山さんらしい軽妙な語り口で描き出しています。
Posted by ブクログ
2作とも読んでようやく「なるほど」と思える。
個人的には一回読んだだけじゃちょっと内容を把握しきれんかった。それはわたしがそういう「活動」をしていたわけじゃないし、そういう世代からも少し遠いところにいるせいもあるとは思う。
でもこういう内容の話にしては取っ付きやすい作品だと思います。
絲山さんの「尖った」部分が出てる。「逃亡くそたわけ」的な、焦燥感というか疾走感というか、そういうのを感じました。
Posted by ブクログ
軽妙な文体で読みやすい。この世代の人はこういう時代を生きて、みたいな世代感が全然分からないためになんとなくぼんやりと霧の中を行くように読み進めていたんだけど、何にも信じられないから神様だけは信じられる、毎日謝ってるっていうバンジャマンの話はすごくわかるなあと思ってしまった。
江崎は大人は生でぬるついて気持ち悪いっていうけど、私は子供の方が生で怖い。神様は人の罪なんて聞かずに応援しろ、祈れって言うけど、ただ聞いてくれるのってむしろすごい応援だと思う。なんか根本が違うんだろうな。江崎はちゃんと人が好きな人というか、結局のところそうだからセクトみたいな活動だってできるんだろう。そう考えると「愛がない」バンジャマンとは正反対の人なんだろう。
Posted by ブクログ
遅すぎた中年、福岡に向かい、ふと京都に降りる。
そこには現在を把握していない、双子がいたが、今はどうやら。
コスプレ神父バンジャマンと交流。
結局双子に会うことはなかったが、その不在こそが隠れた透明の背骨である。
それは作中に形を変えて言及される。
「不在は、美化される。キリストだってそうだ。」
キリストなんかより歌子婆さんみたいな人が今現在生きているってことを美化したいね、という独白や、
なんで大人ってドライでソリッドではなく、生、なんだろう、といった感覚やに、
大いに共感。ずっとそう思っていた。
ちなみに「アブセント」はその双子の片割れ。
Posted by ブクログ
職業的革命家をドロップアウトした正臣、偽神父のバンジャマン。彼らはともに、いわばかけがえのない青春期を失ってしまった。そして、過去における継続的な挫折のゆえに将来への展望もなきに等しい。小説のアイディアとしてはわからなくもないが、やや作為的に過ぎるようにも思う。タイトルの所以となったジョディ・ハリスとロバート・クインの「エスケイプ」も職革の過去には違和感が否めない。一方の「アブセント」は、もう少し自然だが、その分インパクトには幾分か欠けるだろう。小説のテーマは「喪失」であり、読後には一抹の寂寥感が残る。
Posted by ブクログ
アウトローな雰囲気を醸し出す主人公は、左翼運動から身を退いた40の男。ぶらりと訪れた京都でコスプレ神父に出会い、・・・という小説。
1966年生まれが生き抜いた時代とか政治セクトとか革命というのは、'80s生まれの自分にはいまひとつ・・・というより、全く想像が及ばない。彼らなりの青春のかたちなのかな、くらいにしか受け止めていないが、間違っているかもしれない。
文体がぶっきらぼうで主人公も何となくぶっきらぼう且つアウトロー。だけど、話が進めば進むほど、かれが 現実世界に絡め取られていくようで安心する反面すこし寂しい気がした。長年探していたレコードを聞き終えるとともに「ひどく蒸し暑い時間が過ぎたよう」な感じを受けるシーンでは、一度きりの夏が終わってしまうかのような焦燥感がある。
前篇のラストは鉢植えの重さが心地良いのだけど、続く”アブセント”でまた気持ちが沈んでいく。夏休みもとってないし、琵琶湖はどんよりしているし。p.104で「不在は美化される」と主人公が言い、今生きている婆さんを美化したいと言っているけれど、逆に言えば不在じゃないと美化することはできないのかな、とも思う。爽やかに終わる前篇と、あまり暴れるなよと釘を刺す後編。そんな風に映った。
Posted by ブクログ
双子のそれぞれの目線と状況からかかれている。軽い乗りでかかれているが、深く考えてしまう内容だった。正臣も和臣も、新しい人生の第一歩が始まるのだ。両方のラストが印象的。
Posted by ブクログ
最後の学生運動世代の活動家が、活動を引退(?)してから普通の生活を始めるまでの数日間を描いた作品。
私が学生時代にも活動家はまだ残っており、デモや学校封鎖などをやっていましたが、すでに「ちょっと変わった人たち」という見られ方で、自分も距離を置いていました。そのせいか、この世代がテーマの作品にはあまり共感を覚えません。あとがきでは、このテーマの作品の中では異色というような評価が書いてありましたが、それも良く分かりません。
普通に一人の人間を描いた作品としても読めますが、それにしては”核”となる部分の力が弱いように感じました。
Posted by ブクログ
正臣のゆってること、なんだかわかるなあ。
活動家の気持ちはわかんないけど。
この20年何やってたんだろうって、本気で考えると怖すぎ。
自分というもの、自分の居場所。
この先ごまかしきれないな。
Posted by ブクログ
6月くらい? この人の本にしては…という感じ。小説としてはおもしろかった。あと牧師さんみたいにちょっと超越した変わり者かくのうまい。私学生活動とかに興味がないからおもしろくなかったんだと思う。
Posted by ブクログ
おれは必死だよ。でも、必死って祈ることに少しは似てないか。
不在っていうのは影みたいなもんだ。エスケイプしたら不在が残る。教室に、家に、あらゆる、いるべき場所に不在は残る。(中略)不在は美化される。
* * * * *
フランス人なのに日本語しか話せないコスプレ神父。法衣を纏ったら似合ったからという理由で神父になったというくだりは、この本で絲山さんが書きたかったことの例えだと思う。つまり、外側から作られる場合もあるということ。本当に自分の中から出て来るものって少ないんじゃないかということ。人間は不確かで脆い。
人生についての本。人生を思いっきり軽い口調で語った本。相変わらず絲山さんはすごいと思う。やってらんねーよ、なんていう感じの文体で深いことをさらっと書いちゃう。カッコいいことなんて書かない。こうしなきゃいけないことは分かってるんだよ、と弱い部分をひっくるめて進んでいこうとする。
そして相変わらず物語は短い。多分、短いからいいんだと思う。余計な描写が少ないから言いたいことがぎゅっと詰まって簡潔で分かりやすい。
絲山さんの本は何故だかホッとする。
Posted by ブクログ
職業的革命家だったおれもいまや40歳目前。
革命なんて時代遅れなんだよと、遅きに期すが趣旨替えして、可愛い姪の子守に妹の経営する保育所で、働くことにする。
その前に、夜行寝台列車で京都まで旅にでる。ここは思い出の地。
「不在は美化される」
このフレーズのかっこよさ。
「不在っていうのは影みたいなもんだ。エスケイプしたら不在が残る。あらゆる、いるべき場所に不在は残る」
おれの双子の片割れ探しは、不在の確認だった。
アブセントは、その片割れの現在を描く對の物語。
Posted by ブクログ
“革命”っていわれても、ピンとこないんだよなぁ。しかも、その革命ですらあまり絡むことなく終わっちゃうし。
主人公たちが何度も、「俺の人生ってなんだったんだろう」ってゆってるけど、それはこっちがききたい。この物語って…なんだったんだろう…
ただ、そうやって“なんの意味もないこと”について意味もなく悩んでしまう無力な人間のことは、決して嫌いではない。
Posted by ブクログ
短編作品。読みやすかったけど、暫くしたらモヤッとする感情もわいてきて・・。決して不快や重いという訳ではなく、なんか夏の倦怠感を思い出しました。「アブセント」の彼女の実家、知っている場所だったのでちょっと驚いた。