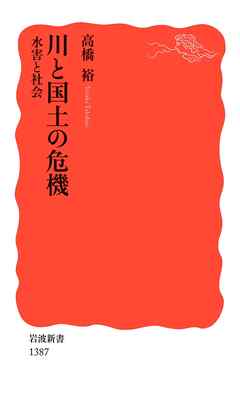感情タグBEST3
Posted by ブクログ
河川工学の老教授が日本の河川に関する課題を論じた書。
最初のうちは、きれい事を並べているだけかなと冷めた気持ちで読んでいたが、ダム建設全盛期の昭和30年代にタム建設反対の訴訟に原告推薦の鑑定人を引き受けたり、多摩川水害訴訟では、原告、被告双方から証人として推薦され、平成の今の時代でも通用する主張を堂々と行ってきた方であることがわかった。その上で、明治生まれの先人を引き合いに出して、住民や役人は川をもっと観察すべしとの主張は説得力があった。
幸田文も著者の講義を聴きに来ていたとのことで、そのときの逸話もおもしろかった。
Posted by ブクログ
川や崖などの地形や水環境といった、自分が興味のあるテーマの本を続けて読む機会を得ました。最後に出会ったのがこの本でした。専門用語などが多く使われ、読みとばした部分も少なくありません。でも、今の日本にとって何が優先されるべきか、あらためてきづかされました。経済成長だけを声高に叫ぶ方々に是非読んでくださればと願います。
「日本がダメなら、ハワイに住めばいいじゃないの」なんて言いだす富裕層が出ないうちに…。
Posted by ブクログ
川と国土は切り離せない
川を考える軸
・流域 山から海
・空から地下
・時間
ダムを作ると砂が溜まる→河口に排出される砂が減る→海岸が侵食される
景観の劣化はリスク増
森林、農地の地籍
終わりのない詰将棋
Posted by ブクログ
近代以降の短期的な要求にもとづく土地利用が、災害に対する危険度を増していったことが具体的に論じられている。『国土の変貌と水害』の入門編ともいえる一冊であり、大河津分水路についてのエピソードは特に興味をひかれた。ダムの嵩上げ、浚渫と下流への土砂運搬、操作目的の変更など、新たな提案もいくつかなされている。
「河川技術者は、河川という自然と、永遠に詰まない将棋を指しているようなものである」。
Posted by ブクログ
国土の変貌と水害、都市と水、地球の水が危ない、といったこれまでの岩波新書での著書のエッセンスがちりばめられている。(さっと読めるわりに)本質をつき続ける記述の勢いに陰りはない。それでいてまた、海岸堤防のことなど、まだまだ新たなテーマをも繰り出してくるのだから恐れ入る。
河川に携わるなら、やはりまずは歴史から知れ(過去の破堤箇所、歴史的治水施設など)というのと、それに地質等への言及が印象的。
それに加え、超過洪水をみすえて、小規模遊水地(耕作放棄地や、水田への地役権設定)までも指摘されていて、グッと来た(ドキッとした)!
歴史という観点からは、(本書でも挙げられている)杉本苑子「孤愁の岸」も、早く読まないとなぁ。
Posted by ブクログ
職場の本屋の平積みから購入。
高橋さんは、昔河川関係の本を読んだ記憶がある。
水害訴訟やダム訴訟で、住民側の証人になっていたと知りちょっとびっくり。
内容は極めてまとも。
(1)東日本大震災について、「地震、津波、火山噴火、洪水など、自然の猛威が原因となる災害に関係する科学者、技術者にとっては、防災施設の限界を再認識し、自然との共生こそが、自然災害に直面する基本姿勢であると確認する機会となった。」(p145)
(2)異なる管理者下の海岸線にわたる課題については、相互に調整を行って全体の最適を求めるべきであり、そのためには日本の海岸全体をどうすべきかの哲学を確立しなければならない。(p129)
海岸堤の議論が盛んになっているが、土木学者からそもそも全体を通じる哲学がないといわれると、愕然とするな。
(3)江東デルタ地帯の網の目状の河川の堤防は地盤沈下に伴いつぎはぎ状にかさ上げされており、地震の際には崩壊するおそれがある。(p112)
全体を通じて、乏しい予算の中で国民の命を守るための政策について、土木構造物も一つの施策だた、避難計画、避難訓練や避難ビルなども含めて、何から整備すべきか、当面、命を救うために投資は何かという発想が感じられる。その意味で土木学者も変わってきている。
Posted by ブクログ
川の源流から河口まで、本来川はひとつながりの自然と考えるべきところを、我々が管理する上での合理性を求めて縦割り行政によって管理したことにより、水害を助長させたのは間違いないと感じた。恐らく高度経済成長期において経済性が優先されていた時期にも、筆者のように災害工学的見地から意見を発していた方は少数ながらおられたと思う。現代社会においても大多数の意見を優先するのでは無く、少数派の意見に耳を傾けその価値を真に理解して物事を決定して行く必要があると感じた。
Posted by ブクログ
【内容】東日本大震災は、臨海地域の開発に依存してきた近代日本への警告である。無思慮な開発は国土の脆弱性を増し、大水害の危険度は増大している。一方、人々は防災を行政に依存するあまり自助の意識が薄れ、災害の可能性すら考えない。水源地の森林から河口の海岸まで、川の流域全体を統一した保全思想と、防災立国の構想が必要だ。 (「BOOK」データベースより)
【感想】河川管理の仕事をしていたので、せっかくなのでと読んだ一冊。河川工学の専門家の著書であり、事務職には難しいところもあったが、本書全体に流れる自然(河川)への深い理解と愛情を強く感じた。あらためて、今の時代の河川行政を考えるのに相応しい多くの示唆に富んだ書。
・「河川は上流の水源地域から中下流域、河口の沿岸域、水の流れる先の海まで、物質的、生態学的、歴史的、文化的に密接に結びついている。」(P90)…もともと歴史文化専攻の僕にとって、河川の流域が有す、1つの歴史的・文化的なつながりを再認識し、何かのきっかけになる気がした。
・「自然に対する深い理解を持った上で、開発や防災技術と自然との調和をわきまえることの重要さ」(P145)…やはり壮大で雄大な相手を知らなくては、人間の開発・防災はうまくいかない。調和して、ともに生きていくことが必要であろう。
・「古来、わが国はさまざまな災害の経験の積み重ねを経て、それぞれの地域ごとに、災害との闘い方、備え方、住まい方、日常の心構えを伝承し、災害文化を育てた。」「あらゆる災害への行政依存。民衆の知恵に基づいた災害文化の凋落」(P179)…近代の治水技術とは違った、近世以前の治水対策から学ぶことは、いまこそ、多いのでなないかと感じた。
・「大都市での水空間の確保は、防災・景観・文化の面で都市に風格を与える」(P183)…治水対策をした上で、いま、このコンクリートの時代だからこそ、水・河川の果たす役割は大きいものがあると思う。
まだまだ、興味深い記載は多い。また関わりのある仕事についたとき、再読してみたい。
Posted by ブクログ
外国人が自由に土地を買える。うん、そうか。
武田信玄の信玄堤とか、昔の人って治水に関しては良い知恵をいっぱい持っていた。気候変動やら何やらでゲリラ雷雨だの河の氾濫だの、水に関する諸問題があるので、国は領土問題ばかりを国土の問題とせず、環境問題もじっくり考えて欲しいものだ。
公共事業というととかく高速道路や鉄道網の整備の話になりがちだが、治水事業などにも注力したほうが良いのではないか。
なんて思った。